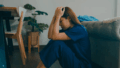「親が遠方に住んでいて、介護が必要になったらどうしよう」
仕事や家庭の事情で実家から離れて暮らしている方にとって、遠方の親の介護は大きな不安の種です。すぐに駆けつけられない距離、頻繁に帰省できない状況。「もっと近くにいられたら」と自分を責めている方も多いのではないでしょうか。
しかし、離れていても親を支える方法はたくさんあります。遠距離介護は決して「介護を放棄すること」ではなく、現代の生活スタイルに合わせた介護の一つの形です。
この記事では、親の介護が遠方の場合にどう対処すればよいのか、具体的な方法から支援制度、成功のポイントまで詳しく解説します。離れていても安心できる仕組みづくりと、罪悪感から解放される考え方をお伝えします。
親の介護が遠方の場合に直面する現実と選択肢
遠方に住む親の介護が必要になった時、どのような選択肢があるのでしょうか。まずは現実的な選択肢を整理していきましょう。
遠方の親の介護で考えられる3つの選択肢

遠方の親の介護が必要になった時、主に3つの選択肢があります。
一つ目は、親の家またはその近くにUターンして介護する方法です。実家に戻り、親と同居または近居しながら介護を行います。親にとっては住み慣れた環境で安心できますが、子どもは仕事や生活環境を大きく変える必要があります。
二つ目は、親を子の居住地に呼び寄せて介護する方法です。親が子どもの住む地域に引っ越し、子どもの近くで介護を受けます。子どもは仕事と介護を両立しやすくなりますが、親は長年住んだ地域を離れることになり、環境の変化がストレスになる可能性があります。
三つ目は、親と離れたまま遠距離介護を続ける方法です。親と子ども双方が生活環境を変えずに、介護サービスや地域の支援を活用しながら介護を行います。お互いの生活を維持できる反面、緊急時の対応や交通費の負担が課題となります。
3つの選択肢の比較
• Uターン介護:親は安心だが子の生活が大きく変わる
• 呼び寄せ介護:子は介護しやすいが親の環境が変わる
• 遠距離介護:双方の生活は維持できるが距離の課題がある
遠距離介護のメリットとデメリットを理解する

遠距離介護を選択する場合、そのメリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
特に重要なのは、親が長年住んだ地域を離れずに済むことです。高齢になるほど環境の変化はストレスとなり、認知症の進行や体調悪化のきっかけになることもあります。住み慣れた場所で、馴染みの人間関係の中で暮らせることは、親の心身の健康にとって大きなメリットです。
最も大きな課題は、緊急時の対応です。親が急に体調を崩した時、転倒した時、すぐに駆けつけられない不安は常につきまといます。また、月に数回の帰省であっても、交通費は年間で数十万円にのぼることもあります。
「離れていて申し訳ない」という罪悪感への向き合い方

遠方の親の介護で多くの人が抱えるのが、「離れていて申し訳ない」という罪悪感です。
「親が困っているのに、自分は遠くで普通の生活をしている」「もっと頻繁に帰省すべきなのに」「もし何かあったらどうしよう」。こうした思いは、心を重くします。
しかし、仕事や家庭、子育てなど、あなたにも守るべき生活があります。それを犠牲にしてまで親の元に駆けつけることが、必ずしも正解とは限りません。むしろ、無理をして共倒れになる方が、親にとっても不幸です。
大切なのは、離れていても親を支える仕組みを作ることです。介護サービスや地域の支援を活用し、定期的な連絡を取り、必要な時には帰省する。こうした形でも、十分に親を支えることができます。

距離があっても親を支える方法はたくさんあります。「離れている=介護を放棄している」ではありません。むしろ、冷静に状況を把握し、適切な支援を受けられる強みもあるんですよ。
【遠方の親のことが気になって、仕事にも集中できない方へ】
遠方から親を支えるための具体的な方法
では、実際に遠方から親を支えるには、どのような方法があるのでしょうか。具体的な手段を見ていきましょう。
地域包括支援センターとケアマネジャーの活用

遠距離介護を成功させる最大の鍵は、地域包括支援センターとケアマネジャーの活用です。
地域包括支援センターは、各市区町村に設置されている高齢者の総合相談窓口です。介護保険の申請、介護サービスの紹介、医療機関との連携など、介護に関する様々な相談に乗ってくれます。遠方に住んでいても、電話で相談することが可能です。
介護保険の認定を受けると、ケアマネジャーが担当についてくれます。ケアマネジャーは、親の状態に応じた介護サービスを提案し、ケアプランを作成してくれる専門家です。遠距離介護の場合、ケアマネジャーは「現地での代理人」のような存在になります。
定期的にケアマネジャーと連絡を取り、親の状態や変化について報告を受けることで、遠方にいても親の様子を把握できます。また、緊急時の連絡先としても頼りになります。
見守りサービスと訪問介護で安心を確保する

遠距離介護での最大の不安は、「親に何かあった時にすぐ気づけない」ことです。この不安を軽減するのが、見守りサービスです。
見守りサービスには様々な種類があります。最も一般的なのは、センサー型の見守りシステムです。室内にセンサーを設置し、一定時間動きがない場合に異常を検知して通知してくれます。プライバシーを侵害しないため、親も受け入れやすいのが特徴です。
また、電気ポットやガスの使用状況を通知するサービスもあります。毎日使う家電の動きから生活リズムを把握し、異常があれば知らせてくれる仕組みです。
訪問介護サービスを定期的に利用することも重要です。週に数回でもヘルパーが訪問することで、親の様子を直接確認してもらえます。入浴介助や掃除だけでなく、「見守り」の役割も果たしてくれるのです。
通信機器や家事代行サービスを組み合わせる

テクノロジーを活用することで、遠距離介護はより安心できるものになります。
スマートフォンやタブレットを使ったビデオ通話は、親の表情を見ながら話ができるため、声だけの電話よりも状態を把握しやすくなります。最近では高齢者でも使いやすい簡単操作のタブレットも販売されています。
また、スマートスピーカーを親の家に設置するのも有効です。「アレクサ、○○に電話して」と声をかけるだけで家族に電話できるため、操作が苦手な高齢者でも使いやすいでしょう。
家事代行サービスを活用することも検討しましょう。掃除や買い物、料理など、日常生活のサポートをプロに任せることで、親の負担を軽減できます。介護保険の対象外のサービスも多いですが、実費で利用する価値は十分にあります。
ネットスーパーや宅配サービスを登録しておくことも便利です。遠方からでも注文し、親の家に届けてもらうことができます。重い荷物を運ぶ負担もなくなります。
遠方から活用できるサービス
• ビデオ通話:表情を見ながらコミュニケーション
• スマートスピーカー:声だけで操作できる
• 家事代行:掃除・買い物・料理をサポート
• ネットスーパー:遠方から食材を注文
• 配食サービス:栄養バランスの取れた食事を配達
• 薬の宅配:薬局から直接自宅に配達
遠方の親の介護で知っておきたい支援制度
遠距離介護には様々な費用がかかります。しかし、知っておくべき支援制度もたくさんあります。
交通費の負担を軽減する割引制度と助成金

遠距離介護で最も負担が大きいのが交通費です。しかし、交通費を軽減する制度がいくつかあります。
JRには「介護帰省割引」という制度があります。介護のための帰省であることを証明できれば、運賃が2割引になります。利用には介護保険被保険者証や要介護認定通知書などが必要です。
航空会社も介護割引を提供しているところがあります。ANAやJALでは、介護のための帰省であれば特別運賃が適用される場合があります。各社の条件を確認してみましょう。
また、一部の自治体では遠距離介護者への交通費助成制度を設けています。親が住む自治体や自分が住む自治体に問い合わせてみてください。助成額は自治体によって異なりますが、年間数万円程度の補助が受けられる場合もあります。
仕事との両立を支える介護休業制度の活用

遠距離介護と仕事を両立するためには、介護休業制度を理解しておくことが重要です。
介護休業制度は、家族の介護のために休業できる法律で定められた制度です。対象家族1人につき、通算93日まで3回に分けて取得できます。遠方の親の介護体制を整えるため、まとまった休みが必要な時に活用できます。
また、介護休暇という制度もあります。これは年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで、1日または時間単位で取得できる休暇です。急な帰省や親の通院付き添いなどに利用できます。
さらに、短時間勤務制度や時差出勤制度を利用できる企業もあります。始業・終業時刻を調整することで、帰省しやすいスケジュールを組むことができます。
これらの制度は法律で定められているため、会社の規模に関わらず利用できます。ただし、事前の申請が必要ですので、早めに会社の人事部に相談しましょう。
自治体の遠距離介護支援サービスを調べる

自治体によっては、遠距離介護者向けの独自の支援サービスを提供しているところもあります。
例えば、定期的に職員が訪問して安否確認をするサービス、緊急通報システムの設置補助、配食サービスの費用助成などです。自治体によって内容は大きく異なるため、親が住む市区町村の福祉課に問い合わせてみましょう。
また、民生委員による見守りサービスも活用できます。民生委員は地域の高齢者の見守りを行っており、定期的な訪問や声かけをしてくれます。地域包括支援センターを通じて依頼することができます。
さらに、地域のボランティア団体による支援もあります。買い物代行、通院付き添い、話し相手など、様々なサポートを提供している団体があります。社会福祉協議会に相談すると、地域のボランティア情報を教えてもらえます。
遠方の親の介護を成功させるポイント
遠距離介護を長期的に続けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
きょうだいや親族と役割分担を明確にする

遠距離介護を一人で抱え込んではいけません。きょうだいや親族と役割分担を明確にすることが重要です。
例えば、「長男は月1回帰省して親の様子を直接確認する」「次男は経済的支援を担当する」「長女は日々の電話連絡を担当する」など、それぞれができる範囲で役割を分担します。
特に、親の近くに住むきょうだいがいる場合は、緊急時の対応を任せられると安心です。遠方に住む側は経済的支援や情報収集を担当するなど、距離に応じた役割分担が効果的です。
役割分担を決める際は、家族会議を開いて話し合うことをおすすめします。メールやLINEだけでなく、顔を見ながら話すことで、お互いの状況や思いを理解し合えます。
定期的な連絡と帰省頻度の適切な設定

遠距離介護では、定期的な連絡と適切な帰省頻度が鍵となります。
電話やビデオ通話は、少なくとも週に1回は行うことをおすすめします。短時間でも構いません。定期的に声を聞き、表情を見ることで、親の変化に気づきやすくなります。
帰省の頻度は、親の介護度や距離、経済状況によって異なりますが、月に1回程度が一つの目安です。ただし、無理のない範囲で設定することが大切です。帰省のたびに疲れ果てていては長続きしません。
帰省した際は、親との時間だけでなく、ケアマネジャーとの面談、医師との相談、介護サービス事業者との打ち合わせなど、今後の介護体制を整える時間も確保しましょう。
親の意向を確認し施設入所も視野に入れる

遠距離介護が難しくなってきた場合、親の意向を確認しながら施設入所も検討することが必要です。
親の介護度が上がり、在宅での生活が困難になった場合、無理に在宅介護を続けることは親にとっても子どもにとっても負担が大きすぎます。介護施設での生活は、プロによる24時間のケアを受けられ、親自身の安全や健康にとってもメリットがあります。
ただし、施設入所を検討する際は、必ず親の意向を確認することが重要です。できれば元気なうちから、将来の介護についての希望を聞いておきましょう。「最期まで自宅にいたい」のか、「施設でもいい」のか。親の価値観を理解しておくことが、適切な判断につながります。
また、施設を選ぶ際は、できるだけ親の住む地域の施設を選ぶことをおすすめします。長年住んだ地域であれば、環境の変化が少なく、友人も面会に来やすくなります。
ココマモで介護の悩みを相談できます
介護家族のためのオンライン相談サービス「ココマモ」では、遠方の親の介護に関する様々な悩みを専門相談員に相談できます。「どんな介護サービスを利用すればいいのか」「施設入所を検討すべきか」「きょうだいとどう役割分担すればいいのか」など、遠距離介護特有の悩みにも対応しています。初回20分の無料相談もありますので、一人で悩まず、まずは相談してみてください。
遠方の親の介護で悩んだ時の相談先―まとめ
親の介護が遠方の場合、物理的な距離からくる不安や罪悪感は大きいものです。しかし、離れていても親を支える方法はたくさんあります。
地域包括支援センターやケアマネジャーを活用し、見守りサービスや訪問介護を組み合わせることで、遠方からでも親の安全を確保できます。通信機器や家事代行サービスなども積極的に活用しましょう。
交通費の割引制度や介護休業制度など、知っておくべき支援制度も多くあります。自治体独自の支援サービスもあるので、親が住む地域の情報を集めることが大切です。
最も大切なのは、一人で抱え込まないことです。きょうだいや親族と役割分担し、専門家の力を借りながら、無理のない介護体制を作りましょう。
「離れていて申し訳ない」という罪悪感を手放してください。離れていても、あなたは十分に親を支えています。距離があるからこそ、冷静に状況を判断し、適切なサービスを選択できる強みもあるのです。
遠距離介護は、現代の生活スタイルに合わせた介護の一つの形です。自分自身の生活も大切にしながら、親を支える方法を見つけていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。