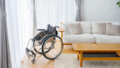「在宅介護支援センターって、どこにあるの?」
「地域包括支援センターとは何が違うの?」
「介護の相談はどこにすればいいの?」
そんな疑問を持っていませんか?

実は、在宅介護支援センターは、現在の地域包括支援センターの前身となった施設なんです。多くが地域包括支援センターへ移行しましたが、現在も一部では在宅介護支援センターとして活動を続けています。
この記事では、在宅介護支援センターとは何か、その役割や業務内容、地域包括支援センターとの違いを詳しく解説します。介護の相談先で迷っている方、地域の支援体制を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
在宅介護支援センターとは何か
在宅介護支援センターとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援する相談機関です。まずは、その成り立ちと現状について見ていきましょう。
在宅介護支援センターの誕生と歴史

在宅介護支援センターは、1989年の高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)によって誕生しました。当時、高齢化が進む中で、高齢者の在宅での福祉や施設福祉の基盤整備を進める必要があったんです。
1994年には老人福祉法が改正され、その中で在宅介護支援センターは「老人介護支援センター」として正式に規定されます。介護保険制度が導入される2000年までの約10年間、地域の高齢者やその家族を支える総合的な相談窓口として、重要な役割を果たしてきました。
在宅介護支援センターは「保険・医療・福祉の連携」を理念として設立され、地域住民の身近な場所で老人福祉に関する情報提供や相談・指導を行ってきた歴史があります。
現在の在宅介護支援センターの状況

2000年に介護保険制度が導入され、2005年の制度改正で地域包括支援センターが創設されました。これにより、多くの在宅介護支援センターが地域包括支援センターへ移行することになります。
現在では、地域包括支援センターのブランチ(相談窓口)やサブセンター(支所)として役割を変えているところが多くあります。一方で、介護保険制度導入後も在宅介護支援センターという名称で事業を継続している地域も存在するんです。
事業を続けている在宅介護支援センターでは、引き続き地域住民の相談支援や地域づくりに取り組んでいます。
在宅介護支援センターの根拠法と位置づけ

在宅介護支援センターは、老人福祉法を根拠法として実施されています。
老人福祉の施策として位置づけられており、市町村または市町村から運営の委託を受けた社会福祉法人などが運営主体となります。財源は予算補助でしたが、2006年度以降は一部例外を除き予算補助は廃止されました。
一方、地域包括支援センターは介護保険法を根拠法とし、介護保険の第1号保険料と公費を財源として運営されています。この法的根拠の違いが、両者の役割や業務内容の違いにもつながっているんです。
在宅介護支援センターの役割と業務内容
在宅介護支援センターは、地域の高齢者とその家族を総合的に支援するために、様々な業務を行っています。具体的な役割を見ていきましょう。
介護に関する相談業務と申請代行

在宅介護支援センターの中心的な役割は、介護に関する相談対応です。
地域に暮らしている方がいつまでも自宅での生活を続けられるように、介護に関する相談や福祉サービスの手続きを援助します。具体的には、介護保険の利用方法の説明、福祉用具の紹介、保健福祉サービスの申請代行、関係機関との連絡調整などを行うんです。
よくある相談内容
介護保険について知りたい。福祉用具を借りたい。病院から退院するけど、今の状態では家で生活できない。高齢の親が一人暮らしで今後が心配。デイサービスやホームヘルパーを利用したい。施設入所について相談したい。
相談は、電話や来所だけでなく、訪問での対応も行っています。困っていることがあれば、気軽に相談できる体制が整っているんです。
【介護の相談、どこから始めればいいかわからない方へ】
地域の巡回訪問と実態把握

在宅介護支援センターの重要な役割の一つが、地域の高齢者を巡回訪問することです。
相談員が担当地域の65歳以上の高齢者の自宅を訪問し、健康状態や生活状況を確認します。これは、介護のニーズを抱えているものの、自ら相談窓口に足を運べない高齢者を発見するために重要な業務なんです。
介護保険制度の導入により、介護サービスの利用は申請主義となりました。そのため、相談や申請が困難な高齢者が支援から取り残されるリスクが高まったんです。
一人暮らしでの孤独死、介護疲れからくる虐待や介護放棄、認知症の早期発見の遅れなど、様々な問題が懸念されます。巡回訪問により、こうした問題を早期に発見し、適切な支援につなげることができるんです。
介護予防教室と講習会の実施

在宅介護支援センターは、介護予防のための教室や講習会も開催しています。
地域の高齢者を対象に、公民館などで運動教室や生活習慣改善の講習会を実施します。運動やレクリエーションに参加してもらうことで、生きがいづくり、閉じこもり防止、認知症予防につなげていくんです。
また、介護に関する知識を深めるための講習会や、介護者の交流会なども開催されます。介護する家族同士が情報交換し、悩みを共有できる場としても機能しているんです。

介護予防教室は、高齢者の健康維持だけでなく、地域のつながりを作る場としても大切な役割を果たしているんですよ。
親の介護でお金がない時の対処法。公的支援制度や負担軽減策はある?
在宅介護支援センターと地域包括支援センターの違い
在宅介護支援センターと地域包括支援センターは、どちらも地域の高齢者を支援する機関ですが、いくつかの違いがあります。詳しく見ていきましょう。
根拠法と財源の違い

最も大きな違いは、根拠となる法律と財源です。
在宅介護支援センターは老人福祉法を根拠法とし、老人福祉の施策として実施されます。財源は予算補助でしたが、2006年度以降は原則として廃止されました。
一方、地域包括支援センターは介護保険法を根拠法とし、介護保険法に基づく「地域支援事業」の一環として実施されます。財源は第1号保険料(65歳以上の介護保険料)と公費です。
この法的根拠の違いにより、両者の位置づけや役割に違いが生まれているんです。
業務内容と専門性の違い

業務内容にも明確な違いがあります。
在宅介護支援センターは、主に老人福祉を中心とする相談、連絡調整が業務の中心でした。相談対応と関係機関への橋渡しが主な役割だったんです。
一方、地域包括支援センターは地域包括ケアの中心機関として、より専門的で包括的な業務を担います。具体的には、以下の4つの業務を行うんです。
地域包括支援センターの4つの業務
1. 介護予防ケアマネジメント。要支援者や要介護になる恐れのある方の介護予防プラン作成。2. 包括的・継続的ケアマネジメント。ケアマネジャーへの支援や関係機関との連携強化。3. 総合相談支援。介護だけでなく、福祉や医療など幅広い相談対応。4. 権利擁護。高齢者虐待の防止、成年後見制度の利用支援など。
地域包括支援センターは、在宅介護支援センターの役割に加えて、医療や介護などの専門家がさまざまな外部機関と連携し、高齢者の抱える課題をワンストップで相談できる窓口として機能しています。
職員配置の違い

職員配置にも大きな違いがあります。
在宅介護支援センターは、1人でも設置が可能でした。社会福祉士などのソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人がいれば運営できたんです。また、居宅介護支援事業所との兼務も可能でした。
一方、地域包括支援センターは原則3名以上の配置が必要です。社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員という3つの専門職を配置することが求められます。また、居宅介護支援事業所との兼務は原則不可とされています。
この専門職の配置により、地域包括支援センターはより専門的で包括的な支援が可能になっているんです。
親の介護をしない兄弟と相続問題。公平な遺産分割を実現するには?
在宅介護支援センターの利用と介護保険
「在宅介護支援センターを利用するには、介護保険が必要なの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。ここでは、利用条件と介護保険との関係について説明します。
介護保険がなくても相談できる

結論から言うと、介護保険の認定を受けていなくても、在宅介護支援センターは利用できます。
在宅介護支援センターは、要介護認定の有無にかかわらず、自宅で生活する高齢者やその家族からの相談を受け付けています。「介護が必要かもしれない」「将来が不安」といった漠然とした悩みでも、気軽に相談できるんです。
介護保険の認定申請の方法がわからない、介護サービスにはどんなものがあるのか知りたい、といった介護保険に関する相談も、もちろん対応してもらえます。
対象となる人

在宅介護支援センターの主な対象者は以下の通りです。
自宅で生活する65歳以上の高齢者とその家族が基本的な対象となります。介護が必要な高齢者本人だけでなく、介護をしている家族からの相談も受け付けています。また、介護予防が必要とされる要支援1・2の方も対象です。
要介護認定を受けていない方でも、将来の介護に不安がある、健康状態が心配といった相談ができます。地域に住む高齢者であれば、誰でも相談できるのが在宅介護支援センターの特徴なんです。
介護保険サービス利用時の役割

介護保険サービスを利用する場合、在宅介護支援センターは利用をサポートする役割を果たします。
要介護認定の申請方法の説明、申請書類の記入支援、申請代行などを行います。認定後は、適切な介護サービスの紹介、ケアマネジャーの選定支援、サービス事業者との連絡調整なども行うんです。
また、介護保険の範囲外のサービスや、地域の福祉サービス、インフォーマルな支援(ボランティアなど)についても情報提供してくれます。介護保険だけでは対応できない部分も含めて、総合的に支援してもらえるのが特徴です。

介護保険のことがよくわからなくても大丈夫。専門職が丁寧に説明し、必要な手続きをサポートしてくれますよ。
レスパイトケアとは。簡単にわかる基本知識。種類・費用・利用方法は?
在宅介護支援センターが果たしてきた役割
在宅介護支援センターは、現在の地域包括ケアシステムの基礎を築いた存在です。その歴史的な役割と意義を振り返ってみましょう。
地域包括ケアの礎を築いた

在宅介護支援センターは、「保険・医療・福祉の連携」という理念のもとに設立されました。
1990年の発足以来、地域住民の身近な場所で老人福祉に関する情報提供や相談・指導の役割を、市町村に代わって担ってきたんです。地域ケア会議や個別の指導などを通して、高齢者の介護状態の悪化や権利侵害などを防ぐなど、高い公益性をもって活動してきました。
この「保険・医療・福祉の連携」という理念は、現在の地域包括支援センターにも引き継がれています。在宅介護支援センターが築いた地域での支援体制が、今日の地域包括ケアシステムの基盤となっているんです。
在宅福祉の最前線での活動

在宅介護支援センターは、地域における老人福祉の最前線で活動してきました。
市町村に代わって高齢者の持つ課題解決に取り組み、地域住民との信頼関係を築きながら、きめ細やかな支援を提供してきたんです。施設に入所せず、住み慣れた自宅で暮らし続けたいという高齢者の願いを支えるために、様々な工夫と努力を重ねてきました。
また、介護する家族の負担軽減にも力を入れ、介護者同士の交流の場を作ったり、介護方法の助言を行ったりしてきました。介護される側だけでなく、介護する側も支えるという視点を持って活動してきたんです。
今後への期待

現在、在宅介護支援センターの機能の多くは、地域包括支援センターが担っています。
しかし、一部地域では今も在宅介護支援センターとして活動を続けており、地域包括支援センターのブランチやサブセンターとして、地域に密着したきめ細やかな支援を提供しています。
名称は変わっても、地域の高齢者福祉を支える役割は変わりません。在宅介護支援センターが築いた地域福祉の歴史を踏まえ、多くの専門職や地域の人々の力で、地域包括ケアをより良いものにしていくことが期待されているんです。
在宅介護支援センターとは。まとめ
在宅介護支援センターとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援する相談機関として、1989年に誕生しました。

介護保険制度導入前は、介護の総合的な相談窓口として地域の最前線で活動してきました。2000年の介護保険制度導入、2005年の地域包括支援センター創設により、多くが移行しましたが、その理念と役割は今も引き継がれています。
地域包括支援センターとの主な違いは、根拠法(老人福祉法と介護保険法)、財源、業務内容の専門性、職員配置などです。地域包括支援センターは、より専門的で包括的な4つの業務(介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護)を担っています。
利用に関しては、介護保険の認定を受けていなくても相談できます。
自宅で生活する高齢者やその家族であれば、誰でも気軽に相談できる窓口なんです。
「親の介護が心配」「将来が不安」といった漠然とした悩みから、介護保険の具体的な利用方法まで、幅広く対応してもらえます。
在宅介護支援センターが築いた「地域で高齢者を支える」という理念は、現在の地域包括ケアシステムに引き継がれています。
名称は変わっても、地域に密着した支援という役割は変わりません。
介護のことで困ったら、まずはお住まいの地域の相談窓口(在宅介護支援センターまたは地域包括支援センター)に連絡してみてください。
専門職が親身になって、あなたの悩みに寄り添い、最適な解決策を一緒に考えてくれます。

介護の悩みは、一人で抱え込まず、まずは相談してみることが大切です。地域には必ず、あなたを支えてくれる窓口がありますよ。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。