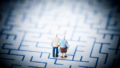「在宅介護を始めたけれど、想像以上に大変で限界を感じている」「毎日のように続く介護で、どれが一番つらいのかもわからなくなってきた」「他の人はどんなことを大変だと感じているのだろう」
在宅介護をしている方なら、一度はこのような思いを抱いたことがあるのではないでしょうか。在宅介護には確かに多くのメリットがありますが、同時に介護者にとって大きな負担となる側面も多く存在します。
実際に、全国の在宅介護経験者を対象とした複数の調査結果を総合すると、在宅介護で大変だと感じることには明確な傾向があることがわかってきました。特に注目すべきは、多くの介護者が「身体的な介護よりも精神的な負担の方がつらい」と感じていることです。この記事では、複数の公式調査や専門機関のデータを基に、在宅介護で大変なことのランキングを詳しく解説し、それぞれの負担を軽減するための具体的な対策についてもご紹介します。
在宅介護で大変なことランキングTOP5
まずは、在宅介護で特に負担が大きいとされるTOP5から詳しく見ていきましょう。これらは多くの介護者が共通して感じている深刻な問題です。
【第1位】コミュニケーションの困難さと精神的ストレス

複数の調査で一貫して1位にランクインしているのが、コミュニケーションの困難さと精神的ストレスです。これは多くの人が想像する「身体的な介護の大変さ」を上回る深刻な問題となっています。
認知症によるコミュニケーション障害が最も深刻な問題として挙げられます。同じ話を何度も繰り返される、質問に対して的外れな答えが返ってくる、突然怒り出したり泣き出したりするといった症状に、介護者は精神的に疲弊していきます。
24時間続く精神的緊張も大きな負担となります。「いつ何が起こるかわからない」「目を離した隙に事故が起こるかもしれない」という不安が常に頭から離れず、心が休まる時間がありません。
【第2位】排泄介助の身体的・精神的負担

排泄介助は、在宅介護の中でも特に負担が大きいケアの一つです。身体的な負担だけでなく、精神的な面でも介護者に大きなストレスを与えます。
排泄介助の主な負担
身体的負担
・トイレへの移乗介助での腰や肩への負担
・おむつ交換時の体位変換や清拭作業
・1日に何度も繰り返される重労働
精神的負担
・においや汚れへの対応によるストレス
・プライバシーへの配慮と心理的抵抗感
・夜間対応による慢性的な睡眠不足
身体的負担の深刻さは想像以上です。トイレへの移乗介助では、体重を支えながらの移動で腰や肩に大きな負担がかかります。1日に何度も繰り返されるこれらの作業により、介護者自身が腰痛や肩こりなどの身体的不調を抱えるケースが非常に多いです。
夜間対応の負担も深刻な問題です。夜中に何度もトイレに起こされる、おむつ交換で睡眠が中断されるといったことが続くと、慢性的な睡眠不足に陥ります。睡眠不足は体力だけでなく精神面にも大きな影響を与え、日中の介護にも支障をきたすようになります。
【第3位】自由時間がなくなる時間的制約の苦しさ

在宅介護では、時間的制約により介護者の生活が大きく制限されることが深刻な問題となっています。多くの介護者が「自分の時間が全くない」ことに大きなストレスを感じています。
24時間体制での見守りが必要になると、介護者は常に気を張っている状態が続きます。認知症の方の徘徊リスクがある場合や、転倒の危険性が高い場合には、文字通り目を離すことができません。
仕事との両立困難も深刻な問題です。急な体調変化で仕事を早退しなければならない、通院の付き添いで休暇を取る必要がある、夜間の介護で睡眠不足になり仕事に集中できないなど、仕事への影響は避けられません。
家事や育児との両立も大きな負担となります。介護をしながら家族の食事を作り、洗濯をし、子どもの世話をするという多重負担に、多くの女性が苦しんでいます。特に「サンドイッチ世代」と呼ばれる40〜50代の女性は、親の介護と子育てを同時に担うことで、極限状態に追い込まれることも少なくありません。
【第4位】食事・入浴介助など日常生活全般のサポート負担

在宅介護では、日常生活全般にわたるサポートが必要となり、その積み重ねが介護者に大きな負担となります。一つ一つは小さなことでも、毎日続くことで疲労が蓄積されていきます。
食事介助の複雑さは多くの人が想像する以上です。単に食べさせるだけでなく、嚥下機能に配慮した食事の準備、食べこぼしの処理、栄養バランスの管理、服薬の確認など、多岐にわたる配慮が必要です。
日常生活サポートの主な内容
食事介助
嚥下機能への配慮・食べこぼし処理・栄養管理・服薬確認
入浴介助
転倒防止・重労働・温度管理・プライバシー配慮
衣服の着脱介助
季節への配慮・体位変換・汚れた衣服の交換
通院の付き添い
車椅子移動・待ち時間付き添い・医師との情報共有
入浴介助の負担も深刻です。転倒防止への注意、体を洗う際の重労働、浴室の温度管理、プライバシーへの配慮など、安全性と尊厳の両方を保ちながらのケアが求められます。特に、一人で入浴介助を行う場合は、万が一の事故への不安も大きなストレスとなります。
服薬管理の責任も重大です。薬の飲み忘れや重複服用を防ぐため、薬の準備から服薬確認まで、介護者が責任を持って管理する必要があります。複数の薬を服用している場合は、薬の相互作用や副作用にも注意を払わなければなりません。
通院の付き添いでは、車椅子での移動、待ち時間の付き添い、医師との情報共有など、一回の通院で半日がかりになることも珍しくありません。
【第5位】経済的負担と介護費用への不安

在宅介護には想像以上の経済的負担が伴い、多くの家庭の家計を圧迫しています。特に長期間にわたる介護では、経済的な不安が介護者の精神的負担を増大させる要因となっています。
在宅介護の主な経済的負担
初期費用
・介護用品やリフォーム費用:数十万円〜数百万円
・車椅子、介護ベッド、手すり設置、段差解消など
継続的な費用
・紙おむつ、介護食、清拭用品、薬代など
・介護サービス利用料(限度額超過分は全額自己負担)
収入減少
・介護離職や労働時間短縮による世帯収入の大幅減少
介護用品やリフォーム費用は、介護開始時にまとまった出費となります。車椅子、介護ベッド、ポータブルトイレ、手すりの設置、段差の解消など、安全で快適な介護環境を整えるために必要な費用は数十万円から数百万円に及ぶことがあります。
介護による収入減少も深刻な問題です。介護のために仕事を辞めたり、労働時間を短縮したりすることで、世帯収入が大幅に減少します。一方で介護費用は増加するため、家計は急速に悪化していきます。

在宅介護で大変なことランキング6位から10位
続いて、6位から10位の問題についても詳しく見ていきましょう。これらも多くの介護者が直面する重要な課題です。
【第6位】夜間対応と徘徊への見守りストレス

夜間の介護対応は、在宅介護の中でも特に介護者の負担が大きい問題の一つです。夜間は専門的なサポートが限られるため、家族だけで対応しなければならないことが多く、大きなストレスとなります。
徘徊への対応は、認知症介護において最も深刻な問題の一つです。夜中に突然起き出して外に出ようとする、家の中を歩き回って転倒のリスクがある、近所に迷惑をかけてしまうのではないかという不安など、介護者は常に気を張っていなければなりません。
夜間のトイレ介助や失禁対応も大きな負担です。1時間おきにトイレに起こされる、おむつ交換のために夜中に何度も起きる、シーツや衣類の交換が必要になるなど、まとまった睡眠を取ることができません。
夜間の不穏行動への対応も困難です。昼夜逆転により夜間に活動的になる、幻覚や妄想により興奮状態になる、大声を出して近所迷惑になるなど、予測不可能な行動に対応し続けることは、介護者にとって大きなストレスとなります。
【第7位】介護サービス活用による負担分散の必要性

在宅介護の負担を軽減するためには、様々な介護サービスを効果的に組み合わせて活用することが重要です。一人ですべてを抱え込まず、プロのサポートを適切に利用することで、介護の質を向上させながら負担を軽減できます。
訪問介護サービスの戦略的活用では、身体介護と生活援助を効果的に組み合わせることがポイントです。最も負担の大きい排泄介助や入浴介助をプロに任せることで、介護者の身体的負担を大幅に軽減できます。
デイサービスの効果的利用により、介護者の休息時間を確保できます。週に3〜4回程度の利用により、介護者は自分の時間を持つことができ、リフレッシュすることが可能です。また、本人にとっても社会とのつながりを保つ重要な機会となります。
【第8位】家族間の役割分担と協力体制づくり

在宅介護を持続可能なものにするためには、家族全体での協力体制を構築することが欠かせません。一人に負担が集中することを避け、それぞれができる範囲で役割を分担することが重要です。
きょうだい間での役割分担では、地理的条件や仕事の状況、得意分野を考慮して分担を決めます。近くに住むきょうだいが日常的なケアを担当し、遠方のきょうだいは経済的な負担や月に一度の泊まり込み介護、各種手続きの代行などを担当するという分担方法があります。
効果的な家族間協力体制
きょうだい間での役割分担
・近居:日常ケア・緊急時対応
・遠方:経済負担・月1回泊まり込み・手続き代行
配偶者との協力
・得意分野での分担・平日と休日での担当交代
定期的な家族会議
・月1回の状況報告・費用精算・今後の計画
緊急時対応体制
・連絡先共有・代替者確保・医療機関連携
重要なのは、「公平性」よりも「持続可能性」を重視することです。
定期的な家族会議の開催により、情報共有と負担の調整を行います。月に一度程度、家族全員が集まって介護の状況報告、費用の精算、今後の計画について話し合うことで、問題の早期発見と解決につながります。
【第9位】介護者自身のメンタルケアと相談窓口活用

在宅介護を長期間続けるためには、介護者自身の心身の健康管理が最も重要です。自分自身をケアすることは決して自分勝手なことではなく、良い介護を続けるために必要不可欠なことです。
定期的な健康チェックを怠らないことが基本です。介護に追われていると自分の体調変化に気づきにくくなりますが、定期的な健康診断や、体調不良を感じた時の早めの受診を心がけることが重要です。
ストレス発散の時間を意識的に作ることも重要です。短時間でも良いので、自分だけの時間を持ち、好きなことをする時間を確保します。読書、音楽鑑賞、散歩、友人との電話など、リフレッシュできる活動を見つけることが大切です。
地域包括支援センターでは、介護に関する総合的な相談に応じており、負担軽減のための具体的なアドバイスを受けることができます。また、介護者向けの交流会や研修会なども開催されており、同じ境遇の人との情報交換の機会も提供されています。
重要なのは、「頑張りすぎない」「完璧を求めない」「助けを求めることを恥ずかしがらない」という心構えです。介護は長期戦であり、持続可能なペースで続けることが最も大切です。
【第10位】将来への不安と長期的な見通しの難しさ

在宅介護では、将来への不安と長期的な見通しの難しさが介護者の精神的負担を大きく増加させています。「いつまで続くのか」「どこまで悪化するのか」といった不安は、日々の介護をより困難なものにします。
介護期間の予測困難により、介護者は常に不安を抱えています。要介護度の進行スピード、認知症の症状変化、身体機能の低下など、個人差が大きく予測が困難なため、長期的な計画を立てることが難しくなります。
経済的な将来不安も深刻です。介護費用の増加、収入減少、自分自身の老後資金への影響など、経済的な不安が重なることで、精神的な負担がさらに増大します。
自分自身の健康への不安も見逃せません。長期間の介護により自分の体力や健康状態が悪化することへの心配、介護者が倒れた場合の対応への不安など、様々な心配が重なります。
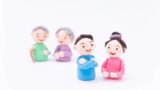

在宅介護の大変さは一人で抱え込む必要はありません。地域包括支援センターやケアマネジャー、そして専門の相談窓口があなたをサポートしています。困ったときは遠慮せずに相談してくださいね。
在宅介護で大変なことランキングTOP10まとめ

在宅介護で大変なことのランキングを通じて、多くの介護者が共通して抱える悩みと困難が明らかになりました。1位のコミュニケーション困難から10位までの様々な負担は、いずれも介護者の心身に大きな影響を与える深刻な問題です。
特に注目すべきは、身体的な負担よりも精神的・時間的な制約の方が上位にランクインしていることです。これは、在宅介護の真の困難さが、単純な肉体労働ではなく、24時間続く精神的緊張や、自分の人生が制限されることへの苦しさにあることを示しています。
しかし、これらの困難は決して一人で抱え込む必要はありません。適切な介護サービスの活用、家族間での協力体制の構築、介護者自身のメンタルケアなど、様々な対策により負担を軽減することが可能です。
重要なのは、「完璧な介護」を目指すのではなく、「持続可能な介護」を心がけることです。介護者自身が健康で安定していてこそ、質の高い介護を長期間続けることができるのです。
在宅介護の困難に直面している方は、一人で悩まず、積極的に周囲のサポートを求めることをお勧めします。地域包括支援センター、ケアマネジャー、かかりつけ医、そして同じ境遇の仲間たちが、きっと力になってくれるはずです。在宅介護は決して一人で背負うものではなく、社会全体で支え合うものなのです。

さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。