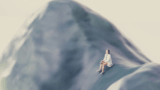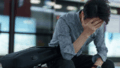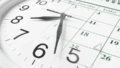「日中は穏やかな母が、夕方になると急に落ち着きがなくなる」「夕暮れ時になると『家に帰る』と言い出して困惑している」「夜になると幻覚を訴えたり、攻撃的になったりして対応に疲れ果てている」
認知症の家族を介護している方の中には、こうした夕方から夜にかけての症状の変化に悩まされている方が少なくありません。この現象は夕暮れ症候群(たそがれ症候群、日没症候群)と呼ばれ、認知症の周辺症状の一つとして知られています。
夕暮れ症候群は、午後3時頃から夕方5時頃にかけて症状が始まり、日没後にピークを迎えることが多いです。朝方になると症状は落ち着く傾向があります。
この記事では、夕暮れ症候群の症状と特徴、発症する原因とメカニズム、家族ができる効果的な対処法と予防策について詳しく解説します。医療機関を受診すべきタイミングや、治療の可能性についてもお伝えします。
夕暮れ症候群の症状と特徴
夕暮れ症候群は、認知症の方に特有の時間帯依存性の症状です。日中は比較的穏やかでも、夕方になると急に症状が強くなるのが最大の特徴です。この症状パターンを理解することが、適切な対応の第一歩となります。
夕方から夜にかけて現れる不安と混乱

夕暮れ症候群の最も典型的な症状は、夕方から夜にかけて強まる不安と混乱です。それまで穏やかに過ごしていた方が、夕暮れ時になると急に落ち着きを失い、そわそわした様子を見せるようになります。
「ここはどこ」「いつ家に帰れるの」といった見当識障害による発言が増えます。自分がいる場所や時間がわからなくなり、強い不安を感じるのです。家族の顔を見ても誰だかわからず、「知らない人がいる」と訴えることもあります。
落ち着きのなさは行動にも現れます。同じ場所を行ったり来たりする徘徊、何度も同じ質問を繰り返す、物を探し回る、引き出しを開け閉めするといった行動が見られます。本人は目的があってそうしているのですが、何を探しているのか自分でもわからなくなっている状態です。
帰宅願望や攻撃的言動が強まる時間帯

夕暮れ症候群で介護家族を最も悩ませるのが、帰宅願望です。自宅にいるにもかかわらず、「家に帰りたい」「家に帰らなくては」と繰り返し訴え、外に出ようとします。施設に入所している場合も同様です。
この帰宅願望は、単なるわがままではありません。認知症により時間や場所の認識が混乱し、「今いる場所が自分の家ではない」と感じているのです。過去の記憶が蘇り、「子どもを迎えに行かなくては」「夕飯の支度をしなくては」といった使命感に駆られることもあります。
家族が引き止めようとすると、攻撃的な言動や興奮状態が現れることもあります。怒鳴る、物を投げる、手を振り払う、暴言を吐くといった行動は、本人の中で高まっている不安や恐怖の表れです。
こうした攻撃性は、決して家族を傷つけたいわけではありません。混乱と不安の中で、自分を守ろうとする防衛反応なのです。普段は温厚な方でも、夕暮れ症候群の時間帯には人が変わったようになることがあります。
幻覚や妄想が出現するメカニズム

夕暮れ症候群では、幻覚や妄想が出現することもあります。特に視覚的な幻覚が多く、「部屋に知らない人がいる」「虫が這っている」「子どもが泣いている」といった訴えが典型的です。
夕暮れ時の薄暗さが、幻覚を引き起こす大きな要因です。明るさが不十分になると、影や物の輪郭がはっきりせず、認知機能が低下している脳はそれを誤って解釈します。カーテンの揺れが人に見えたり、服が掛かっているのを人が立っていると認識したりするのです。
妄想も夕暮れ時に強まります。「家族が自分の物を盗んだ」「誰かに見張られている」「毒を盛られている」といった被害妄想が現れることがあります。これは認知症による記憶障害と判断力の低下が背景にあります。
物を置いた場所を忘れて見つからないと、「誰かが盗んだ」と結論づけます。家族が心配して声をかけると、「監視されている」と感じます。認知機能の低下により、出来事を正しく解釈できなくなっているのです。
夕暮れ症候群の原因とメカニズム
夕暮れ症候群は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。認知機能の低下を土台に、生体リズムの乱れ、環境変化、疲労などが重なることで症状が現れます。
認知機能の低下と見当識障害の影響

夕暮れ症候群の根本的な原因は、認知症による認知機能の低下です。特に見当識障害(時間、場所、人がわからなくなる)が大きく影響します。
見当識障害により、夕方の環境変化に対応できなくなります。明るさが変わる、家族が帰宅する、テレビの内容が変わるといった夕方特有の変化を、脳が正しく処理できません。その結果、混乱と不安が増大するのです。
短期記憶障害も症状を悪化させます。数分前のことを忘れてしまうため、同じ質問を繰り返したり、同じ行動を何度もしたりします。家族が「さっき説明したでしょう」と言っても、本人にはその記憶がないのです。
判断力と理解力の低下により、状況を正しく判断できなくなります。自分がなぜここにいるのか、今何をすべきなのかがわからず、強い不安と焦燥感に駆られます。
生体リズムの乱れと体内時計の異常

夕暮れ症候群の重要な原因の一つが、生体リズム(体内時計)の乱れです。人間の体には約24時間周期のリズムがあり、朝の日光を浴びることでリセットされ、睡眠と覚醒が調節されています。
この体内時計を調整しているのが、脳の視交叉上核という部位です。認知症や加齢によりこの機能が衰えると、夕方の休息モードへの切り替えがうまくいかなくなります。体は休もうとしているのに、脳は覚醒したままという不一致が生じるのです。
メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌リズムの乱れも影響します。通常、メラトニンは夕方から夜にかけて分泌が増え、眠気を促します。しかし認知症ではこのリズムが崩れ、夜間に十分に分泌されず、不眠や夜間の覚醒を招きます。
昼夜逆転も生体リズムの乱れの結果です。夜間に眠れず、日中に眠ってしまうと、ますます体内時計が狂い、夕暮れ症候群が悪化するという悪循環に陥ります。
環境変化と疲労の蓄積が引き金となる

夕暮れ症候群の引き金となるのが、夕方特有の環境変化です。薄暗くなることで視覚的な刺激が不足し、見当識障害が悪化します。影が長く伸び、物の輪郭がぼやけることで、幻覚や混乱の原因となります。
夕方は家族の帰宅や夕食の準備など、家庭内の活動が活発になる時間帯です。音や人の動きが増えると、認知症の方にとっては刺激過多となり、不安や興奮を招きます。慣れない環境や予期しない出来事に対応できず、混乱するのです。
日中の疲労の蓄積も見逃せません。一日の活動で心身ともに疲れが溜まると、夕方にはエネルギーが枯渇し、認知機能がさらに低下します。疲れると判断力や自制心が弱まり、症状が表面化しやすくなるのです。
逆に、日中の刺激が不足している場合も問題です。一日中部屋にこもって何もしないでいると、昼と夜の区別がつかなくなり、体内リズムの乱れを招きます。適度な活動と休息のバランスが重要です。
薬の影響も考慮すべき要因です。向精神薬や睡眠薬の効果が切れる時間帯に症状が悪化したり、副作用でせん妄や錯乱が起きたりすることがあります。複数の薬を服用している場合、相互作用にも注意が必要です。
夕暮れ症候群への効果的な対処法と予防策
夕暮れ症候群は完全に防ぐことは難しいですが、適切な対処法と予防策により症状を緩和することは可能です。環境整備、生活リズムの調整、コミュニケーションの工夫により、本人も家族も穏やかに過ごせる時間を増やせます。
照明と環境を整えて不安を軽減する方法

夕暮れ症候群への最も効果的な対処法の一つが、照明の工夫です。夕方になる前、まだ明るいうちから室内の照明をつけ、部屋全体を明るく均一に保ちます。薄暗くなってから慌ててつけるのではなく、早めに点灯することがポイントです。
照明は明るさだけでなく、色温度も重要です。昼白色から温白色の明るい照明を使い、暗い影ができないようにします。間接照明だけでは不十分で、天井照明でしっかりと明るさを確保しましょう。
カーテンの閉め方にも配慮が必要です。夕暮れの薄暗い外の景色が見えると、不安を増幅させることがあります。早めにカーテンを閉め、外の暗さを意識させない工夫が有効です。
環境を整えることも大切です。家具の配置を変えたり、新しい物を置いたりすると混乱の原因になります。できるだけ慣れ親しんだ環境を維持し、安心感を提供しましょう。
規則正しい生活リズムと適度な活動

夕暮れ症候群を予防するには、規則正しい生活リズムの維持が極めて重要です。毎日同じ時間に起床し、食事を取り、就寝することで、体内時計が整い、症状が軽減されます。
特に重要なのが朝の過ごし方です。朝起きたらカーテンを開け、日光を浴びることで体内時計がリセットされます。朝食もしっかりと取り、一日の始まりを明確にします。
日中は適度な活動を取り入れましょう。散歩、体操、家事の手伝い、趣味の活動など、本人ができる範囲で体を動かし、頭を使うことが大切です。活動により適度な疲労感が生まれ、夜の睡眠の質が向上します。
ただし、過度な活動は逆効果です。疲れすぎると夕方の混乱が増します。本人の体力に合わせて、午前中に活動し、午後は休息を取るといったメリハリをつけることが効果的です。
昼寝は30分以内に抑えます。長時間の昼寝は夜間の不眠につながり、生体リズムを乱す原因となります。どうしても眠い場合は、午後2時までに短時間の仮眠を取る程度にとどめましょう。
本人の感情に寄り添うコミュニケーション

夕暮れ症候群への対応で最も大切なのが、本人の感情に寄り添うコミュニケーションです。症状が現れた時、否定したり説得したりするのは逆効果です。
「家に帰りたい」と訴えた時、「ここがあなたの家でしょう」と説明しても、本人には理解できません。それどころか、混乱と不安が深まります。「そうですか、家に帰りたいんですね」と、まずは気持ちを受け止めましょう。
その上で、「でも今日は遅いから、明日にしましょうか」「少し休んでから考えましょう」と、穏やかに別の提案をします。話題を変えたり、好きなことに誘ったりすることで、気持ちが切り替わることも多いです。
幻覚や妄想を訴えた時も、否定せず共感する姿勢が重要です。「そんなものは見えません」ではなく、「そうなんですね、怖かったですね」と気持ちを受け止めます。その上で、「でも今は大丈夫ですよ、私がそばにいますから」と安心感を与えます。
穏やかな声のトーン、ゆっくりとした話し方、優しい表情も大切です。急かしたり、大きな声を出したりすると、本人の不安が増します。時間に余裕を持ち、焦らず対応することを心がけましょう。
夕暮れ症候群で医療機関を受診すべきタイミング
夕暮れ症候群は認知症の周辺症状の一つですが、専門的な医療支援が必要な場合もあります。症状の程度や介護者の負担を考慮し、適切なタイミングで医療機関を受診することが大切です。
症状が悪化して介護に支障をきたす場合

以下のような状況になったら、医療機関への受診を検討すべきタイミングです。
医療機関を受診すべき状況
夕方から夜にかけての不安、興奮、混乱、攻撃的言動が頻繁に現れて、日常生活や介護に大きな支障をきたしている
幻覚や妄想による症状が強く、本人や周囲の安全が危ぶまれる恐れがある
症状が悪化して睡眠障害(夜間の不眠や昼夜逆転)が長期間続いている
家庭での対応が困難になってきて、介護者の身体的・精神的負担が非常に大きくなっている
症状の原因が不明で、急激な変化がある(感染症、薬の副作用、身体的な病気の可能性)
受診先は、認知症専門の医療機関や老年精神科、神経内科が適しています。かかりつけ医がいれば、まず相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらうのが一般的です。
医療機関では、症状の原因の評価(認知症の進行度、合併症の有無、薬剤の見直しなど)、症状緩和のための薬物療法や非薬物療法の提案、介護者への支援や情報提供、ケアプランの作成支援などが受けられます。
夕暮れ症候群は治るのか専門的治療の可能性

「夕暮れ症候群は治るのか」という質問は、多くの家族が抱く疑問です。結論から言うと、完全に「治る」というより、症状の管理・緩和を目指すというのが現実的な考え方です。
夕暮れ症候群は病名ではなく、認知症の周辺症状の現れ方の一つです。認知症そのものが進行性の疾患であるため、夕暮れ症候群も根本的に治すことは難しいのが実情です。
しかし、適切な治療とケアにより、症状を大幅に軽減することは可能です。薬物療法では、抗認知症薬や抗精神病薬、睡眠薬などが症状に応じて処方されます。ただし薬には副作用もあるため、医師と相談しながら慎重に調整します。
非薬物療法も重要です。光療法(朝に強い光を浴びる)、アロマセラピー、音楽療法、回想法などが症状緩和に効果があるとされています。環境調整や生活リズムの改善も、薬と同等かそれ以上の効果を持つことがあります。
50代での発症など、若年性認知症の場合でも、夕暮れ症候群は起こり得ます。若年性認知症では進行が早い傾向があるため、より早期からの専門的な支援が重要です。
うつ病との違いと正確な診断の重要性

夕暮れ症候群は、うつ病とは異なる症状です。混同されることがありますが、両者には明確な違いがあります。
夕暮れ症候群は、主に認知症の方に見られる夕方から夜間に症状が悪化する行動・心理症状です。不安や混乱、攻撃的な言動、帰宅願望などが現れ、日中は比較的落ち着いていることが多いという時間帯依存性が特徴です。
一方、うつ病は時間帯に限らず抑うつ気分や意欲低下が見られ、本人も症状を自覚することが多いです。朝方に症状が強く、夕方には少し楽になるという逆のパターンを示すこともあります。
ただし、高齢者の場合は認知症とうつ病が合併することもあります。「老人性うつ」と呼ばれる状態では、認知症様の症状も現れるため、専門医による正確な診断が不可欠です。
うつ病であれば、抗うつ薬や精神療法で改善可能なことが多いです。夕暮れ症候群と誤診されて適切な治療を受けられないと、症状が長引いてしまいます。逆に、夕暮れ症候群をうつ病と誤診し、不適切な薬物療法を行うことも問題です。

夕暮れ症候群は、認知症介護の中でも特に辛い症状の一つです。でも、原因を理解し適切に対処することで、穏やかな時間は増やせます。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けてくださいね。
夕暮れ症候群について:まとめ
夕暮れ症候群は、認知症の方に多く見られる、夕方から夜にかけて不安や混乱、落ち着きのなさ、攻撃的言動、帰宅願望、幻覚、妄想などが出現または悪化する症状です。日中は比較的穏やかでも、午後3時頃から症状が始まり、夕方5時から夜7時頃にピークを迎えます。
原因は、認知機能の低下を土台に、生体リズムの乱れ、環境変化、疲労の蓄積、薬の影響などが複合的に絡み合っています。特に見当識障害、体内時計の異常、夕暮れの薄暗さによる視覚的刺激の変化が、症状を引き起こす主要因です。
対処法としては、早めの照明点灯で部屋を明るく保つ、規則正しい生活リズムの維持、本人の感情に寄り添うコミュニケーションが効果的です。否定や説得は逆効果で、共感し安心感を与えることが大切です。
症状が悪化して介護に支障をきたす場合、幻覚や妄想が強い場合、睡眠障害が続く場合、介護者の負担が大きくなった場合は、医療機関への受診を検討しましょう。完全に治すことは難しいですが、適切な治療とケアにより症状を大幅に軽減することは可能です。
夕暮れ症候群との付き合い方を見つけることで、本人も家族も、より穏やかな日々を過ごせるようになります。焦らず、できることから少しずつ取り組んでいきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。