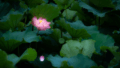「父が最近よくつまずくようになった」「母が夜中にトイレに行く時、転ばないか心配で仕方ない」「一度転んでから、本人が外出を怖がるようになってしまった」
高齢の家族が転倒するのではないかという不安は、多くの介護家族が抱える共通の悩みです。実際、令和3年の人口動態調査によると、65歳以上の高齢者の転倒による死亡者数は9,509人で、交通事故死者数の約4倍にものぼります。
転倒は骨折や頭部外傷を引き起こし、寝たきりや要介護状態につながる重大なリスクです。しかし原因を理解し、適切な対策を講じることで、転倒のリスクは確実に減らすことができます。
この記事では、高齢者の転倒の原因を内的要因(身体的原因)と外的要因(環境的原因)に分けて詳しく解説します。転倒がもたらす深刻な影響と統計データもお伝えし、家族ができる具体的な予防策をご紹介します。
高齢者の転倒の原因となる内的要因(身体的原因)
高齢者の転倒の原因は、大きく分けて内的要因と外的要因に分類されます。まずは身体の内側にある原因、つまり内的要因について詳しく見ていきましょう。加齢による身体機能の変化が、転倒リスクを高める根本的な要因となっています。
加齢による筋力低下とバランス感覚の衰え

高齢者の転倒の原因として最も基本的なものが、加齢に伴う筋力の低下です。特に下肢の筋力が衰えると、歩行時の安定性が失われ、ちょっとした段差でもつまずきやすくなります。
筋力低下は40代から始まり、60代以降は年間約1~2%のペースで筋肉量が減少します。太ももの筋肉(大腿四頭筋)やふくらはぎの筋肉が弱くなると、立ち上がる動作や階段の上り下りが困難になります。
さらに、バランス感覚や反射神経の低下も転倒リスクを高めます。若い頃は無意識に体のバランスを取れていたものが、加齢により平衡感覚を司る三半規管の機能が衰え、とっさの対応ができなくなるのです。
姿勢の変化も見逃せません。背中が丸くなる円背姿勢になると、重心が前方に移動し、バランスを崩しやすくなります。歩幅も狭くなり、すり足歩行になることで、わずかな段差でもつまずく原因となります。
視力・聴覚の低下と認知機能の衰えによる判断ミス

高齢者の転倒の原因として見落とされがちなのが、感覚器の衰えです。視力の低下により、段差や障害物の認識が不十分になります。特に白内障や緑内障などの眼疾患がある場合、視野が狭くなったり、明暗の変化への適応が遅れたりします。
夜間や薄暗い場所では視力がさらに低下するため、トイレに行く際や廊下を歩く際に転倒するリスクが高まります。距離感や奥行きの把握も難しくなり、階段の踏み外しにつながることもあります。
聴覚の低下も転倒リスクに関係します。周囲の音が聞こえにくくなると、背後から来る人や物に気づけず、驚いてバランスを崩すことがあります。また、認知機能の低下による判断ミスも深刻な原因です。
認知症や軽度認知障害(MCI)がある高齢者は、注意力や空間認知能力が低下し、危険な場所や状況の判断ができなくなります。複数の動作を同時に行うと混乱しやすく、歩きながら物を持つ、話しながら歩くといった動作で転倒しやすくなります。
疾患と薬剤の副作用が引き起こすふらつき

高齢者の転倒の原因として、基礎疾患の影響も無視できません。パーキンソン病は筋肉のこわばりや動作の緩慢さを引き起こし、歩行が不安定になります。変形性膝関節症や変形性股関節症は痛みにより歩行バランスを崩します。
起立性低血圧は、立ち上がった瞬間に血圧が急低下し、めまいやふらつきを起こします。不整脈や心疾患により脳への血流が一時的に減少すると、意識が遠のき転倒につながることもあります。
さらに見落とされがちなのが、薬剤の副作用です。睡眠薬や抗不安薬は眠気やふらつきを引き起こし、転倒リスクを高めます。抗精神病薬や抗てんかん薬もめまいや運動機能の低下をもたらすことがあります。
高齢者は複数の疾患を抱えていることが多く、多剤併用(ポリファーマシー)により副作用のリスクがさらに増大します。薬が5種類以上になると転倒リスクが顕著に高まるという報告もあります。
高齢者の転倒の原因となる外的要因(環境的原因)
内的要因と同じくらい重要なのが、生活環境に潜む転倒の原因です。外的要因は家族の工夫次第で改善できるものが多く、転倒予防に直結します。自宅内の危険エリアを理解し、環境整備を進めましょう。
自宅内の段差や照明不足などの危険エリア

高齢者の転倒の原因として最も多いのが、自宅内の段差です。玄関の上がり框、部屋の敷居、畳とフローリングの境目など、わずか数センチの段差でもつまずきの原因となります。
特に危険なのは、浴室、階段、廊下の3箇所です。浴室は濡れた床で滑りやすく、浴槽のまたぎ動作でバランスを崩しやすい環境です。階段は踏み外すと重大な怪我につながり、廊下は照明が不十分だと障害物に気づけません。
照明不足も見落とされがちな転倒の原因です。夜間のトイレ動線が暗いと、家具や壁にぶつかったり、段差が見えなかったりします。寝ぼけた状態での移動はさらに危険です。
床に置かれた障害物も問題です。電気コード、新聞や雑誌、スリッパ、ペットのおもちゃなど、床に散乱している物につまずく事故が後を絶ちません。カーペットの端が浮いていたり、マットがずれていたりすることも転倒リスクとなります。
履物や床の状態が転倒リスクを高める

高齢者の転倒の原因として意外に多いのが、足に合わない履物です。サイズが大きすぎるスリッパは脱げやすく、つまずきの原因となります。かかとのないサンダルも不安定で危険です。
靴底がすり減っていたり、滑りやすい素材だったりする靴も要注意です。特に雨の日や濡れた床では、滑りやすい靴底が重大な転倒事故を引き起こします。室内では素足や靴下だけで歩くことも滑りやすく危険です。
床の状態も転倒リスクに大きく影響します。フローリングにワックスをかけすぎると滑りやすくなります。タイル床やリノリウムの床も、濡れると非常に滑りやすい素材です。
浴室の床は特に注意が必要です。石鹸カスやシャンプーの泡が残っていると、滑って転倒する危険性が高まります。浴室マットや滑り止めシートの設置が効果的です。
慣れない環境での転倒リスクの増加

高齢者の転倒の原因として見落とされがちなのが、慣れない環境での転倒です。病院や介護施設、親戚の家など、普段と違う場所では空間認識が難しく、転倒リスクが高まります。
入院中や施設入所直後は特に注意が必要です。ベッドの高さが自宅と違う、トイレの位置がわからない、廊下の幅が狭い、といった環境の違いに戸惑い、転倒事故が起こりやすくなります。
施設では人手不足により、スタッフの目が届かない時間帯に転倒するケースも少なくありません。夜間のトイレ動線の確保や、ナースコールの使い方の徹底など、施設側の対策も重要です。
外出先での転倒も深刻です。不整地や坂道、舗装されていない道路、雨で濡れた路面など、屋外には転倒リスクが多数潜んでいます。天候や路面状況に応じた外出判断も大切です。
高齢者の転倒による深刻な影響と統計データ
高齢者の転倒は、単なる「転んだ」で済まされない深刻な問題です。統計データが示す転倒の実態を理解することで、予防の重要性をあらためて認識できます。
転倒による死亡者数は交通事故の約4倍

令和3年の人口動態調査によると、65歳以上の高齢者の転倒・転落・墜落による死亡者数は9,509人にのぼります。これは同年の交通事故死者数2,150人の約4倍という驚くべき数字です。
転倒は交通事故よりもはるかに身近で、日常的に起こり得る危険なのです。にもかかわらず、その深刻さは十分に認識されていません。「たかが転倒」と軽視することが、命を落とす結果につながっています。
2023年には約6万7,000人の高齢者が転倒事故で救急搬送されています。そのうち多くが自宅での転倒であり、最も安全であるはずの自宅が、最も危険な場所になっているという皮肉な現実があります。
転倒による死亡の多くは、転倒そのものではなく、転倒後の合併症によるものです。頭部外傷による頭蓋内出血、骨折後の肺炎、長期臥床による感染症などが命を奪います。
転倒後の骨折が要介護状態につながる現実

転倒による骨折は、高齢者を要介護状態に陥らせる主要因です。要介護になる原因の第3位は「骨折・転倒」で、全体の16.1%を占めています。
特に深刻なのが大腿骨骨折です。太ももの付け根の骨折は、手術や長期のリハビリが必要となり、元の歩行能力を取り戻せないことも少なくありません。骨折をきっかけに寝たきりになるケースは非常に多いのです。
背骨の圧迫骨折も見過ごせません。痛みにより動けなくなると、活動量が減少し、筋力低下と廃用症候群の悪循環に陥ります。一度寝たきりになると、回復は極めて困難です。
頭部外傷も重大です。高齢者は頭蓋骨が薄く、わずかな衝撃でも頭蓋内出血を起こすリスクがあります。特に抗凝固薬を服用している場合、出血のリスクはさらに高まります。
転倒が引き起こす悪循環と生活の質の低下

転倒による影響は身体的なものだけではありません。心理的な影響も深刻です。一度転倒を経験すると、「また転ぶのではないか」という恐怖が生まれます。
この転倒恐怖感(転倒後症候群)により、本人は外出を避け、活動量が減少します。すると筋力がさらに低下し、バランス能力も衰え、ますます転倒しやすくなるという悪循環に陥ります。
活動量の低下は、社会的孤立にもつながります。外出しなくなると、友人との交流が減り、趣味の活動もできなくなります。生きがいを失い、うつ状態に陥る高齢者も少なくありません。
統計によると、65歳以上の自宅に住む高齢者の約2割、施設入居者では約3割以上が、1年間に少なくとも1回は転倒を経験しています。転倒は決して珍しい出来事ではなく、誰にでも起こり得る身近な危険なのです。

転倒予防は介護の最重要課題の一つです。原因を理解し、適切な対策を講じることで、家族の健康寿命を守ることができます。専門家と相談しながら、できることから始めていきましょう。
高齢者の転倒の原因を理解して:まとめ
高齢者の転倒の原因は、内的要因(身体的原因)と外的要因(環境的原因)の複合的な要素によって引き起こされます。加齢による筋力低下、バランス感覚の衰え、視力や認知機能の低下といった内的要因と、自宅内の段差、照明不足、不適切な履物といった外的要因が絡み合い、転倒リスクを高めています。
転倒による影響は深刻です。65歳以上の転倒死亡者数は交通事故死者数の約4倍にのぼり、転倒後の骨折が要介護状態につながるケースは非常に多いです。転倒恐怖感による活動量低下が、さらなる筋力低下を招く悪循環も見逃せません。
しかし、原因を理解し適切な対策を講じることで、転倒リスクは確実に減らせます。環境整備、適切な履物の選択、筋力トレーニング、薬の見直し、定期的な視力検査など、できることから始めていきましょう。
転倒予防は、高齢者の健康寿命を延ばし、生活の質を維持するための最重要課題です。今日からできる小さな一歩が、大切な家族の命と生活を守ることにつながります。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。