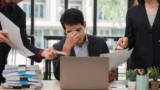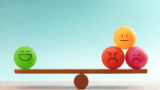「介護休業の93日を使い切ってしまった」
「まだ親の介護は続くのに、もう休めないのだろうか」
「これからどうやって仕事と介護を両立すればいいの」
介護休業を使い切った後、多くの人がこのような不安に直面します。

介護休業は対象家族1人につき通算93日までと決まっていますが、使い切った後も仕事と介護を両立する方法はいくつもあります。介護休暇、時短勤務、フレックスタイム、在宅勤務など、活用できる制度や働き方は残されているんです。
この記事では、介護休業を使い切った後に利用できる制度、給与や生活設計の考え方、仕事を続けるための具体的な工夫を詳しく解説します。介護休業後も働き続けるための道筋を一緒に見つけていきましょう。
介護休業を使い切った後に使える制度
介護休業を使い切っても、他の制度を組み合わせることで仕事と介護の両立は可能です。どのような選択肢があるか確認しましょう。
介護休暇で突発的な対応をカバー

介護休業を使い切った後も、介護休暇は別の制度として利用できます。
介護休暇は、対象家族1人につき年間5日まで、2人以上の場合は年間10日まで取得できる制度です。介護休業とは独立した制度のため、休業を使い切った後でも問題なく使えるんです。
介護休暇の大きな特徴は、時間単位での取得が可能な点です。1日単位だけでなく、1時間や2時間といった細かい単位で取得できるため、通院の付き添いや介護サービス事業者との打ち合わせなど、短時間の用事に柔軟に対応できます。
介護休暇は法律上無給ですが、会社によっては有給としているところもあります。就業規則を確認してみましょう。無給の場合でも、有給休暇が残っていれば併用することで収入への影響を抑えられます。
年間5日または10日という日数は決して多くありませんが、計画的に使うことで突発的な介護ニーズに対応できる貴重な制度です。介護休業を使い切った後の「保険」として活用しましょう。
時短勤務や所定外労働の制限を活用

介護をする労働者には、法律で認められた働き方の選択肢があります。
時短勤務制度は、介護のために所定労働時間を短縮できる制度です。1日あたり2時間を上限に、勤務時間を短縮できます。たとえば、9時から18時の勤務を9時から16時に変更することで、夕方の介護時間を確保できるんです。
また、所定外労働(残業)の制限を請求することもできます。会社に申し出ることで、残業を免除してもらえるため、定時に帰宅して介護に向き合う時間を作れます。
さらに、深夜業(午後10時から午前5時までの労働)の制限も請求できます。夜勤がある職種の場合、この制度を利用することで夜間の介護に対応しやすくなるでしょう。
法律で認められた働き方の選択肢
短時間勤務制度(1日最大2時間短縮)、所定外労働の制限(残業免除)、深夜業の制限(午後10時から午前5時の勤務免除)、これらは介護休業を使い切った後も利用できる制度です。
ただし、時短勤務を利用すると収入は減少します。1日2時間短縮すれば、単純計算で給与は約75%になるでしょう。収入減と介護時間確保のバランスを考えて、どの程度短縮するか判断する必要があるんです。
フレックスタイムや在宅勤務の交渉

法律で義務付けられている制度以外にも、会社と交渉して柔軟な働き方を実現できる可能性があります。
フレックスタイム制度は、始業時刻と終業時刻を自分で調整できる制度です。会社にこの制度がある場合、介護のニーズに合わせて出勤時間を変更できます。朝の介護が必要なら遅めに出勤し、夕方の介護が必要なら早めに退勤するといった調整が可能です。
在宅勤務(テレワーク)も、介護と仕事の両立に有効な働き方です。通勤時間がなくなることで、その分を介護に充てられます。また、自宅で仕事をしながら親の様子を見守ることもできるんです。
これらの働き方は法律で義務付けられているわけではないため、会社に制度がない場合もあります。しかし、介護休業を使い切った状況を説明し、仕事を続けるために柔軟な働き方が必要だと訴えることで、会社が個別に対応してくれる可能性もあるでしょう。
介護と仕事の両立がきつい時の解決策。無理せず続ける方法と支援制度
介護休業を使い切った後の給与と生活設計
介護休業を使い切った後、収入面や生活設計にどのような影響があるのか確認しておきましょう。
介護休業給付金は終了するが通常給与に戻る

介護休業期間中は、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。これは休業前賃金の約67%にあたる金額です。
介護休業を使い切って職場復帰すると、給付金の支給は終了しますが、通常の給与が再び支払われるようになります。収入は休業前の水準に戻るわけです。
ただし、時短勤務を利用する場合は別です。勤務時間が短くなった分、給与も減少します。1日2時間短縮すれば、給与は約75%程度になることを覚悟しておく必要があるでしょう。
介護休業給付金は、あくまで休業期間中の一時的な経済支援です。使い切った後は給付金に頼れないため、通常の給与で生活費と介護費用を賄う必要があるんです。家計の見直しや、介護サービスの利用計画の調整が必要になるでしょう。
介護サービス利用料と収入のバランス

介護休業を使い切った後は、介護サービスを活用しながら働くことが基本になります。
デイサービス、訪問介護、ショートステイなどの介護保険サービスは、自己負担額が発生します。サービスを多く利用すれば、その分費用もかさむでしょう。しかし、自分が仕事を続けられることで、長期的には収入を確保できるんです。
重要なのは、介護サービスの利用料と収入のバランスを考えることです。仕事を辞めて自分で介護をすれば、サービス利用料は節約できますが、収入がなくなります。一方、仕事を続けながらサービスを利用すれば、費用はかかりますが安定した収入を得られます。
また、高額介護サービス費制度により、月々の自己負担額には上限があります。所得に応じて月15,000円から44,400円程度の範囲で上限が設定されているため、サービスをたくさん利用しても自己負担額は一定額以上にはなりません。
別の家族の介護なら再度取得できるケース

介護休業を使い切ったと思っても、状況によっては再度取得できる場合があります。
介護休業の93日間という上限は、対象家族1人ごとに設定されています。たとえば、父親の介護で93日を使い切った後、母親が介護を必要とする状態になった場合、母親のために新たに93日間の介護休業を取得できるんです。
また、同じ家族であっても、介護の状況が大きく変わった場合は再取得できる可能性があります。たとえば、一度介護休業を取得して在宅介護の体制を整えたものの、その後容態が急変して入院し、退院後の介護体制を再度整える必要が生じた場合などです。
配偶者の両親など、複数の対象家族がいる場合は、それぞれの家族について介護休業を取得できます。義父の介護で93日、義母の介護で93日というように、別々にカウントされるわけです。
介護疲れしてる人にかける言葉の選び方。励ましの言葉とNGワード
使い切った後も仕事を続けるための工夫
介護休業を使い切った後も、工夫次第で仕事と介護の両立は可能です。具体的な方法を見ていきましょう。
介護サービスを最大限活用して負担を分散

介護休業を使い切った後は、自分一人で介護を抱え込まないことが何より重要です。
デイサービスを週3〜4回利用すれば、その間は仕事に集中できます。訪問介護を組み合わせることで、朝の身支度や夕方の食事準備などをプロに任せられるんです。また、月に数日ショートステイを利用すれば、自分の休息時間も確保できます。
介護保険サービスだけでなく、配食サービスや見守りサービス、移動支援サービスなど、様々な民間サービスも活用しましょう。費用はかかりますが、仕事を続けられることで得られる収入と、精神的な安定を考えれば十分に価値があるでしょう。
サービス活用の組み合わせ例
平日はデイサービスを週3回利用、デイサービスがない日は訪問介護で身支度や食事準備を依頼、夜間は見守りサービスを利用、月に1〜2回ショートステイで自分の休息時間を確保、配食サービスで食事の負担を軽減
ケアマネージャーと密に連携し、自分の就労状況を説明しながら、最適なサービスプランを組み立てましょう。「仕事を続けながら介護したい」という意思を明確に伝えることが大切です。
職場との継続的なコミュニケーション

介護休業を使い切った後も、職場との対話を続けることが重要です。
上司や人事部に、現在の介護状況や今後の見通しを定期的に報告しましょう。急な休みや遅刻・早退の可能性があることを理解してもらい、協力を得ることが必要です。
また、時短勤務や残業免除などの制度を利用したい場合は、早めに相談することが大切です。会社側も業務調整が必要になるため、突然の申し出では対応が難しくなるでしょう。

介護を理由に職場に迷惑をかけていると感じて、申し訳なく思う気持ちはよくわかります。でも、法律で認められた権利を使うことに遠慮は要りません。堂々と制度を活用し、必要な配慮を求めましょう。
同僚との関係も大切です。自分の状況を適度に共有し、理解と協力を得られるようにコミュニケーションを取りましょう。急な休みで同僚に負担をかけた時は、感謝の気持ちを伝えることも忘れずに。
家族間での役割分担の見直し

介護休業を使い切ったタイミングで、家族間での役割分担を見直すことも重要です。
介護が長期化する中、一人だけが全ての負担を背負い続けることは困難です。兄弟姉妹がいる場合は、改めて役割分担を話し合いましょう。直接的な介護は難しくても、経済的な支援や週末の手伝いなど、できることはあるはずです。
配偶者や子どもがいる場合も、家事や介護の一部を分担してもらうことを検討しましょう。一人で全てを抱え込むと、心身ともに疲弊してしまいます。
また、自分自身の健康管理も忘れてはいけません。介護疲れで体調を崩せば、仕事も介護も続けられなくなります。定期的に休息を取り、ストレスを発散する時間を確保することが、長期的に仕事と介護を両立するために必要なんです。
介護休業を使い切った後の選択肢。まとめ
介護休業を使い切った後も、仕事と介護の両立を続ける方法はいくつもあります。制度を理解し、適切に活用することが大切です。

使い切った後に活用できる制度としては、介護休暇(年間5日または10日)、時短勤務制度(1日最大2時間短縮)、所定外労働の制限(残業免除)、深夜業の制限があります。これらは介護休業とは独立した制度のため、休業を使い切った後でも利用できるんです。
給与面では、介護休業給付金の支給は終了しますが、通常の給与が再び支払われるようになります。時短勤務を利用する場合は収入が減少するため、介護サービスの利用料とのバランスを考える必要があるでしょう。ただし、長期的な視点では仕事を続ける方が経済的に安定します。
また、別の家族が介護を必要とする状態になった場合や、同じ家族でも介護の状況が大きく変化した場合は、再度介護休業を取得できる可能性があります。対象家族ごとに93日の枠があることを覚えておきましょう。
仕事を続けるための工夫としては、介護サービスを最大限活用すること、職場との継続的なコミュニケーションを保つこと、家族間での役割分担を見直すことが重要です。自分一人で全てを抱え込まず、周囲の協力を得ながら進めることが、持続可能な両立の鍵になります。
介護は長期戦です。
介護休業を使い切ったからといって、仕事を辞める必要はありません。
様々な制度や働き方を組み合わせ、自分に合った両立の形を見つけていくことが大切です。
一人で悩まず、職場や家族、専門家に相談しながら、無理のない範囲で仕事と介護を続けていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。