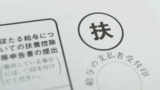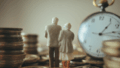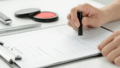「特別養護老人ホームの費用はどのくらいかかるの?」「年金だけで支払えるか心配」「自己負担を少しでも抑える方法はないの?」
特別養護老人ホーム(特養)への入居を検討している方にとって、費用の問題は最も重要な関心事の一つです。公的施設として比較的安価とはいえ、月々の自己負担額がどの程度になるのか、正確に把握しておくことは大切です。
この記事では、特養費用の自己負担について、居室タイプ別の詳細な料金から、知っておくべき減免制度まで、実践的な情報を総合的にお伝えします。年金収入での支払い可能性から費用を大幅に軽減する方法まで、あなたの経済状況に合った選択ができるよう、具体的なガイドをご提供します。
特養費用の自己負担額と基本的な仕組み
特養の費用構造を理解することで、自分にとって最適な選択ができるようになります。まずは基本的な仕組みから詳しく見ていきましょう。
特養費用を構成する3つの自己負担項目

特養費用の自己負担は、3つの主要項目で構成されています。これらを理解することで、月々の支払い額を正確に把握できます。
1. 介護サービス費は、日常的な介護や看護を受けるための費用です。要介護度と居室タイプによって金額が決まり、介護保険が適用されるため、所得に応じて1割~3割の自己負担となります。
2. 居住費(家賃相当)は、部屋を利用するための費用です。多床室(相部屋)からユニット型個室まで、選択する居室タイプによって大きく異なります。この費用は介護保険の対象外のため、全額自己負担となります。
3. 食費は、1日3食分の食事代です。施設外で食事をした日でも基本的に3食分を支払う必要があります。ただし、入院や外泊で複数日不在の場合は、事前申請により食費を停止できます。
要介護度別の自己負担額の違いと計算方法

介護サービス費は要介護度によって大きく変動します。要介護度が高いほど必要な介護が増えるため、自己負担額も増加します。
要介護3の場合(1割負担):
・従来型個室・多床室:約21,000円
・ユニット型個室・個室的多床室:約23,700円
要介護5の場合(1割負担):
・従来型個室・多床室:約25,000円
・ユニット型個室・個室的多床室:約27,800円
自己負担割合は所得によって決まります。一般的には1割負担ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります。65歳以上の単身世帯の場合、年間所得280万円以上で2割、340万円以上で3割負担となります。
計算例:要介護4で2割負担の場合
・基本料金:約24,000円(1割負担)
・実際の負担額:約48,000円(2割負担)
ユニット型と従来型の費用差と選び方のポイント

特養の居室には大きく分けて「従来型」と「ユニット型」があり、それぞれ費用とサービス内容が異なります。
従来型施設は、従来からある特養の形態です。多床室(4人部屋が主流)と個室があり、共同の食堂や浴室を利用します。費用を抑えたい方に適していますが、プライバシーの確保には限界があります。
ユニット型施設は、10人以下の小グループ(ユニット)で構成され、各ユニットに専用の食堂・居間があります。より家庭的な環境で生活できますが、費用は従来型より高くなります。
月額費用の差額(要介護3、1割負担の場合)
・従来型多床室:約8.9万円
・ユニット型個室:約12.6万円
・差額:約3.7万円
老人ホームの費用が払えない時は?早期相談と公的支援で解決する方法
居室タイプ別特養費用の自己負担額詳細比較
具体的な居室タイプごとの費用を詳しく解説します。あなたの予算と希望に合った選択ができるよう、実際の金額を中心にお伝えします。
多床室の特養費用自己負担額と年金での支払い可能性

多床室(相部屋)は、特養の中で最も費用を抑えられる選択肢です。年金収入のみで支払いを検討している方にとって、現実的な選択となることが多いです。
多床室の月額費用内訳(要介護3、1割負担の場合)
・居住費:27,450円
・食費:43,350円
・介護サービス費:21,960円
・合計:92,760円
要介護度別の多床室費用(1割負担)
・要介護1:88,470円
・要介護3:92,760円
・要介護5:96,930円
年金での支払い可能性を検討してみましょう。厚生年金の平均受給額は月額約14万円、国民年金のみの場合は約6.5万円です。厚生年金受給者であれば、多床室の費用は年金の範囲内で支払い可能ですが、国民年金のみの場合は不足が生じます。
ただし、減免制度を活用することで大幅な負担軽減が可能です。住民税非課税世帯で預貯金が一定額以下の場合、月額負担を5万円程度まで抑えることができる場合があります。
ユニット型個室の特養費用自己負担額とメリット

ユニット型個室は、プライバシーと快適性を重視する方におすすめの選択肢です。費用は高くなりますが、その分充実したサービスと環境を享受できます。
ユニット型個室の月額費用内訳(要介護3、1割負担の場合)
・居住費:61,980円
・食費:43,350円
・介護サービス費:24,450円
・合計:129,780円
要介護度別のユニット型個室費用(1割負担)
・要介護1:125,430円
・要介護3:129,780円
・要介護5:133,980円
ユニット型個室の特徴として、個人の生活リズムを尊重した介護が受けられること、家族との面会時間も他の利用者を気にする必要がないこと、個人の荷物を十分に置けることなどがあります。
費用対効果を考えると、月額約13万円で24時間の介護サービス、3食の食事、個室での生活が可能となります。有料老人ホームと比較すると、同等のサービスを大幅に安い費用で利用できます。
従来型個室の特養費用自己負担額と選択基準

従来型個室は、プライバシーを確保したいが費用も抑えたい方にとって、バランスの取れた選択肢となります。
従来型個室の月額費用内訳(要介護3、1割負担の場合)
・居住費:36,930円
・食費:43,350円
・介護サービス費:21,960円
・合計:102,240円
3つの居室タイプの費用比較(要介護3、1割負担)
・多床室:92,760円
・従来型個室:102,240円(多床室+9,480円)
・ユニット型個室:129,780円(多床室+37,020円)
従来型個室を選ぶべき基準:
・個人のプライバシーを確保したい
・ユニット型個室の費用は負担が大きい
・多床室では睡眠や休息に支障がある
・家族との面会時に配慮が必要
従来型個室は、多床室に月額約1万円プラスするだけで個室を利用できるため、コストパフォーマンスの高い選択肢と言えます。ただし、施設数が限られているため、希望する地域に従来型個室のある特養があるかの確認が必要です。
75歳以上の親を扶養に入れる別居時の手続き。条件と必要書類を解説
特養費用の自己負担を減免する制度と申請方法
特養の費用負担を大幅に軽減できる制度があります。これらの制度を活用することで、年金収入だけでも特養への入居が現実的になる場合があります。
負担限度額認定で特養費用自己負担を大幅軽減

負担限度額認定は、特養費用の自己負担を軽減する最も重要な制度です。条件を満たせば、居住費と食費の負担額に上限が設けられ、大幅な負担軽減が可能になります。
認定の条件
・世帯全員が住民税非課税
・本人および配偶者の預貯金が一定額以下
・年金収入等が基準額以下
第2段階の軽減例(年金収入80万円以下、単身)
・多床室居住費:27,450円 → 0円
・食費:43,350円 → 11,700円
・月額軽減額:59,100円
第3段階(1)の軽減例(年金収入80~120万円)
・ユニット型個室居住費:61,980円 → 26,400円
・食費:43,350円 → 19,500円
・月額軽減額:59,430円
申請に必要な書類:
・介護保険負担限度額認定申請書
・本人および配偶者の通帳コピー(過去2か月分)
・有価証券等の残高証明書
・同意書
社会福祉法人減免制度の活用と申請手続き

社会福祉法人減免制度は、負担限度額認定を受けても生活が困窮する方のための追加支援制度です。社会福祉法人が運営する特養で利用できます。
減免の対象と割合
・介護サービス費:1/4または1/2軽減
・食費:1/4または1/2軽減
・居住費:1/4または1/2軽減
利用条件
・世帯全員が住民税非課税
・年間収入が単身世帯で150万円以下
・預貯金が単身世帯で350万円以下
・居住用不動産以外の資産を所有していない
・介護保険料を滞納していない
具体的な軽減例(多床室、要介護3、1/2軽減の場合)
・介護サービス費:21,960円 → 10,980円
・月額軽減額:10,980円
申請手続きの流れ
1. 市区町村窓口で申請書を入手
2. 必要書類(収入証明、資産証明等)を準備
3. 申請書を提出し審査を受ける
4. 認定証の交付を受ける
5. 施設に認定証を提示して軽減適用
高額介護サービス費との併用で負担をさらに軽減

高額介護サービス費は、月の介護サービス費自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。特養利用時にも適用されます。
自己負担上限額(世帯単位、月額)
・住民税非課税世帯:24,600円
・課税所得380万円未満:44,400円
・課税所得380万円以上690万円未満:93,000円
・課税所得690万円以上:140,100円
特養での適用例(要介護5、2割負担の場合)
・介護サービス費:55,600円
・上限額(課税所得200万円):44,400円
・払い戻し額:11,200円
減免制度との併用効果
負担限度額認定や社会福祉法人減免制度と高額介護サービス費は併用可能です。複数の制度を活用することで、実質的な負担をさらに軽減できます。

各種減免制度は申請が必要です。制度を知らずに高い費用を払い続けることがないよう、入居前に必ず市区町村の窓口で相談しましょう。条件によっては月額10万円以上の軽減も可能です。
特養費用の自己負担を抑える実践的なまとめ
特養費用の自己負担について、居室タイプ別の詳細な料金と効果的な軽減方法をお伝えしました。適切な知識と準備により、経済的な負担を大幅に軽減しながら、質の高い介護サービスを受けることが可能です。
費用選択の基本戦略として、まず年金等の収入と預貯金額を正確に把握し、減免制度の適用可能性を確認することが重要です。多床室なら月額約9万円、従来型個室なら約10万円、ユニット型個室なら約13万円が基本的な自己負担額となります。
減免制度の活用により、条件を満たせば負担を大幅に軽減できます。負担限度額認定では居住費と食費を、社会福祉法人減免制度では介護サービス費も含めて軽減可能です。高額介護サービス費制度と併用することで、さらなる負担軽減が期待できます。
実践的な進め方として、まず市区町村の介護保険窓口で減免制度の詳細を確認し、必要書類を準備します。複数の特養を見学し、居室タイプと費用を比較検討することで、最適な選択ができるでしょう。
特養への入居は長期間の取り組みとなります。適切な費用計画と減免制度の活用により、安心して質の高い介護サービスを受けることができるでしょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。