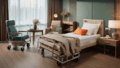「介護サービスの自己負担額が高くて家計を圧迫している」「毎月の介護費用をもう少し抑えられないかな」「高額介護サービス費って聞いたことはあるけど、どんな制度なの?」
介護が必要になると、介護保険を利用しても月々の自己負担額が予想以上に大きくなることがあります。特に複数のサービスを利用したり、施設に入所したりする場合、経済的な負担は深刻な問題となります。
そんな時に知っておきたいのが「高額介護サービス費」制度です。この記事では、高額介護サービス費の仕組みから具体的な計算方法、申請手続きまで、わかりやすく解説します。いくら戻るのかの計算例も交えて、あなたの介護費用負担を軽減するための実践的な情報をお伝えします。
高額介護サービス費制度の基本知識と仕組み
高額介護サービス費制度について、基本的な仕組みから詳しく理解していきましょう。この制度を正しく理解することで、介護費用の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
高額介護サービス費の対象となるサービスと条件

高額介護サービス費制度とは、1か月間の介護保険サービス自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超過分が後から払い戻される制度です。この制度により、介護費用の過度な負担から家計を守ることができます。
対象となるサービスは主に以下の3つのカテゴリーに分かれています:
居宅サービスでは、訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイなど、自宅で生活しながら利用するサービスが含まれます。これらのサービスの自己負担額が高額介護サービス費の対象となります。
施設サービスでは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの施設で受けるサービスが対象です。ただし、居住費や食費は対象外となる点に注意が必要です。
地域密着型サービスでは、認知症対応型デイサービスや小規模多機能型居宅介護などのサービスが含まれます。
自己負担上限額の区分と最新の限度額一覧

高額介護サービス費の自己負担上限額は、所得水準によって6つの段階に分かれています。2025年現在の最新の限度額は以下の通りです
第1段階(生活保護受給者など):月額15,000円(個人・世帯とも)
第2段階(住民税非課税で年金収入等80万円以下):個人15,000円、世帯24,600円
第3段階(住民税非課税の世帯):世帯24,600円
第4段階(課税所得380万円未満):世帯44,400円
第5段階(課税所得380万円以上690万円未満):世帯93,000円
第6段階(課税所得690万円以上):世帯140,100円
この区分は、令和3年8月の制度改正により、高所得者の負担限度額が見直されました。特に課税所得380万円以上の世帯では、負担限度額が段階的に引き上げられています。
対象外となる費用と注意すべきポイント

高額介護サービス費制度を利用する際に、見落としがちな注意点があります。これらを理解しておくことで、制度を効果的に活用できます。
対象外となる主な費用として、特定福祉用具(ポータブルトイレ、歩行器など)の購入費、住宅改修費(手すり設置、段差解消など)の自己負担分があります。これらは介護保険が適用されても、高額介護サービス費の計算には含まれません。
施設利用時の居住費・食費・日用品費も対象外です。例えば、特別養護老人ホームに入所した場合、介護サービス費は高額介護サービス費の対象となりますが、部屋代や食事代は別途自己負担となります。
また、自治体による対応の違いも注意が必要です。基準は全国一律ですが、申請手続きのサポート体制や給付までの期間は市町村によって異なります。お住まいの自治体の窓口で詳細を確認することをおすすめします。
親の介護でお金がない時の対処法。公的支援制度や負担軽減策はある?
高額介護サービス費でいくら戻るか具体的な計算方法
実際にどのくらいの金額が戻ってくるのか、具体的な計算方法を詳しく解説します。様々なケースを想定した計算例も交えて、わかりやすくお伝えします。
世帯単位と個人単位の違いと計算の仕組み

高額介護サービス費の計算方法は、世帯内の介護利用者数によって異なります。基本的な計算式は以下の通りです。
還付金額 = 実際の自己負担額 - 負担上限額
単身世帯での計算例を見てみましょう。住民税非課税で年金収入70万円の方(第2段階)の場合
・負担上限額:個人15,000円
・月の自己負担額:28,000円
・還付金額:13,000円(28,000円-15,000円)
複数人利用時の按分計算では、まず世帯全体の還付額を算出し、その後各人の負担額に応じて按分します。例えば、課税所得200万円の夫婦世帯(第4段階)で
・世帯の負担上限額:44,400円
・夫の自己負担額:30,000円
・妻の自己負担額:20,000円
・世帯の合計負担額:50,000円
・世帯の還付額:5,600円(50,000円-44,400円)
この5,600円を按分すると
・夫の還付額:3,360円(5,600円×30,000円÷50,000円)
・妻の還付額:2,240円(5,600円×20,000円÷50,000円)
施設入所時の高額介護サービス費計算例

施設入所時の高額介護サービス費について、具体的な例で計算してみましょう。
特別養護老人ホーム入所の場合
・要介護5、自己負担1割
・多床室利用、所得区分第4段階(世帯上限44,400円)
・月の介護サービス費自己負担額:26,000円
・居住費:25,200円(対象外)
・食費:43,350円(対象外)
この場合、介護サービス費26,000円は上限44,400円以下のため、高額介護サービス費の還付は発生しません。ただし、居住費・食費については、別途「介護保険負担限度額認定」により軽減される可能性があります。
介護老人保健施設の場合
・要介護4、自己負担2割
・個室利用、所得区分第5段階(世帯上限93,000円)
・月の介護サービス費自己負担額:98,000円
この場合の還付額は:5,000円(98,000円-93,000円)となります。
複数人利用時の按分計算と実際の還付額

同一世帯で複数人が介護サービスを利用している場合の、より詳細な計算例をご紹介します。
親子3世代同居のケース
・祖父(要介護3):デイサービス・訪問介護利用、月額32,000円
・祖母(要介護2):デイサービス利用、月額18,000円
・世帯の課税所得:250万円(第4段階、上限44,400円)
計算手順
1. 世帯の合計負担額:50,000円(32,000円+18,000円)
2. 世帯の還付額:5,600円(50,000円-44,400円)
3. 祖父の還付額:3,584円(5,600円×32,000円÷50,000円)
4. 祖母の還付額:2,016円(5,600円×18,000円÷50,000円)
夫婦で異なるサービスを利用するケース
・夫:ショートステイ・デイサービス利用、月額35,000円
・妻:訪問介護・訪問看護利用、月額28,000円
・世帯の課税所得:450万円(第5段階、上限93,000円)
この場合、世帯の合計負担額63,000円は上限93,000円以下のため、還付は発生しません。
65歳以上の介護保険料はいくら?地域差や軽減制度完全完全解説
高額介護サービス費の申請手続きといつ振り込まれるか
高額介護サービス費を確実に受け取るための申請手続きについて、詳しく解説します。申請のタイミングから振込時期まで、実践的な情報をお伝えします。
申請の流れと必要書類の準備方法

高額介護サービス費の申請は、自治体からの通知に基づいて行うのが一般的です。申請の流れを順を追って説明します。
ステップ1:自治体からの通知待ち
対象となる月の約3~4か月後に、お住まいの市区町村から「高額介護サービス費支給申請書」が郵送されます。この通知には、対象期間、支給予定額、申請期限などが記載されています。
ステップ2:必要書類の準備
・高額介護サービス費支給申請書(通知に同封)
・印鑑(シャチハタ不可)
・振込先口座の通帳またはキャッシュカード
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
ステップ3:申請書の提出
郵送または市区町村の介護保険窓口への持参により申請します。郵送の場合は、簡易書留での送付をおすすめします。
ステップ4:審査と決定通知
申請書受理後、自治体で審査が行われ、支給が決定すると「支給決定通知書」が送付されます。
いつ振り込まれるかのスケジュールと注意点

高額介護サービス費がいつ振り込まれるかは、多くの方が気になるポイントです。一般的なスケジュールをご説明します。
標準的な振込スケジュール:
・サービス利用月:1月
・自治体からの通知:4月頃
・申請書提出:4月~5月
・振込実行:5月~6月頃
つまり、実際にサービスを利用してから約4~6か月後に振り込まれるのが一般的です。ただし、自治体の処理状況や申請時期により、さらに時間がかかる場合もあります。
振込が遅れる要因として、以下のようなケースがあります。
・申請書の記載不備や必要書類の不足
・年度末や年度初めの処理遅延
・介護給付費の確定処理の遅れ
・金融機関の口座情報に誤りがある場合
振込確認の方法として、通帳記帳やインターネットバンキングで「コウガクカイゴ」「市区町村名」などの名義での入金を確認できます。
申請忘れを防ぐコツと期限管理の重要性

高額介護サービス費の申請には2年間の時効があります。この期限を過ぎると、たとえ対象者であっても還付を受けることができなくなります。
申請忘れを防ぐための実践的な方法をご紹介します。
家族での情報共有体制を作りましょう。介護を担当している方が一人で管理するのではなく、家族間で申請書の到着や手続き状況を共有することで、申請漏れを防げます。
カレンダーやスマートフォンのリマインダー機能を活用して、申請期限の管理を行います。申請書が届いたら、すぐに手続き予定日をスケジュールに入れることをおすすめします。
介護サービス利用料の家計簿をつけることで、高額になりそうな月を事前に把握できます。月末に自己負担額を集計し、上限額と比較する習慣をつけましょう。
ケアマネジャーとの連携も有効です。高額介護サービス費の対象になりそうな場合は、ケアマネジャーに相談し、申請手続きのサポートを受けることもできます。

申請書が届かない場合は、自治体に問い合わせることも大切です。住所変更の届け出漏れや、介護保険料の滞納により通知が停止されている場合があります。不明な点は遠慮なく相談しましょう。
【介護のお金の制度、他にも見落としていませんか?】
介護保険負担限度額認定で預貯金がばれる?知恵袋にもよくある疑問を解説
高額介護サービス費を最大限活用するための実践的なまとめ
高額介護サービス費制度は、介護費用の負担軽減に大変有効な制度です。しかし、制度を知らなかったり、申請を忘れたりすることで、本来受け取れるはずの還付金を逃してしまうケースも少なくありません。
制度活用のポイントとして、まず自分の世帯がどの所得区分に該当するかを正確に把握することが重要です。区分により負担上限額が大きく異なるため、正確な把握が還付額の予測につながります。
計算方法の理解により、毎月の自己負担額を把握し、上限額を超えそうな月を事前に予測できるようになります。特に施設利用や複数サービス利用時は、還付の可能性が高くなります。
申請手続きの確実な実行のため、家族間での情報共有とスケジュール管理を徹底しましょう。申請期限の2年を過ぎると還付を受けられなくなるため、期限管理は特に重要です。
介護は長期にわたる取り組みであり、経済的な負担も継続します。高額介護サービス費制度を適切に活用することで、その負担を軽減し、より安心して介護に取り組むことができるでしょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。