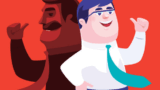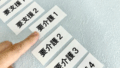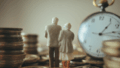「母の物忘れがひどくなって、要介護認定を申請したいけど認定されるか不安」「認定調査でどんなことを聞かれるの?うまく説明できるか心配」「軽い認定しか出ないかもしれない…適切な介護度をもらうにはどうしたらいい?」
要介護認定の申請を検討している方にとって、要介護認定の基準がどのようなものなのか、そして適切な認定を受けるためには何が必要なのかを知ることは非常に重要です。実際、準備不足により本来より軽い認定を受けてしまい、必要な介護サービスを十分に利用できない方も少なくありません。
しかし、要介護認定の基準は複雑で、多くの方が「どのように評価されるのかわからない」「何を準備すればいいのかわからない」と感じています。認定結果によって利用できるサービスや費用負担が大きく変わるため、事前に正しい知識を身につけることが大切なのです。
この記事では、要介護認定の基準について、判定の仕組みから具体的な準備方法まで、実際に適切な認定を受けるために必要な全ての情報をわかりやすく解説します。一人で不安を抱えず、正しい知識で適切なサービス利用につなげましょう。
要介護認定の基準となる5つの評価分野と時間基準
「母は食事はできるけど、お風呂は見守りが必要。これって要介護になるの?」このような疑問を持つ方のために、要介護認定の基準がどのように決められているのかを詳しく説明します。
要介護認定の基準時間による8段階の判定区分

要介護認定の基準は、「介護にどのくらいの時間がかかるか」を基準として判定されます。この「要介護認定等基準時間」により、8段階の要介護度に分類されます。
具体的な時間基準を見てみましょう:
- 非該当(自立):25分未満
- 要支援1:25分以上32分未満
- 要支援2:32分以上50分未満
- 要介護1:32分以上50分未満
- 要介護2:50分以上70分未満
- 要介護3:70分以上90分未満
- 要介護4:90分以上110分未満
- 要介護5:110分以上
「あれ?要支援2と要介護1が同じ時間なのはなぜ?」と思われる方も多いでしょう。実は、この2つは時間だけでなく、認知機能の状態と将来の見通しによって区別されます。
直接生活介助から医療関連行為まで5分野の詳細

要介護認定の基準では、介護に必要な時間を5つの分野に分けて計算します。「うちの場合はどの分野に当てはまるのかしら?」と思いながら読んでみてください。
1. 直接生活介助(一番重要な分野)
日常生活の基本的な動作への直接的な介助を評価します。多くの方が最も気になる分野です:
- 入浴介助:「一人で洗えなくて、背中を流してもらってる」
- 排泄介助:「トイレまでは行けるけど、拭き取りが不十分」
- 食事介助:「むせやすくて、見守りながらじゃないと心配」
- 更衣介助:「ボタンが留められなくて、毎朝手伝ってる」
2. 間接生活介助(思っている以上に重要)
「料理はできなくなったけど、これも評価されるの?」はい、しっかり評価されます:
- 掃除:「掃除機をかけるのがしんどくて、週1回お手伝いしてもらってる」
- 洗濯:「重い洗濯物を干すのは無理になった」
- 調理:「火の始末が心配で、ガスコンロは使わせられない」
- 買い物:「一人で買い物に行くと、同じものを何度も買ってくる」
3. 問題行動関連行為(認知症がある場合は重要)
「徘徊はないけど、夜中に何度も起きて困ってる」このような行動も評価対象です:
- 昼夜逆転:「夜中に起きて、朝まで眠らない日がある」
- 同じ話の繰り返し:「5分おきに同じことを聞いてくる」
- 物忘れによる失敗:「冷蔵庫に同じものがたくさん入ってる」
- 不安・抑うつ:「急に泣き出したり、怒り出したりする」
4. 機能訓練関連行為
リハビリや訓練が必要な場合の時間も含まれます:
- 歩行訓練:「転倒予防のため週2回リハビリに通ってる」
- 嚥下訓練:「むせやすいので、飲み込みの練習をしてる」
5. 医療関連行為
医療的なケアが必要な場合:
- 服薬管理:「薬を飲み忘れるので、毎回確認が必要」
- 血圧測定:「毎日の血圧チェックが欠かせない」
- 傷の処置:「褥瘡があって、毎日ガーゼ交換してる」
要介護認定の基準における認知症加算の仕組み

「父は身体的には元気だけど、認知症の症状があって手がかかる」このような場合に重要なのが認知症加算です。
認知症加算は、認知症による介護の困難さを適切に評価するための仕組みです。例えば、計算上は要介護1相当でも、認知症加算により要介護2や3に認定されることがあります。
認知症加算で評価される主な症状:
- 短期記憶の問題:「さっき言ったことを覚えてない」
- 見当識の問題:「今がいつか、ここがどこかわからない」
- 判断力の低下:「危険なことがわからない」
- 意思疎通の困難:「言いたいことが伝わらない」
認知症でデイサービスを嫌がる理由と対応法は?症状への理解が大切
要介護認定の基準に基づく一次判定と二次判定の流れ
「認定調査の後、どんなふうに要介護度が決まるの?」多くの方が気になるプロセスを、わかりやすく説明します。
コンピュータによる一次判定の要介護認定基準

認定調査が終わった後、まずコンピュータによる一次判定が行われます。「機械的な判定で大丈夫?」と心配される方もいますが、これは全国統一の基準で公平に判定するための重要なプロセスです。
一次判定では、認定調査の74項目の回答をコンピュータが分析し、要介護認定等基準時間を算出します。この74項目は以下のように分類されています:
- 身体機能・起居動作:12項目
- 生活機能:12項目
- 認知機能:9項目
- 精神・行動障害:15項目
- 社会生活への適応:6項目
介護認定審査会での二次判定プロセス

一次判定の後は、介護認定審査会での二次判定が行われます。ここでは、保健・医療・福祉の専門家が、一人ひとりの状況を詳しく検討します。
「どんな人が審査してるの?」審査会のメンバーは以下のような専門家です:
- 医師:病気や障害の医学的判断
- 看護師:医療的ケアの必要性を評価
- 社会福祉士:生活全般の支援ニーズを検討
- 介護福祉士:日常的な介護の視点で評価
- ケアマネジャー:実際のサービス利用の観点から判断
二次判定で特に重視されるのは
- 特記事項:調査員が記載した個別の状況
- 主治医意見書:医師からの専門的意見
- 一次判定との整合性:コンピュータ判定が適切かの確認
主治医意見書が要介護認定の基準に与える影響

「先生には何を伝えておけばいいの?」主治医意見書は、認定結果を大きく左右する重要な書類です。
主治医意見書で特に重要な項目は
1. 認知症の詳細評価
- 「物忘れがひどくて、薬を飲んだかどうか覚えてない」
- 「夜中に徘徊して、家族が眠れない」
- 「急に怒り出したり、泣き出したりする」
2. 身体機能の医学的評価
- 「関節の痛みで、立ち上がりに時間がかかる」
- 「脳梗塞の後遺症で、右半身に麻痺がある」
- 「呼吸器の病気で、階段の昇降が困難」
3. 今後の見通し
- 「症状は進行性で、今後悪化が予想される」
- 「リハビリにより改善の可能性がある」
- 「現状維持が精一杯の状況」

主治医への相談で大切なのは、日常の具体的な困りごとを詳しく伝えることです。「夜間にトイレに起きる回数」「転倒しそうになった回数」「薬を飲み忘れる頻度」など、数字で表せることは具体的に伝えましょう。
悪いケアマネージャーの見極め方と対処法とは?知っておきたい知識
要介護認定の基準を満たすための申請準備と対策
「認定調査で、うまく説明できるか心配」「普段より調子が良い時に調査を受けてしまったらどうしよう」このような不安を抱えている方のために、適切な認定を受けるための準備方法をお伝えします。
認定調査で要介護認定の基準を正確に伝える方法

認定調査は約60~90分で行われ、この短い時間で本人の状態を正確に伝える必要があります。「いつもできないことも、その時だけできてしまった」という話をよく聞きますが、適切な準備をすることで防ぐことができます。
調査前2週間から始める準備
1. 介護日記をつける
「母は何時頃、どんなことで困るのか」を記録しましょう
- 「朝7時:着替えのボタンが留められず、10分手伝った」
- 「昼12時:薬を飲んだか聞いたら『飲んでない』と答えたが、薬ケースは空だった」
- 「夜9時:トイレの場所がわからなくなり、案内した」
2. 困りごとチェックリストを作る
調査当日に伝え忘れがないよう、事前にリストアップ
- 転倒リスク:「先月、お風呂で滑って尻もちをついた」
- 火の始末:「コンロの火を消し忘れることが月に2回ある」
- 徘徊:「夜中に外に出ようとして、止めることがある」
- 服薬管理:「薬を2回飲んだり、飲み忘れたりする」
要介護認定の基準判定に影響する特記事項の重要性

「調査項目の答えだけで判定されるの?」いえ、特記事項も同じくらい重要です。特記事項とは、74項目では表現できない個別の状況を記載する部分で、要介護度の変更理由になることが多い重要な項目です。
特記事項に記載してもらうべき内容
1. 安全面での心配事
- 「階段の上り下りで手すりを掴み損ねそうになることがある」
- 「お風呂で立ち上がる時にふらつくため、必ず付き添っている」
- 「包丁を使わせるのが心配で、野菜は全部切って準備している」
2. 認知症に関する具体的エピソード
- 「夜中に『泥棒が入ってくる』と言って興奮することがある」
- 「デイサービスの迎えを『知らない人だから乗らない』と拒否する」
- 「お金を隠したことを忘れて『盗まれた』と大騒ぎする」
3. 介護者の負担状況
- 「夜間のトイレ介助で、家族が睡眠不足になっている」
- 「一人にしておけないため、買い物にも一緒に連れて行く」
- 「仕事を早退して病院に付き添うことが月に3回ある」
適切な要介護認定の基準判定を受けるための事前準備

「調査当日に何を準備すればいいの?」適切な認定を受けるために、調査当日までにできる準備をまとめました。
調査当日の環境づくり
1. 普段の状況を再現する
- 「いつも使っている杖や歩行器を手の届く場所に置く」
- 「お薬手帳や診察券を見えるところに準備する」
- 「転倒防止のために設置した手すりやマットを見てもらう」
2. 本人への事前説明
「張り切りすぎて、普段できないことをやってしまう」のを防ぐため:
- 「今日は介護保険を使うための調査だから、普段通りで大丈夫」
- 「できないことは、できないと正直に答えてね」
- 「家族も一緒にいるから、安心して」
3. 家族の役割分担
- 主介護者:日常の介護状況の詳細を説明
- その他の家族:客観的な観察結果を補足
- 本人:できるだけ自分の言葉で状況を説明
ケアマネージャーへの相談。できること・できないことの範囲は?
要介護認定の基準理解で適切なサービス利用を:まとめ
要介護認定の基準は複雑に感じられますが、5つの評価分野における介護の必要時間を基準とした明確な仕組みがあります。しかし、「基準を知っているだけ」では十分ではありません。大切なのは、その基準に沿って普段の介護状況を正確に伝えることです。
多くの方が「認定調査で緊張してうまく説明できなかった」「普段より調子が良い時に調査を受けてしまった」と後悔されています。しかし、事前の準備と正しい知識があれば、このような失敗は防ぐことができます。
適切な要介護認定を受けるために最も重要なのは、日常の介護状況を具体的な数字と事例で説明することです。介護日記をつけ、困りごとをリストアップし、主治医とも事前に相談しておくことで、本人の状態を正確に伝えることができます。
要介護認定は、適切な介護サービスを受けるための重要な入口です。正しい知識と十分な準備で、本人にとって本当に必要なサービスを受けられる認定結果を得て、安心した介護生活を送りましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。