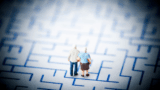「成年後見制度を利用したいけれど、ひどいという話をよく聞くので不安」「実際にどんな問題があるのか知りたい」「親の認知症が進行しているけれど、本当に成年後見制度を利用すべきか迷っている」
成年後見制度について調べていると、「ひどい制度だ」という声を目にすることがありませんか?実際に、家族の判断能力低下に直面した多くの方が、この制度の利用を検討する際に不安を感じています。
この記事では、成年後見制度がなぜひどいと言われるのか、その具体的な問題点と実際のトラブル事例を詳しく解説します。さらに、制度を利用する前に知っておくべき代替手段や、適切な判断をするためのポイントもお伝えします。制度の実態を正しく理解して、最適な選択ができるよう支援いたします。
成年後見制度がひどいと批判される深刻な問題点
成年後見制度は本来、認知症や知的障がいなどで判断能力が十分でない方を法的に保護するための重要な制度です。しかし、実際の運用において様々な問題が指摘され、利用者や家族から厳しい批判を受けています。
後見人による横領・不正の深刻な実態

成年後見制度の最も深刻な問題の一つが、後見人による不正行為です。令和4年の最高裁判所の調査によると、後見人による不正被害額は約7億5千万円にも及んでいます。
特に問題なのは、専門職である弁護士や司法書士、社会福祉士が後見人となった場合でも不正が発生していることです。「専門家だから安心」という期待が裏切られるケースが続出しており、制度への信頼を大きく損ねています。
不正の手口として最も多いのは、本人名義の預金口座からの無断出金です。後見人が本人の財産管理権限を悪用し、高額な報酬を不当に引き出したり、個人的な用途で資金を流用したりする事例が報告されています。
家族の希望が無視される選任システム

成年後見制度のもう一つの大きな問題は、家族の希望する後見人が選任されないケースが多いことです。家庭裁判所が後見人を選任する際、家族が「息子に後見人になってもらいたい」と希望しても、第三者の専門職が選ばれることがあります。
これは、家庭裁判所が「客観性や専門性を重視する」という方針によるものですが、家族にとっては「なぜ身内ではダメなのか」という不満が生まれます。特に、長年介護をしてきた家族が後見人になれないことで、介護方針や財産管理について意見の相違が生じることがあります。
さらに、後見監督人が別途選任される場合もあり、家族の関与はますます制限されます。本人を最もよく知っている家族の意見が制度運用に反映されにくい構造となっています。
一度始めると止められない制約の重大性

成年後見制度の最も致命的な問題は、一度制度の利用を開始すると、原則として本人が亡くなるまで終了できないことです。「お試し」や「一時的な利用」という概念が存在しないため、家族は長期間にわたって制約を受け続けることになります。
この制約により、家族の状況が変化しても制度を柔軟に見直すことができません。例えば、本人の判断能力が一時的に回復した場合や、家族の介護体制が整った場合でも、後見制度は継続されます。
また、後見人と家族の関係が悪化した場合でも、後見人の変更は非常に困難です。家庭裁判所が後見人の解任を認めるのは、明らかな不正や職務怠慢が証明された場合に限られており、「性格が合わない」「方針が違う」程度の理由では変更できません。
成年後見制度の具体的な問題点とトラブル事例
成年後見制度の問題は理論的なものだけでなく、実際の利用者が直面する具体的なトラブルとして現れています。ここでは、実際に発生している問題事例を詳しく見ていきましょう。
財産管理の自由度が極端に制限される現実

成年後見制度では、本人の財産保護を優先するため、積極的な資産活用が大幅に制限されます。これにより、家族が本人のために良かれと思う支出でも、家庭裁判所の許可なしには実行できません。
具体的には、以下のような制限があります:
高額な医療機器の購入や住宅のバリアフリー工事など、本人の生活向上のための支出でも、一定金額を超える場合は家庭裁判所の許可が必要です。許可申請には時間がかかるため、緊急性のある対応が困難になります。
生前贈与や相続対策は原則として認められません。節税効果のある資産移転や、家族への経済的支援も制限されるため、税負担が増大したり、家族の生活に影響を与えたりする可能性があります。
不動産の処分や活用にも厳しい制限があります。本人が住んでいない実家を売却したい場合でも、家庭裁判所が「本人の利益に反する」と判断すれば許可されません。
専門職後見人とのコミュニケーション問題

専門職が後見人に選任された場合、家族とのコミュニケーション不足が深刻な問題となることがあります。
多くの専門職後見人は複数の案件を抱えているため、個別の案件に十分な時間を割けない現実があります。家族からの相談や要望に対する対応が遅れたり、本人の状況変化への配慮が不足したりすることがあります。
また、専門職後見人は法律や財産管理の専門家ではありますが、医療や介護の専門知識は限定的です。本人の健康状態や介護ニーズを十分に理解せずに判断を行うことで、家族との間に認識の相違が生じることがあります。
さらに、定期的な面談や報告が形式的になりがちで、本人や家族の真のニーズを汲み取れない場合があります。これにより、制度は機能していても、本人の生活の質向上には繋がらない状況が生まれます。
家族間での対立を招く制度運用の課題

成年後見制度の利用により、かえって家族間の関係が悪化するケースも少なくありません。
制度利用前は協力していた家族が、後見人選任後に「誰が主導権を握るか」「財産管理の方針をどうするか」といった点で対立することがあります。特に、一人の家族が後見人に選任された場合、他の家族から「独占的に財産を管理している」と疑われることがあります。
第三者の専門職が後見人になった場合でも、家族間での意見調整が困難になります。それぞれの家族が後見人に異なる要望を伝えることで、後見人が板挟みになったり、家族間の調整役としての負担が増加したりします。
また、後見人の判断や方針について家族が疑問を持っても、十分な説明を受けられない場合があります。これにより、家族間での不信や対立が深まることがあります。
成年後見制度の費用負担と経済的デメリット
成年後見制度の利用を躊躇する大きな理由の一つが、高額な費用負担です。制度利用にかかる具体的な費用とその負担感について詳しく解説します。
申立て時にかかる高額な初期費用

成年後見制度の申立てには、様々な費用が発生します。
家庭裁判所への提出に必要な基本費用として、申立手数料(収入印紙)約800円、登記手数料(収入印紙)約2,600円、郵便切手代3,270〜4,210円程度が必要です。
さらに、医師による診断書作成費用が数千円〜1万円程度、戸籍謄本・住民票等の取得費用が数百円〜数千円程度かかります。
最も高額なのは、家庭裁判所で鑑定が必要と判断された場合の鑑定費用で、10万円〜20万円程度が必要になります。この鑑定は申立て後に裁判所が判断するため、事前に費用を正確に把握することが困難です。
専門家に申立て手続きを依頼する場合は、弁護士・司法書士への報酬として15万円〜30万円程度が追加で必要です。
継続的な報酬負担で家計を圧迫する現実

成年後見制度の最も大きな経済的負担は、後見人への継続的な報酬支払いです。
後見人報酬は家庭裁判所が管理財産額や業務内容に基づいて決定しますが、一般的には月額2万円〜6万円程度となっています。年間に換算すると24万円〜72万円という高額な費用負担となります。
特に問題なのは、この報酬が本人の死亡まで継続することです。認知症の進行は一般的に10年以上の長期間にわたるため、総額では数百万円から一千万円を超える報酬を支払うことになります。
報酬は本人の財産から支払われますが、本人の収入が年金のみの場合、年金収入を上回る報酬負担となることもあります。この場合、本人の財産を取り崩して報酬を支払うことになり、最終的に本人の生活費や介護費用が不足する可能性があります。
費用対効果から見た成年後見制度の課題

成年後見制度の費用対効果を考える際、実際に提供されるサービス内容と費用負担を比較検討することが重要です。
月額3万円の報酬を支払う場合、年間36万円という金額で受けられるサービスが、実際にその価値に見合っているかを検討する必要があります。多くの場合、後見人の主な業務は財産管理と定期的な報告書作成であり、日常的な介護支援や生活サポートは含まれません。
同じ費用で民間の財産管理サービスや家事支援サービスを利用した方が、より具体的で実用的なサポートを受けられる場合があります。また、家族信託などの代替制度を利用すれば、継続的な費用負担なしに財産管理の仕組みを構築できることもあります。
さらに、後見人報酬は税務上の控除対象にならない場合が多いため、実質的な負担はより重くなります。医療費控除や介護費用控除のような税制上の優遇措置も限定的です。
成年後見制度を避ける代替手段と対策
成年後見制度の問題点を理解した上で、より柔軟で費用対効果の高い代替手段を検討することが重要です。ここでは、成年後見制度以外の選択肢とその活用方法を詳しく解説します。
家族信託で成年後見制度の問題を回避する方法

家族信託は、成年後見制度の多くの問題を解決できる優れた代替手段です。
家族信託では、本人(委託者)が判断能力のあるうちに、信頼できる家族(受託者)に財産管理を託します。成年後見制度とは異なり、家庭裁判所の関与なしに、家族の判断で柔軟な財産管理が可能です。
家族信託の最大のメリットは、継続的な費用負担がないことです。信託契約時に専門家への報酬(通常30万円〜100万円程度)を支払えば、その後の管理費用はかかりません。10年以上継続する可能性のある成年後見制度と比較すると、大幅なコスト削減が可能です。
また、家族信託では生前贈与や相続対策も可能で、積極的な資産活用ができます。本人の意思を尊重した柔軟な財産管理により、家族の実情に合わせた運用が実現できます。
任意後見制度と専門家選びの重要性

任意後見制度は、法定後見(成年後見制度)の問題点を解決できる有効な選択肢です。
任意後見制度では、本人が判断能力のあるうちに、将来の後見人を自分で選んで契約を結びます。これにより、「家族の希望が無視される」という法定後見の問題を回避できます。
任意後見契約では、後見人に与える権限や報酬額も事前に取り決めることができます。法定後見のように家庭裁判所が一方的に決定するのではなく、本人と後見人予定者が合意した内容で契約できるため、より納得のいく制度利用が可能です。
ただし、任意後見制度でも後見監督人の選任や継続的な費用負担は発生するため、家族信託と比較して検討することが重要です。
専門家選びにおいては、単に資格や経験だけでなく、家族の価値観や本人の生活スタイルを理解してくれる専門家を選ぶことが重要です。複数の専門家から話を聞き、説明の分かりやすさや対応の丁寧さを比較検討しましょう。
事前相談で制度利用の失敗を防ぐ方法

制度選択で失敗しないためには、十分な事前相談と情報収集が不可欠です。
まず、複数の専門家(弁護士、司法書士、税理士、ファイナンシャルプランナーなど)から意見を聞くことが重要です。専門家によって推奨する制度や手法が異なることがあるため、多角的な視点から検討する必要があります。
家族全体での話し合いも欠かせません。制度利用後に家族間で対立が生じないよう、事前に全員の考えや希望を整理し、合意形成を図ることが重要です。
また、本人の判断能力がある段階での相談が理想的です。本人の意思を確認し、本人が納得できる方法を選択することで、後悔のない制度利用が可能になります。
専門家相談で適切な判断を行う重要性
成年後見制度やその代替手段について適切な判断をするためには、専門家のサポートを受けることが非常に重要です。特に、複雑な制度の比較検討や、家族の具体的な状況に応じた最適解の発見は、専門的な知識と経験が必要です。
制度選択における専門的アドバイスの価値

成年後見制度、家族信託、任意後見制度など、選択肢が多様化する中で、どの制度が最適なのかを判断することは非常に困難です。
専門家は、家族の状況、本人の財産内容、将来の見通しなどを総合的に分析し、最も適した制度を提案できます。また、複数の制度を組み合わせた活用方法や、制度利用のタイミングについても的確なアドバイスを提供できます。
特に重要なのは、将来起こりうるリスクを事前に把握し、対策を講じることです。専門家の経験に基づいたリスク分析により、後悔のない制度選択が可能になります。
家族の不安を解消する相談サポート

成年後見制度に関する悩みは、法律的な問題だけでなく、家族の感情的な負担も大きく関わっています。「親の財産をどう守ればよいか」「家族間の関係を悪化させずに解決したい」「本人の意思を尊重したい」といった複雑な想いを抱えている方が多いでしょう。
このような状況では、制度に詳しいだけでなく、介護や家族関係の問題にも精通した専門相談員のサポートが有効です。法的な観点だけでなく、家族の心情に寄り添った解決策を一緒に考えることができます。
専門相談員は、各家族の状況に応じた最適な制度選択についてアドバイスを提供し、制度利用前の準備から制度選択後のフォローアップまで、継続的なサポートを行います。
初回20分の無料相談を利用して、現在の状況を整理し、最適な制度選択に向けた方向性を見つけることができます。夜の時間帯にも対応しているため、日中は忙しい方でも利用しやすくなっています。
「成年後見制度を利用すべきか迷っている」「他の選択肢についても詳しく知りたい」「家族で合意できる解決策を見つけたい」といった場合は、専門家のサポートを受けることで、より安心できる判断ができるでしょう。
まとめ
成年後見制度がひどいと言われる理由には、後見人による不正、家族の希望が反映されない選任システム、高額な費用負担、一度始めると止められない制約など、深刻な構造的問題があります。
制度利用により、財産管理の自由度が極端に制限され、専門職後見人とのコミュニケーション不足や家族間対立が生じることもあります。特に、継続的な報酬負担は数百万円から一千万円を超える可能性があり、費用対効果の面で疑問視されています。
しかし、家族信託や任意後見制度などの代替手段を活用することで、成年後見制度の問題点を回避しながら、より柔軟で費用対効果の高い財産管理が可能です。
成年後見制度は確かに課題の多い制度ですが、適切な知識と準備があれば、より良い選択肢を見つけることができます。一人で悩まず、専門家のサポートを受けながら、家族にとって最適な解決策を見つけてください。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。