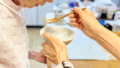「親を老人ホームに入れたのに、なかなか会いに行けない」「面会に行こうと思うと、なぜか足が重くなる」「会いに行けない自分は冷たい人間なのだろうか」
老人ホームに家族が来ない、または行きたくないと感じる状況は、実は多くの家族が抱えている悩みです。施設のスタッフから「もっと面会に来てあげて」と言われて辛い思いをしたり、親に「もっと来てほしい」と言われて罪悪感を抱いたりする方もいるでしょう。
しかし、老人ホームに家族が来ない理由には、単なる無関心ではない様々な事情があります。この記事では、家族が来ない理由、行きたくない気持ちの正体、そして罪悪感との向き合い方について詳しく解説します。
老人ホームに頻繁に行けないからといって、親を愛していないわけではありません。それぞれの事情や心の葛藤を理解することが、自分自身を許す第一歩になります。
老人ホームに家族が来ない現実的な理由
老人ホームに家族が来ない理由は、決して愛情がないからではありません。様々な現実的な事情が、面会を困難にしています。
距離と交通の問題

遠方に住んでいる場合、物理的に面会が困難になります。親の住んでいた地域の施設に入所したものの、子供は別の都道府県に住んでいるケースも珍しくありません。
片道数時間かかる距離だと、往復だけで丸一日を費やすことになります。交通費も往復で数万円かかることもあり、頻繁に訪問するのは経済的にも時間的にも大きな負担です。
また、交通の便が悪い場所にある施設の場合、車がないと訪問できないこともあります。免許を持っていない、車を運転できない家族にとって、これは大きな障壁となるでしょう。
仕事や子育ての忙しさ

多くの家族は、仕事や子育てで日々忙しく、面会の時間を確保するのが難しい状況にあります。平日は仕事で帰りが遅く、週末は子供の習い事や家事に追われる。
特に働き盛りの40代〜50代の世代は、仕事の責任も重く、簡単に休みを取れない立場の方も多いでしょう。子育て中の場合は、小さい子供を連れての面会も大変です。
面会に行きたい気持ちはあっても、スケジュール調整が難しく、気づけば何ヶ月も経ってしまうこともあります。罪悪感を感じながらも、日々の生活に追われて面会に行けない自分を責めてしまう方も少なくありません。
時間の確保が難しい理由
・平日は仕事で帰宅が遅い
・週末は家事や子供の世話で忙しい
・急な仕事や予定変更で訪問できなくなる
・面会時間が限られている
・長時間の面会は体力的にも精神的にも負担
経済的な負担と家族自身の健康問題

老人ホームの費用に加えて、頻繁な面会による交通費も家計を圧迫します。施設費用だけでも月々十数万円かかる中、往復の交通費が毎回数千円から数万円では、経済的に続けられません。
また、家族自身の健康問題も面会を困難にする大きな要因です。持病があったり、体調が優れなかったりすると、長時間の移動や面会は体力的に厳しいものがあります。
感染症が流行している時期は、親に感染させるリスクを考えて面会を控える判断をする場合もあるでしょう。これは親を思っての決断であり、決して無関心からではありません。
親の介護でお金がない時の対処法。公的支援制度や負担軽減策はある?
老人ホームに行きたくない心理的な理由
物理的な理由だけでなく、心理的な要因も老人ホームへの足を遠のかせます。この気持ちを理解することが、自分を許すための第一歩です。
親の変化を見るのがつらい

老人ホームに行きたくない最も大きな理由の一つが、親の変化を見るのがつらいという感情です。認知機能の低下、体力の衰え、以前とは違う親の姿を見ることは、心に大きな痛みをもたらします。
自分のことを忘れている親、会話が成り立たない親、寝たきりになってしまった親。元気だった頃の姿を知っているからこそ、現在の変わり果てた姿を受け入れるのが難しいのです。
面会に行くたびに、親の衰えを目の当たりにすることで、自分自身も深く傷つきます。「こんなに辛いなら、行かない方がいいのではないか」と考えてしまう気持ちは、決して親を愛していないからではありません。
会話やコミュニケーションへの不安

久しぶりの面会では、何を話せばよいのかわからない不安を感じる方も多いでしょう。特に認知症の親の場合、会話が成り立たなかったり、同じことを何度も繰り返されたりすることがあります。
「家に帰りたい」「ここはどこ?」と繰り返し尋ねられたり、「誰も来てくれない」と責められたりすると、どう対応すればいいのか戸惑ってしまいます。親を悲しませたくない、傷つけたくないという思いが、かえって面会へのハードルを上げてしまうのです。
また、施設のスタッフや他の入居者の目も気になります。「もっと頻繁に来てあげて」というプレッシャーを感じたり、他の家族と比較されているような気持ちになったりすることもあるでしょう。
介護疲れと心の距離

家族が老人ホームに来ない背景には、介護疲れや心の距離があることも少なくありません。長年の在宅介護で心身ともに疲弊し、施設入所後も親と関わることに抵抗を感じてしまうケースがあります。
在宅介護中に親から暴言を吐かれたり、拒否されたりした経験がある場合、施設入所後も心の傷が癒えていないこともあります。「やっと解放された」という安堵感と、「会いに行くべき」という義務感の間で揺れ動く気持ち。
また、親子関係が元々良好でなかった場合、施設入所を機に距離を置きたいと感じることもあるでしょう。これは決して冷たいことではなく、自分を守るための自然な反応です。
【老人ホームに行けない罪悪感、一人で抱えていませんか?】
老人ホームに行きたくない罪悪感との向き合い方
老人ホームに行けない、行きたくないと感じることへの罪悪感。この感情とどう向き合うかが、自分自身を許すためのポイントです。
罪悪感の正体を理解する

「会いに行けない自分は冷たい人間なのではないか」という罪悪感。この感情の正体を理解することが、自分を許す第一歩になります。
罪悪感や孤独感をどう整理するかは、制度の問題ではなく心の問題です。「親の面倒は子供が見るべき」という社会的な価値観や、「もっと親孝行すべきだった」という後悔の念が、罪悪感を増幅させています。
しかし、頻繁に面会に行けないからといって、親を愛していないわけではありません。むしろ、罪悪感を感じるということは、親のことを大切に思っている証拠なのです。
現実的な面会頻度を設定する

罪悪感を軽減するには、自分にとって現実的な面会頻度を設定することが大切です。「毎週行かなければ」という理想ではなく、自分の生活状況に合わせた頻度を考えましょう。
距離が近い場合は月2〜4回、遠方の場合は月1回や2ヶ月に1回など、無理のない計画を立てます。大切なのは、継続できる頻度であることです。
面会に行けない期間は、電話やビデオ通話で顔を見せる方法もあります。施設のスタッフに親の様子を聞いたり、手紙を送ったりすることも、親との繋がりを保つ方法の一つです。
面会以外の関わり方
・週に1回は電話で話す
・月に1回はビデオ通話をする
・季節ごとに手紙や写真を送る
・施設のスタッフから様子を聞く
・誕生日や記念日には特別な贈り物
専門家に相談して心を整理する

「会いに行けない自分は冷たいのでは?」と悩む方が多いです。こうした誰にも言えない家族の葛藤を、一人で抱え込む必要はありません。
施設のソーシャルワーカーや地域包括支援センターの相談員も、あなたの悩みを理解してくれる心強い味方です。専門家に話すことで、気持ちが整理され、自分を許せるようになることもあります。

老人ホームに頻繁に行けないことで自分を責める必要はありません。できる範囲で関わり続けることが大切ですよ。
在宅介護で家族が感じるストレスの解消法は?改善方法を徹底解説
施設スタッフからの呼び出しにどう対応するか
老人ホームから家族への呼び出しや連絡があった場合、どう対応すべきか悩む方もいるでしょう。
呼び出しが必要な場合とは

施設から家族に連絡が来るのは、緊急性の高い場合や重要な決断が必要な場合です。親の体調が急変した、転倒して怪我をした、入院が必要になったなど、医療的な対応が必要な時には必ず連絡があります。
また、親が強く家族を求めている場合や、精神的に不安定な状態が続いている場合も、施設から連絡が来ることがあります。ただし、これらの場合は緊急性が低いため、すぐに駆けつける必要はありません。
契約内容の確認や費用の支払いに関する事務的な連絡もあります。これらは面会に行かなくても、電話や郵送で対応できることがほとんどです。
「もっと来てほしい」と言われた時の対処法

施設のスタッフや親から「もっと来てほしい」と言われると、罪悪感や プレッシャーを強く感じるでしょう。しかし、この言葉の背景を理解することが大切です。
親が「もっと来てほしい」と言うのは、寂しさや不安の表れです。しかし、それは必ずしも頻繁な面会を求めているわけではありません。むしろ、「自分のことを忘れていないか」「まだ愛されているか」という確認を求めているのです。
この場合、面会の頻度を増やすよりも、面会時の質を高めることが重要です。短時間でも、しっかりと向き合い、話を聞き、愛情を伝えることで、親の不安は和らぎます。
施設任せでも問題ないケース

専門家に任せているので家族が頻繁に来なくても問題ない、と感じるケースもあります。施設のスタッフが適切にケアしている場合、過度に介入する必要はありません。
親が施設での生活に慣れ、他の入居者やスタッフと良好な関係を築いている場合、家族の過度な干渉がかえってマイナスになることもあります。親が安心して生活できているなら、それが最も大切なことです。
ただし、完全に任せきりにするのではなく、定期的に施設スタッフと連絡を取り、親の様子を確認することは重要です。親の生活状況や健康状態について把握しておくことで、必要な時に適切な判断ができます。
老人ホームに家族が来ない状況を改善する方法
もし老人ホームに行きたいけれど行けない状況を改善したいと思うなら、具体的な方法を試してみましょう。
面会のハードルを下げる工夫

面会に行くハードルを下げることで、気軽に訪問できるようになります。まずは短時間の面会から始めてみましょう。30分や1時間程度の短い時間でも、親は喜んでくれます。
仕事帰りに立ち寄る、買い物のついでに顔を出すなど、「ついで」の形にすることで心理的な負担が軽くなります。わざわざ時間を作って行くと考えると重く感じますが、日常の動線の中に組み込むと気軽に訪問できるでしょう。
また、兄弟姉妹や他の家族と交代で面会に行く方法も効果的です。一人で全ての責任を負う必要はありません。家族で協力し合うことで、それぞれの負担を軽減できます。
面会を気軽にする工夫
・短時間の面会から始める
・「ついで」に訪問する習慣をつける
・家族で交代制にする
・面会時間を柔軟に設定する
・事前に電話してから行く
オンライン面会の活用

遠方に住んでいる場合や頻繁に訪問できない場合は、ビデオ通話などのオンライン面会を活用しましょう。多くの施設では、タブレットやパソコンを使ったオンライン面会に対応しています。
顔を見ながら話すことで、親の表情や様子を確認でき、電話よりも安心感があります。孫の顔を見せることもでき、親にとって楽しみな時間になるでしょう。
週に1回はビデオ通話、月に1回は実際に訪問するなど、オンラインと対面を組み合わせることで、無理なく親との繋がりを保つことができます。
施設のイベントに参加する

施設で開催されるイベントや行事に参加することも、親との関わりを持つ良い機会です。誕生会、季節のイベント、運動会などに参加することで、親も喜び、他の入居者やスタッフとも交流できます。
イベントという目的があることで、面会に行きやすくなる効果もあります。普段の面会では何を話せばいいか悩む方も、イベントの場では自然に会話が弾むでしょう。
施設の様子や親の生活環境を知ることもできるため、安心材料にもなります。親が楽しそうに過ごしている姿を見ることで、罪悪感も軽減されるはずです。
親の介護をしたくないと感じる場合の対処法。現実的な選択をするには
老人ホームに家族が来ない状況と向き合う:まとめ
老人ホームに家族が来ない理由は様々です。距離や交通の問題、仕事や子育ての忙しさ、経済的な負担や健康問題など、現実的な事情がある場合も多いでしょう。
また、親の変化を見るのがつらい、会話やコミュニケーションへの不安、介護疲れや心の距離など、心理的な理由で老人ホームに行きたくないと感じることもあります。これらの感情は決して珍しいものではなく、多くの家族が抱えている悩みです。
大切なのは、罪悪感の正体を理解し、自分を許すことです。頻繁に面会に行けないからといって、親を愛していないわけではありません。現実的な面会頻度を設定し、できる範囲で関わり続けることが重要です。
「会いに行けない自分は冷たいのでは?」と悩んでいるなら、一人で抱え込まず専門家に相談しましょう。罪悪感や孤独感をどう整理するかは制度の問題ではなく心の問題です。誰にも言えない家族の葛藤を、安心して話せる場所があります。
老人ホームに行けない、行きたくないという気持ちを抱えながらも、親を思う心は変わりません。自分を責めるのではなく、今できる形で親との繋がりを大切にしていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。