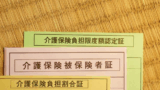「夫が75歳になって後期高齢者医療制度に移ったけれど、私の健康保険はどうなるの?」「保険料は今までより高くなるのかしら」「何か手続きが必要なのかわからなくて不安」
夫が75歳を迎えると、自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。このとき、まだ75歳未満の妻の健康保険がどうなるのか、戸惑う方は少なくありません。
特に今まで夫婦で同じ保険に入っていた場合、保険が分かれることで保険料の負担がどう変わるのか、手続きに漏れはないか、心配になりますよね。
この記事では、夫が後期高齢者医療制度、妻が国民健康保険という状況での保険料の計算方法、必要な手続き、見落としがちな注意点まで、わかりやすく解説します。制度を正しく理解して、無駄な負担を避け、安心して生活を続けられるようサポートいたします。
夫が後期高齢者医療制度に移行すると妻の国民健康保険はどうなるか
夫が75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険から自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。このとき、まだ75歳未満の妻の保険がどうなるかは、夫婦がどの保険に加入していたかによって異なります。
夫婦で保険が分かれる基本的な仕組み

夫婦がともに国民健康保険に加入していた場合、夫が75歳になると自動的に後期高齢者医療制度へ移行しますが、妻は引き続き国民健康保険に加入したままとなります。
この場合、特別な脱退手続きや新たな加入手続きは基本的に不要です。市区町村が自動的に処理を行い、夫の後期高齢者医療保険料と妻の国民健康保険料がそれぞれ別々に計算されるようになります。
一方、夫が会社の健康保険(社会保険)に加入していて、妻がその被扶養者だった場合は状況が異なります。夫が75歳で後期高齢者医療制度に移行すると、妻は自動的に被扶養者の資格を失います。
世帯主への保険料請求と支払い方法

保険料の請求と支払いについては、少し複雑に感じるかもしれません。しかし、仕組みを理解すれば心配することはありません。
夫が75歳になる前は、夫婦両方の国民健康保険料が世帯主宛に一括して請求されていました。夫が75歳になった月からは、夫の後期高齢者医療保険料は夫個人に、妻の国民健康保険料は引き続き世帯主(多くの場合は夫)にそれぞれ別々に請求されます。
つまり、世帯主である夫のもとには、自分の後期高齢者医療保険料の通知と、妻の国民健康保険料の通知の2通が届くことになります。それぞれ納付先や納付方法が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
夫の後期高齢者医療保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)で納付します。ただし、年金額が年間18万円未満の場合や、介護保険料と合わせた保険料が年金額の半分を超える場合などは、納付書や口座振替(普通徴収)での納付となります。
一方、妻の国民健康保険料は、納付書または口座振替で納付するのが一般的です。自治体によっては、クレジットカード払いやスマートフォン決済に対応している場合もあります。
【保険や年金の手続き、漏れがないか不安ではありませんか?】
社会保険の被扶養者だった妻の手続き

夫が会社の健康保険に加入していて、妻がその被扶養者だった場合、夫の75歳到達により妻は被扶養者の資格を失います。この場合、妻自身で新たな健康保険に加入する手続きが必要となります。
最も一般的なのは、国民健康保険への加入です。手続きは市区町村の窓口で行い、資格喪失日から14日以内に届け出る必要があります。
手続きに必要な書類は以下の通りです。
国民健康保険加入に必要な書類
・健康保険資格喪失証明書(夫の勤務先の健康保険組合から発行)
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑(自治体によっては不要)
もう一つの選択肢として、子どもなど別の家族が会社の健康保険に加入している場合、その被扶養者になることも可能です。この場合、子どもの勤務先で手続きを行います。
被扶養者になれる条件は、年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、扶養者の年収の半分未満であることなどが一般的です。ただし、健康保険組合によって基準が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
【最新版】介護保険料はいつから支払う?年齢別の納付方法も解説
夫が後期高齢者で妻が国民健康保険になる場合の保険料計算
夫が後期高齢者医療制度に移行し、妻が国民健康保険に加入する場合、それぞれの保険料がどのように計算されるのか、具体的に見ていきましょう。
それぞれの保険料算定方法の違い

後期高齢者医療保険料と国民健康保険料では、計算方法が大きく異なります。それぞれの仕組みを理解しておくと、保険料の通知が来たときに戸惑うことがありません。
夫の後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額の合計で計算されます。均等割額はすべての加入者に一律でかかる金額で、所得割額は前年の所得に応じて計算される金額です。
具体的な計算式は以下の通りです。
後期高齢者医療保険料 = 均等割額 + 所得割額
所得割額 = (前年の総所得金額等 – 基礎控除43万円) × 所得割率
均等割額と所得割率は都道府県ごとに異なり、毎年改定されます。また、所得が少ない方には均等割額の軽減措置があり、世帯の所得に応じて7割・5割・2割の軽減が適用されることがあります。
一方、妻の国民健康保険料は、自治体によって計算方法が異なりますが、一般的には医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳以上の場合)のそれぞれについて、所得割・均等割・平等割を組み合わせて計算します。
旧被扶養者への軽減措置と減免制度

夫が会社の健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことで、被扶養者だった妻が新たに国民健康保険に加入する場合、「旧被扶養者」として特別な軽減措置を受けられます。
旧被扶養者とは、65歳から74歳までの方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった方の被扶養者だった方を指します。この場合、国民健康保険加入時に以下の軽減が適用されます。
旧被扶養者への軽減措置
・所得割:全額免除
・均等割:5割軽減
・平等割:5割軽減(世帯に他の国保加入者がいない場合)
・適用期間:資格取得日の属する月以後2年間
この軽減措置により、今まで保険料負担がなかった妻の国民健康保険料も、急激な負担増を避けることができます。ただし、軽減措置を受けるには申請が必要な自治体もあるため、必ず窓口で確認しましょう。
また、世帯の所得が基準以下の場合には、旧被扶養者でなくても均等割・平等割の軽減を受けられます。世帯の総所得金額に応じて、7割・5割・2割の軽減が適用されます。
さらに、収入が大幅に減少した場合や災害に遭った場合など、特別な事情がある場合には、保険料の減免を申請できることもあります。生活が困窮している場合は、早めに自治体の窓口に相談することをおすすめします。

軽減措置は自動的に適用される場合もありますが、申請が必要なケースもあります。知らずに損をしないよう、必ず確認しましょうね。
世帯分離した場合の保険料への影響

夫婦の保険料負担を軽減する方法として、「世帯分離」を検討する方もいらっしゃいます。世帯分離とは、同じ住所に住んでいながら、住民票上の世帯を別々にすることです。
世帯分離をすると、それぞれの世帯の所得に応じて保険料が計算されるため、所得の低い妻の国民健康保険料が軽減される可能性があります。
例えば、夫に年金収入があり、妻の収入が少ない場合、同じ世帯だと世帯全体の所得で計算されますが、世帯分離すると妻の低所得に応じた軽減措置を受けやすくなります。
ただし、世帯分離にはデメリットもあります。
世帯分離は、保険料だけでなく、介護サービスの自己負担額や税金など、様々な面に影響を及ぼします。安易に判断せず、自治体の窓口や専門家に相談してから決めることをおすすめします。
親の介護でお金がない時の対処法。公的支援制度や負担軽減策はある?
夫が後期高齢者で妻が国民健康保険の場合の見落としがちな注意点
制度の基本はわかっても、実際の手続きや納付の段階で見落としがちなポイントがあります。ここでは、特に注意すべき点を詳しく解説します。
軽減措置の申請忘れと期限切れ

旧被扶養者への軽減措置は、自動的に適用される自治体と申請が必要な自治体があります。申請が必要な場合、申請を忘れると通常の保険料が請求されてしまいます。
夫が後期高齢者医療制度に移行したタイミングで、妻が旧被扶養者に該当するかどうか、また軽減措置の申請が必要かどうかを必ず確認しましょう。多くの自治体では、国民健康保険の加入手続きと同時に軽減措置の申請も行えます。
また、旧被扶養者の軽減措置には2年間という期限があります。2年経過後は通常の保険料計算に戻るため、保険料が大きく上がる可能性があります。この時期が近づいたら、家計への影響を考えて準備しておくことが大切です。
納付方法の変化と口座管理

夫が後期高齢者医療制度に移行すると、保険料の納付方法が変わります。これまで一つの保険料を支払っていたのが、2つの異なる保険料を別々に納付することになるため、管理が複雑になります。
夫の後期高齢者医療保険料は、原則として年金からの天引きです。ただし、天引きが始まるまでには数ヶ月かかることがあり、それまでは納付書での支払いとなります。
一方、妻の国民健康保険料は、口座振替または納付書での支払いが一般的です。それぞれ納付期限が異なるため、納付漏れや二重払いに注意が必要です。
特に注意したいのが、口座振替を利用している場合です。夫の後期高齢者医療保険料が年金天引きになった後も、以前の口座から国民健康保険料(妻の分)が引き落とされ続けます。口座残高が不足していると、妻の保険料が未納となってしまいます。
医療費と介護費用が重なる時期の家計管理

夫が75歳を迎える時期は、医療費や介護費用の負担が増えやすいタイミングでもあります。保険料の変化だけでなく、医療費・介護費用も含めた総合的な家計管理が重要になります。
後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合が所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。夫の所得状況によっては、これまで3割負担だった医療費が1割負担になることもあり、医療費の実質負担が減る場合もあります。
一方で、加齢に伴い通院回数や薬の種類が増えることも多く、医療費の総額は増加傾向にあります。また、介護が必要になった場合には、介護保険サービスの自己負担も加わります。
保険料の変化だけに注目するのではなく、医療費・介護費用も含めた総合的な支出を把握することが大切です。特に以下のような状況では、家計への影響が大きくなります。
医療費・介護費用が増えやすい状況
・慢性疾患で定期的な通院・服薬が必要な場合
・入院や手術を控えている場合
・介護認定を受けており、介護サービスを利用している場合
・夫婦ともに医療機関を受診する頻度が高い場合
医療費と介護費用の自己負担が高額になった場合には、高額療養費制度や高額介護サービス費制度、さらには高額医療・高額介護合算療養費制度などの負担軽減制度を利用できます。
これらの制度は申請が必要な場合が多いため、医療費や介護費用の領収書は必ず保管しておきましょう。また、制度の詳細や申請方法がわからない場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談することをおすすめします。
夫が後期高齢者で妻が国民健康保険の場合の保険制度:まとめ
夫が75歳で後期高齢者医療制度に移行すると、妻は引き続き国民健康保険に加入するか、新たに加入手続きが必要になります。保険が分かれることで保険料の計算や納付方法が変わるため、基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。
特に、社会保険の被扶養者だった妻は、国民健康保険への加入手続きが必要となり、旧被扶養者としての軽減措置を受けられる可能性があります。ただし、申請が必要な場合もあるため、必ず自治体の窓口で確認しましょう。
介護保険料はいつまで払う?支払い期間と免除・軽減制度を詳しく解説
保険料の納付は、夫の後期高齢者医療保険料と妻の国民健康保険料が別々に請求されるため、納付漏れや口座残高不足に注意が必要です。それぞれの納付期限を把握し、計画的に管理することが重要になります。
また、この時期は医療費や介護費用の負担も増えやすいタイミングです。保険料だけでなく、医療費・介護費用も含めた総合的な家計管理を心がけ、高額療養費制度などの負担軽減制度を積極的に活用しましょう。
夫婦で支え合いながら、健康で充実した生活を送れるよう、制度を上手に活用していきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。