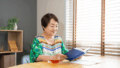「おじいちゃんが定年後、何もせずに家にいることが多くて心配」「趣味を持ってほしいけれど、何を勧めればいいかわからない」「趣味がないことで、体力や気力が落ちていかないか不安」
大切なおじいちゃんが毎日テレビを見ているだけの生活を送っている姿を見て、心配になっている方は多いのではないでしょうか。実際に、60代の約4人に1人が「自分は無趣味だ」と感じているという調査結果があり、特に男性は定年後に趣味を見つけることに苦労する傾向があります。
この記事では、おじいちゃんに趣味がない理由と背景、後期高齢者の男性に人気の趣味ランキングTOP10、趣味を見つけるための具体的な方法、家族が注意すべきサポートのポイント、そして専門家への相談が必要な場合について詳しく解説します。おじいちゃん本人が楽しめる活動を見つけるための実践的なヒントをお届けします。
おじいちゃんに趣味がない理由と背景を理解する
なぜおじいちゃんに趣味がないのか、その背景を理解することが、適切なサポートの第一歩になります。
定年後の環境変化で趣味から遠ざかる男性の特徴

多くの男性は、定年退職を機に大きな環境変化を経験します。この変化が、趣味から遠ざかる原因になることがあります。
会社での人間関係が中心だった生活から、突然その関係がなくなることで、社会とのつながりが急激に減少します。毎日通勤していた場所がなくなり、話す相手もいなくなると、何をすればいいかわからなくなってしまうのです。
また、若い頃は釣りやゴルフなどの趣味を楽しんでいても、長年仕事が忙しく趣味から離れていたため、再開するきっかけがつかめないという方も多くいます。「今さら始めるのも気が引ける」「以前の仲間はもういない」といった思いが、趣味の再開を妨げてしまいます。
さらに、定年後は「やるべきこと」がなくなり、目的意識を失うことも大きな要因です。仕事という明確な目標があった生活から、自由な時間が増えても何をすればいいかわからず、結局テレビを見て過ごす日々になってしまうのです。
体力低下や健康面の不安が新しいことを妨げる

年齢とともに、体力の低下や健康面の不安が、新しいことを始めるハードルになります。
若い頃は楽しんでいたゴルフやテニスも、膝や腰が痛くなり続けられなくなった。長距離の運転が辛くなり、釣りに行く機会が減った。このように、身体的な制約により、これまでの趣味を続けられなくなることがあります。
また、「新しいことを始めて、もし体を壊したらどうしよう」という不安から、何も始められない方もいます。転倒のリスクや、急に体調が悪くなることへの恐れが、行動を妨げてしまうのです。
視力や聴力の低下も大きな要因です。新聞の文字が読みにくくなり読書をやめた、テレビの音が聞こえにくくなり映画鑑賞を楽しめなくなったといったケースは珍しくありません。これらは治療や補助具で改善できる場合も多いのですが、「年だから仕方ない」とあきらめてしまうことがあります。
仕事中心の生活で趣味を持つ習慣がなかった

現在のシニア男性の多くは、仕事中心の生活を送ってきた世代です。このことが、趣味がない大きな理由になっています。
「仕事が趣味」という言葉通り、仕事に全力を注ぎ、家族を支えることに人生を捧げてきた方が多くいます。休日も接待ゴルフや仕事関係の付き合いで埋まり、純粋に自分が楽しむための趣味を持つ時間がなかったのです。
また、趣味は「お金と時間の無駄」と考え、仕事と家族のために我慢してきた方もいます。そのため、いざ定年を迎えて自由な時間ができても、何を楽しめばいいかわからないという状態になってしまいます。
さらに、「今さら新しいことを始めても上手くできない」「若い人に混じるのは恥ずかしい」といった思いから、一歩を踏み出せない方も多くいます。プライドが邪魔をして、初心者として学ぶことに抵抗を感じてしまうのです。
親の介護でメンタルがやられる原因と対処法。心の健康を守るには?
おじいちゃんに人気の趣味ランキングTOP10
実際に後期高齢者の男性に人気がある趣味を、ランキング形式でご紹介します。それぞれの趣味の特徴や始め方も解説しますので、参考にしてください。
1位から5位:ガーデニング・釣り・写真など手軽に始められる趣味

【第1位】園芸・ガーデニング・庭いじり
多くの住環境で可能で、自然に触れながら適度な運動になることから、最も人気の高い趣味となっています。
特徴:植物の成長を見守る楽しみがあり、毎日の水やりや手入れが生活のリズムを作ります。土に触れることでストレス軽減効果があり、自分で育てた野菜を収穫する達成感も得られます。
始め方:まずは育てやすいトマトやハーブなど、プランター栽培から始めるのがおすすめです。ホームセンターで苗と土、プランターを購入すれば、すぐに始められます。
【第2位】映画鑑賞(映画館以外)
動画配信サービスの普及により、自宅で気軽に映画を楽しめるようになりました。
特徴:体力を使わず、座って楽しめるため、体力に自信がない方でも無理なく続けられます。さまざまなジャンルの作品に触れることで、知的刺激を受けることができます。
始め方:NETFLIXやAmazon Prime Videoなどの動画配信サービスに登録します。家族にサポートしてもらいながら、使い方を覚えると良いでしょう。
【第3位】釣り
自然の中でリラックスでき、釣った魚を料理する楽しみもある人気の趣味です。
特徴:静かな環境で集中することで、ストレス解消になります。釣り仲間との交流も楽しめ、社会とのつながりを保てます。釣果を家族に喜んでもらえることも励みになります。
始め方:近くの釣り堀や管理釣り場から始めると、道具のレンタルもでき、初心者でも楽しめます。海釣りや川釣りは、経験者と一緒に行くと安全です。
【第4位】日曜大工
体を動かしながらものづくりの楽しさを味わえる、男性に特に人気の趣味です。
特徴:棚や椅子など、実用的なものを作れる達成感があります。頭と手を使うことで脳の活性化にもなり、作品を家族に喜んでもらえることもやりがいになります。
始め方:まずは簡単な小物入れや本立てなどから挑戦します。ホームセンターのDIY教室に参加すると、基本的な技術を学べます。
【第5位】音楽鑑賞(CD・スマートフォン)
音楽配信サービスの普及により、気軽に多くの音楽を楽しめるようになりました。
特徴:リラックス効果があり、ストレス解消になります。若い頃に好きだった音楽を聴くことで、当時の思い出を振り返る楽しみもあります。
始め方:手持ちのCDから始めるのが簡単です。スマートフォンやタブレットで音楽配信サービスを利用すると、さらに多くの曲を楽しめます。
6位から10位:ウォーキング・囲碁将棋・グラウンドゴルフなど

【第6位】写真撮影・プリント
思い出づくりや外出の楽しみとして根強い人気があります。
特徴:散歩のついでに風景や花を撮影することで、外出する目的ができます。撮った写真を家族に見せたり、SNSに投稿したりすることで、コミュニケーションのきっかけにもなります。
始め方:スマートフォンのカメラから始めるのが手軽です。慣れてきたら、コンパクトデジタルカメラを購入すると、より本格的に楽しめます。
【第7位】スポーツ観戦
仲間との交流や非日常感を味わえる娯楽として人気です。
特徴:好きなチームや選手を応援することで、生活に張り合いが生まれます。試合の話題で家族や友人と盛り上がることもできます。
始め方:テレビで好きなスポーツを観戦することから始めます。興味が深まったら、スタジアムや球場に実際に足を運んでみるのも良いでしょう。
【第8位】囲碁・将棋
脳トレや社交の場として楽しめる、伝統的な趣味です。
特徴:先を読む力や深く考える力を使うため、認知症予防に効果的です。地域の公民館やクラブに通うことで、仲間との交流も楽しめます。
始め方:地域の囲碁・将棋クラブに参加するのが一番です。オンラインゲームやアプリでも対局できますが、対面での交流がより楽しめます。
【第9位】ウォーキング・散歩
健康維持と外出促進、気分転換に最適な手軽な運動です。
特徴:特別な道具が不要で、今日からでも始められます。季節の変化を感じながら歩くことで、気分転換になり、適度な運動で体力維持にも役立ちます。
始め方:まずは家の周りを10分歩くことから始めます。歩数計やスマートフォンのアプリで歩数を記録すると、達成感が得られます。
【第10位】グラウンドゴルフ
ルールが簡単で、体力に不安がある方でも無理なく楽しめるスポーツです。
特徴:ゴルフに似ていますが、より手軽で危険も少なく、高齢者に適しています。地域のチームに参加することで、仲間との交流も楽しめます。
始め方:地域のグラウンドゴルフ協会や公民館で、初心者向けの体験会が開催されています。道具も安価でレンタルもあるため、気軽に始められます。
男性に特に人気の日曜大工や音楽鑑賞の魅力

ランキング上位の趣味の中でも、男性に特に人気が高いのが日曜大工と音楽鑑賞です。その魅力を詳しく見ていきましょう。
日曜大工が男性に人気の理由
ものづくりの達成感を味わえることが最大の魅力です。計画を立て、材料を選び、実際に手を動かして作品を完成させる過程は、仕事と似た充実感を得られます。
また、作ったものが家族の役に立つことで、「自分はまだ役に立っている」という実感を得られます。孫のためのおもちゃ箱、妻のための収納棚など、家族に喜んでもらえることが大きなやりがいになります。
さらに、自宅のガレージや庭で作業できるため、外出する必要がなく、自分のペースで取り組めることも人気の理由です。
音楽鑑賞が男性に人気の理由
若い頃に聴いていた音楽を改めて楽しむことで、当時の思い出が蘇り、心が癒されるという効果があります。ビートルズ、サイモン&ガーファンクル、井上陽水など、青春時代の音楽を聴くことで、若々しい気持ちを取り戻せます。
また、音楽は座って楽しめるため、体力に自信がない方でも無理なく続けられます。音楽配信サービスを利用すれば、何万曲もの音楽を気軽に楽しめるようになり、新しい音楽との出会いも期待できます。
その他の人気趣味
ランキング外でも人気の趣味として、俳句・川柳、読書、カラオケ、料理、パズルなどがあります。これらも体力や興味に合わせて選べる良い選択肢です。
在宅介護で家族の負担を軽減するには?持続可能な介護体制の構築法
おじいちゃんが趣味を見つけるための具体的な方法
ランキングを見ても、実際にどうやって趣味を見つければいいか迷う方も多いでしょう。ここでは、具体的な方法をご紹介します。
昔好きだったことや興味があったことを振り返る

新しいことを始めるより、昔好きだったことを再開する方が、心理的なハードルが低く、楽しめる可能性が高くなります。
振り返りのヒント
若い頃、何をして遊んでいたか思い出してみる
学生時代に所属していた部活動やサークルは何だったか
社会人になってから楽しんでいた趣味はあったか
「いつかやってみたい」と思っていたことは何か
例えば、学生時代に写真部だった方なら、カメラを趣味にする。釣りが好きだったけれど仕事が忙しくて行けなくなった方なら、再び釣りを始める。こうした「昔の自分」に戻ることで、自然と楽しめる活動が見つかります。

「昔は○○が好きだったよね」と家族が声をかけることで、おじいちゃんも思い出すきっかけになります。昔のアルバムを一緒に見るのも良い方法ですよ。
家族と一緒に体験教室や地域活動に参加する

一人で新しいことを始めるのは勇気がいりますが、家族と一緒なら安心して挑戦できます。
家族で参加できる体験教室の例
陶芸教室:孫と一緒に茶碗や湯呑みを作る
料理教室:息子や娘と一緒にそば打ちやパン作りに挑戦
写真教室:家族で撮影会に参加する
木工教室:椅子や棚を一緒に作る
家族と一緒に参加することで、会話のきっかけにもなり、共通の思い出を作ることができます。また、家族が楽しんでいる姿を見ることで、おじいちゃん自身も「やってみようかな」という気持ちになりやすいです。
地域活動への参加
公民館やコミュニティセンターでは、さまざまな講座やサークル活動が行われています。地域の掲示板や広報誌をチェックし、興味のある活動を見つけてみましょう。
地域の清掃活動やお祭りの準備など、社会貢献的な活動に参加することで、「誰かの役に立っている」という充実感も得られます。
体力や予算に合わせて無理なく始められるものを選ぶ

趣味を長く続けるためには、自分の体力と予算に合ったものを選ぶことが重要です。
体力別おすすめ趣味
体力に自信がある:ゴルフ、釣り、ハイキング、グラウンドゴルフ、日曜大工
適度な運動をしたい:ガーデニング、ウォーキング、軽い体操、写真撮影
座ってできるもの:囲碁・将棋、読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、俳句・川柳
予算別おすすめ趣味
ほとんどお金がかからない:ウォーキング、図書館での読書、テレビでの映画鑑賞、俳句・川柳
初期費用が少し必要:ガーデニング(プランター、土、苗)、囲碁・将棋(碁盤・将棋盤)、塗り絵(塗り絵本、色鉛筆)
継続的に費用がかかる:釣り(道具、餌代)、ゴルフ(クラブ、プレー料金)、習い事(月謝)
大切なのは、「楽しい」と感じられるかどうかです。体力や予算の制約はありますが、その中で自分が心から楽しめるものを見つけることが、趣味を長く続ける秘訣です。
おじいちゃんの趣味探しで家族が注意すべきポイント
おじいちゃんが趣味を見つけるために、家族ができるサポートはたくさんあります。ただし、いくつか注意すべきポイントがあります。
押し付けず本人の興味を尊重する声かけ方法

最も避けたいのは、「これをやりなさい」という押し付けです。本人が興味を持たなければ、どんなに良い趣味でも続きません。
良い声かけの例:
「最近、近所で○○が人気らしいよ。おじいちゃんも興味ある?」(選択肢として提示)
「一緒に○○やってみない?」(一緒に楽しむ提案)
「昔、○○が好きだったよね。また始めてみたら?」(昔の興味を思い出させる)
避けたい声かけの例:
「趣味がないとボケるよ」(脅し)
「何もしないでテレビばかり見ていてはダメだ」(否定)
「○○さんは△△をやっているのに」(比較)
特に男性は、プライドが高く、命令口調で言われると反発してしまうことが多いです。本人の自主性を尊重しながら、さりげなく提案することが大切です。
一緒に楽しむことで自然に趣味につながる工夫

家族が一緒に楽しむことで、おじいちゃんも「やってみようかな」という気持ちになりやすくなります。
一緒に楽しむアイデア
ガーデニング:孫と一緒にプランターで野菜を育て、成長を一緒に見守る
散歩:週末に一緒に近所を歩き、季節の変化を楽しむ
映画鑑賞:家族で映画を観て、感想を話し合う
釣り:息子や孫と一緒に釣りに出かけ、釣果を競う
料理:孫におじいちゃんの得意料理を教えてもらう
特に孫との交流は、おじいちゃんにとって大きなモチベーションになります。「孫に教える」「孫と一緒に楽しむ」という形にすることで、自然と趣味につながっていくことがあります。
続かない時の対応と見守りの大切さ

新しい趣味を始めても、続かないことはよくあります。そんな時、責めたり、がっかりした態度を見せるのは逆効果です。
続かない理由はさまざま
思っていたより体力的に辛かった
思っていたより楽しくなかった
周りの人とうまくいかなかった
お金がかかりすぎた
プライドが傷ついた(初心者扱いされて嫌だった)
寛容な対応の例
「合わないこともあるよね。また他に興味があることがあれば教えてね」
「挑戦したこと自体がすごいことだよ」
「無理しなくていいよ。楽しくないなら意味がないからね」
大切なのは、趣味を持つこと自体が目的ではなく、おじいちゃんが心地よく過ごせることです。無理に何かをさせようとするよりも、本人のペースを尊重し、見守る姿勢が大切です。
趣味がない状態が続く場合の相談先とサポート
さまざまな趣味を提案しても興味を示さない、何をしても楽しそうにしない状態が続く場合は、別の問題が隠れている可能性があります。
無気力や抑うつのサインを見逃さない

以下のような状態が2週間以上続いている場合は、単なる趣味がない状態ではなく、老後うつの可能性も考慮する必要があります。
何に対しても興味や喜びを感じられない
食欲がない、または食べすぎてしまう
眠れない、または寝すぎてしまう
疲れやすく、いつも体がだるいと訴える
「生きていても仕方ない」「迷惑をかけている」といった否定的な発言が増えた
身だしなみに構わなくなった
表情が暗く、笑顔が見られなくなった
地域包括支援センターや医療機関への相談

心配な状態が続く場合、相談できる窓口があります。
【地域包括支援センター】
高齢者とその家族の総合相談窓口です。保健師、社会福祉士、ケアマネジャーなどの専門職が常駐しており、無料で相談できます。心身の健康、介護、認知症への対応など、幅広い相談が可能です。
【かかりつけ医】
普段から通っている医師に相談するのも良い方法です。必要に応じて、精神科や心療内科への紹介状を書いてもらえます。
【精神科・心療内科】
老後うつの専門的な診断と治療を受けられます。「精神科に行くのは抵抗がある」という方も多いですが、最近は「メンタルクリニック」など、入りやすい雰囲気の病院も増えています。
家族だけで抱え込まず専門家の力を借りる

おじいちゃんの状態を心配するあまり、家族自身が疲弊してしまうこともあります。家族だけで抱え込まず、相談できる場を持つことが大切です。
「趣味を見つけてあげたいけれど、何をしてもうまくいかない」「おじいちゃんの無気力な様子を見ていると、自分も気が滅入ってしまう」「このままでいいのか不安で仕方ない」
こうした悩みは、一人で抱えていると解決が難しくなります。専門家に相談することで、客観的なアドバイスを得られたり、気持ちが楽になったりすることがあります。
おじいちゃんの趣味がない時の対処法:まとめ
おじいちゃんに趣味がない時の対処法と、人気の趣味ランキングについてお伝えしました。
おじいちゃんに趣味がない理由として、定年後の環境変化、体力低下や健康面の不安、仕事中心の生活で趣味を持つ習慣がなかったことが挙げられます。これらは自然なことであり、本人を責めるべきではありません。
人気の趣味ランキングTOP10は、1位ガーデニング、2位映画鑑賞、3位釣り、4位日曜大工、5位音楽鑑賞、6位写真撮影、7位スポーツ観戦、8位囲碁・将棋、9位ウォーキング、10位グラウンドゴルフでした。それぞれの趣味には特徴があり、体力や予算に合わせて選ぶことができます。
家族が注意すべきポイントは、押し付けず本人の興味を尊重すること、一緒に楽しむことで自然に趣味につなげること、続かない時も責めずに見守ることです。
何をしても興味を示さず、無気力な状態が2週間以上続く場合は、老後うつの可能性も考慮し、地域包括支援センターやかかりつけ医に相談しましょう。家族だけで抱え込まず、専門家の力を借りることが、おじいちゃんと家族の両方にとって大切です。
趣味を持つことも大切ですが、それよりも大切なのは、おじいちゃんが心地よく、自分らしく過ごせることです。本人のペースを尊重しながら、見守り、サポートしていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。