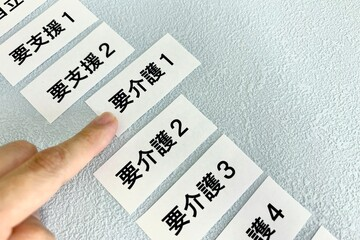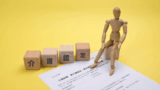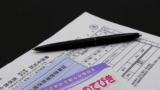「親の要介護認定を申請したいけど、どの程度で認定されるの?」「要介護度で一番多いのはどのレベル?」「自分の将来の介護リスクを知りたい」
要介護認定の申請を検討している方や、将来の介護について考えている方にとって、実際の認定状況を知ることは重要です。厚生労働省の最新データによると、要介護認定一番多いのは「要介護1」で、全認定者の約20.7%を占めています。
しかし、年齢や性別によって最も多い介護度は変化し、予防方法も異なります。正しい知識を持つことで、適切な介護計画を立て、介護度の進行を遅らせることも可能になります。
この記事では、最新の統計データを基に要介護認定の実態を詳しく解説し、年齢・男女別の傾向分析から、要介護度の進行を防ぐ具体的な予防策まで、実用的な情報をお伝えします。
要介護認定一番多いのは要介護1の詳細データ
要介護認定の実態を正確に理解するために、まず最新の統計データから詳しく見ていきましょう。数字の背景にある意味を理解することで、将来への備えも明確になります。
全体の20.7%を占める要介護1認定者の特徴

2024年3月末時点での要介護・要支援認定者総数708万人のうち、要介護1が146.4万人で最も多く、全体の20.7%を占めています。
要介護1の状態は、基本的な日常生活動作はほぼ自分でできるものの、複雑な動作や判断を要する場面で部分的な介助が必要な段階です。具体的には以下のような特徴があります:
- 立ち上がりや歩行に軽度の支えが必要
- 家事や金銭管理で見守りや手助けが必要
- 認知機能の軽度な低下が見られることがある
- 入浴や服薬管理で部分的な介助が必要
要介護1が最も多い理由として、多くの高齢者が最初に要介護認定を受ける段階であることが挙げられます。65歳になって初回申請をする方の多くが、軽度の支援が必要な状態で要介護1に認定されるケースが多いのです。
要介護1から要介護5までの認定者数分布

要支援・要介護の認定者数を介護度別に詳しく見ると、明確な傾向が見えてきます:
- 要支援1:102万人(14.4%)
- 要支援2:99.6万人(14.1%)
- 要介護1:146.4万人(20.7%)
- 要介護2:119.1万人(16.8%)
- 要介護3:92.7万人(13.1%)
- 要介護4:89.5万人(12.6%)
- 要介護5:59万人(8.3%)
この分布から、要介護度が高くなるほど認定者数が減少する「逆ピラミッド型」の構造であることがわかります。要介護5が最も少ないのは、重度の介護状態になる前に亡くなる方が多いことや、施設入所により在宅での生活が困難になることが影響しています。
また、要支援1・2と要介護1の合計で約49.2%と、軽度から中軽度の介護・支援が必要な方が全体の約半数を占めていることも重要なポイントです。
要介護認定一番多い理由と背景要因

要介護1が最も多い背景には、日本の高齢化社会の特徴的な構造があります。
第一に、介護保険制度の利用開始タイミングが影響しています。多くの方が65歳到達とともに要介護認定を申請し、軽度の支援が必要な状態で要介護1と認定されます。この時点では重篤な疾患や障害はなく、日常生活の一部で支援が必要な状態です。
第二に、健康寿命と平均寿命の差が関係しています。2022年の健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳で、平均寿命(男性81.05歳、女性87.09歳)との差は男性約8.4年、女性約11.7年です。この期間の多くが要介護1~3の状態で過ごされています。
第三に、疾患の種類と進行パターンも要因です。要介護状態になる主な原因は以下の通りです:
- 認知症:約18.7%
- 脳血管疾患:約16.1%
- 高齢による衰弱:約12.8%
- 骨折・転倒:約12.5%
- 関節疾患:約10.8%
年齢別で見る要介護認定一番多い介護度の変化
要介護認定の傾向は年齢によって大きく変化します。各年代で最も多い介護度を理解することで、将来の介護リスクを予測し、適切な準備ができます。
40~64歳は要介護2、65歳以上は要介護1が最多

年齢層別の分析では、興味深い傾向が見られます。40~64歳では要介護2が最も多く、これは65歳以上の傾向とは異なる特徴的なパターンです。
40~64歳で要介護認定を受ける場合は、特定疾病(16種類の疾患)が原因となります。主な疾患は以下の通りです
- がん(末期)
- 脳血管疾患
- 早期の認知症
- パーキンソン病
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
これらの疾患は、発症すると急激に身体機能が低下することが多く、軽度の支援段階を経ずに、ある程度重い介護度で認定されることが特徴です。40~64歳の認定者数は全体の約1.8%(13.1万人)と少数ですが、より重度の介護が必要な状態から始まる傾向があります。
一方、65歳以上では加齢による緩やかな機能低下が主な原因となるため、要介護1から始まることが多くなります。
75歳を境に急増する要介護認定率の実態

年齢別の要介護認定率を詳しく見ると、75歳を境に急激な増加が見られます
- 65~69歳:約2.8%(約36人に1人)
- 70~74歳:約8.2%(約12人に1人)
- 75~79歳:約18.4%(約5人に1人)
- 80~84歳:約32.1%(約3人に1人)
- 85~89歳:約55.2%(約2人に1人)
- 90歳以上:約82.8%(約5人に4人)
この急激な変化の背景には、後期高齢者(75歳以上)特有の身体変化があります。医学的には、75歳頃から以下のような変化が顕著になります
- 筋力低下(サルコペニア)の進行
- 認知機能の低下リスク増大
- 複数疾患の併発(多病性)
- 転倒・骨折リスクの増大
- 薬剤の副作用が出やすくなる
90歳以上で変わる介護度分布パターン

90歳以上になると、介護度の分布パターンに大きな変化が現れます。他の年代と異なり、重度の介護度(要介護4・5)の割合が大幅に増加します。
90歳以上の介護度別分布
- 要支援1:17.4万人(8.6%)
- 要支援2:21万人(10.4%)
- 要介護1:38.9万人(19.2%)
- 要介護2:36.4万人(17.9%)
- 要介護3:33.2万人(16.4%)
- 要介護4:35万人(17.3%)
- 要介護5:20.9万人(10.3%)
注目すべきは、要介護4の認定者数が要介護1に匹敵する水準まで増加していることです。これは90歳以上では、身体機能の著しい低下と複数の疾患による重篤化が主な要因となります。
また、認知症の有病率も90歳以上では50.3%と、2人に1人が認知症を発症することから、身体的介護と認知症ケアの両方が必要となる複合的な介護ニーズが増加します。
要介護認定一番多い介護度を進行させない予防策
要介護1が最も多い状況を踏まえ、この段階での適切な対応と予防策を実践することで、介護度の進行を遅らせ、質の高い生活を維持することができます。
要介護1から悪化を防ぐ日常的な取り組み

要介護1の段階では、適切な対応により介護度の進行を大幅に遅らせることが可能です。研究によると、積極的な介護予防に取り組む場合と何もしない場合では、3年後の介護度に1~2段階の差が生まれることがわかっています。
効果的な日常的取り組みは以下の通りです
身体機能維持の取り組み
- 1日30分以上の歩行(室内でも可)
- 椅子からの立ち上がり運動(1日20回×3セット)
- 片足立ち運動(左右各1分×2回)
- スクワット運動(1日10回×3セット)
- ストレッチ体操(毎日15分)
認知機能維持の取り組み
- 読書や新聞を読む習慣(1日30分以上)
- 計算ドリルやパズル(週3回以上)
- 日記を書く習慣
- 新しい趣味や習い事への挑戦
- 家族や友人との積極的な会話
介護予防サービスの効果的な活用方法

要介護1では、介護サービスと併せて介護予防サービスを積極的に活用することが重要です。これらのサービスは介護度の進行を遅らせる効果が科学的に証明されています。
通所型介護予防サービス
- 通所介護(デイサービス):社会交流と軽度な運動
- 通所リハビリテーション:専門的な機能訓練
- 認知症対応型通所介護:認知機能向上プログラム
訪問型介護予防サービス
- 訪問介護:生活機能向上のための指導
- 訪問リハビリテーション:個別機能訓練
- 訪問看護:健康管理と医療的ケア
地域支援事業の活用
- 介護予防教室:体操教室、栄養教室
- 認知症予防教室:脳トレーニング、回想法
- 地域サロン:社会参加と交流促進
- ボランティア活動:生きがいづくり
健康寿命を延ばすライフスタイルの見直し

要介護認定を受けた後でも、ライフスタイルの見直しにより健康寿命を延ばすことは十分可能です。実際、要介護状態になってからの生活習慣改善により、要介護度が改善した事例も多く報告されています。
睡眠の質の改善
- 規則正しい就寝・起床時間の確立
- 昼寝は15~30分以内に制限
- 寝室環境の整備(温度、湿度、照明)
- 就寝前のカフェイン・アルコール摂取制限
社会参加の促進
- 地域活動への積極的な参加
- 趣味のサークルや同好会への加入
- ボランティア活動による社会貢献
- 世代間交流プログラムへの参加
住環境の整備
- 段差の解消(スロープ設置、段差解消機)
- 手すりの設置(階段、廊下、浴室)
- 照明の増設(転倒予防)
- 滑り止めマットの設置
- 緊急通報システムの導入

要介護1の段階では、まだまだ改善の余地があります。特に、適切な運動と栄養管理、そして社会参加を続けることで、介護度の進行を大幅に遅らせることができるんです。諦めずに前向きに取り組むことが大切ですね。
要介護認定一番多い要介護1への理解を深めて:まとめ
要介護認定における実態の分析から、要介護認定一番多いのは要介護1で全体の20.7%を占めることが明らかになりました。この事実は、多くの高齢者が最初に軽度の支援を必要とする段階から介護生活をスタートすることを示しています。
年齢別の傾向では、40~64歳は要介護2が最多、65歳以上では要介護1が最多となり、75歳を境に認定率が急激に上昇することも確認できました。特に90歳以上では重度の介護度の割合が高くなる一方で、要介護1も依然として多く、高齢者の多様な支援ニーズが浮き彫りになりました。
重要なのは、要介護1の段階で適切な予防策を実践することで、介護度の進行を大幅に遅らせることが可能だということです。日常的な運動習慣、栄養管理、社会参加、そして介護予防サービスの効果的活用により、質の高い生活を長期間維持できます。
要介護状態になっても、決して諦める必要はありません。正しい知識と適切な支援により、自分らしい生活を続けることができるのです。今日から始められることを一つずつ実践し、健康で充実した日々を送りましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。