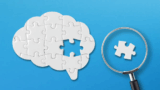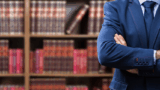「夜中になっても親が眠ってくれない」「昼夜逆転してしまって困っている」「徘徊があって心配で眠れない」
認知症の方を介護している家族なら、睡眠に関する悩みは非常に深刻な問題ですよね。実際に、認知症の方の約45%が何らかの睡眠障害を抱えているといわれており、家族の負担も計り知れません。
認知症による睡眠障害は、単に「眠らない」だけでなく、介護者の睡眠不足や精神的負担にもつながる問題です。しかし、適切な対処法を知ることで、認知症の方の睡眠リズムを改善し、家族全体の生活の質を向上させることは可能です。この記事では、認知症の方が寝ない原因から具体的な寝かせる方法まで、実践的な対策をご紹介します。
認知症で寝ない人が多い原因と睡眠障害のメカニズム
認知症の方の睡眠問題を解決するためには、まずなぜ眠れなくなるのか、その根本的な原因を理解することが大切です。
昼夜逆転と体内時計の乱れが起こる理由

認知症になると、脳の松果体という部分が影響を受け、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が不規則になります。
また、認知症による記憶障害により、「今が何時なのか」「昼なのか夜なのか」という時間の感覚が曖昧になることも大きな要因です。朝起きたことを忘れてしまい、「まだ朝が来ていない」と思い込んで夜中に活動を始めることもあります。
不安や痛み、環境要因が睡眠に与える影響

認知症の方が寝ない背景には、身体的・心理的な不快感も大きく関わっています。
身体的な痛みや不快感も見逃せません。関節痛、便秘、頻尿など、年齢を重ねることで増える身体の不調は、認知症の方にとってより深刻なストレスとなります。痛みを的確に伝えることができないため、イライラや不眠として現れることが多いのです。
環境の変化に敏感になることも特徴的です。いつもと違う音、におい、人の気配などが睡眠を妨げることがあります。特に、介護者が緊張していると、その雰囲気を敏感に察知して不安になることもあります。
夜間徘徊と睡眠障害の関連性

夜間の徘徊は、認知症の睡眠障害の中でも特に家族の負担が大きい症状の一つです。
徘徊が起こる背景
・過去の記憶が蘇り「仕事に行かなければ」「子どもを迎えに行かなければ」という使命感
・寝床が落ち着かない、トイレに行きたいけれど場所が分からないなどの身体的ニーズ
・「何かをしなければならない」という混乱した意識での衝動
認知症の方の睡眠問題は、単独の原因ではなく、これらの要因が複合的に絡み合って起こることが多いため、総合的なアプローチが必要になります。
認知症の方を寝かせる具体的な方法
認知症の方の睡眠問題を改善するためには、日常生活の中でできる具体的な工夫が重要です。薬に頼る前に、まずは生活環境や習慣を見直してみましょう。
就寝環境を整える照明・温度・寝具の工夫

良質な睡眠を促すためには、寝室の環境を整えることが最も基本的で効果的な方法です。
寝具の選び方も睡眠の質に大きく影響します。枕の高さは首のカーブに合わせて調整し、マットレスは適度な硬さがあるものを選びましょう。柔らかすぎると寝返りが打ちにくく、硬すぎると身体が痛くなってしまいます。
生活リズムを規則正しくする日中の過ごし方
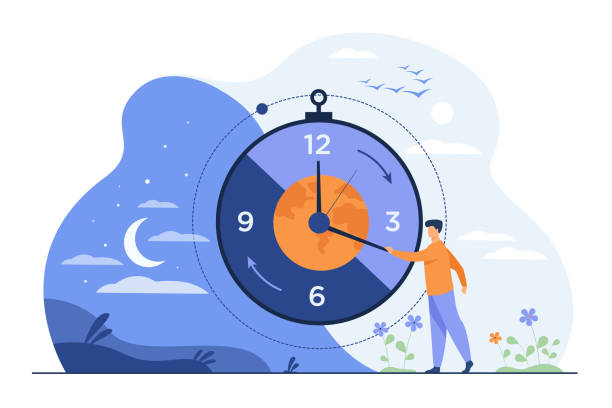
認知症の方の睡眠リズムを整えるためには、日中の過ごし方が非常に重要になります。
生活リズム作りの基本
・起床時間と就寝時間を毎日同じ時刻に設定
・食事の時間も決まった時間に摂る(朝食、昼食、夕食)
・夕食は就寝の3時間前までに済ませる
・寝る前の飲食は控えめにする
日中の活動量を適度に増やすことも効果的です。散歩、軽い体操、家事の手伝いなど、本人の体力に合わせた活動を取り入れることで、夜の疲労感を適度に作り出せます。デイサービスやデイケアを利用している場合は、そこでの活動も睡眠リズム作りに活用できます。
日光浴は体内時計の調整に特に効果的です。午前中に15~30分程度、ベランダや庭で日光を浴びることで、メラトニンの分泌リズムが整いやすくなります。外出が困難な場合は、窓際で過ごすだけでも効果があります。
リラックス効果を高める入眠前のケア

就寝前の1~2時間は、心身をリラックスさせて自然な眠気を促すための大切な時間です。
就寝前のルーティンを作ることも重要です。毎日同じ順序で着替え、歯磨き、トイレなどを行うことで、身体が「眠る時間」であることを認識しやすくなります。このルーティンは、認知症の方にとって安心できる習慣となります。
認知症の睡眠問題への総合的なアプローチ
認知症の方の睡眠問題は複雑で、一つの方法だけでは解決しないことが多いため、様々なアプローチを組み合わせることが重要です。
薬物療法と非薬物療法の使い分け

睡眠薬の使用については、医師との慎重な相談が必要です。
睡眠薬を使用する場合も、必ず医師の指示に従い、効果と副作用を定期的に評価することが大切です。急に薬を中止すると離脱症状が起こることがあるため、減量や中止は医師の指導のもとで段階的に行いましょう。
漢方薬という選択肢もあります。抑肝散などの漢方薬は、認知症の方の不安や興奮を和らげ、間接的に睡眠の改善につながることがあります。副作用が比較的少ないとされていますが、こちらも医師との相談が必要です。
家族の負担軽減と専門家への相談タイミング

認知症の方の睡眠問題は、介護者の負担も非常に大きくなるため、一人で抱え込まずに適切なサポートを求めることが重要です。
ただし、こうした公的なサービスでは、日々の細かな不安や夜中の急な変化に対する相談は難しいことも多いのが現実です。「今夜も眠ってくれない」「この対応で良いのか分からない」「夜中に不安で眠れない」といった、その時々の具体的な悩みを気軽に相談できる場所があると、介護者の精神的負担は大きく軽減されます。
専門医への相談が必要なサイン
・睡眠障害が1ヶ月以上続く場合
・日中の生活に大きな支障が出ている場合
・徘徊により安全面での心配がある場合
・介護者の負担が限界に達している場合
医師に相談する際は、睡眠の状況を詳しく記録しておくことが重要です。何時に寝て何時に起きたか、夜中に起きた回数、日中の様子などを記録することで、より適切な診断と治療につながります。

介護者自身の健康管理も忘れてはいけません。睡眠不足や慢性的なストレスにより、介護者がうつ状態になることも少なくありません。「自分のことは後回し」ではなく、介護者自身の健康も大切にすることが、結果的に良いケアにつながりますよ。
kurisuプロフィールを編集
睡眠日記の活用と継続的なケアのポイント
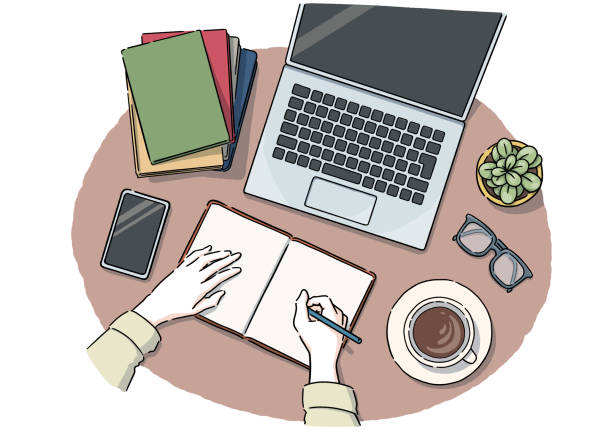
認知症の方の睡眠パターンを改善するためには、現状を正確に把握し、継続的に取り組むことが重要です。
睡眠日記は最低でも2週間、できれば1ヶ月程度継続することで、有意義なデータが得られます。記録を見返すことで、「雨の日は眠りが浅い」「デイサービスの日は夜よく眠る」など、睡眠に影響する要因が見えてくることがあります。
記録は簡単で構いません。スマートフォンのアプリを使ったり、紙のカレンダーに簡単な記号で記録したりと、続けやすい方法を選びましょう。介護者が負担に感じない程度の記録で十分です。
認知症の進行や身体状況の変化により、以前有効だった方法が効かなくなることもあります。柔軟に対応を変えていく姿勢が大切です。
まとめ
認知症の方の睡眠問題は、介護する家族にとって大きな負担となりますが、適切な対処法を知ることで改善することができます。
重要なのは、まず睡眠障害の原因を理解し、薬に頼る前に生活環境や日常習慣の見直しを行うことです。照明の調整、生活リズムの規則化、リラックス効果を高める入眠前のケアなど、日常の中でできる工夫を組み合わせることで、多くの場合改善が期待できます。
睡眠の改善は時間がかかるプロセスです。睡眠日記をつけて現状を把握し、継続的に取り組むことで、認知症の方とその家族の両方にとって、より良い生活を実現できるでしょう。
介護は一人で背負うものではありません。困った時には遠慮なく周囲のサポートを求め、家族全体で支え合いながら、無理のない介護を続けていくことが最も大切です。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。