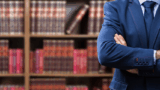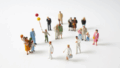「認知症の父が暴言を吐くようになって、もう半年が経つ。いつまでこの状態が続くのか」「母の暴言がひどくて、この先どうなるのか不安で仕方がない」「暴言が収まったと思ったら、また始まった。いったい何が原因なの?」
認知症の方の暴言に悩まされている家族の多くが、「いつまで続くのか」という疑問を抱いています。介護に関する相談の約4割が、認知症による暴言や暴力などの行動・心理症状(BPSD)に関するものというデータもあり、多くの家族が同じ悩みを抱えているのが現実です。
認知症の暴言には明確な終わりがあるわけではありませんが、その背景を理解し、適切に対処することで軽減することは可能です。この記事では、暴言がいつまで続くのかという疑問にお答えし、家族ができる具体的な対処法をお伝えします。
認知症の暴言がいつまで続くかは個人差が大きい理由

認知症の進行段階と暴言の関係性
認知症の暴言がいつまで続くかを理解するためには、まず認知症の進行段階と暴言の関係性を知ることが重要です。暴言の出現や継続期間は、認知症の種類、進行速度、個人の性格や生活歴などによって大きく異なります。
認知症の初期段階では、物忘れが増えたり判断力が低下したりすることで、本人が混乱や不安を感じやすくなります。この段階では、「自分がおかしくなっているのではないか」という恐怖や、「周りの人が自分をバカにしている」という被害妄想から暴言が始まることが多くあります。
中期段階になると、認知機能の低下がより顕著になり、日常生活に大きな支障をきたすようになります。この時期の暴言は、介護を受けることへの抵抗、環境の変化への戸惑い、身体的な不快感をうまく表現できないことなどが原因となることが多いです。
興味深いことに、認知症の進行段階と暴言の頻度は必ずしも比例しません。初期段階で強い暴言が見られたものの、中期になって落ち着く場合もあれば、逆に中期から後期にかけて暴言が激しくなる場合もあります。
後期段階では、言語能力自体が著しく低下するため、暴言の形は変化します。言葉による暴言よりも、行動による表現(物を投げる、叩くなど)が多くなったり、逆に表現力の低下により暴言が減少したりすることもあります。
アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など、認知症の種類によっても暴言の特徴は異なります。特に前頭側頭型認知症では、脳の前頭葉の機能低下により感情のコントロールが困難になるため、他の認知症よりも暴言や攻撃的行動が出やすい傾向があります。
重要なのは、暴言は認知症の必然的な症状ではないということです。認知症になったすべての人が暴言を発するわけではなく、また暴言が出ても永続的に続くとは限りません。適切な環境調整や対応により、暴言を軽減したり、期間を短縮したりすることは十分可能です。
また、暴言の背景にある感情や欲求を理解することで、コミュニケーションの方法を工夫し、暴言に代わる表現方法を見つけることもできます。家族が暴言を「単なる問題行動」として捉えるのではなく、「本人なりのメッセージ」として理解しようとする姿勢が、状況改善の第一歩となります。
環境や体調による暴言の変動パターン
認知症の暴言は、本人の体調や周囲の環境によって大きく変動します。この変動パターンを理解することで、暴言がいつまで続くかを予測し、適切なタイミングで対策を講じることができます。
身体的な不調は暴言の大きな誘因となります。便秘、尿路感染症、痛み、発熱、薬の副作用などにより体調が悪い時は、不快感を言葉でうまく表現できないために暴言として現れることがあります。これらの身体的問題が解決されると、暴言も自然に収まることが多くあります。
せん妄状態も暴言を引き起こす重要な要因です。入院、手術、環境の変化、感染症などがきっかけでせん妄状態になると、一時的に強い暴言や攻撃的行動が現れることがあります。せん妄による暴言は、原因が治療されれば通常1週間から2ヶ月程度で改善します。
環境の変化も暴言に大きな影響を与えます。住み慣れた場所から施設への入所、家族構成の変化、介護者の交代、季節の変化、騒音や明るさの変化など、様々な環境要因が暴言の引き金となることがあります。
特に注意すべきなのが「夕暮れ症候群」と呼ばれる現象です。夕方から夜にかけて、不安や混乱が強くなり、暴言や徘徊などの問題行動が現れやすくなります。これは体内時計の乱れや、薄暗くなることによる視覚的混乱が原因と考えられています。
人間関係のストレスも暴言の持続に影響します。家族間の緊張、介護者の疲労やイライラ、来客の多さ、介護スタッフとの相性などが暴言の頻度や強度に影響します。特に、介護者が感情的になって対応すると、それが本人に伝わって暴言がエスカレートする悪循環に陥ることがあります。
薬の影響も見逃せません。新しい薬の開始、薬の変更、飲み忘れ、重複服用などにより、一時的に暴言が増加することがあります。逆に、適切な薬物治療により暴言が軽減される場合もあります。
季節や天候の変化も暴言に影響することがあります。気圧の変化、湿度の変化、日照時間の変化などが、認知症の方の精神状態に影響を与えることが知られています。
これらの変動要因を理解することで、暴言が一時的なものなのか、より長期的な対策が必要なものなのかを判断することができます。また、変動パターンを記録することで、暴言が起こりやすい条件を特定し、予防的な対策を講じることも可能になります。
暴言が一時的に収まるケースと再発する理由
認知症の暴言は、完全に消失することは少ないものの、一時的に収まることは珍しくありません。しかし、多くの家族が経験するのは、「落ち着いたと思ったら、また始まった」という再発のパターンです。
暴言が一時的に収まる要因としては、まず身体的な問題の改善があります。感染症の治療、便秘の解消、痛みの軽減、適切な薬物調整などにより、体調が改善すると暴言も軽減されます。このような場合の改善は比較的早く、数日から数週間で効果が現れることが多いです。
環境の調整も暴言の軽減に効果的です。騒音の除去、照明の調整、馴染みのある物の配置、安心できる人による介護などにより、本人の不安や混乱が軽減され、暴言が収まることがあります。
薬物療法による改善も期待できます。抗認知症薬、抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬などを適切に使用することで、暴言を含む行動・心理症状が軽減される場合があります。ただし、薬の効果には個人差があり、副作用にも注意が必要です。
介護者の対応の改善も重要な要因です。感情的にならずに落ち着いて対応する、本人のペースに合わせる、肯定的な言葉をかけるなど、接し方を改善することで暴言が減少することがあります。
しかし、これらの改善は必ずしも永続的ではありません。暴言が再発する理由として、まず認知症の進行があります。一時的に改善しても、根本的な脳の機能低下は進行し続けるため、新たな混乱や不安が生じ、暴言が再発することがあります。
新たなストレス要因の出現も再発の原因となります。季節の変化、家族の状況変化、介護体制の変更、健康状態の変化などにより、再び暴言が現れることがあります。
薬の効果の減弱も考慮すべき要因です。同じ薬を長期間使用していると効果が薄れることがあり、暴言が再発する場合があります。
また、「記憶はなくても感情は残る」という認知症の特徴も再発に影響します。不快な体験や感情の記憶は残りやすく、似たような状況になると暴言が再発することがあります。
介護者の疲労やストレスの蓄積も再発要因の一つです。一時的に改善したことで安心して対応がおろそかになったり、疲労が蓄積して感情的な対応が増えたりすると、暴言が再発することがあります。
重要なのは、暴言の再発を「失敗」として捉えるのではなく、「波のある症状の自然な経過」として理解することです。再発があっても、適切な対応を継続することで、再び改善する可能性は十分にあります。
認知症の暴言を本人のSOSサインとして理解する

暴言に隠された不安や混乱のメッセージ
認知症の暴言を理解するためには、それを単なる「問題行動」として捉えるのではなく、本人からの「SOSサイン」や「メッセージ」として受け取ることが重要です。暴言の背景には、必ず本人なりの理由や感情があります。
最も多い暴言の背景にあるのが、強い不安感です。認知症により記憶や判断力が低下すると、「今どこにいるのか分からない」「なぜここにいるのか分からない」「家族がどこに行ったのか分からない」といった状況に置かれることがあります。このような混乱状態では、不安が極度に高まり、それが暴言として表現されます。
孤独感や疎外感も暴言の大きな要因です。家族が忙しそうにしている、会話についていけない、自分だけが取り残されているような感覚を持つことで、注意を引こうとして暴言を発することがあります。「構ってほしい」「話を聞いてほしい」という気持ちが、否定的な言葉として現れることがあります。
自尊心の傷つきも見逃せない要因です。できないことが増える、失敗が多くなる、子ども扱いされるなどの経験により、自尊心が傷つき、それが怒りや暴言として表現されることがあります。「自分はまだちゃんとできる」「バカにするな」という気持ちが暴言の背景にあることが多いです。
身体的な不快感を言葉で表現できないことも、暴言の原因となります。痛み、かゆみ、のどの渇き、空腹、暑さ、寒さなどの身体的不快感を、認知機能の低下により適切に表現できないため、「いやだ」「やめろ」といった暴言として現れることがあります。
恐怖感も暴言を引き起こします。知らない人が近づいてくる、知らない場所にいる、何をされるか分からないといった恐怖感から、自分を守ろうとして攻撃的な言葉を発することがあります。これは本能的な防御反応として理解することができます。
過去の記憶との混同も暴言の背景にあります。現在の状況を過去の嫌な記憶と重ね合わせてしまい、その時の感情が蘇って暴言として現れることがあります。例えば、介護者を昔の嫌な上司と勘違いして、その時の怒りが暴言として表現されることがあります。
コントロール感の喪失も重要な要因です。自分の意思で物事を決められない、自分のペースで行動できないといった状況に置かれることで、せめて言葉だけでもコントロールしようとして暴言を発することがあります。
これらの背景を理解することで、暴言への対応方法も変わってきます。単に「やめなさい」と制止するのではなく、本人の気持ちに寄り添い、不安や混乱を軽減する方向で対応することが効果的です。
家族の対応が暴言の持続に与える影響
認知症の暴言の持続期間や頻度は、家族や介護者の対応によって大きく左右されます。適切な対応により暴言を軽減することができる一方で、不適切な対応により暴言がエスカレートしたり、長期化したりすることもあります。
最も避けるべき対応は、感情的になって言い返すことです。暴言に対して怒りで応じたり、論理的に反論したりすると、本人の混乱や興奮がさらに高まり、暴言がエスカレートする悪循環に陥ります。認知症により論理的思考が困難になっているため、理屈で説得しようとしても効果がないばかりか、逆効果になることが多いです。
否定や訂正を繰り返すことも暴言を悪化させる要因です。「そんなことはない」「間違っている」「思い出して」といった否定的な言葉は、本人の自尊心を傷つけ、さらなる暴言を引き起こします。認知症の方にとって、自分の認識が否定されることは非常につらい体験です。
無視をしたり、突き放したりする対応も問題です。暴言を無視することで一時的に収まる場合もありますが、本人の孤独感や疎外感が増し、より強い暴言として現れることがあります。また、介護を拒否したり、関わりを避けたりすることで、本人の不安がさらに高まることもあります。
一方で、暴言を軽減する効果的な対応もあります。まず重要なのは、冷静さを保つことです。深呼吸をして感情を落ち着かせ、本人の気持ちに寄り添う姿勢を示すことが大切です。「つらいんですね」「困っているんですね」といった共感的な言葉をかけることで、本人の気持ちが落ち着くことがあります。
話題を変えることも効果的です。暴言が始まったら、本人の好きな話題や楽しい思い出について話すことで、気分を転換させることができます。昔の仕事の話、家族の思い出、好きな食べ物の話など、本人が喜ぶ話題を見つけておくことが重要です。
物理的な距離を取ることも必要な場合があります。暴言がエスカレートしている時は、一度その場を離れて、お互いに冷静になる時間を作ることが効果的です。「ちょっとお茶を入れてきますね」といった自然な理由で距離を取ることができます。
環境を調整することも重要です。騒音を減らす、照明を調整する、馴染みのある音楽をかけるなど、本人がリラックスできる環境を作ることで暴言を軽減することができます。
一貫した対応を心がけることも大切です。家族や介護者が異なる対応をすると、本人が混乱してしまいます。家族全員で対応方法を共有し、一貫したアプローチを取ることが効果的です。
本人のペースに合わせることも重要です。急かしたり、無理強いしたりせず、本人のペースに合わせて介護を行うことで、ストレスを軽減し、暴言を予防することができます。
症状として受け止める心構えの重要性
認知症の暴言に長期間向き合うためには、それを「症状」として受け止める心構えが重要です。この心構えを持つことで、家族の精神的負担を軽減し、より効果的な対応が可能になります。
まず理解すべきなのは、暴言は認知症という病気の症状の一つであり、本人の本来の性格や意思ではないということです。脳の機能低下により、感情のコントロールや適切な表現ができなくなっているのであり、本人も戸惑い、苦しんでいることが多いのです。
「病気が言わせている」という視点を持つことで、暴言を個人的な攻撃として受け取らずに済みます。「お母さんが私を憎んでいるから暴言を吐く」のではなく、「認知症という病気が暴言を引き起こしている」と理解することで、感情的になることを避けることができます。
また、暴言は本人なりのコミュニケーション手段でもあります。適切な言葉で気持ちを表現することが困難になっているため、暴言という形でしか感情を表現できない状況にあると理解することが大切です。
完璧な対応を求めないことも重要です。認知症の症状は複雑で予測困難な面があり、どんなに適切に対応しても暴言が完全になくなることは稀です。「完全に止めなければならない」と考えるのではなく、「少しでも軽減できれば良い」「一時的に収まれば良い」という現実的な目標を持つことが大切です。
症状の変動を受け入れることも必要です。良い日もあれば悪い日もあり、改善したと思ったら再び悪化することもあります。これは病気の自然な経過であり、対応が間違っているわけではないことを理解することが重要です。
本人も苦しんでいることを忘れてはいけません。暴言を発している本人も、自分の行動や言動に戸惑い、コントロールできない状況に苦しんでいることが多いのです。暴言の後に申し訳なさそうな表情を見せたり、混乱した様子を示したりすることがあります。
長期戦になることを覚悟することも大切です。認知症は進行性の疾患であり、症状との付き合いも長期間になることが予想されます。短期間で解決しようとするのではなく、持続可能な対応方法を見つけることが重要です。
自分自身の感情を大切にすることも忘れてはいけません。症状として受け止めるとはいえ、暴言を受け続けることは精神的に大きな負担です。自分の感情を否定せず、つらい時はつらいと認め、適切なサポートを求めることが重要です。
認知症の暴言への効果的な対処法と軽減策

暴言が起きた時の具体的な対応方法
認知症の暴言が起きた時の対応は、その場の安全を確保しながら、本人の気持ちを落ち着かせることを最優先に考える必要があります。具体的で実践的な対応方法を身につけることで、暴言の時間を短縮し、エスカレートを防ぐことができます。
暴言が始まったら、まず自分自身の安全を確保することが重要です。本人が興奮している時は、物を投げたり、手を出したりする可能性があるため、適切な距離を保ちながら対応します。決して威圧的な態度を取らず、低い姿勢で穏やかに接することが大切です。
言葉による対応では、まず本人の感情を受け止めることから始めます。「お疲れさまです」「大変でしたね」「つらかったですね」といった共感的な言葉をかけることで、本人の気持ちが少し落ち着くことがあります。この時、暴言の内容が事実と異なっていても、まずは本人の気持ちを受け止めることが重要です。
反論や説得は避けるべきです。「そんなことはありません」「間違っています」といった否定的な言葉は、本人の興奮をさらに高めてしまいます。代わりに、「そうですね」「そんな気持ちになったんですね」といった受容的な言葉を使います。
気分転換を図ることも効果的です。本人の好きな話題、楽しい思い出、好きな食べ物の話などに話題を変えることで、気分を転換させることができます。「お茶でも飲みませんか」「外の景色を見てみましょう」といった具体的な提案も効果的です。
身体的なケアも重要です。のどが渇いている、トイレに行きたい、暑い・寒いといった身体的不快感が暴言の原因になっている場合があります。水分補給、トイレ誘導、室温調整などの基本的なケアを行うことで、暴言が収まることがあります。
環境の調整も即座に行います。騒音がある場合は静かな場所に移動する、明るすぎる場合は照明を調整する、人が多い場合は人数を減らすなど、本人がリラックスできる環境を作ります。
馴染みのある物や人の活用も効果的です。本人の写真、愛用していた物、好きな音楽などを使って気持ちを落ち着かせることができます。また、本人が信頼している人がいる場合は、その人に対応を代わってもらうことも考慮します。
時間をかけることも大切です。急いで暴言を止めようとするのではなく、時間をかけて徐々に気持ちを落ち着かせることが重要です。10分、20分かかっても、焦らずに対応を続けることが効果的です。
記録を取ることも忘れてはいけません。いつ、どのような状況で暴言が起きたか、どのような対応が効果的だったかを記録しておくことで、今後の対応に活かすことができます。
暴言が収まった後のフォローも重要です。本人が落ち着いたら、優しい言葉をかけたり、好きなことをして過ごしたりすることで、良い感情で終わるように心がけます。
環境調整と専門家による治療の活用
認知症の暴言を軽減するためには、環境の調整と専門家による適切な治療の両方が重要です。これらを組み合わせることで、暴言の頻度や強度を大幅に軽減することが可能です。
住環境の調整は、暴言の予防と軽減に大きな効果があります。まず、騒音の除去が重要です。テレビの音量、外からの騒音、人の話し声などが本人の混乱を招くことがあるため、静かで落ち着いた環境を作ることが大切です。
照明の調整も効果的です。明るすぎる照明は興奮を招き、暗すぎる照明は不安を増大させることがあります。自然光を取り入れつつ、柔らかい間接照明を使用することで、リラックスできる環境を作ることができます。
室温や湿度の管理も重要です。暑すぎたり寒すぎたりすると、不快感から暴言が起こりやすくなります。適切な室温(20-25度程度)と湿度(50-60%程度)を保つことが大切です。
馴染みのある物の配置も効果的です。本人が長年使っていた家具、写真、思い出の品などを配置することで、安心感を与えることができます。新しい物や見慣れない物は混乱を招くことがあるため、できるだけ馴染みのある物を使用します。
色彩の工夫も暴言軽減に役立ちます。赤や黄色などの刺激的な色は興奮を招きやすく、青や緑などの落ち着いた色はリラックス効果があります。壁の色、カーテンの色、家具の色などを工夫することで、穏やかな環境を作ることができます。
専門医による治療も重要な選択肢です。認知症専門医や精神科医は、暴言を含む行動・心理症状(BPSD)の治療に豊富な経験を持っています。薬物療法だけでなく、非薬物療法についてもアドバイスを受けることができます。
薬物療法では、抗認知症薬(ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン、メマンチン)が使用されることがあります。これらの薬は認知機能の改善だけでなく、行動・心理症状の軽減にも効果があることが報告されています。
精神症状が強い場合は、抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬などが使用されることもあります。ただし、これらの薬は副作用のリスクもあるため、専門医による慎重な判断が必要です。
非薬物療法も重要な治療選択肢です。音楽療法、アロマテラピー、リハビリテーション、作業療法、回想法などが暴言の軽減に効果があることが報告されています。
定期的な健康チェックも欠かせません。身体的な問題(感染症、便秘、痛みなど)が暴言の原因になっている場合があるため、定期的に医師のチェックを受けることが重要です。
薬の見直しも定期的に行う必要があります。薬の効果は時間とともに変化することがあり、また副作用が暴言を引き起こすこともあるため、定期的に薬の種類や量を見直すことが大切です。
家族が自分を守るための距離の取り方
認知症の暴言に長期間対応するためには、家族自身が自分を守り、精神的・身体的健康を維持することが不可欠です。適切な距離の取り方を身につけることで、持続可能な介護が可能になります。
物理的な距離を取ることは、安全確保と感情的距離の両方に効果があります。暴言がエスカレートしている時は、一時的にその場を離れることが有効です。「お茶を入れてきます」「電話に出ます」といった自然な理由で距離を取り、お互いに冷静になる時間を作ります。
感情的な距離を保つことも重要です。暴言を個人的な攻撃として受け取るのではなく、「病気の症状」として客観視することで、感情的ダメージを軽減することができます。「これは認知症が言わせているのであって、本当の親の気持ちではない」と自分に言い聞かせることが効果的です。
時間的な距離を作ることも大切です。24時間体制で介護を続けることは不可能であり、定期的に休息を取ることが必要です。デイサービス、ショートステイ、訪問介護などのサービスを活用して、自分の時間を確保することが重要です。
第三者の力を借りることも有効です。他の家族、友人、近所の人、専門的なサポートグループなどに協力を求めることで、一人で抱え込むことを避けることができます。話を聞いてもらうだけでも、精神的な負担が軽減されます。
趣味や楽しみを維持することも重要です。介護に追われて自分の趣味や楽しみを諦めてしまうと、ストレスが蓄積し、暴言への対応も感情的になりがちです。短時間でも自分の好きなことをする時間を作ることが大切です。
専門的なサポートを受けることも考慮すべきです。カウンセリング、家族会への参加、介護者向けの支援プログラムなどを活用することで、精神的な支えを得ることができます。
健康管理を怠らないことも重要です。介護のストレスで自分の健康を害してしまっては、継続的な介護ができなくなります。定期的な健康チェック、適切な食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけることが大切です。
罪悪感を持ちすぎないことも重要です。「もっと頑張らなければ」「自分が悪い」といった罪悪感は、ストレスを増大させ、適切な判断を妨げます。完璧な介護者になろうとするのではなく、できる範囲で最善を尽くすという考え方が大切です。
将来の計画を立てることも心の安定につながります。このまま在宅介護を続けるのか、施設入所を検討するのか、どのような支援を利用するのかなど、将来の見通しを立てることで、不安を軽減することができます。
まとめ
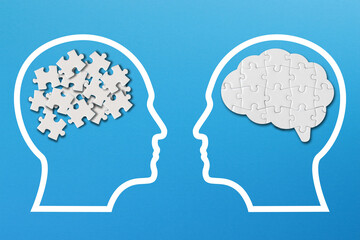
認知症の暴言がいつまで続くかという問いに対する答えは、「個人差が非常に大きく、明確な期間は特定できない」というのが現実です。しかし、暴言は決して永続的な症状ではなく、適切な理解と対応により軽減することは十分可能です。
重要なのは、暴言を本人からのSOSサインとして理解し、その背景にある不安や混乱に寄り添うことです。また、家族自身も自分を守りながら、持続可能な介護を続けるための工夫が必要です。
暴言への対応は一朝一夕にマスターできるものではありませんが、専門家のサポートを受けながら、家族なりの対応方法を見つけていくことが大切です。完璧を求めるのではなく、少しずつ改善していくという長期的な視点を持つことが重要です。
もし現在、認知症の暴言で悩んでいるのなら、一人で抱え込まず、地域包括支援センターや認知症専門医に相談してみてください。あなたの状況に応じた具体的なアドバイスとサポートを受けることができるはずです。暴言は確かにつらい症状ですが、適切な支援があれば乗り越えていくことができます。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。