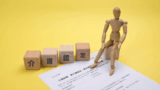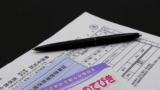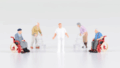「親に介護が必要になってきたけれど、介護認定の等級って何段階あるの?」「要支援と要介護の違いがよくわからない」「介護認定の等級によって、どんなサービスが受けられるの?」
介護保険制度を利用する際に避けて通れないのが、介護認定の等級判定です。この等級によって利用できるサービスや費用負担が大きく変わるため、制度を正しく理解することが重要です。
この記事では、介護認定の等級制度について、8段階の区分から申請手続き、等級別のサービス内容、費用負担まで、わかりやすく完全解説します。介護が必要になった時に慌てずに済むよう、事前に制度を理解しておきましょう。
介護認定の等級制度の基本知識と仕組み
介護認定の等級制度は、介護保険制度の根幹を成す重要な仕組みです。個人の介護や支援の必要度を客観的に評価し、適切なサービスを提供するために設けられています。まずは基本的な知識から理解していきましょう。
介護認定等級の8段階区分と判定基準

介護認定の等級は、8段階の区分に分かれており、支援や介護の必要度に応じて判定されます。非該当(自立)から要介護5まで、段階的に介護の必要度が高くなっていきます。
介護認定等級の8段階区分
非該当(自立):支援や介護が必要ない状態
要支援1:部分的な支援が必要な状態
要支援2:要支援1より多くの支援が必要な状態
要介護1:日常生活で部分的な介護が必要
要介護2:生活全般で介護が必要
要介護3:ほぼ全面的な介護が必要
要介護4:介護なしでは日常生活が困難
要介護5:寝たきりで常時介護が必要
判定基準は全国共通で、要介護認定等基準時間という客観的な指標を使用します。この基準時間は、介護に要する手間を時間に換算したもので、身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応の5つの領域で評価されます。
例えば、要支援1の基準時間は25分以上32分未満、要介護1は32分以上50分未満、要介護5は110分以上となっており、介護にかかる時間が長いほど等級が上がります。
要支援と要介護の違いと等級変更の条件

介護認定等級の中で、要支援と要介護の違いを理解することは非常に重要です。この区分により、利用できるサービスの種類や内容が大きく異なります。
要支援(要支援1・2)の特徴:
・日常生活に一部支障があるが、支援により改善や維持が可能
・6か月にわたり継続的な介護は必要ない状態
・介護予防に重点を置いたサービスが中心
・状態の悪化を防ぐことが主な目的
要介護(要介護1~5)の特徴:
・6か月にわたり継続的な介護が必要な状態
・または今後6か月以内に状態が大きく進行すると予想される
・現在の状態を維持・改善するための介護サービスが中心
・生活全般にわたる支援が必要
等級変更は、区分変更申請により可能です。体調の悪化や改善により、現在の等級では適切なサービスが受けられない場合に申請できます。例えば、要支援2だった方が転倒により歩行困難になった場合、要介護への変更申請を行うことができます。
介護認定等級別の利用可能サービスと限度額

介護認定の等級により、1か月あたりの支給限度額と利用できるサービスの種類が決まります。限度額内であれば1割~3割の自己負担でサービスを利用できます。
等級別月額支給限度額(1割負担の場合)
要支援1:約5,030円(限度額約50,320円)
要支援2:約10,530円(限度額約105,310円)
要介護1:約16,760円(限度額約167,650円)
要介護2:約19,700円(限度額約197,050円)
要介護3:約27,040円(限度額約270,480円)
要介護4:約30,930円(限度額約309,380円)
要介護5:約36,210円(限度額約362,170円)
等級が上がるほど利用できるサービスの幅も広がります。特別養護老人ホームへの入所は原則要介護3以上、夜間対応型訪問介護は要介護1以上など、等級による制限があります。
また、福祉用具のレンタルについても等級による制限があります。車いすや特殊寝台は要介護2以上、認知症老人徘徊感知機器は要介護3以上でないと利用できません。
介護認定の等級申請から認定までの手続き
介護認定の等級を受けるためには、適切な手続きを行う必要があります。申請から認定までの流れを理解し、スムーズに手続きを進められるよう準備しましょう。
介護認定等級申請に必要な書類と申請方法

介護認定等級の申請は、市区町村の介護保険担当窓口で行います。申請者は本人または家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行を依頼することも可能です。
申請に必要な書類:
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証(65歳以上の場合)
・健康保険証(40歳以上65歳未満の場合)
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
申請書には、現在の身体状況や困っていることを具体的に記載することが重要です。「階段の昇降が困難」「入浴時に転倒しそうになる」など、具体的な生活上の支障を記載することで、適切な等級判定につながります。
認定調査と主治医意見書による等級判定過程

申請後、認定調査員による訪問調査と主治医意見書の2つの資料を基に等級判定が行われます。この過程を理解することで、適切な準備ができます。
認定調査の内容:
認定調査員が自宅や施設を訪問し、全国共通の74項目について聞き取り調査を行います。調査項目は以下の5分野に分かれています:
・身体機能・起居動作(12項目):麻痺の有無、関節の動き、起き上がりなど
・生活機能(13項目):移乗、歩行、入浴、排尿・排便など
・認知機能(9項目):意思の伝達、記憶、理解力など
・精神・行動障害(15項目):徘徊、興奮、自傷行為など
・社会生活への適応(6項目):薬の管理、金銭管理、集団への適応など
主治医意見書の役割:
主治医が作成する意見書では、病名、症状、治療内容、リハビリの必要性などが記載されます。認知症の症状や精神的な状態についても重要な判定材料となります。
調査時は、普段の状態を正確に伝えることが重要です。「今日は調子が良い」といった場合でも、普段困っていることを具体的に説明しましょう。家族の同席により、客観的な情報を提供することも大切です。
【認定調査、ちゃんと準備できているか不安ではありませんか?】
介護認定等級の有効期間と区分変更手続き

介護認定の等級には有効期間が設定されており、期間満了前に更新手続きが必要です。また、状態の変化があった場合は有効期間中でも等級変更が可能です。
有効期間の設定:
・新規申請:原則6か月(3~12か月の範囲で調整)
・更新申請:原則12か月(3~36か月の範囲で調整)
・区分変更:原則6か月(3~12か月の範囲で調整)
区分変更が必要な場合:
・病気やケガにより状態が悪化した場合
・リハビリにより状態が改善した場合
・認知症の症状が進行した場合
・現在の等級では必要なサービスが利用できない場合
区分変更の申請は随時可能ですが、前回の認定から一定期間経過していることが望ましいとされています。ケアマネジャーや地域包括支援センターと相談し、適切なタイミングで申請しましょう。
更新時期が近づくと、市区町村から通知が届きます。通知を受けたら早めに更新手続きを行い、サービス利用に支障が出ないよう注意しましょう。
介護認定等級別の具体的なサービス内容と費用
介護認定の等級により利用できるサービスは大きく異なります。ここでは、等級別の具体的なサービス内容と、実際の利用例について詳しく解説します。
要支援1・2で受けられる介護予防サービス

要支援1・2の方は、介護予防サービスが中心となります。状態の悪化を防ぎ、自立した生活を継続することが主な目的です。
要支援1で利用可能なサービス例:
・介護予防訪問介護:週1~2回程度の生活援助
・介護予防通所介護:週1回程度のデイサービス
・介護予防福祉用具貸与:手すり、歩行器など
・介護予防住宅改修:段差解消、手すり設置など(上限20万円)
要支援2で利用可能なサービス例:
・介護予防訪問介護:週2~3回程度の生活援助
・介護予防通所介護:週2回程度のデイサービス
・介護予防短期入所生活介護:月数日のショートステイ
・介護予防特定施設入居者生活介護:有料老人ホーム等での生活支援
要介護1から3の等級別サービス利用例

要介護1から3は、軽度から中等度の介護が必要な段階で、在宅サービスを中心としながら、必要に応じて施設サービスも利用できます。
要介護1の方の一般的なサービス利用例:
・訪問介護:週2回(身体介護1回、生活援助1回)
・通所介護:週1回
・福祉用具貸与:歩行器、シルバーカーなど
・月額費用:約12,000円~15,000円(1割負担)
要介護2の方の一般的なサービス利用例:
・訪問介護:週3回(身体介護2回、生活援助1回)
・通所介護:週2回
・福祉用具貸与:車いす、特殊寝台など
・月額費用:約15,000円~19,000円(1割負担)
要介護3の方の一般的なサービス利用例:
・訪問介護:週4回(身体介護中心)
・通所介護:週2回
・短期入所生活介護:月3~4日
・福祉用具貸与:車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具など
・月額費用:約20,000円~27,000円(1割負担)
要介護3以上になると、特別養護老人ホームへの入所申込みも可能になります。ただし、入所には待機期間があるため、早めの申込みが重要です。
要介護4・5の重度等級で利用可能な施設サービス

要介護4・5は重度の介護が必要な段階で、24時間体制の見守りや介護が必要となります。在宅サービスの限界を超える場合も多く、施設サービスの検討が重要になります。
要介護4の方の在宅サービス利用例:
・訪問介護:1日2回(身体介護中心)
・通所介護:週3回
・短期入所生活介護:月5~7日
・夜間対応型訪問介護:安否確認と緊急時対応
・月額費用:約25,000円~30,000円(1割負担)
要介護5の方の在宅サービス利用例:
・訪問介護:1日3回(身体介護中心)
・通所介護:週2回
・短期入所生活介護:月7~10日
・訪問看護:週1回
・月額費用:約30,000円~36,000円(1割負担)
利用可能な施設サービス:
・特別養護老人ホーム:要介護3以上、月額費用8~15万円
・介護老人保健施設:要介護1以上、月額費用9~17万円
・介護療養型医療施設:要介護1以上、月額費用10~20万円
・介護医療院:要介護1以上、月額費用9~18万円

介護認定の等級によってサービス内容が大きく変わります。現在の状態に最適なサービスを受けるためには、正確な認定調査が重要ですね。
専門家に相談することの重要性
介護認定の等級申請や適切なサービス選択は、制度が複雑で判断に迷うことも多いため、専門家のサポートを受けることが重要です。
認定申請と等級判定のサポート

地域包括支援センターは、介護認定の申請代行から認定後のサービス利用まで、包括的にサポートしてくれる頼りになる存在です。認定調査の準備や、適切な等級判定を受けるためのアドバイスも提供してくれます。
また、ケアマネジャーは、認定後のサービス利用について専門的な知識を持っており、等級に応じた最適なケアプランを作成してくれます。
介護の悩みと専門相談の活用

介護認定の等級や制度について不安を感じている方は、専門家に相談することをおすすめします。
介護認定の等級は、今後の介護生活を大きく左右する重要な制度です。一人で悩まず、専門的な知識と経験を持つ相談員からのアドバイスを受けることで、適切な等級認定と最適なサービス利用につなげることができるでしょう。
初回20分の無料相談を利用して、現在の疑問や不安を専門家と一緒に整理してみませんか。夜間も対応しているため、忙しい方でも相談しやすい環境が整っています。
介護認定等級を理解して適切なサービスを受ける方法:まとめ
介護認定の等級制度は、非該当から要介護5まで8段階の区分により、個人の介護や支援の必要度を客観的に評価する重要な仕組みです。
要支援1・2は介護予防が中心で月額5,000円~10,500円、要介護1~5は本格的な介護サービスが利用でき月額16,700円~36,200円の範囲でサービスを受けることができます。等級が上がるほど利用できるサービスの幅が広がり、特別養護老人ホームなどの施設サービスも段階的に利用可能になります。
適切な等級認定を受けるためには、認定調査で普段の状態を正確に伝えることが重要です。家族の同席や具体的な困りごとの説明により、客観的で正確な情報提供を心がけましょう。
介護認定の等級は、介護を受ける方とその家族にとって生活の質を左右する重要な制度です。事前に制度を理解し、適切な準備を行うことで、必要な時に迅速かつ適切なサービスを受けることができるでしょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。