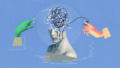「両親とも認知症になって、お互いの面倒を見合っている状況が心配」「認知症の夫が認知症の妻を介護しているが、果たして適切なケアができているのか不安」「遠方に住む両親の様子がおかしい。認知症同士で生活しているようだが、どう対応すべきか」
このような状況は「認認介護」と呼ばれ、高齢化が進む日本社会で急速に増加している深刻な問題です。厚生労働省の調査によると、要介護者と主な介護者がともに65歳以上の「老老介護」世帯は約6割に上り、そのうち認知症同士の「認認介護」も相当数存在すると推測されています。
認認介護は、介護する側もされる側も認知機能が低下しているため、適切なケアが困難になり、様々な危険やリスクを抱えています。しかし、適切な支援体制を構築することで、安全で質の高い生活を維持することは可能です。この記事では、認認介護の実態と問題点を詳しく解説し、具体的なリスクへの対処法から、活用できる制度・サービス、そして家族や地域ができるサポートまで、包括的な解決策をお伝えします。
認認介護の実態と深刻化する社会的背景
まずは、認認介護とは何か、そしてなぜ現代社会でこの問題が深刻化しているのかを理解しましょう。
認認介護とは?老老介護との違いと特徴

認認介護とは、認知症の高齢者が、同じく認知症の配偶者や家族を介護している状態を指します。
例えば、軽度認知症の80歳の夫が、中等度認知症の78歳の妻の食事や入浴の介助をしているケースや、認知症の70代の息子が、同じく認知症の90代の母親の世話をしている状況などが該当します。
老老介護が「65歳以上の高齢者が65歳以上の家族を介護する状況」を指すのに対し、認認介護は介護者と被介護者の双方が認知症という点で大きく異なります。
服薬管理ができない、または忘れてしまうため、薬の飲み忘れや重複投与のリスクが高くなります。認知症の進行を抑制する薬や、高血圧・糖尿病などの慢性疾患の薬が適切に管理されないと、健康状態の急激な悪化につながる可能性があります。
食事の準備や栄養管理が困難になります。料理の手順を忘れる、火の扱いが危険になる、食材の賞味期限が分からなくなる、同じものばかり食べるなどの問題が生じ、栄養失調や食中毒のリスクが高まります。
金銭管理能力が失われることで、詐欺被害に遭いやすくなったり、公共料金の支払いを忘れたり、不必要な買い物を繰り返したりする問題が発生します。
清潔保持が困難になり、入浴や着替え、掃除などが適切に行われず、不衛生な環境での生活を強いられる場合があります。
最も深刻なのは、問題が発生していても周囲に助けを求めることができない点です。認知症の症状により、自分たちの置かれた状況を正確に把握できず、必要な支援を受けることなく孤立してしまうのです。
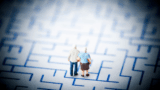
高齢化社会で増加する認認介護の現状

日本の認認介護が増加している背景には、急速に進行する高齢化社会の構造的な問題があります。
2025年には団塊の世代がすべて75歳以上となり、認知症高齢者数は約700万人に達すると予測されています。認知症の有病率は年齢とともに上昇し、80歳代前半で約2割、90歳代前半で約5割の人が認知症になるとされています。
核家族化の進行により、子どもたちが遠方に住んでいるケースが多く、高齢の親の変化に気づくのが遅れがちです。また、子ども自身も50代、60代となり、仕事や自分の健康問題を抱えているため、親の介護に十分な時間を割けない現実があります。
地域コミュニティの希薄化も問題を深刻化させています。かつては近所同士の付き合いが密で、高齢者の異変に早期に気づく仕組みが自然に存在していました。しかし現在では、隣近所との関係が疎遠になり、認認介護の状況が長期間発見されないケースが増えています。
さらに、認知症に対する社会の理解不足や偏見により、家族が認知症を隠そうとする傾向もあります。「恥ずかしい」「周りに迷惑をかけたくない」という思いから、外部の支援を拒み、結果として認認介護の状況が悪化してしまうのです。
認認介護が見落とされやすい理由と早期発見の重要性

認認介護は、その特性上、問題が表面化するまでに長期間を要することが多く、発見が遅れがちです。
認知症の症状は個人差が大きく、軽度の段階では日常生活がある程度維持できるため、周囲から見ると「普通に生活している」ように見えることがあります。特に、長年連れ添った夫婦の場合、お互いの習慣や癖を熟知しているため、認知症の初期症状を「年のせい」「いつものこと」として受け流してしまいがちです。
認知症の進行は緩やかなため、同居している家族も変化に気づきにくいという問題もあります。毎日一緒にいると、少しずつ進行する変化を「正常範囲内の老化」として受け入れてしまい、客観的な判断ができなくなってしまうのです。
また、認知機能がある程度保たれている段階で適切な支援体制を構築することで、将来への備えもできます。成年後見制度の利用、遺言書の作成、介護サービスの事前相談など、重要な判断や手続きは、判断能力があるうちに行う必要があります。
さらに重要なのは、家族や地域の支援ネットワークを早期に構築することです。認知症が軽度の段階であれば、本人たちも支援を受け入れやすく、スムーズに必要なサービスを導入できます。
定期的な安否確認、服薬管理の支援、栄養状態のチェック、住環境の安全確認など、小さなサポートを積み重ねることで、認認介護による重大なリスクを予防できるのです。
認認介護が抱える深刻なリスクと問題点
認認介護では、介護者と被介護者双方の認知機能低下により、様々な深刻なリスクが生じます。
服薬管理と健康管理ができない危険性

認認介護における最も深刻な問題の一つが、適切な服薬管理と健康管理ができないことです。
認知症の治療には、アルツハイマー型認知症の進行を遅らせるドネペジル(アリセプト)、メマンチン(メマリー)などの薬剤が使用されます。これらの薬は、決められた時間に正確な量を服用することで効果を発揮しますが、認知症患者が自分で管理することは困難です。
高血圧、糖尿病、心疾患などの慢性疾患を抱えている高齢者は多く、これらの薬の管理も複雑になります。血圧降下薬の飲み忘れは脳卒中のリスクを高め、糖尿病薬の不適切な服用は血糖コントロール不良による合併症を引き起こす可能性があります。
薬を飲んだかどうか忘れてしまい、同じ薬を何度も服用する重複投与のリスクがあります。血圧降下薬や糖尿病薬の過剰摂取は、生命に関わる低血圧や低血糖を引き起こす可能性があります。
逆に、薬を飲み忘れることで病状が悪化するリスクもあります。認知症治療薬の中断は症状の急激な悪化を招き、高血圧薬の中断は脳卒中や心筋梗塞のリスクを高めます。
薬の種類や量を間違える誤薬のリスクも深刻です。似たような外見の薬を取り違える、他人の薬を服用してしまう、期限切れの薬を服用するなどの事故が起こりやすくなります。
健康状態の変化に気づけない問題も深刻です。体調不良や異常な症状が現れても、認知症により適切な判断ができず、重篤な状態になってから発見されることがあります。
脱水症状、栄養失調、感染症、骨折などの身体的な問題が見過ごされ、命に関わる状況に発展することもあります。特に夏場の熱中症は、高齢者にとって生命に関わる危険性がありますが、認認介護では適切な対応が困難です。
定期通院ができなくなることで、慢性疾患の管理が困難になります。通院日を忘れる、病院への行き方が分からなくなる、症状を正確に医師に伝えられないなどの問題が生じ、医療との連携が断たれてしまいます。
火災・事故・介護放棄のリスク増大

認認介護では、日常生活での安全管理ができなくなることで、重大な事故のリスクが著しく高くなります。
認認介護の場合、火災が発生しても適切な避難行動が取れず、双方が犠牲になるケースもあります。
転倒・転落事故も頻繁に発生します。足腰の筋力低下に加え、認知症による空間認識能力の低下で、階段を踏み外す、浴室で滑る、夜間にトイレに行く際に転倒するなどの事故が起こりやすくなります。
骨折した場合の対応も困難になります。痛みを適切に訴えることができない、応急処置の方法が分からない、救急車の呼び方が分からないなどの問題により、適切な治療を受けるまでに時間がかかってしまいます。
食中毒や誤飲のリスクも高まります。賞味期限切れの食品を食べる、腐った食材を使って調理する、食べ物ではないものを口にするなど、危険な行動が増加します。
特に、洗剤や薬品を飲み物と間違えて摂取する事故は、生命に直結する危険性があります。認知症の進行により、色や匂いでの識別能力が低下し、このような事故が発生しやすくなります。
徘徊による行方不明も深刻な問題です。認知症の症状により、家の場所が分からなくなる、目的もなく外出して帰れなくなるケースが増加します。認認介護の場合、配偶者が徘徊に出かけても、それを止めることができない、警察に通報できないなどの問題が生じます。
さらに深刻なのは、介護放棄や虐待のリスクです。認知症の進行により介護者の判断力が低下すると、適切なケアを提供できなくなります。食事を与えない、清潔を保てない、必要な医療を受けさせないなどの介護放棄が無自覚のうちに発生することがあります。
また、認知症の症状によるイライラや混乱から、介護者が被介護者に対して暴言や暴力を振るってしまうケースもあります。これは意図的な虐待ではなく、認知症の症状による行動ですが、結果的に被介護者の心身に深刻な影響を与えてしまいます。

介護者と被介護者双方の心理的負担

認認介護では、身体的なリスクだけでなく、心理的・精神的な負担も非常に大きくなります。
認知症の進行により、長年連れ添った配偶者や家族の人格が変化することで、深い喪失感や悲しみを感じることがあります。「あいまいな喪失」と呼ばれるこの状態は、物理的には存在しているのに、精神的には失ってしまったような複雑な感情を生み出します。
介護者自身も認知症であるため、この複雑な感情を整理し、受け入れることが困難になります。混乱、不安、怒り、絶望感などの負の感情が増幅され、精神的な不安定さが増加します。
夜間の徘徊や不穏行動により、十分な睡眠が取れなくなることで、身体的疲労と精神的ストレスが蓄積されます。慢性的な疲労状態は、判断力のさらなる低下を招き、悪循環を生み出します。
経済的不安も心理的負担を増大させます。認知症の進行により金銭管理ができなくなり、生活費や医療費に関する不安が常にある状態は、大きなストレス要因となります。
将来への不安も深刻です。「この状況がいつまで続くのか」「さらに状態が悪化したらどうなるのか」「誰が自分たちを助けてくれるのか」といった不安が、日常的に心を支配してしまいます。
こうした心理的負担は、認知症の症状をさらに悪化させる可能性があります。ストレスは認知機能の低下を促進し、うつ状態や不安障害を併発させることもあります。

特に夜間に不安が強くなることが多く、「誰にも言えない」「夜中に不安で眠れない」といった状況が頻繁に発生します。このような時に気軽に相談できる場所があることは、心理的負担の軽減にとって極めて重要です。

認認介護を支える制度とサービスの活用法
認認介護の困難な状況を改善するためには、様々な制度やサービスを適切に活用することが不可欠です。
地域包括支援センターを中心とした支援体制

認認介護への対応で最も重要なのは、地域包括支援センターを中心とした包括的な支援体制の構築です。
地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支える地域の拠点として、各市町村に設置されています。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が配置されており、認認介護のような複雑な問題にも対応できる体制が整っています。
地域包括支援センターの主なサポート内容
・認認介護の実態調査(家庭訪問による専門的評価)
・要介護認定の申請支援と代行手続き
・適切な医療機関への紹介と受診調整
・24時間対応可能な緊急連絡体制の整備
・家族間の調整と情報共有のサポート
・地域見守りネットワークの構築
認認介護の発見段階では、包括支援センターが中心となって実態調査を行います。家庭訪問により、住環境の安全性、健康状態、認知機能の程度、日常生活の自立度などを専門的な視点で評価し、緊急度と必要な支援内容を判断します。
要介護認定の申請支援も重要な役割です。認認介護の状況では、家族だけで要介護認定の手続きを行うことは困難な場合が多いため、包括支援センターが代行したり、手続きをサポートしたりします。
認知症の診断や治療についても、適切な医療機関への紹介と受診調整を行います。かかりつけ医との連携により、認知症の進行度合いを正確に把握し、最適な治療方針を決定するサポートをします。
緊急時対応体制の整備も包括支援センターの重要な機能です。24時間対応可能な連絡体制を構築し、急病、事故、徘徊などの緊急事態に迅速に対応できるよう準備します。
家族への相談支援も継続的に行います。認認介護では、遠方に住む子どもたちが状況を理解し、適切な支援を提供することが重要です。包括支援センターが家族間の調整役となり、情報共有と役割分担を促進します。
地域の見守りネットワークの構築も推進します。民生委員、町内会、商店街、宅配業者、郵便局員など、日常的に高齢者と接する機会のある地域住民や事業者と連携し、異変の早期発見体制を作ります。
介護保険サービスの戦略的な組み合わせ

認認介護では、複数の介護保険サービスを戦略的に組み合わせることで、安全で質の高い生活を支援することが可能です。
特に重要なのは服薬管理支援です。薬剤師や看護師と連携し、一週間分の薬をセットする薬ケースの活用、服薬チェック表の記入、残薬の確認などを通じて、適切な服薬を確保します。
訪問看護サービスでは、医師の指示に基づいて看護師が定期的に訪問し、健康状態のモニタリング、医療的なケア、家族への指導を行います。血圧測定、血糖値チェック、創傷処置、点滴管理など、医療と介護の橋渡し役を担います。
認知症の行動・心理症状(BPSD)への対応も訪問看護の重要な役割です。興奮、不安、徘徊、不眠などの症状に対して、薬物療法と非薬物療法を組み合わせた専門的なケアを提供します。
デイサービスでは、入浴、食事、リハビリ、レクリエーション活動などを通じて、身体機能と認知機能の維持・向上を図ります。また、他の利用者との交流により、社会性の維持と精神的な安定を促進します。
ショートステイでは、認認介護では双方が疲弊しやすいため、定期的に利用することで、心身のリフレッシュを図ることができます。また、介護者の体調不良や入院時の緊急避難先としても重要な役割を果たします。
小規模多機能型居宅介護は、通所、訪問、宿泊を組み合わせた柔軟なサービスです。認認介護のように複雑で変化しやすい状況に対して、ニーズに応じてサービス内容を調整できるメリットがあります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間体制でサポートを提供するサービスです。認認介護では夜間の不安や緊急事態のリスクが高いため、いつでも専門職に相談できる体制があることは大きな安心材料となります。

多職種連携による見守りネットワークの構築

認認介護を安全に支援するためには、多職種が連携した包括的な見守りネットワークが不可欠です。
多職種連携の構成メンバー
・医療職:かかりつけ医、専門医、薬剤師、看護師
・介護職:ケアマネジャー、ヘルパー、デイサービススタッフ
・福祉職:地域包括支援センター職員、社会福祉士
・地域住民:民生委員、近隣住民、商店街、配達業者
医療職との連携では、かかりつけ医、専門医(認知症疾患医療センターの医師、精神科医、神経内科医)、薬剤師、看護師が中心となります。定期的な診察による健康状態の把握、薬物療法の調整、急変時の対応などを通じて、医学的な安全性を確保します。
介護職との連携では、ケアマネジャーが全体のコーディネート役を担い、ヘルパー、デイサービススタッフ、ショートステイスタッフなどが日常的なケアを提供します。情報共有システムを活用し、利用者の状態変化や気づいた点を関係者間で迅速に共有します。
福祉職との連携では、地域包括支援センターの社会福祉士が中心となり、権利擁護、経済的支援、家族調整などの相談支援を行います。成年後見制度の利用、生活保護の申請、虐待の予防・対応なども重要な役割です。
地域住民との連携では、民生委員・児童委員が中心的な役割を果たします。日常的な見守り活動を通じて、異変の早期発見と関係機関への通報を行います。近隣住民、商店街、宅配業者、郵便局員なども見守りネットワークの重要な構成員です。
AIやICTを活用した見守りシステムも導入が進んでいます。センサーによる活動量の測定、服薬管理アプリ、緊急通報システム、オンライン健康相談など、技術を活用したサポートにより、24時間の安心を提供できます。
家族との連携も欠かせません。遠方に住む子どもたちとも定期的に情報共有し、必要に応じて帰省やサポートを要請します。オンライン会議システムを活用したケア会議により、距離に関係なく家族が支援に参加できる仕組みも整備されています。

継続的な支援体制の調整や、関係者間の連携については、ケアマネジャーや地域包括支援センターの専門職と相談しながら進めることが重要です。一人で抱え込まず、チーム一体となって認認介護をサポートしていく姿勢が求められます。
認認介護とは?まとめ
認認介護は、高齢化社会の進展とともに今後ますます増加が予想される深刻な社会問題です。介護者と被介護者双方の認知機能低下により、服薬管理、健康管理、安全管理など、日常生活の基本的な部分で様々なリスクが生じます。
しかし、地域包括支援センターを中心とした支援体制、介護保険サービスの戦略的活用、多職種連携による見守りネットワークなど、適切な制度とサービスを組み合わせることで、認認介護でも安全で質の高い生活を維持することは可能です。
また、認認介護は一人や一つの機関だけで解決できる問題ではありません。医療、介護、福祉、地域住民が連携し、チーム一体となって支援していく体制づくりが不可欠です。
認知症になっても、適切なサポートがあれば尊厳を持って生活を続けることができます。認認介護という困難な状況にある方々が、孤立することなく、安心して生活できる社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができることから始めていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。