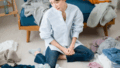「親の介護を施設に任せるなんて親不孝なのではないか」「施設に預けるなんて冷たい子どもだと思われるのではないか」「でも、もう自分一人では限界…」
親の介護を施設に任せることを検討している方の多くが、このような複雑な心境を抱えています。厚生労働省の調査によると、介護者の約6割が「施設利用に対して罪悪感を感じたことがある」と回答しており、この悩みは決して珍しいものではありません。
しかし、親の介護を施設に任せることは決して「逃げ」や「親不孝」ではありません。むしろ、親と家族の両方にとって最適なケアを提供し、持続可能な介護体制を構築するための合理的で愛情に満ちた選択なのです。この記事では、罪悪感を手放し、適切な判断ができるよう、施設選びから費用まで包括的に解説します。
親の介護を施設に任せることへの罪悪感を手放す方法
親の介護を施設に任せることに対する罪悪感は、多くの家族が抱く自然な感情です。しかし、この罪悪感にとらわれすぎることで、適切な判断を妨げてしまう可能性があります。まずは、なぜ罪悪感を感じるのか、そしてどうすれば健全な判断ができるのかを考えてみましょう。
「施設=親不孝」という思い込みから解放されるために

「親の面倒は子どもが見るもの」という価値観は、長い間日本社会に根付いてきました。しかし、この考え方は現代の社会情勢や家族構成、働き方の変化に必ずしも適合するものではありません。
現代の介護施設は、単に「親を預ける場所」ではありません。専門的な知識と技術を持った介護福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士、栄養士、社会福祉士などの多職種チームが連携して、利用者一人ひとりに最適なケアを提供する専門機関なのです。
家族による介護と施設による介護を比較した場合、必ずしも家族による介護の方が優れているとは言えません。むしろ、専門的な技術や知識、適切な設備が整った施設の方が、安全で質の高いケアを提供できる場合が多いのです。
真の親孝行とは、親の安全と健康を確保し、尊厳を保ちながら生活してもらうことではないでしょうか。そのために最適な環境が施設であるならば、施設を選択することこそが親孝行と言えるでしょう。
また、多くの親自身も「子どもに迷惑をかけたくない」「子どもには自分の人生を大切にしてほしい」と願っています。子どもが介護のために自分の人生を犠牲にすることを、本当に喜ぶ親がどれだけいるでしょうか。
専門的ケアが親にもたらす安全性と生活の質向上

LIFULL介護が2022年に実施した調査によると、施設入居後のご本人の変化として「性格が穏やかになった」「体や病気の症状が改善した」「明るくなった」がトップ3として挙げられました。この結果は、施設介護が単なる「預かりサービス」ではなく、積極的に生活の質を向上させるサービスであることを示しています。
専門的な24時間ケアによる安全性の向上は、施設介護の最大のメリットの一つです。移乗介助、入浴介助、排泄介助などは、専門的な技術と適切な福祉用具を使用することで、利用者の身体的負担を最小限に抑えながら、安全に行うことができます。
医療的ケアの充実も重要なポイントです。看護師が常駐している施設では、血圧測定、血糖値チェック、薬の管理、創傷処置などの専門的な医療的ケアを24時間体制で受けることができます。急変時の対応も迅速で、医療機関との連携も密に行われています。
認知症ケアにおいても、施設の専門性は大きな価値があります。認知症の症状に応じた適切な対応、徘徊や興奮への安全な対処、認知機能の維持・改善を目的としたプログラムなど、家族だけでは対応が困難な場面でも、専門的な知識と経験に基づいたケアが提供されます。
社会的交流の機会も大幅に増加します。在宅での介護では外部との接触が限られがちですが、施設では同年代の利用者との交流、職員との日常的なコミュニケーション、ボランティアとの触れ合いなど、豊富な人間関係を築くことができます。
介護の社会化と現代の価値観の変化

現代では、介護は家族だけで担うものではなく、社会全体で支え合うものという認識が広がっています。2000年に導入された介護保険制度は、まさに「介護の社会化」を目的として作られました。つまり、介護を家族の私的な問題ではなく、社会全体で解決すべき課題として位置づけたのです。
少子高齢化の進行により、従来の家族介護モデルは持続可能ではなくなっています。核家族化の進行、女性の社会進出、共働き世帯の増加、未婚率の上昇など、社会構造の変化により、家族だけで介護を担うことが現実的でない状況が増えています。
政府も「地域包括ケアシステム」を推進し、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される仕組みづくりを進めています。このシステムでは、家族、地域、専門機関が連携して高齢者を支えることが前提となっています。
企業の介護支援制度も充実
・介護休業制度(最大93日間の休業が可能)
・介護休暇制度(年間5日または10日の休暇取得)
・時短勤務制度やフレックスタイム制度
・介護費用の一部支援や相談窓口の設置
施設利用に対する世間の目も大きく変わっています。以前は「施設に入れるなんて」という批判的な見方もありましたが、現在では「適切な判断」「賢い選択」として評価されることが増えています。
国際的にも、介護の社会化は一般的な流れです。北欧諸国では早くから介護の社会化が進んでおり、家族が介護をすべて担うという考え方はむしろ少数派となっています。
重要なのは、施設に任せることと家族の関わりを放棄することは全く別のことだということです。施設に入居しても、家族としての愛情や関心、精神的サポートは継続できますし、むしろ介護の負担から解放されることで、より良い親子関係を築けることも多いのです。
親の介護を施設に任せる費用と経済的な準備
親の介護を施設に任せることを検討する際、最も気になるのが費用の問題です。施設の種類や立地によって費用は大きく異なりますが、適切な情報を持って計画的に準備することで、経済的な負担を軽減することができます。
施設種類別の費用相場と内訳詳細

施設選択において費用は重要な要素ですが、単純に安い施設を選べば良いというものではありません。提供されるサービス内容と費用のバランスを考慮し、親のニーズに最適な選択をすることが大切です。
公的施設の費用相場
特別養護老人ホーム(特養)は、要介護3以上の方が対象で、入居一時金は不要、月額費用は5万円から15万円程度です。居住費と食費は所得に応じて軽減措置があり、住民税非課税世帯では大幅に軽減されます。ただし、入居待機者が多く、申し込みから入居まで数年かかることもあります。
介護老人保健施設(老健)は、医療ケアとリハビリに重点を置いた施設で、月額費用は8万円から17万円程度です。在宅復帰を目指す中間施設としての性格が強く、原則として3か月から6か月程度の利用期間となります。
介護医療院は、長期にわたって医療的ケアが必要な方を対象とした施設で、月額費用は9万円から20万円程度です。医療保険と介護保険の両方が適用されるため、医療的ケアが充実しています。
民間施設の費用相場
介護付き有料老人ホームは最も一般的で、入居一時金が0円から数千万円、月額費用が15万円から40万円程度と幅が広くあります。立地、設備、サービス内容によって大きく異なるため、詳細な比較検討が必要です。
月額費用の内訳(例:介護付き有料老人ホーム)
・管理費:5万円~10万円
・食費:5万円~7万円
・居住費:3万円~15万円
・介護サービス費:2万円~6万円(要介護度により変動)
・その他:医療費、理美容代、おむつ代など月3万円~8万円
住宅型有料老人ホームは、生活支援サービスは提供しますが、介護サービスは外部事業者と別途契約する形態です。月額費用は12万円から30万円程度で、介護度が上がると外部サービス利用料が増加する傾向があります。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、安否確認と生活相談サービスが提供される住宅で、比較的自立度の高い方に適しています。月額費用は10万円から25万円程度ですが、介護が必要になった場合の追加費用を考慮しておく必要があります。
グループホームは認知症の方を対象とした小規模な施設で、家庭的な環境で生活できるのが特徴です。月額費用は12万円から20万円程度で、認知症専門のケアが受けられます。
費用負担を軽減する制度と活用方法

介護施設の費用負担を軽減するための制度は複数あります。これらを適切に活用することで、経済的な負担を大幅に削減することができます。
介護保険負担限度額認定制度
この制度は、住民税非課税世帯の方が対象で、施設での居住費と食費が大幅に軽減されます。認定を受けると、1日あたりの居住費が多床室で370円、個室で820円に軽減され、食費も1日1,445円に軽減されます。年間で数十万円の負担軽減につながる重要な制度です。
高額介護サービス費制度
月の介護サービス利用料の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。一般的な所得の世帯では月額44,400円が上限となり、それを超えた分は後日返金されます。
医療費控除の活用
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院では、施設サービス費の一部が医療費控除の対象となります。年間の医療費が10万円を超える場合、確定申告により所得税と住民税の軽減が可能です。
社会福祉法人等利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営する施設では、低所得の方を対象とした独自の軽減制度があります。介護サービス費の自己負担分や居住費・食費が軽減される場合があります。
地方自治体の独自制度
多くの自治体で、独自の介護費用軽減制度を設けています。利用料の助成、入居一時金の貸付、家族介護者への支援金など、地域によって様々な制度があるため、居住地の自治体に確認することが重要です。
親の資産状況に応じた費用計画の立て方

施設介護の費用計画を立てる際は、親の資産状況を正確に把握し、長期的な視点で検討することが重要です。厚生労働省の調査によると、介護を必要とする人の約84%が、自身や配偶者の収入や貯蓄から介護費用を捻出しています。
資産状況の把握方法
まず、親の収入(年金、不動産収入、その他)と貯蓄(預貯金、株式、保険、不動産など)を正確に把握しましょう。年金額は年金定期便や年金事務所で確認でき、平均的な厚生年金受給額は月額約14万円、国民年金は月額約6万円程度です。
費用計画のシミュレーション
平均的な施設利用期間は約4年から5年と言われています。月額20万円の施設を利用した場合、5年間で1,200万円の費用がかかる計算になります。年金収入を差し引いた実質的な負担額を算出し、貯蓄で賄えるかを検討しましょう。
例えば、月額20万円の施設費用に対して年金収入が月額12万円ある場合、実質負担は月額8万円となります。5年間では480万円の貯蓄が必要となる計算です。
不動産の活用検討
持ち家がある場合、売却して介護費用に充てることも選択肢の一つです。また、リバースモーゲージ(自宅を担保とした融資制度)を活用することで、住み慣れた家を手放さずに資金を調達することも可能です。
家族による費用負担
親の資産だけでは費用が不足する場合、家族による負担を検討する必要があります。兄弟姉妹間で公平に分担するためには、事前に話し合いを行い、収入や家族構成を考慮した負担割合を決めることが重要です。
必要に応じて、家庭裁判所での調停を利用することも可能です。感情的な対立を避け、客観的な基準で負担割合を決めることができます。
施設入所を検討すべきタイミングと判断基準
親の介護を施設に任せるタイミングの判断は、決して「もう限界だから」という理由だけで決めるべきではありません。親の状態、家族の状況、将来の見通しなど、様々な要因を総合的に考慮して、最適なタイミングを見極めることが重要です。
家族の介護限界と適切な入所時期の見極め

LIFULL介護が2023年に行った調査によると、施設入居のきっかけには「認知症の進行」「骨折・脳血管疾患などの病気」「入院をきっかけとした身体機能の低下」を挙げる方が大半でした。興味深いのは、半数以上の方が「入居時の要介護度は2以下だった」と回答している点です。
これは、重度になってから慌てて施設を探すのではなく、将来を見据えた早めの準備と入所が重要であることを示しています。
身体的限界のサイン
介護者の身体的限界を示すサインには以下のようなものがあります:
- 腰痛や肩こりが慢性化し、日常生活に支障をきたしている
- 夜間の介護で十分な睡眠が取れない状態が続いている
- 親の体重が増加し、移乗介助が困難になっている
- 入浴介助での転倒リスクが高まっている
- 医療的ケアが複雑化し、対応に不安を感じている
精神的限界のサイン
精神的な限界は身体的限界よりも気づきにくいことがあります:
経済的な持続可能性
在宅介護の継続には、介護者の就労継続が重要な要素となります。介護のために離職すると、収入の減少と将来の年金減額のダブルパンチを受けることになります。介護離職による生涯収入の減少額は平均で約2,000万円にも上ると言われています。
適切な入所時期の判断基準
施設入所の適切なタイミングは「限界に達する前」です。具体的には以下の状況が複数該当する場合、入所を真剣に検討すべきでしょう:
- 要介護度が2以上になり、日常生活の多くの場面で介助が必要
- 認知症の症状が進行し、見守りが24時間必要な状態
- 医療的ケアが必要で、家族の対応では不安が大きい
- 介護者が就労継続困難な状況に陥っている
- 家族関係の悪化が介護に影響を与えている
親の状態変化と安全性を考慮した判断ポイント

親の状態変化を客観的に評価し、安全性の観点から施設入所を検討することも重要です。感情的な判断ではなく、具体的な指標に基づいた客観的な判断を行いましょう。
転倒リスクの増大
高齢者の転倒は骨折につながりやすく、要介護状態の悪化や生命に関わる重篤な結果を招く可能性があります。以下の状況が見られる場合は、安全性の観点から施設入所を検討すべきです:
- 歩行が不安定で、杖や歩行器を使用しても転倒の危険がある
- 夜間のトイレでふらつきが見られる
- 薬の副作用でめまいやふらつきが生じている
- 住環境の段差や階段の昇降に不安がある
認知症症状による安全上の問題
認知症の進行により、以下のような安全上の問題が生じた場合は、専門的なケアが必要と判断されます:
医療的ケアの複雑化
疾患の進行により医療的ケアが複雑化した場合、家族だけでの対応では限界があります:
- 複数の薬剤管理が必要で、服薬スケジュールが複雑
- インスリン注射や血糖値測定が必要
- 褥瘡の処置やカテーテル管理が必要
- 嚥下機能低下により誤嚥性肺炎のリスクが高い
社会的孤立の進行
一人暮らしの親の場合、社会的孤立の進行も重要な判断要素となります。近所付き合いの減少、外出頻度の低下、会話相手の不在などにより、認知機能の低下や抑うつ状態を招く可能性があります。
親が施設入所を拒否する場合の説得方法

施設入所が客観的に必要と判断される状況でも、親本人が強く拒否することは珍しくありません。このような場合、感情的な説得ではなく、親の気持ちに寄り添いながら段階的にアプローチすることが重要です。
拒否の理由を理解する
まず、なぜ施設入所を拒否するのか、その理由を深く理解することから始めましょう。一般的な拒否理由には以下のようなものがあります:
- 「家族に迷惑をかけたくない」という遠慮
- 「まだ大丈夫」という現状認識の相違
- 施設に対する古い偏見やイメージ
- 住み慣れた環境への愛着
- 費用への心配
- 変化への不安や恐怖
段階的なアプローチ方法
急に「施設に入って」と言うのではなく、段階的にアプローチすることが効果的です:
段階的説得のステップ
1. **現状の不安を共有**:「心配だから一緒に考えたい」
2. **情報収集の提案**:「とりあえず見学だけしてみよう」
3. **体験利用の提案**:「数日だけ体験してみない?」
4. **メリットの具体的説明**:「こんな良いことがある」
5. **最終的な決断支援**:「一緒に決めよう」
第三者の活用
家族以外の第三者から説得してもらうことも効果的です:
- かかりつけ医師から医学的な観点でのアドバイス
- ケアマネジャーから専門的な見地での説明
- 地域包括支援センターの職員による相談
- 施設の相談員による丁寧な説明
- 同じ経験をした知人からの体験談
具体的な不安の解消
親が抱く具体的な不安に対して、一つひとつ丁寧に対応することが重要です。費用の心配があれば具体的な金額と支払い方法を説明し、施設のイメージが古い場合は最新の施設を見学してもらいます。

親の気持ちを理解しつつ、安全性を最優先に考えることが大切です。時間をかけて話し合い、親自身が納得できる選択をサポートしましょう。無理強いは逆効果になることもあるので、焦らずに進めることが重要ですよ。
緊急時の対応
転倒による骨折、急病による入院など、緊急事態が発生した場合は、親の同意を得やすいタイミングでもあります。このような機会を活用して、冷静に今後のことを話し合うことも重要です。
ただし、親の意思を完全に無視することはできませんし、すべきでもありません。最終的には親の気持ちを尊重しつつ、安全性とのバランスを考慮した現実的な解決策を見つけることが求められます。
親の介護を施設に任せる決断。まとめ

親の介護を施設に任せる決断は、決して簡単なものではありません。しかし、罪悪感にとらわれることなく、親と家族の両方にとって最適な選択肢を冷静に検討することが重要です。
現代の介護は社会全体で支え合うものという認識が広がり、専門的な施設でのケアが親の安全と生活の質向上に大きく貢献することが実証されています。LIFULL介護の調査でも、施設入居後に「性格が穏やかになった」「症状が改善した」「明るくなった」という前向きな変化が報告されています。
費用面では、公的な軽減制度を適切に活用することで経済的負担を大幅に削減できます。負担限度額認定制度、高額介護サービス費制度、医療費控除など、利用可能な制度を漏れなく活用しましょう。
施設入所のタイミングは「限界に達してから」ではなく「限界に達する前」が理想的です。要介護度2程度の比較的軽度な段階で入所を検討することで、親も新しい環境に適応しやすく、家族も余裕を持って対応できます。
最も大切なことは、親の安全と尊厳を守り、家族全体の幸せを考慮した上で決断することです。施設に任せることは愛情に基づいた前向きな選択であり、入所後も家族としての関わりは継続できます。
一人で悩まず、ケアマネジャーや地域包括支援センターなどの専門家に相談しながら、親と家族にとって最適な介護の形を見つけていきましょう。適切な支援を受けることで、親も家族も安心して生活できる環境を築くことができるはずです。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。