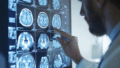「介護休業の93日間は年度が変わったらリセットされるの?」「土日も含めて数えるって本当?」「転職したら日数はどうなる?」
親の介護が必要になったとき、介護休業制度の利用を考える方は多いでしょう。しかし、93日間という期間の数え方やリセットの有無について、正確な情報を知らないまま取得すると、思わぬタイミングで休業できなくなる可能性があります。
この記事では、介護休業93日のリセットに関する正確なルールと、土日祝日を含む正しい数え方について詳しく解説します。分割取得の活用法から給付金申請のタイミングまで、実践的な情報をお伝えします。
介護休業93日の基本ルールとリセットの真実
介護休業制度を正しく活用するために、まず93日間の基本的なルールを理解しておきましょう。多くの方が誤解しているポイントも含めて、詳しく解説します。
対象家族1人につき通算93日までの原則

介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで取得できる制度です。この「通算」という言葉が重要なポイントとなります。
対象家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を指します。例えば、父親の介護で93日取得した場合、その後母親が要介護状態になれば、母親について改めて93日まで取得できます。
通算93日の意味は、複数回に分けて取得しても合計で93日が上限ということです。1回目に30日、2回目に40日取得した場合、残りは23日となります。
年度が変わっても93日はリセットされない

多くの方が誤解している点ですが、介護休業の93日は年度をまたいでもリセットされません。有給休暇のように年度ごとに新しく付与される制度ではないのです。
例えば、3月に30日間の介護休業を取得し、4月に新年度を迎えても、残りの日数は63日のままです。「新年度になったから、また93日使える」という考えは間違いです。
この原則は、同じ対象家族について、同じ勤務先で勤務している限り継続して適用されます。10年前に30日使っていても、その記録は残っており、新たに介護休業を取得する際は残り63日からスタートすることになります。
転職した場合のみリセットされる例外ケース

介護休業の93日がリセットされる唯一のケースが、勤務先が変わった場合です。転職により新しい職場で働き始めると、前の職場での取得日数はリセットされます。
例えば、A社で父親の介護のために70日間の介護休業を取得した後にB社へ転職した場合、B社では父親について改めて93日まで介護休業を取得できることになります。
ただし、これは法律上の原則であり、新しい職場での介護休業取得には別途条件があります。入社後1年未満の労働者は対象外となる場合もあるため、転職先の就業規則を確認する必要があります。
転職時のリセットに関する注意点
転職によって介護休業日数がリセットされますが、これを悪用して頻繁に転職を繰り返すことは、キャリア形成の面でも倫理的な面でも推奨されません。介護休業制度は本来、労働者の仕事と介護の両立を支援するための制度です。
介護休業93日の正しい数え方を理解する
介護休業の日数を正確に把握するためには、正しい数え方を理解することが不可欠です。間違った数え方をすると、予定していた日数が使えなくなる可能性があります。
土日祝日も含むカレンダー日数での計算方法

介護休業の93日間は、カレンダー上の日数で数えます。これは、土日祝日や会社の休日も含めた連続した日数という意味です。
例えば、月曜日から金曜日まで5日間の介護休業を取得した場合、実際に会社を休んだのは5日間ですが、介護休業日数としてはその間の土日を含めて7日間としてカウントされます。
これは有給休暇の数え方とは異なる点です。有給休暇は実際に勤務日に取得した日数だけをカウントしますが、介護休業はカレンダー通りに連続した日数として計算されるのです。
分割取得時の具体的な数え方の実例

介護休業は最大3回まで分割して取得できます。分割取得時の日数の数え方を具体例で見ていきましょう。
【具体例1】標準的な分割取得パターン
1回目:4月1日(月)〜4月14日(日)=14日間
2回目:6月15日(月)〜7月14日(日)=30日間
3回目:9月1日(月)〜9月30日(日)=30日間
合計:74日間(残り19日間)
【具体例2】週末を含む短期取得パターン
1回目:5月10日(金)〜5月12日(日)=3日間
この場合、金曜日の1日だけ会社を休んだとしても、土日を含めて3日間としてカウントされます。
分割取得では、各回の開始日と終了日をカレンダーで確認し、その間の全日数を合計することで、正確な取得日数を把握できます。
復職期間中の日数カウントの扱い

介護休業を取得した後、一時的に職場復帰した期間は、介護休業日数にはカウントされません。これは分割取得を活用する上で重要なポイントです。
例えば、4月1日から30日間の介護休業を取得し、5月1日に職場復帰した場合、5月中は介護休業日数としてカウントされません。その後6月1日から再び介護休業を取得した場合、残りの日数は63日となります。
この仕組みにより、介護の状況に応じて柔軟に休業と復職を繰り返すことができます。ただし、分割回数は最大3回までという制限があるため、頻繁に短期間の休業を繰り返すことはできません。
親の介護でお金がない時の対処法。公的支援制度や負担軽減策はある?
介護休業を最大限活用する計画的な取得方法
93日間という限られた期間を有効に活用するためには、計画的な取得方法を理解しておくことが重要です。給付金の申請方法や、93日使い切った後の選択肢も含めて解説します。
3回までの分割取得を効果的に使うポイント

介護休業は最大3回まで分割取得できる制度です。この分割取得を効果的に活用することで、介護の各段階に適切に対応できます。
【推奨される分割取得パターン】
1回目:介護体制の構築期間(2〜4週間)
親が突然倒れた直後など、緊急時に介護サービスの手配や施設の見学、医療機関との調整などを行う期間として利用します。
2回目:状態悪化時の対応期間(2〜6週間)
介護の状態が悪化し、新たな体制構築が必要になった際に利用します。施設への入所手続きや在宅介護サービスの見直しなどに活用できます。
3回目:終末期の付き添い期間(残りの日数)
看取りの時期など、できるだけ長く付き添いたい場合に残りの日数をまとめて使用します。
介護休業給付金の申請手続きとタイミング

介護休業を取得すると、介護休業給付金を受給できる可能性があります。給付金は休業開始時の賃金の67%が支給されるため、経済的な負担を軽減できます。
【給付金の受給要件】
雇用保険に加入しており、介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
【申請のタイミング】
介護休業終了日の翌日から2ヶ月以内に、会社を通じてハローワークに申請します。通常は会社の人事部門が手続きを代行してくれますが、自分で申請することも可能です。
分割取得の場合、各回の休業終了後にそれぞれ申請する必要があります。例えば、3回に分けて取得した場合は、3回それぞれについて申請手続きが必要となります。
93日使い切った後に利用できる制度

介護休業の93日間を使い切った後も、仕事と介護を両立するための制度があります。これらを組み合わせることで、長期的な介護に対応できます。
【介護休暇制度】
年間5日間(対象家族が2人以上の場合は10日間)、半日単位または時間単位で取得できる制度です。通院の付き添いや介護サービスの手続きなど、短時間の対応に活用できます。
【所定労働時間の短縮措置】
介護休業とは別に、介護が必要な期間中、所定労働時間を短縮できる制度です。1日の労働時間を6時間程度に短縮することで、介護と仕事の両立がしやすくなります。
【所定外労働の制限】
介護が必要な期間中、残業を制限できる制度です。定時で帰宅できるため、介護サービスの時間調整がしやすくなります。
【深夜業の制限】
午後10時から午前5時までの深夜勤務を制限できる制度です。夜間の介護に対応する必要がある場合に有効です。
93日使い切った後の選択肢チェックリスト
□ 介護休暇(年5日または10日)を活用する
□ 所定労働時間の短縮措置を申請する
□ 所定外労働の制限を申請する
□ 深夜業の制限を申請する
□ フレックスタイム制度を利用する
□ テレワークの導入を検討する
【93日で足りるのか、正直不安ではありませんか?】

介護休業は93日という限られた期間ですが、計画的に活用すれば効果的に介護体制を整えられます。分割取得や他の制度との組み合わせも検討してみてくださいね。
介護休業93日のリセットと数え方:まとめ
介護休業の93日間について、リセットの有無と正しい数え方を理解することで、制度を最大限に活用できます。
93日のリセットに関する重要ポイントは、年度が変わってもリセットされないこと、ただし転職した場合のみ新しい職場で改めて93日取得できることです。同じ対象家族について通算93日が上限という原則を忘れないようにしましょう。
正しい数え方は、土日祝日を含むカレンダー日数で計算することです。実際の勤務日数ではなく、連続した期間として日数をカウントします。
分割取得の活用により、介護の各段階に応じて柔軟に対応できます。最大3回まで分割できるため、緊急時、状態変化時、終末期など、それぞれのタイミングで適切に利用しましょう。
介護は長期戦になることも多く、介護休業だけでなく、介護休暇や労働時間短縮制度なども組み合わせて、持続可能な介護体制を構築することが重要です。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。