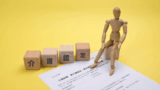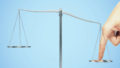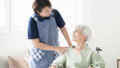「親に介護が必要になったけれど、どこに相談すればいいの?」
「居宅介護支援事業所って何をしてくれるところ?」
「ケアプランって自分で作れないの?」
介護が必要になった時、多くの方がこのような疑問を抱きます。

実は、居宅介護支援事業所は在宅介護を支える重要な拠点なんです。ケアマネジャーが常駐し、介護サービスの計画から調整まで、包括的にサポートしてくれる専門機関です。
この記事では、居宅介護支援事業所とは何かをわかりやすく解説します。役割や利用方法、他の機関との違いまで詳しく紹介しますので、初めて介護サービスを利用する方もぜひ参考にしてください。
居宅介護支援事業所とは何かをわかりやすく説明
居宅介護支援事業所について、基本的な役割から順番に見ていきましょう。難しい言葉は使わず、わかりやすく説明していきます。
ケアプラン作成の専門機関としての役割

居宅介護支援事業所の最も重要な役割は、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成することです。
ケアプランとは、どのような介護サービスを、いつ、どれくらい利用するかを決めた計画書のことです。訪問介護、デイサービス、福祉用具のレンタルなど、様々なサービスを組み合わせて、その人に最適な介護プランを立てます。
このケアプランがないと、介護保険を使ったサービスは利用できません。つまり、居宅介護支援事業所は在宅介護を始めるための入口となる大切な場所なんです。
また、ケアプランは一度作ったら終わりではありません。利用者の状態は変化していきますので、定期的に見直しを行い、その時々に最適な内容に更新していくんです。
ケアマネジャーが常駐する相談窓口

居宅介護支援事業所には、ケアマネジャー(介護支援専門員)という専門職が常駐しています。
ケアマネジャーは、介護に関する幅広い知識と経験を持つ専門家です。看護師、介護福祉士、社会福祉士などの資格を持ち、5年以上の実務経験を積んだ後、難関試験に合格した人だけがなれる職業なんです。
このケアマネジャーが、利用者や家族の相談に乗り、状態を評価し、最適なケアプランを作成します。介護のことで困ったことがあれば、いつでも相談できる頼れる存在といえるでしょう。
また、居宅介護支援事業所は「ケアプランセンター」という別名でも呼ばれています。どちらも同じ機関を指していますので、覚えておくと便利です。
【介護の始め方、何から手をつければいいかわからない方へ】
利用料が無料である理由

居宅介護支援事業所の大きな特徴は、利用者の自己負担が一切ないということです。
ケアプランの作成費用、ケアマネジャーへの相談料、サービス調整の費用など、居宅介護支援にかかる費用は全て介護保険から支払われます。利用者や家族は1円も払う必要がないんです。
なぜ無料なのでしょうか。それは、適切なケアプランを作ることが介護保険制度の根幹だからです。お金の心配なく、誰でも専門家のサポートを受けられるようにすることで、必要な人が必要なサービスを利用できる仕組みになっています。
ただし、居宅介護支援は無料でも、実際の介護サービス(訪問介護やデイサービスなど)の利用には、所得に応じて1〜3割の自己負担が発生します。この点は混同しないよう注意が必要です。
居宅介護支援事業所でできること
居宅介護支援事業所では、ケアプラン作成以外にも様々なサポートを受けられます。具体的に見ていきましょう。
介護保険申請の代行サポート

介護サービスを利用するには、まず市区町村で要介護認定の申請をする必要があります。
この申請手続きは、本人や家族が行うこともできますが、書類の準備や記入が複雑で戸惑う方も多いんです。また、病気や怪我で本人が動けない、家族も仕事で忙しいといった事情で、申請に行くこと自体が難しい場合もあります。
そんな時、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが申請を代行してくれます。必要な書類を揃え、記入を手伝い、市区町村の窓口に提出するところまで、全てサポートしてくれるんです。
介護認定申請の流れ
市区町村の窓口で申請→認定調査員による訪問調査→主治医意見書の作成→審査会での判定→認定結果の通知(申請から約30日)→ケアプラン作成→サービス利用開始
また、認定調査の際にも、ケアマネジャーが立ち会って、利用者の状態を正確に伝えるサポートをしてくれることもあります。
個別のケアプラン作成と定期的な見直し

要介護認定を受けたら、一人ひとりに合わせたケアプランを作成します。
ケアマネジャーは、まず利用者の自宅を訪問し、心身の状態、生活環境、家族の状況、本人の希望などを詳しく聞き取ります。これをアセスメント(課題分析)といいます。
次に、このアセスメントをもとに、どのようなサービスが必要かを検討し、ケアプランの原案を作成します。原案ができたら、利用者や家族、サービス事業所の担当者が集まって「サービス担当者会議」を開き、みんなで内容を確認して最終的なプランを決定するんです。
サービスが始まった後も、月に1回以上は自宅を訪問し、サービスが適切に提供されているか、状態に変化はないかを確認します。このモニタリングを通じて、常に最適なケアプランを維持していくわけです。
各種サービス事業所との連絡調整

ケアプランに基づいて、様々なサービス事業所との連絡調整も居宅介護支援事業所の重要な役割です。
在宅介護では、訪問介護、デイサービス、訪問看護、福祉用具レンタルなど、複数のサービスを組み合わせて利用することが一般的です。それぞれ別々の事業所がサービスを提供しますので、連絡や調整が必要になるんです。
ケアマネジャーは各サービス事業所との窓口となり、利用開始の手続き、スケジュール調整、サービス内容の変更など、全ての調整を担当します。利用者や家族が個別に連絡を取る必要はなく、ケアマネジャーに相談すれば全て対応してもらえるわけです。
また、急な入院や体調の変化など、予期せぬ事態が起きた時も、ケアマネジャーが中心となって対応します。必要なサービスの追加や変更、緊急のショートステイの手配など、迅速に対応してくれるんです。

ケアマネジャーは介護のコーディネーターなんですね。複数の事業所とのやり取りを一手に引き受けてくれるので、家族の負担がぐっと軽くなりますよ。
ケアマネージャーへの相談。できること・できないことの範囲は?
居宅介護支援事業所の利用方法をわかりやすく解説
実際に居宅介護支援事業所を利用するには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。順を追って説明します。
利用できる人の条件と対象者

居宅介護支援事業所を利用できるのは、要介護1〜5の認定を受けた方です。
要支援1・2の方は、原則として地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。ただし、2024年4月の法改正により、指定を受けた居宅介護支援事業所でも要支援者のケアプランを作成できるようになりました。
居宅介護支援という名前から「自宅に住んでいる人だけ」と思われがちですが、実は住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に住んでいる方も利用できるんです。特別養護老人ホームのような介護保険施設に入所している場合は、施設のケアマネジャーが担当するため、居宅介護支援事業所は利用しません。
事業所の探し方と選び方のポイント

居宅介護支援事業所は、利用者が自由に選ぶことができます。
まず、事業所のリストは市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターで入手できます。インターネットで「お住まいの地域名 居宅介護支援事業所」と検索しても見つけられます。全国に約38,000か所ありますので、選択肢は豊富です。
では、どのように選べばよいのでしょうか。まず重要なのは、自宅から近い事業所を選ぶことです。ケアマネジャーは定期的に自宅を訪問しますので、あまり遠いと対応が遅れる可能性があります。
事業所を選ぶポイント
自宅からの距離、事業所の規模と安定性、ケアマネジャーの経験年数、対応可能な時間帯、特定事業所加算の有無(質の高いサービスの目安)、口コミや評判、実際に会って話した印象
また、担当ケアマネジャーとの相性も大切です。長い付き合いになりますので、話しやすい、信頼できると感じる人を選びましょう。もし合わないと感じたら、事業所やケアマネジャーを変更することも可能なんです。
契約から利用開始までの流れ

事業所を選んだら、契約手続きから利用開始までの流れを確認しましょう。
まず、選んだ事業所に連絡して面談の予約を取ります。面談では、利用者の状態、家族の状況、希望するサービスなどを詳しく聞かれます。この時、介護保険証、介護認定通知書、健康保険証などを持参するとスムーズです。
面談で双方が納得できれば、契約書を交わします。契約書には、提供されるサービスの内容、個人情報の取り扱い、契約の解除方法などが記載されていますので、よく確認してから署名しましょう。
契約後、ケアマネジャーが自宅を訪問してアセスメントを行い、ケアプランを作成します。プランができたら、サービス担当者会議を開いて内容を確認し、問題がなければサービス利用が開始されます。
居宅介護支援事業所と他機関の違い
介護に関わる機関は複数あり、それぞれの違いを理解することが大切です。混同しやすい機関との違いを見ていきましょう。
地域包括支援センターとの違い

最も混同されやすいのが、地域包括支援センターです。
地域包括支援センターは、地域の65歳以上の全ての高齢者を対象とした総合相談窓口です。介護認定を受けていなくても相談できますし、介護以外の健康や生活の相談にも対応してくれます。市区町村が運営主体となっており、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーという3つの専門職が配置されています。
一方、居宅介護支援事業所は、要介護1以上の認定を受けた方を対象に、ケアプラン作成に特化した機関です。様々な法人が運営しており、ケアマネジャーが配置されています。
要支援の方は地域包括支援センター、要介護の方は居宅介護支援事業所が担当するのが基本です。ただし、要支援から要介護に変更になった場合は、スムーズに引き継ぎが行われます。
訪問介護事業所との違い

もう一つ混同されやすいのが、訪問介護事業所です。
訪問介護事業所は、実際に介護サービスを提供する事業所です。ホームヘルパー(訪問介護員)が自宅に訪問し、食事の準備、入浴介助、掃除、買い物など、日常生活の支援を行います。
居宅介護支援事業所は、このような訪問介護サービスを含めて、どのサービスをどう組み合わせるかを計画する機関です。つまり、計画を立てる側と実際にサービスを提供する側という違いがあるんです。
それぞれの機関を使い分ける方法

それでは、どの機関にいつ相談すればよいのでしょうか。
介護が必要になりそうだけれど、まだ認定を受けていない段階では、地域包括支援センターに相談します。「最近親の様子が変わってきた」「介護保険について知りたい」といった漠然とした相談も受け付けてくれます。
要介護認定を受けたら、居宅介護支援事業所を選んで契約します。以降は、介護に関する全ての相談は担当ケアマネジャーが窓口になります。
ただし、虐待の相談、権利擁護の相談、認知症に関する地域の取り組みなど、介護サービス以外の相談は地域包括支援センターが担当します。必要に応じて両方を活用するのが賢い方法です。

どこに相談すればいいか迷ったら、まず地域包括支援センターに電話してみてください。適切な窓口を案内してもらえますよ。
居宅介護支援事業所とは。まとめ
居宅介護支援事業所とは、在宅介護を支える重要な拠点です。ケアマネジャーが常駐し、要介護認定を受けた方のケアプランを作成し、介護サービス全体を調整する専門機関なんです。

最大の特徴は、利用者の自己負担が一切ないことです。ケアプラン作成、サービス調整、月1回以上の訪問など、全ての費用が介護保険から支払われます。お金の心配なく、専門家のサポートを受けられる仕組みになっています。
居宅介護支援事業所の役割は、単にケアプランを作ることではありません。利用者一人ひとりの状態や希望を理解し、最適なサービスを組み合わせ、継続的に見守りながら、その人らしい生活を支えることなんです。
全国に約38,000か所の事業所があり、自宅から近い場所を選べます。担当ケアマネジャーとの相性も大切ですので、実際に会って話してから決めることをお勧めします。もし合わないと感じたら、遠慮なく変更することも可能です。
地域包括支援センターとの違いも理解しておきましょう。地域包括支援センターは誰でも相談できる総合窓口で、要支援者のケアプランを作成します。居宅介護支援事業所は要介護者専門のケアプラン作成機関です。必要に応じて両方を活用することで、より充実したサポートを受けられます。
介護が必要になったら、まず要介護認定の申請をしましょう。認定を受けたら、居宅介護支援事業所を選んで契約します。以降は担当ケアマネジャーが心強いパートナーとなり、介護生活を一緒に支えてくれるんです。
「どこに相談すればいいかわからない」と悩んだら、まず地域包括支援センターに連絡してみてください。適切な窓口を案内してもらえますし、居宅介護支援事業所の紹介もしてくれます。
介護は決して一人で抱え込むものではありません。居宅介護支援事業所という専門機関を上手に活用しながら、住み慣れた自宅での生活を続けていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。