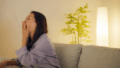「母が転んで起き上がれないと電話があり、慌てて駆けつけた」「父が一人で倒れていて、どれくらい床に横たわっていたのかわからない」「転倒後に自力で立てなくなり、救急車を呼ぶべきか迷った」
高齢者が転倒して起き上がれない状態は、介護家族にとって最も恐れる事態の一つです。実際、90歳以上の超高齢者の約3割が、転倒後に1時間以上起き上がれない状態を経験しているという調査結果もあります。
起き上がれないまま長時間床に横たわっていると、脱水、低体温、肺炎、褥瘡などの深刻な合併症リスクが高まります。しかし、正しい対処法を知っていれば、慌てずに適切な対応ができます。
この記事では、高齢者が転倒して起き上がれない原因、転倒直後の安全確認と救急車を呼ぶべき基準、安全な介助手順と予防策について詳しく解説します。万が一の事態に備えた知識を身につけましょう。
高齢者が転倒して起き上がれない主な原因
高齢者が転倒後に起き上がれなくなる原因は、複数の要因が絡み合っています。身体的な内的要因と環境的な外的要因の両方を理解することが、予防と適切な対処につながります。
筋力低下と関節の硬さが起き上がりを困難にする

高齢者が転倒後に起き上がれない最大の原因は、加齢による筋力の低下です。特に足腰や体幹の筋肉が衰えると、床から立ち上がるために必要な力が不足します。若い頃なら簡単にできた動作が、筋力の衰えによりできなくなるのです。
起き上がる動作には、複数の筋肉群の協調運動が必要です。腹筋、背筋、太ももの筋肉、お尻の筋肉などが連動して働くことで、床から体を持ち上げることができます。これらの筋肉のどれか一つでも著しく弱っていると、起き上がりは困難になります。
さらに、関節の硬さも起き上がりを妨げる要因です。膝関節や股関節の可動域が狭くなると、曲げ伸ばしが十分にできず、四つん這いの姿勢を取ることすら難しくなります。関節の柔軟性が失われると、起き上がるための体勢が取れないのです。
認知機能の低下と姿勢の悪さによる影響

高齢者が転倒後に起き上がれない原因として、認知機能の低下も大きく影響します。認知症や軽度認知障害がある場合、起き上がるための手順がわからなくなったり、安全確保の行動が取れなくなったりします。
転倒した時のパニック状態も判断力を鈍らせます。「どうやって起き上がればいいのか」「助けを呼ぶべきか」といった冷静な判断ができず、ただ横たわったまま時間が過ぎてしまうケースも少なくありません。
姿勢の悪さも起き上がりを困難にします。背中が丸まった円背姿勢や、前かがみの姿勢が習慣化していると、重心を正しく移動できません。起き上がる際には体重を前方に移し、膝と手で体を支える必要がありますが、姿勢が悪いとこの動作ができないのです。
また、バランス感覚の低下により、起き上がろうとしてもふらついてしまい、再び転倒する恐怖から動けなくなることもあります。転倒恐怖感が強いと、自分で起き上がろうとする意欲そのものが失われる場合もあります。
薬の副作用と環境要因が転倒後のリスクを高める

高齢者が転倒後に起き上がれない原因として、薬の副作用も見落とせません。睡眠薬や抗不安薬の影響でふらつきや眠気が生じると、転倒後に意識がもうろうとして起き上がる気力を失うことがあります。
降圧薬による起立性低血圧も問題です。立ち上がろうとした瞬間に血圧が急低下し、めまいや失神を起こすため、起き上がることができません。多剤併用により複数の副作用が重なると、リスクはさらに高まります。
環境要因も起き上がりを困難にします。床が滑りやすいと、手や膝で体を支えようとしても滑ってしまい、起き上がれません。周囲に掴まるための手すりや家具がないと、支えなしで起き上がることは極めて困難です。
照明が暗い場所で転倒すると、周囲の状況が把握できず、どこに手をつけばいいのか、どの方向に起き上がればいいのかがわかりません。段差や障害物が多い環境では、起き上がろうとして再び転倒するリスクも高まります。
転倒して起き上がれない時の正しい対処法
高齢者が転倒して起き上がれない状態を発見したら、慌てず冷静に対処することが重要です。安全確認、救急判断、適切な介助の3つのステップを理解しておきましょう。
転倒直後の安全確認と救急車を呼ぶべき基準

転倒した高齢者を発見したら、まず意識の有無を確認します。名前を呼んで反応があるか、目を開けているか、質問に答えられるかをチェックしましょう。意識がない、または意識が朦朧としている場合は、すぐに119番通報します。
次に、痛みの有無を確認します。「どこか痛いところはありますか」と尋ね、本人の訴えを聞きます。動けないほどの強い痛みがある場合、特に骨折の疑いがある時は、無理に動かさず救急車を呼びます。
以下の症状がある場合は、ためらわず救急車を呼ぶべきです。
すぐに救急車を呼ぶべき症状
意識がない、意識が朦朧としている
強い頭痛や顔の片側の麻痺がある
けいれんが止まらない
呼吸困難や胸の激しい痛みがある
動けないほどの強い痛み、骨折の疑い(強い痛み、腫れ、変形、骨が飛び出している)
大量出血が止まらない
嘔吐や吐き気が続く、吐血や血便がある
顔色が真っ青、冷や汗をかいている、ぐったりしている
高齢者は外見上は軽そうでも、内部の損傷が重篤な場合があります。事故直後は異常がなくても、後から症状が悪化することもあります。迷ったら救急相談窓口(#7119)やかかりつけ医に相談してください。
安全に起き上がらせるための介助手順

救急搬送の必要がなく、安全が確認できた場合は、ゆっくりと起き上がる介助を行います。焦らず、段階的に体勢を変えることが大切です。以下の手順で介助しましょう。
安全な起き上がり介助の手順
①近くに手すりのある椅子を用意する
安定した椅子を本人の近くに移動させます。背もたれと肘掛けがあるものが理想的です。
②横向きの姿勢にする
仰向けの状態から、まず横向き(側臥位)の姿勢にします。膝を曲げ、両手を胸の前で組んでもらい、介助者が肩と腰を支えて横に向けます。
③四つん這いの姿勢をとってもらう
横向きから、手と膝をついて四つん這いの姿勢になってもらいます。介助者は腰や背中を支え、ゆっくりと体を起こします。
④椅子のそばまで移動し、手すりを掴んでもらう
四つん這いのまま、椅子の方へ移動します。椅子の肘掛けや座面をしっかり掴んでもらいます。
⑤骨盤を支えつつ、ゆっくりと立ち上がりを補助する
介助者は本人の骨盤(腰の骨)を両手で支え、立ち上がりを補助します。本人のペースに合わせて、ゆっくりと行います。
介助の際は、本人の体力や理解度に合わせて無理をしないことが重要です。痛みや違和感を訴えたら、すぐに中止してください。一人での介助が難しい場合は、複数人で協力するか、専門家を呼びましょう。
長時間起き上がれない場合の深刻なリスク

高齢者が転倒後に長時間起き上がれない状態は、非常に深刻なリスクをもたらします。BMJ誌の研究によると、90歳以上の高齢者の約3割が、転倒後1時間以上床に横たわったままの状態を経験しています。
長時間横たわっていると、まず脱水症状が起こります。水分を摂取できないだけでなく、床の上で体温が奪われることで発汗が減り、気づかないうちに脱水が進行します。特に夏場や冬場の床は体温を奪いやすく危険です。
低体温症も命に関わるリスクです。床からの冷気により体温が低下し、意識レベルが低下します。高齢者は体温調節機能が衰えているため、若い人よりも低体温になりやすいのです。
長時間同じ姿勢で横たわっていると、褥瘡(床ずれ)が発生します。わずか数時間でも皮膚組織が壊死し始めることがあり、一度できると治療に長期間を要します。また、動かないことで肺の底に分泌物が溜まり、沈下性肺炎を起こすリスクも高まります。
さらに、筋肉が圧迫されることで横紋筋融解症という深刻な状態になることもあります。筋肉組織が壊死し、腎不全を引き起こす可能性があります。
【離れて暮らす親の「転倒」が心配ではありませんか?】
高齢者の転倒と起き上がれない状態を予防する方法
転倒して起き上がれない状態を予防するには、転倒そのものを防ぐことと、万が一転倒しても起き上がる力を維持することの両方が重要です。日常的な取り組みで、リスクは大幅に減らせます。
筋力トレーニングとバランス運動の重要性

転倒を予防し、起き上がる力を維持するために最も重要なのが、日頃からの筋力トレーニングです。特に下肢の筋力を鍛えることで、転倒リスクが減るだけでなく、万が一転倒しても自力で起き上がれる可能性が高まります。
自宅でできる簡単なトレーニングとして、椅子からの立ち座り運動が効果的です。背もたれのある安定した椅子に座り、手を使わずに立ち上がる動作を繰り返します。1日10回×3セットを目安に行いましょう。
片足立ち運動も有効です。壁や手すりに軽く手を添えて、片足を少し浮かせた状態を保ちます。左右各30秒ずつ、1日2~3回行うことで、バランス感覚と筋力が向上します。
バランス運動も転倒予防に効果的です。かかとから つま先へ、つま先からかかとへと重心を移動させる運動や、その場で足踏みをする運動などが推奨されます。
住環境の安全対策と転倒予防の工夫

転倒を予防するための住環境の整備も欠かせません。まず、段差の解消やスロープの設置により、つまずきのリスクを減らします。玄関、部屋の敷居、浴室の出入口など、わずかな段差でも対策が必要です。
手すりの設置は、転倒予防だけでなく、起き上がりの助けにもなります。廊下、階段、トイレ、浴室など、移動が多い場所や転倒リスクの高い場所に手すりを取り付けましょう。起き上がる際の支えとしても活用できます。
照明の確保も重要です。夜間のトイレ動線には、センサーライトやフットライトを設置します。暗がりでの転倒を防ぎ、万が一転倒しても周囲の状況を把握しやすくなります。
床の滑り止め対策も忘れずに行いましょう。浴室には滑り止めマット、廊下やリビングには滑りにくい床材を選びます。カーペットの端は固定し、電気コードは壁際に配線します。
緊急時の備えと家族ができるサポート

転倒後に長時間起き上がれない状態を避けるため、緊急時の備えが非常に重要です。特に一人暮らしの高齢者や、日中独居となる高齢者には、緊急通報システムの導入を強く推奨します。
緊急通報装置は、ボタンを押すだけで警備会社や家族に通報できるシステムです。ペンダント型やブレスレット型のものは、常に身につけておくことで、転倒後すぐに助けを呼べます。
見守りセンサーやカメラの設置も有効です。一定時間動きがない場合に家族に通知が届くシステムや、遠隔地から様子を確認できるカメラにより、早期発見が可能になります。
家族ができるサポートとしては、定期的な電話連絡や訪問が重要です。毎日決まった時間に電話をすることで、異変に気づきやすくなります。また、近所の方との関係を築き、何かあった時に助けを求められる体制を作っておくことも大切です。

転倒後に起き上がれない状態は、命に関わる深刻な事態です。予防と備えの両方が大切。専門家と相談しながら、できることから始めていきましょう。
高齢者の転倒で起き上がれない時の対処:まとめ
高齢者が転倒して起き上がれない主な原因は、筋力低下、関節の硬さ、認知機能の低下、姿勢の悪さ、薬の副作用、環境要因など、複数の要因が絡み合っています。加齢により起き上がるために必要な筋力が失われ、バランス感覚も衰えることで、自力での起き上がりが困難になります。
転倒直後は慌てず、意識の有無、痛みの有無を確認し、救急車を呼ぶべき症状がないかをチェックします。安全が確認できたら、横向き→四つん這い→椅子を支えに立ち上がるという段階的な介助を行います。長時間起き上がれない状態は、脱水、低体温、肺炎、褥瘡などの深刻なリスクをもたらします。
予防策としては、日頃からの筋力トレーニングとバランス運動、住環境の安全対策、緊急通報システムの導入が有効です。転倒そのものを防ぐとともに、万が一転倒しても起き上がる力を維持し、早期発見できる体制を整えることが重要です。
高齢者の転倒と起き上がれない状態は、命に関わる深刻な問題です。しかし適切な予防策と対処法を知ることで、リスクを大幅に減らせます。一人で抱え込まず、医師、理学療法士、ケアマネジャーなどの専門家とも連携しながら、大切な家族の安全を守っていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。