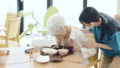「最近、親が新聞を読むのを嫌がるようになった」「テレビに近づいて見るようになった」「文字を読むのに時間がかかるようになった」
高齢のご家族の目が見えにくくなってきたとき、どう対応すればよいのか悩みますよね。視力低下は高齢者の生活の質を大きく低下させ、転倒や事故のリスクも高めます。
実は高齢者の目が見えにくくなる原因はさまざまで、適切な対策を取ることで、見えにくさを大きく改善できることも多いのです。
この記事では、高齢者の目が見えにくい原因から、生活環境の工夫、予防のための日常習慣、家族ができるサポート方法まで、実践的な対策を詳しく解説します。早期発見と適切な対応で、高齢者の視力と生活の質を守りましょう。
高齢者の目が見えにくい主な原因とは
高齢者の目が見えにくくなる原因は、加齢による自然な変化から、治療が必要な病気まで多岐にわたります。まずは原因を正しく理解しましょう。
加齢による目の変化と代表的な眼疾患

加齢とともに、目にはさまざまな変化が起こります。これらは自然な老化現象ですが、進行すると日常生活に支障をきたすこともあります。
老眼(presbyopia)は、最も一般的な加齢性の視力変化です。40代頃から始まり、60代以降はほとんどの人が経験します。目の水晶体が硬くなり、ピント調節機能が低下するため、近くのものが見えにくくなります。新聞や本を遠ざけて読むようになったら、老眼のサインです。
白内障は、高齢者の視力低下の最大の原因です。水晶体が濁ることで、視界が白くかすむ、まぶしく感じる、二重に見えるといった症状が現れます。80歳以上ではほぼ全員に何らかの白内障の変化が見られますが、進行度には個人差があります。
緑内障は、視神経が障害され、視野が徐々に狭くなる病気です。初期には自覚症状がほとんどなく、気づいたときにはかなり進行していることが多い危険な疾患です。一度失われた視野は戻らないため、早期発見が極めて重要です。
加齢黄斑変性は、網膜の中心部(黄斑)が障害される病気で、視界の中心が歪んだり、暗く見えたりします。欧米では成人の失明原因の第1位で、日本でも増加傾向にあります。ものが歪んで見える、中心が暗く見えるといった症状があれば、すぐに眼科を受診しましょう。
糖尿病網膜症は、糖尿病の合併症として起こる目の病気です。血糖コントロールが不十分だと、網膜の血管が障害され、視力が低下します。糖尿病がある方は、定期的な眼科検診が必須です。
日常生活で気づきにくい視力低下のサイン

高齢者の視力低下は、本人も家族も気づきにくいことがあります。「歳のせい」と思い込んで放置されることも多いため、以下のサインに注意しましょう。
行動の変化に注目することが大切です。新聞や本を読むのを避けるようになった、趣味の細かい作業(裁縫、プラモデルなど)をしなくなった、テレビを見る時間が減ったといった変化は、視力低下のサインかもしれません。
気づきにくい視力低下のサイン
・テレビに近づいて見るようになった
・新聞や本を遠ざけて読む
・読書や細かい作業を避ける
・階段の上り下りが慎重になった
・つまずいたり、ぶつかったりすることが増えた
・料理の失敗が増えた
・外出を嫌がるようになった
・表情が読みにくくなった
片目ずつの視力チェックを怠っていることも見落としの原因です。両目で見ていると、片方の目が悪くなっていても気づきにくいため、定期的に片目ずつ見え方を確認することが大切です。
夜間や暗い場所での見えにくさも重要なサインです。夜間の運転を嫌がる、暗い場所で歩くのを怖がる、夕方になると活動が鈍るといった変化があれば、視力低下を疑いましょう。
色の識別困難も見逃されがちです。服の色の組み合わせがおかしくなった、食材の新鮮さを見分けられなくなったといった変化も、視力低下のサインです。
認知機能への影響にも注意が必要です。視力低下により情報が入りにくくなると、脳への刺激が減り、認知症のリスクが高まることが研究で明らかになっています。「最近ボーッとしている」「会話が減った」といった変化も、視力低下が原因かもしれません。
すぐに受診すべき危険な目の症状

以下の症状が現れた場合は、すぐに眼科を受診する必要があります。これらは重大な目の病気のサインである可能性があります。
網膜剥離は、緊急性の高い疾患です。視野の一部が欠ける、カーテンがかかったように見える、飛蚊症が急に増えるといった症状があれば、すぐに受診しましょう。治療が遅れると失明の危険があります。
急性緑内障発作は、目の痛み、充血、急激な視力低下、吐き気などを伴います。眼圧が急上昇する緊急事態で、数時間以内に治療しないと失明することもあります。
硝子体出血も緊急性の高い状態です。糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症などで起こり、突然視界が暗くなったり、赤く見えたりします。

「様子を見よう」と思っているうちに、取り返しのつかないことになる場合もあります。少しでも異常を感じたら、すぐに眼科を受診してくださいね。
一人暮らしの高齢者の限界サインは?安全な生活を続ける基準を解説
高齢者の目が見えにくい時の生活環境対策
視力が低下しても、生活環境を工夫することで、日常生活の質を大きく向上させることができます。ここでは具体的な対策をご紹介します。
照明と色のコントラストを活用した工夫

明るさの確保は、視力低下がある高齢者にとって最も重要な対策の一つです。一般的に、高齢者は若い人の2〜3倍の明るさが必要だと言われています。
部屋全体の照明を見直しましょう。天井の照明だけでなく、スタンドライトやスポットライトを組み合わせることで、必要な場所を十分に明るくできます。特に読書や作業をする場所には、高輝度のスタンドライトを置くと効果的です。
色のコントラストを強調することも非常に効果的です。視力が低下すると、似た色の区別が難しくなるため、コントラストをはっきりさせることで見やすくなります。
キッチンでの工夫として、まな板を黒色にすると、白い食材(大根、玉ねぎ、豆腐など)が見やすくなります。逆に、濃い色の食材(肉、魚など)を扱うときは白いまな板を使うとよいでしょう。食器も、ご飯を盛るお茶碗は濃い色、煮物を盛る皿は白色にするなど、食材とのコントラストを考えて選びます。
階段や段差には、コントラストテープを貼ると安全性が高まります。段の縁に黄色や白のテープを貼ることで、段差がはっきり見えるようになり、転倒リスクが減ります。
壁と床の色も考慮しましょう。壁と床の色が似ていると、境界がわかりにくくなります。できれば、壁は明るい色、床は暗めの色にするなど、コントラストをつけることをおすすめします。
拡大鏡や補助具を使った読み書きの対策

読み書きが困難になると、生活の質が大きく低下します。補助具を活用することで、この問題を大きく改善できます。
拡大鏡(ルーペ)は、最も手軽な補助具です。手持ち式、置き型、首掛け式など、用途に応じてさまざまなタイプがあります。新聞を読むなら置き型、外出先で使うなら首掛け式が便利です。倍率は2〜3倍程度から試すとよいでしょう。
拡大読書器は、カメラで文字を拡大してモニターに映す機械です。倍率を自由に変えられ、コントラストも調整できるため、非常に見やすくなります。据え置き型と携帯型があり、据え置き型は本や新聞を読むのに、携帯型は外出先で使うのに適しています。
読み書きを楽にする補助具
・拡大鏡(ルーペ):手軽で持ち運びしやすい
・拡大読書器:大きく拡大でき、長時間の使用に適する
・大きな文字の時計・電卓・リモコン
・音声付き体温計・血圧計
・太い芯の鉛筆・ペン
・罫線が太いノート
書類を見やすくする工夫も大切です。白い紙に太い黒字で書くことで、コントラストが上がり読みやすくなります。ボールペンよりも、太めのフェルトペンやマジックで書くとよいでしょう。
日常生活用具も、見やすいものを選びましょう。大きな文字の時計、ボタンが大きいリモコン、音声で時刻を知らせる置き時計など、高齢者向けの製品が多数販売されています。
福祉制度の活用も検討しましょう。身体障害者手帳を取得すると、拡大読書器などの補助具を補助金で購入・レンタルできる場合があります。視力が一定以下になった場合は、眼科医に相談してみてください。
デジタル機器の設定変更と音声機能活用

スマートフォンやタブレットは、設定を変更することで視力低下がある高齢者にも使いやすくなります。デジタル機器は情報収集や家族とのコミュニケーションに欠かせないため、ぜひ活用しましょう。
文字サイズの変更は、最も基本的な設定です。iPhoneやiPadなら「設定」→「画面表示と明るさ」→「テキストサイズ」で文字を大きくできます。Androidスマホなら「設定」→「ディスプレイ」→「フォントサイズ」で調整できます。
画面の明るさも調整しましょう。明るすぎても暗すぎても見にくいため、環境に合わせて適切な明るさに設定します。自動調整機能をオンにしておくと便利です。
音声読み上げ機能は、画面の文字を音声で読み上げてくれる便利な機能です。iPhoneなら「設定」→「アクセシビリティ」→「読み上げコンテンツ」で設定できます。ニュースやメール、Webサイトなどを音声で聞くことができるため、目の負担を大きく減らせます。
音声入力も活用しましょう。文字を入力する代わりに、話した内容を文字に変換してくれます。メールやメッセージの返信が楽になります。
白黒反転表示は、白い背景と黒い文字を反転させる機能です。白内障などで光がまぶしく感じる方には、黒い背景に白い文字の方が見やすいことがあります。
ブルーライトカットも重要です。青色光は目の疲れや睡眠の質低下を引き起こすため、夜間モードやナイトシフト機能を使って、画面の色温度を暖色系に変更しましょう。
在宅介護で家族の負担を軽減するには?持続可能な介護体制の構築法
高齢者の視力低下を予防する日常習慣
視力低下を完全に防ぐことはできませんが、適切な生活習慣で進行を遅らせることは可能です。日々の習慣を見直しましょう。
目の健康を守る食事と栄養素

バランスの良い食事は、目の健康維持に欠かせません。特に、抗酸化作用のある栄養素を積極的に摂取することで、加齢による目の病気の予防に役立ちます。
ルテインとゼアキサンチンは、目の黄斑部に存在する色素で、加齢黄斑変性の予防に効果があるとされています。ほうれん草、ケール、ブロッコリー、とうもろこし、卵黄などに多く含まれます。1日に6〜10mgの摂取が推奨されています。
アスタキサンチンは、強力な抗酸化作用を持つ赤い色素です。鮭、エビ、カニなどに含まれ、眼精疲労の軽減や加齢黄斑変性の予防に効果があるとされています。
ビタミンAは、目の粘膜を保護し、夜間の視力維持に必要な栄養素です。にんじん、かぼちゃ、レバーなどに多く含まれます。不足すると夜盲症(暗いところで見えにくくなる)の原因になります。
ビタミンCとEは、抗酸化作用により白内障や加齢黄斑変性の進行を遅らせる効果があります。柑橘類、いちご、ピーマン(ビタミンC)、ナッツ類、アボカド(ビタミンE)を積極的に摂りましょう。
オメガ3脂肪酸は、ドライアイの改善や加齢黄斑変性の予防に効果があります。青魚(さば、いわし、さんま)やくるみに多く含まれます。週に2〜3回は魚を食べるようにしましょう。
水分補給も忘れずに。高齢者は喉の渇きを感じにくいため、意識的に水分を摂ることが大切です。脱水状態になると、ドライアイが悪化します。
紫外線対策と適切な目の休息方法

紫外線は目の大敵です。長年紫外線を浴び続けると、白内障や加齢黄斑変性のリスクが高まります。適切な対策で目を守りましょう。
UVカットサングラスは、屋外での必須アイテムです。紫外線カット率99%以上のものを選びましょう。色が濃いだけでUVカットされていないサングラスは、瞳孔が開いてかえって紫外線が入りやすくなるため、必ず「UV400」や「紫外線透過率1.0%以下」と表示されたものを選んでください。
紫外線から目を守る方法
・UVカット率99%以上のサングラスを着用
・つばの広い帽子(7cm以上)で顔全体を守る
・午前10時〜午後2時の外出を避ける
・日陰を選んで歩く
・UVカットコンタクトレンズの使用
・車の窓にUVカットフィルムを貼る
つばの広い帽子も効果的です。つばが7cm以上ある帽子なら、紫外線を50%以上カットできます。サングラスと組み合わせると、さらに効果が高まります。
目の休息も大切です。テレビやパソコン、スマートフォンを長時間見続けると、目が疲れ、ドライアイや眼精疲労の原因になります。
20-20-20ルールを実践しましょう。20分ごとに、20フィート(約6メートル)以上離れたものを、20秒間見るという方法です。これにより、目の筋肉がリラックスし、疲労が軽減されます。
まばたきを意識的に増やすことも重要です。画面を見ているとき、まばたきの回数は通常の3分の1程度に減ると言われています。意識的にまばたきをすることで、涙が目全体に行き渡り、ドライアイを防げます。
目を温めるのも効果的です。蒸しタオルやホットアイマスクで目を温めると、血行が良くなり、疲れが取れます。1日1回、5〜10分程度温めるとよいでしょう。
定期検診と早期発見の重要性

定期的な眼科検診は、視力低下の早期発見に欠かせません。多くの目の病気は、初期には自覚症状がほとんどないため、定期検診で見つけることが重要です。
検診の頻度は、年齢や持病によって異なります。40歳以上は年に1回、緑内障や糖尿病などのリスクがある方は半年に1回の受診が推奨されています。
自宅でできるチェックも習慣にしましょう。片目ずつ、見え方に変化がないか定期的に確認します。新聞の文字が読めるか、テレビが見えるか、顔が識別できるかなどをチェックします。
アムスラーチャートを使った自己チェックも有効です。格子状の図を片目ずつ見て、線が歪んで見えたり、中心が暗く見えたりしないかを確認します。加齢黄斑変性の早期発見に役立ちます。
糖尿病がある方は、血糖コントロールが良好でも、必ず定期的に眼底検査を受けましょう。糖尿病網膜症は自覚症状がないまま進行し、気づいたときには重症化していることが多い病気です。
メガネやコンタクトレンズは、定期的に度数を確認しましょう。合わないメガネを使い続けると、眼精疲労や頭痛の原因になります。年に1回は眼科で視力をチェックし、必要に応じて度数を調整しましょう。
認知症の介護で家族が限界を感じている場合。共倒れを防ぐ解決策
家族ができる高齢者の目が見えにくい時のサポート
視力低下がある高齢者には、家族の適切なサポートが欠かせません。具体的にどのような支援ができるのかを見ていきましょう。
コミュニケーションの工夫と声かけのポイント

視力が低下した高齢者とのコミュニケーションには、いくつかの配慮が必要です。適切な声かけで、相手の不安を軽減し、安心感を与えることができます。
指示語を避けることが大切です。「これ」「あれ」「そこ」といった言葉は、目が見えにくい方には伝わりません。「右手側の机の上」「あなたの前、30cmくらいのところ」など、具体的な位置や距離を伝えましょう。
時計の文字盤を使った説明も効果的です。「食器の12時の位置にご飯、3時の位置に味噌汁、6時の位置に魚があります」と伝えると、食事の配置がわかりやすくなります。
席を離れるときは、必ず声をかけましょう。「ちょっとトイレに行ってきます」「5分ほど席を外します」など、一言伝えるだけで、相手の不安が軽減されます。戻ったときも「戻りました」と声をかけることが大切です。
表情や身振りに頼らないことも重要です。うなずいたり、首を振ったりするだけでなく、「はい」「いいえ」と言葉で伝えましょう。ジェスチャーや指差しも見えないため、必ず言葉で説明します。
触れることの価値も忘れずに。手を握る、肩に手を置くといったスキンシップは、視覚以外の感覚を通じて安心感を与えます。ただし、突然触れると驚かせてしまうため、「手を握りますね」と声をかけてから触れましょう。
安全な生活空間づくりと転倒防止対策

視力低下がある高齢者にとって、転倒は最大のリスクです。家の中を安全な環境に整えることで、事故を防ぐことができます。
障害物を取り除くことが第一歩です。床に置いてある物、電気コード、小さな段差など、つまずきやすいものは極力なくしましょう。特に動線上には何も置かないことが重要です。
転倒を防ぐ住環境の工夫
・床に物を置かない(新聞、雑誌、バッグなど)
・電気コードはまとめて壁際に固定
・カーペットや絨毯は滑り止めシートで固定
・段差にはスロープや目印テープ
・階段には両側に手すり
・浴室やトイレに手すりを設置
・滑りにくい床材に変更
手すりの設置は、転倒防止に非常に効果的です。階段、廊下、浴室、トイレなど、必要な場所に手すりを付けましょう。工事が難しい場合は、突っ張り式の手すりも利用できます。
浴室の安全対策は特に重要です。濡れた床は滑りやすく、視力低下があるとさらに危険です。滑り止めマットを敷く、シャワーチェアを使う、浴槽用手すりを付けるなどの対策をしましょう。
夜間の対策も忘れずに。寝室からトイレまでの動線に足元灯を設置すると、夜中のトイレも安全です。人感センサー付きのライトなら、自動で点灯するため便利です。
家具の配置も見直しましょう。動線を妨げる家具は移動させ、角が尖った家具にはコーナーガードを付けます。よく使う物は、手の届きやすい高さに配置します。
ロービジョンケアと福祉制度の活用

ロービジョンケアとは、視力が低下しても、残された視機能を最大限に活用して、生活の質を維持・向上させる支援のことです。眼科医、視能訓練士、作業療法士などの専門家が連携して行います。
ロービジョン外来のある眼科では、視力低下に応じた具体的な生活の工夫や、補助具の選び方を教えてもらえます。拡大鏡や拡大読書器の使い方、照明の調整方法、日常生活動作の訓練などを受けられます。
身体障害者手帳の取得も検討しましょう。視力が一定以下(両眼の視力の和が0.08以下など)になった場合、身体障害者手帳を申請できます。手帳を取得すると、以下のような支援を受けられます。
補装具費支給制度では、拡大読書器、盲人用時計、点字器などの補助具を、補助金で購入・レンタルできます。自己負担は原則1割で、所得に応じて上限額が設定されています。
日常生活用具給付制度も利用できます。音声体温計、音声血圧計、拡大読書器などが対象で、市町村によって給付内容が異なります。
税金の控除も受けられます。障害者控除により、所得税や住民税が軽減されます。等級によって控除額が異なります。
高齢者の目が見えにくい時の対策と改善:まとめ
高齢者の目が見えにくくなる原因は、老眼、白内障、緑内障、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症など多岐にわたります。初期には自覚症状が少ないことも多いため、日常生活での行動の変化に注意し、早期発見につなげることが重要です。
生活環境の対策としては、照明を明るくする、色のコントラストを活用する、拡大鏡や補助具を使う、デジタル機器の設定を変更するといった工夫が効果的です。これらの対策により、視力が低下しても日常生活の質を大きく向上させることができます。
視力低下の予防には、ルテインやアスタキサンチンなどの抗酸化成分を含む食事、UVカットサングラスや帽子での紫外線対策、適切な目の休息、そして定期的な眼科検診が欠かせません。特に緑内障や糖尿病網膜症は自覚症状がないまま進行するため、定期検診での早期発見が重要です。
視力が一定以下になった場合は、身体障害者手帳の取得も検討しましょう。補装具費支給制度や日常生活用具給付制度を利用することで、経済的負担を軽減しながら、必要な補助具を手に入れることができます。
高齢者の目が見えにくくなることは、決して珍しいことではありません。しかし、適切な対策を取ることで、多くの場合、見えにくさを改善し、安全で快適な生活を続けることができます。早期発見、適切な治療、生活環境の工夫、そして家族の温かいサポートが、高齢者の視力と生活の質を守る鍵となります。
「見えにくい」と感じたら、「歳のせい」と諦めず、まずは眼科を受診しましょう。そして、専門家のアドバイスを受けながら、できる対策から始めていくことが大切です。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。