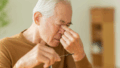「最近、親が『しんどい』『疲れた』ばかり言う」
「以前より元気がなく、動くのを嫌がるようになった」
「ただの老化なのか、病気なのか判断できない」
高齢の親が「しんどい」と訴えるとき、家族としてどう対応すればよいのか迷いますよね。実は高齢者の「しんどい」という訴えには、命に関わる病気のサインから心理的な問題まで、さまざまな原因が隠れています。高齢者の疲れやすさを「年齢のせい」「持病のせい」と不定愁訴として簡単に解釈してしまいがちですが、その裏に重大な疾患が隠れている場合もあります。
高齢者の「しんどい」は、単なる老化ではなく重大な病気のサインである可能性があります。厚生労働省によると、75歳以上の約4割が心臓・血管系の疾患を抱えており、高齢者の15%がうつ症状を抱えています。この記事では、高齢者がしんどいと感じる主な原因を身体的・心理的・生活習慣の3つの視点から解説し、すぐに受診が必要な危険サイン、家族ができる具体的な対応方法までお伝えします。
高齢者がしんどいと感じる3つの主な原因
高齢者が「しんどい」と感じる原因は非常に多岐にわたります。ここでは原因を大きく3つに分類して、それぞれ詳しく見ていきましょう。
身体的原因:心臓・貧血・腎臓機能低下がしんどさを引き起こす

高齢者のしんどさの原因として、まず考えられるのが身体的な要因です。加齢に伴う身体機能の低下だけでなく、さまざまな病気や体調不良が関係しています。
〈心臓や血管の問題〉高血圧、心不全、狭心症などがあると、全身に十分な血液が行き渡らず、疲れやすくなります。特に動いたときに息切れや動悸がある場合は、心臓に負担がかかっている可能性があります。厚生労働省によると、75歳以上の約4割が心臓・血管系の疾患を抱えているというデータもあります。高齢の方が息切れ、倦怠感、身体活動の低下を訴えるときは、心不全の可能性も考慮する必要があります。
〈貧血〉赤血球が減少すると、体中に酸素が行き渡らなくなり、常にだるさを感じるようになります。顔色が悪い、立ちくらみがする、爪が白っぽいといった症状があれば、貧血を疑ってみましょう。高齢者は鉄分不足だけでなく、慢性疾患による貧血も多く見られます。
〈腎臓や肝臓の機能低下〉これらの臓器が正常に働かないと、体内に老廃物が溜まり、全身倦怠感につながります。顔色が浅黒くなったり、黄疸が出たりする場合は要注意です。血液検査でクレアチニンやBUN(尿素窒素)の値が高い場合は、腎機能の低下が疑われます。
〈栄養不足と脱水〉高齢になると食が細くなり、必要な栄養素が不足しがちです。特にタンパク質、鉄分、ビタミンB群の不足は、疲労感やだるさに直結します。また、高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、知らないうちに脱水になっていることがあります。尿の色が濃い、回数が減った、口の中が乾燥しているといった症状があれば脱水を疑いましょう。
心理的原因:孤独感・うつ病・不安がしんどさの原因に

身体には特に異常がないのに「しんどい」と感じる場合、心理的な要因が大きく関わっていることがあります。高齢者の心の健康は、身体の健康と密接につながっています。
〈うつ病・抑うつ状態〉気分が沈む、何にも興味が持てない、疲れやすいといった症状が2週間以上続く場合は、うつ病の可能性があります。高齢者のうつ病は、「頭が痛い」「体がだるい」といった身体症状として現れることが多いため、見逃されやすいのが特徴です。実際、65歳以上の約15%がうつ症状を抱えているというデータもあります。
国立長寿医療研究センターによると、高齢者のうつ病は身体不調や身体疾患の罹患が発症契機になることが多く、生活機能の低下から「老年症候群」に結びつきやすいという特徴があります。脳卒中などの病気後にうつ状態になる高齢者も少なくなく、身体の自由が奪われたことがきっかけで意欲が低下してしまうケースが多く見られます。
〈孤独感と社会的孤立〉配偶者や友人を亡くしたり、子どもが独立したりして、一人で過ごす時間が増えると、心に大きな負担がかかります。高齢者は親、兄弟姉妹、パートナーとの別や、職を離れることにより社会的立場をなくし、加齢によって身体的にも不安が出てきます。これらの環境の変化により、意欲が低下してしまうことがあります。内閣府の調査では、一人暮らしの高齢者の約4割が「孤独を感じる」と回答しています。
生活習慣が原因のしんどさ:睡眠・運動・栄養の問題

日々の生活習慣も、高齢者のしんどさに大きく影響します。睡眠、運動、食事のバランスが崩れると、体調不良やだるさにつながります。
〈睡眠の問題〉夜中に何度も目が覚める、朝早く目覚めてしまう、眠りが浅いといった睡眠障害があると、十分な休息が取れず、日中のしんどさにつながります。高齢になると、夜間の睡眠時間が短くなり、眠りが浅いことから、何度も目が覚めることがあります。これは老化現象の一つですが、睡眠薬に頼りすぎると、かえって日中の眠気やふらつきを引き起こすこともあります。
適度な運動の重要性
無理のない範囲での散歩や体操は、筋力維持だけでなく、気分転換や睡眠の質向上にもつながります。軽めの運動で血流が良くなり、筋肉に溜まった乳酸が排出されやすくなります。また、神経伝達物質「セロトニン」が分泌され、自律神経が整い、精神的な疲れが和らぐ効果も期待できます。ただし、体調が悪いときに無理に動くのは逆効果です。運動不足になると新陳代謝が落ち、水分や血液の巡りが悪くなり、筋肉に乳酸がたまりやすくなって疲労感が出やすくなります。
〈食事と栄養〉食欲がなくなり、食事量が減ると、必要な栄養やエネルギーが不足します。特に一人暮らしの高齢者は、食事を作るのが面倒になり、簡単なもので済ませてしまうことが多く、栄養バランスが崩れがちです。低栄養状態が続くと、体が必要とする栄養が不足し、要介護のリスクが高まります。
高齢者のしんどさで注意すべき危険サインと受診の目安
高齢者のしんどさの中には、すぐに医療機関を受診すべき危険なサインが隠れていることがあります。見逃さないためのポイントを押さえておきましょう。
すぐに119番が必要な緊急症状とは

以下の症状が見られた場合は、すぐに救急車を呼ぶか、緊急受診が必要です。これらは命に関わる重大な病気のサインである可能性があります。
〈胸の痛みや圧迫感〉心筋梗塞や狭心症の可能性があります。特に「胸を締め付けられるような痛み」「重いものが乗っているような感じ」と表現される場合は、すぐに救急車を呼びましょう。冷や汗、吐き気、左肩や腕の痛みを伴うこともあります。

救急車を呼ぶべきか迷ったら、#7119(救急安心センター)に電話すると、看護師などの専門家が相談に乗ってくれますよ。24時間対応なので、夜間でも安心です。
長引くしんどさで医師に相談すべきケース

緊急ではないものの、長引くしんどさは、何らかの病気が隠れている可能性があります。以下のような状態が続く場合は、早めにかかりつけ医に相談しましょう。
医師に相談すべき症状
・2週間以上続く倦怠感やだるさ
・少し動いただけで息切れがする
・食欲がなく、半年で体重が5%以上減っている
・夜眠れない、または日中眠すぎる
・気分の落ち込みが2週間以上続いている
・手足のむくみが取れない
・37度台の微熱が1週間以上続いている
・早朝の倦怠感とめまいが続く(低血圧の可能性)
〈体重の減少〉意図しない体重の減少は、高齢者にとって注意すべきサインです。意図的にダイエットしているわけではないのに、半年で5%以上体重が減った場合(50kgの人なら2.5kg以上)は、がんや甲状腺の病気、糖尿病、消耗性疾患などの可能性があります。高齢者の体重減少は、消耗性疾患や悪性腫瘍などが潜在していることもあるため注意が必要です。
見逃しやすい初期サインと観察ポイント

高齢者の体調変化は、目立たない形で進行することが多くあります。家族が日頃から観察することで、早期発見につながります。
〈行動や習慣の変化〉以前は楽しんでいた趣味に興味を示さなくなった、外出を嫌がるようになった、人と会うのを避けるようになったといった変化は、心身の問題を示しているかもしれません。社会参加の減少はフレイル状態、介護状態に陥る可能性を大きく上げてしまいます。
【高齢の親の「しんどい」に戸惑っていませんか?】
高齢者がしんどいときの家族の具体的対応方法
高齢者が「しんどい」と訴えたとき、家族としてどのように対応すればよいのでしょうか。適切な関わり方を知っておくことで、高齢者の心身の負担を軽減できます。
話をよく聞き共感する姿勢が最も重要

高齢者が「しんどい」と言ったとき、まず大切なのは話をよく聞く姿勢です。忙しい日常の中で、つい「いつものことだから」「年のせいだから」と流してしまいがちですが、本人にとっては深刻な悩みかもしれません。
〈共感的に聞く〉「そんなことで」「気のせいじゃない?」といった否定的な言葉は避け、「そうなんですね」「つらいですよね」と、まず相手の気持ちを受け止めましょう。高齢者は自分の不調を訴えることに罪悪感を持っていることも多いため、否定されると余計に不安になります。
無理をさせず適切な休息環境を整える

しんどさを訴える高齢者には、無理をさせない環境づくりが必要です。高齢者は周囲に迷惑をかけたくないという思いから、無理をしてしまうことが多いのです。
体調や生活の変化を記録して医師に正確に伝える

高齢者の体調管理には、記録をつけることが非常に有効です。日々の変化を記録しておくことで、受診時に医師へ正確な情報を伝えられます。
記録しておくべき10項目
・日付と時間
・しんどさの程度(10段階評価など)
・どんなしんどさか(だるい、疲れた、痛いなど)
・いつから始まったか
・どんなときに強くなるか
・食事の量と内容
・睡眠時間と質
・排泄の状況
・体温・血圧(測定できる場合)
・薬の服用状況
完璧に記録しようとすると続きません。気づいたことだけでも書き留めておく、週に一度まとめて振り返るなど、自分たちに合った方法で続けることが大切です。
高齢者がしんどい原因への根本的対策とサポート体制
高齢者のしんどさに対処するには、一時的な対応だけでなく、根本的な対策とサポート体制が必要です。家族だけで抱え込まず、適切な支援を活用しましょう。
心理的負担への専門家活用と人とのつながり

身体的な問題だけでなく、心理的な負担にも目を向けることが大切です。孤独感や不安感、抑うつ状態などは、適切なケアで改善できることが多くあります。
〈専門家のサポート〉抑うつ状態や不安が強い場合は、心療内科や精神科の受診を勧めます。地域包括支援センターでは、高齢者とその家族の相談に応じており、心身の悩みだけでなく、介護サービスの利用方法なども相談できます。
家族だけで抱え込まない介護サービス活用

高齢者のしんどさに対応するとき、家族だけで全てを抱え込む必要はありません。むしろ、適切なサポートを活用することで、高齢者にとっても家族にとっても良い結果につながります。
活用できる主なサービス
・訪問介護(ホームヘルパー)
・訪問看護(健康管理・医療処置)
・デイサービス(通所介護)
・ショートステイ(短期入所)
・訪問リハビリテーション
・配食サービス(栄養管理)
・見守りサービス(緊急通報システム)
継続的な見守りと早期発見で健康を守る

高齢者の健康を守るには、継続的な見守りが欠かせません。日々の小さな変化に気づくことで、大きな問題になる前に対処できます。
「様子がおかしいな」と感じたら、「もう少し様子を見よう」と先延ばしにせず、早めに医師や専門家に相談しましょう。早期に対応することで、重症化を防げることも多くあります。
まとめ:高齢者のしんどさへの理解と適切な対応
高齢者が「しんどい」と感じる原因は、身体的要因(心臓・貧血・腎臓機能低下・栄養不足)、心理的要因(孤独感・うつ病・不安感)、生活習慣要因(睡眠不足・運動不足・食事の問題)の3つに大きく分けられます。厚生労働省によると、75歳以上の約4割が心臓・血管系の疾患を抱えており、高齢者の15%がうつ症状を抱えています。
特に注意すべきは、すぐに受診が必要な危険サインです。激しい胸の痛み、顔の片側の麻痺、ろれつが回らない、強い呼吸困難などの症状が見られたら、迷わず119番を呼びましょう。また、2週間以上続く倦怠感、体重減少(半年で5%以上)、食欲不振、むくみなどの症状がある場合は、早めに医師に相談することが大切です。
心理的な負担には、人とのつながりを維持することや趣味を楽しむことが効果的です。必要に応じて心療内科やカウンセリングなどの専門家のサポートも活用しましょう。介護保険サービス、訪問看護、デイサービスなど、利用できるサポートは積極的に活用し、家族だけで全てを抱え込まないことが大切です。日々の小さな変化に気づき、早めに対応することで、大きな問題を防ぐことができるのです。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。