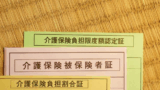「夫が75歳になったけれど、私の保険料はどうなるの?」「今までより高くなるのかしら」「年金も少ないのに、負担が増えるのではないかと不安」
夫が後期高齢者医療制度に移行すると、妻の健康保険料がどう変わるのか、気になりますよね。特に年金収入が少ない妻の場合、保険料の負担が家計に与える影響は小さくありません。
実際、妻の年齢や収入状況、これまで加入していた保険の種類によって、保険料は大きく変わります。場合によっては軽減措置を受けられることもあるため、制度を正しく理解することが重要です。
この記事では、後期高齢者の妻の保険料について、具体的な金額の目安から計算方法、軽減措置、さらには見落としがちな注意点まで、わかりやすく解説していきます。正しい知識を身につけて、無駄な負担を避け、安心して生活できるようサポートいたします。
後期高齢者の妻の保険料は年齢と収入で大きく変わる
夫が75歳で後期高齢者医療制度に移行した後、妻の保険料がどうなるかは、妻自身の年齢と収入状況によって大きく異なります。まずは基本的な仕組みを理解しましょう。
妻が75歳以上の場合の後期高齢者医療保険料

妻も75歳以上であれば、夫と同様に後期高齢者医療制度に加入します。この場合、妻自身の保険料が個別に計算され、請求されることになります。
後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額の合計で算出されます。均等割額は全員に共通してかかる基本料金で、所得割額は前年の所得に応じて計算される変動部分です。
具体的な計算式は次の通りです。
保険料 = 均等割額 + 所得割額
所得割額 = (前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円) × 所得割率
均等割額と所得割率は都道府県ごとに設定されており、毎年見直されるため、金額は年度や地域によって異なります。例えば、東京都の場合、令和6年度・7年度の均等割額は47,300円、所得割率は9.67%となっています。
妻の年金収入別の保険料例(埼玉県の場合)
・年金収入80万円の妻:年間保険料 約8,340円〜12,510円(7〜8割軽減適用時)
・年金収入120万円の妻:年間保険料 約25,000円〜35,000円
・年金収入200万円の妻:年間保険料 約60,000円〜80,000円
このように、年金収入が少ないほど保険料は安くなり、軽減措置も適用されやすくなります。後ほど詳しく説明しますが、低所得の場合は均等割額が最大7割軽減されることもあるのです。
妻が74歳以下で国民健康保険に加入する場合の保険料

妻がまだ74歳以下の場合は、後期高齢者医療制度には加入できません。夫婦で国民健康保険に加入していた場合、妻は引き続き国民健康保険に加入し、妻の分の国民健康保険料が世帯主に請求されることになります。
国民健康保険料の計算方法は市区町村によって異なりますが、一般的には医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳以上の場合)のそれぞれについて、所得割・均等割・平等割を組み合わせて計算します。
夫が後期高齢者医療制度に移行すると、夫の分の国民健康保険料はなくなりますが、妻の分は引き続き請求されます。ただし、世帯の加入者数が減ることで、平等割の負担が軽減される自治体もあるため、必ずしも保険料が高くなるわけではありません。
妻が社会保険の被扶養者から国民健康保険に切り替わる場合の保険料

夫が会社の健康保険に加入していて、妻がその被扶養者だった場合、夫が75歳になると妻は被扶養者の資格を失います。この場合、妻は新たに国民健康保険に加入する必要があり、これまで保険料負担がなかった妻にも保険料が発生するのです。
ただし、このような「旧被扶養者」には特別な軽減措置があるため、急激な負担増を避けることができます。
旧被扶養者への特別な軽減措置
・対象:65歳〜74歳で、後期高齢者医療制度の被保険者となった方の被扶養者だった方
・所得割:全額免除
・均等割:5割軽減
・平等割:5割軽減(世帯に他の国保加入者がいない場合)
・適用期間:資格取得日の属する月以後2年間
この軽減措置により、今まで保険料負担がなかった妻でも、急に高額な保険料を請求されることはありません。ただし、軽減措置の適用には申請が必要な自治体もあるため、必ず窓口で確認しましょう。
介護保険料はいつまで払う?支払い期間と免除・軽減制度を詳しく解説
後期高齢者の妻の保険料を軽減する制度と申請方法
後期高齢者医療保険料には、所得が少ない方のための軽減制度がいくつか用意されています。これらの制度を知っているかどうかで、保険料の負担は大きく変わってきます。
均等割額の軽減措置と所得基準

後期高齢者医療保険料の均等割額は、世帯の所得が一定基準以下の場合、自動的に軽減されます。軽減割合は7割・5割・2割の3段階があり、所得が少ないほど大きな軽減を受けられる仕組みです。
軽減の判定は、世帯主と世帯に属する後期高齢者医療制度加入者全員の総所得金額等の合計で行われます。具体的な基準は次の通りです。
均等割額の軽減基準(令和6年度・7年度)
・7割軽減:世帯の総所得金額等が 43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数 − 1) 以下
・5割軽減:世帯の総所得金額等が 43万円 + 29.5万円 × 被保険者数 + 10万円 × (給与所得者等の数 − 1) 以下
・2割軽減:世帯の総所得金額等が 43万円 + 54.5万円 × 被保険者数 + 10万円 × (給与所得者等の数 − 1) 以下
例えば、年金収入が80万円の妻の場合、給与所得控除後の所得は約30万円となるため、7割軽減の対象となります。東京都の均等割額47,300円が7割軽減されると、実際の負担は約14,190円となり、大幅に負担が軽くなるのです。
この軽減措置は、基本的に自動的に適用されます。ただし、所得の申告がされていないと判定ができないため、年金収入が少なくても必ず所得の申告を行うことが重要です。

年金収入しかなくても、確定申告や住民税の申告を忘れずに行いましょう。申告がないと、軽減措置を受けられないことがあるんです。
所得割額の軽減と確定申告での注意点

所得割額は前年の所得に応じて計算されるため、所得が少なければその分保険料も安くなります。特に年金収入が少ない妻の場合、所得割額がゼロになることも珍しくありません。
所得割額の計算では、前年の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額に所得割率をかけます。つまり、所得が43万円以下であれば、所得割額は発生しないのです。
年金収入の場合、公的年金等控除が適用されるため、実際の所得はかなり少なくなります。65歳以上の方の場合、年金収入が110万円以下であれば、公的年金等控除後の所得は0円となり、所得割額は一切かかりません。
確定申告では、医療費控除や社会保険料控除などを適用することで、所得をさらに減らすことができます。これにより、保険料の軽減につながる場合もあるため、控除できるものは忘れずに申告しましょう。
減免制度の活用と申請のタイミング

均等割額の軽減措置とは別に、特別な事情がある場合には保険料の減免を受けられる制度もあります。減免制度は自治体によって基準が異なりますが、主に以下のような場合に適用されることが多いです。
保険料減免が認められる主なケース
・災害により住宅や家財に大きな損害を受けた場合
・世帯の生計維持者が死亡、または重度の障害を負った場合
・事業の廃止や失業により収入が大幅に減少した場合
・刑事施設や労役場などに収容された場合
・生活保護を受給することになった場合
減免制度は、軽減措置と違って申請が必要です。該当する事情が生じたら、できるだけ早く市区町村の窓口に相談しましょう。申請のタイミングが遅れると、減免が受けられる期間が短くなる可能性があります。
また、減免は納期限を過ぎた保険料には原則として適用されないため、保険料の支払いが困難な場合は、納期限前に必ず相談することが重要です。
親の介護でお金がない時の対処法。公的支援制度や負担軽減策はある?
後期高齢者の妻の保険料で見落としがちな注意点
保険料の基本的な仕組みは理解できても、実際の手続きや納付の段階で見落としがちなポイントがあります。ここでは特に注意が必要な点を詳しく見ていきましょう。
月割り計算と年度途中の切り替えタイミング

夫婦のどちらかが年度の途中で75歳になった場合、保険料は月割りで計算されます。このタイミングでの計算が複雑で、混乱しやすいポイントとなっています。
例えば、世帯主である夫が10月に75歳になる場合を考えてみましょう。夫は9月までは国民健康保険に加入し、10月からは後期高齢者医療制度に移行します。この場合、夫の国民健康保険料は4月〜9月の6ヶ月分、後期高齢者医療保険料は10月〜翌年3月の6ヶ月分が請求されることになります。
一方、妻の国民健康保険料は1年分(12ヶ月分)がそのまま請求されます。ただし、請求のタイミングは自治体によって異なり、夫の移行前に年間分が一括請求されている場合もあれば、移行後に再計算されて減額される場合もあります。
自己負担割合の変動と高額療養費制度への影響
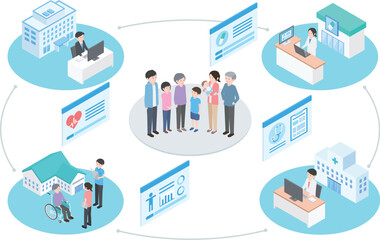
夫が後期高齢者医療制度に移行すると、妻が70歳〜74歳の国民健康保険加入者の場合、医療費の自己負担割合が変わる可能性があります。これは見落としがちですが、家計に大きな影響を与えることがあるため注意が必要です。
70歳〜74歳の国民健康保険加入者の自己負担割合は、世帯の所得によって2割または3割に分かれます。夫が後期高齢者医療制度に移行すると、世帯構成が変わるため、妻の自己負担割合の判定基準も変わるのです。
具体的には、夫の所得が高く、夫婦合わせての所得で3割負担だった妻が、夫が抜けることで世帯の所得が下がり、2割負担になるケースがあります。逆のパターンは稀ですが、世帯構成の変化によって負担割合が変わることを理解しておきましょう。
自己負担割合が変わった場合、新しい保険証または資格確認書が郵送されます。医療機関を受診する際は、必ず最新の保険証を提示するようにしてください。
また、高額療養費制度の自己負担限度額も、世帯の所得区分によって決まります。夫が後期高齢者医療制度に移行することで、妻の所得区分が変わる可能性があるため、医療費が高額になる場合は事前に確認しておくことをおすすめします。
介護費用と医療費が重なる時期の家計管理と相談先

夫が75歳を迎える時期は、医療費や介護費用の負担が増えやすいタイミングでもあります。保険料の変化だけでなく、医療費・介護費用も含めた総合的な家計管理が重要になってきます。
後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合が所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。多くの場合、75歳になると自己負担割合が下がるため、医療費の実質負担が減ることもあります。
しかし一方で、加齢に伴い通院回数が増えたり、薬の種類が増えたりすることも多く、医療費の総額は増加傾向にあります。さらに、介護が必要になった場合には、介護保険サービスの自己負担も加わります。
保険料・医療費・介護費用の3つが同時に発生すると、家計への負担は一気に重くなります。特に以下のような状況では、早めの対策が必要です。
負担が重くなりやすい状況
・夫婦ともに慢性疾患で定期的な通院・服薬が必要な場合
・どちらか一方が入院や手術を控えている場合
・介護認定を受けて、介護サービスを利用している場合
・年金収入が少なく、貯蓄も限られている場合
医療費と介護費用の自己負担が高額になった場合には、高額療養費制度や高額介護サービス費制度、さらには高額医療・高額介護合算療養費制度などの負担軽減制度を利用できます。
これらの制度を活用するには申請が必要な場合が多いため、医療費や介護費用の領収書は必ず保管しておきましょう。また、制度の詳細や申請方法がわからない場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談することをおすすめします。
【最新版】介護保険料はいつから支払う?年齢別の納付方法も解説
後期高齢者の妻の保険料と負担軽減策:まとめ
夫が後期高齢者医療制度に移行した後の妻の保険料は、妻の年齢と収入状況によって大きく変わります。妻も75歳以上であれば後期高齢者医療保険料が個別に計算され、74歳以下であれば国民健康保険料が引き続き請求されることになります。
特に年金収入が少ない妻の場合、均等割額の軽減措置により、保険料負担を大幅に抑えることができます。7割・5割・2割の軽減措置は基本的に自動適用されますが、所得の申告が必要なため、年金収入が少なくても必ず申告を行いましょう。
また、社会保険の被扶養者だった妻が国民健康保険に切り替わる場合には、旧被扶養者としての特別な軽減措置を受けられます。ただし、申請が必要な自治体もあるため、必ず窓口で確認することが大切です。
年度途中での切り替えタイミングや、自己負担割合の変動など、見落としがちな注意点も多くあります。保険料の通知が届いたら内容をしっかり確認し、不明な点があれば早めに自治体の窓口に問い合わせることをおすすめします。
夫婦で支え合いながら、健康で安心できる生活を送れるよう、制度を上手に活用していってください。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。