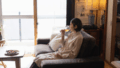「医療費も介護費も両方かかって、家計が本当に厳しい」
「毎月の支払いで貯金がどんどん減っていく」
「何か負担を軽くする制度はないのだろうか」
医療と介護の両方が必要になると、想像以上に費用負担が重くなります。

実は、医療保険と介護保険の自己負担を合算して軽減できる「高額介護合算療養費制度」という仕組みがあるんです。この制度を知っているかどうかで、年間の負担額が大きく変わることもあります。
この記事では、高額介護合算療養費制度の仕組みをわかりやすく解説し、どのような世帯が対象になるのか、実際にいくら戻ってくるのか、どうやって申請すればいいのかを具体的にお伝えします。複雑に見える制度も、ポイントを押さえれば理解できます。
高額介護合算療養費制度とは何か
高額介護合算療養費は、医療と介護の両方を利用している世帯の経済的負担を軽減するための制度です。まずは制度の基本的な仕組みから見ていきましょう。
医療費と介護費を合算して負担を軽減する仕組み

高額介護合算療養費制度は、同一世帯で医療保険と介護保険の両方を利用している場合に、1年間の自己負担額の合計が基準額を超えたとき、その超過分が払い戻されるという仕組みです。
計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。この期間に支払った医療費の自己負担額と介護費の自己負担額を合算し、世帯の所得区分に応じた限度額を超えた部分が支給されるんです。
たとえば、同じ世帯で親が介護サービスを利用し、配偶者が病院に通っている場合、それぞれの自己負担額を合わせて計算できます。医療だけ、介護だけでは限度額を超えなくても、合算すれば支給対象になるケースは少なくありません。
この制度は自動的に適用されるわけではなく、自分で申請する必要があります。知らないと損をしてしまう可能性があるため、医療と介護の両方を利用している世帯は必ず確認しておきたい制度なんです。
高額療養費との違いをわかりやすく比較

「高額療養費」と「高額介護合算療養費」は名前が似ているため混同されがちですが、まったく別の制度です。両方を理解しておくことで、より効果的に負担を軽減できます。
高額療養費は、医療費の自己負担が1か月単位で高額になった場合に、月ごとの限度額を超えた分が払い戻される制度です。対象は医療保険のみで、介護費は含まれません。多くの場合、事前に「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払いが限度額までで済むようになっています。
一方、高額介護合算療養費は、医療費と介護費を合算し、年間単位で計算する制度です。毎月の負担はそれぞれ限度額以内でも、1年間を通して見ると大きな負担になっている世帯を支援するための仕組みなんです。
2つの制度の使い分け
高額療養費は月ごとの医療費が高額な場合に自動的に適用される制度で、高額介護合算療養費は年間を通して医療と介護の両方の負担が重い場合に申請して利用する制度です。両方を併用することで、負担をさらに軽減できます。
重要なのは、高額療養費で払い戻された後の自己負担額を基に、高額介護合算療養費の計算が行われるという点です。つまり、高額療養費を先に適用した上で、さらに年間合算で限度額を超えていれば追加で払い戻されるという二段階の支援が受けられるわけです。
対象となる世帯の条件と計算期間

高額介護合算療養費の対象になるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、同一世帯で同じ医療保険に加入していることが前提です。たとえば、夫婦で同じ健康保険に入っている場合、それぞれの医療費と介護費を合算できます。しかし、夫が会社の健康保険、妻が国民健康保険に加入している場合は、別世帯扱いとなり合算できません。
また、計算期間内に医療保険または介護保険に加入していた期間が必要です。期間の途中で保険を変更した場合や、他の市区町村に転居した場合は、それぞれの期間ごとに自己負担額証明書を取得する必要があります。
計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。この期間内に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、所得区分に応じた限度額と比較します。支給額は、限度額を超えた分から500円を差し引いた金額になります。
【医療費と介護費の負担、使える制度を見逃していませんか?】
親を施設に入れる時の葛藤。罪悪感と向き合い最善の選択をするために
高額介護合算療養費の自己負担限度額
実際にいくら戻ってくるかは、世帯の所得区分によって決まる年間の自己負担限度額によって変わります。自分の世帯がどの区分に該当するか確認しましょう。
所得区分ごとの年間限度額一覧

高額介護合算療養費の自己負担限度額は、世帯の所得によって細かく区分されています。所得が高いほど限度額も高く設定されているのが特徴です。
70歳以上の方がいる世帯の場合、所得区分は「現役並み所得者」「一般」「低所得者」に分かれます。現役並み所得者はさらにⅠ・Ⅱ・Ⅲの3段階に細分化され、限度額は年間67万円から212万円までの幅があるんです。
一般の所得区分の世帯では、年間の限度額は56万円に設定されています。これは最も多くの世帯が該当する区分で、医療費と介護費の合計が年間56万円を超えた場合、超過分が支給されることになります。
70歳未満の方のみの世帯の場合、所得区分は標準報酬月額によって決まります。最も高い区分では年間212万円、最も低い区分では年間34万円が限度額です。自分の標準報酬月額は、健康保険証や給与明細で確認できます。
70歳以上と70歳未満での計算方法の違い

高額介護合算療養費の計算方法は、世帯に70歳以上の方がいるかどうかで大きく変わります。
70歳以上の方の医療費は、すべての医療機関の自己負担額を合算できます。たとえば、内科で5,000円、整形外科で3,000円、歯科で2,000円かかった場合、合計1万円として計算されるんです。
一方、70歳未満の方の医療費は、1つの医療機関ごとに月21,000円以上の自己負担があった分のみが対象になります。複数の医療機関にかかっていても、それぞれが月21,000円未満であれば合算対象外です。同じ医療機関でも、入院と外来は別計算になる点にも注意が必要です。
介護保険の自己負担額については、年齢に関係なくすべての自己負担額を合算できます。デイサービス、訪問介護、ショートステイなど、利用したすべてのサービスの自己負担額が対象です。
実際の支給額をわかりやすく計算例で確認

具体的な数字で見ると、制度の仕組みがより理解しやすくなります。いくつかのケースを見てみましょう。
ケース1:70歳以上の夫婦で一般所得区分の世帯
夫が要介護3で介護サービスを利用し、年間の自己負担額が40万円。妻は持病があり病院に通院し、年間の医療費自己負担額が25万円。合計65万円の自己負担がありました。
一般所得区分の限度額は56万円なので、65万円-56万円=9万円が限度額超過分です。ここから500円を差し引いた8万9,500円が支給されます。
ケース2:70歳未満の単身世帯で標準報酬月額28万円~50万円
親の介護をしながら自身も通院している方で、介護費の年間自己負担額が30万円、医療費の自己負担額が45万円(月21,000円以上のもののみ)。合計75万円の自己負担がありました。
この所得区分の限度額は67万円なので、75万円-67万円=8万円が超過分です。ここから500円を差し引いた7万9,500円が支給されます。

高額療養費や高額介護サービス費で既に払い戻しを受けていても、さらに年間合算で限度額を超えていれば追加で支給されるんです。二重に助成を受けられるわけですね。
高額介護合算療養費の申請方法と必要書類
高額介護合算療養費は自動的に支給されるわけではなく、自分で申請する必要があります。申請の流れと必要な書類を確認しましょう。
申請の流れと自己負担額証明書の取得手順

高額介護合算療養費の申請は、少し複雑に見えますが、手順を踏めば確実に手続きできます。
まず、市区町村の介護保険担当窓口で「自己負担額証明書」を取得します。これは、計算期間中にどれだけ介護サービスの自己負担があったかを証明する書類です。窓口で「高額介護合算療養費の申請をしたい」と伝えれば、必要な書類を案内してもらえます。
自己負担額証明書を入手したら、次に加入している医療保険の窓口に申請書を提出します。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合は市区町村の窓口、会社の健康保険に加入している場合は健康保険組合や協会けんぽの窓口になります。
申請の基本的な流れ
1. 市区町村の介護保険窓口で自己負担額証明書を取得
2. 医療保険の窓口で支給申請書に必要事項を記入
3. 自己負担額証明書と一緒に申請書を提出
4. 審査後、指定した口座に支給
計算期間中に医療保険や介護保険を変更した場合、または他の市区町村に転居した場合は、それぞれの期間ごとに自己負担額証明書が必要になります。複数の証明書を集めてから、最終的に加入している医療保険に申請する形です。
申請に必要な書類と提出先

申請に必要な書類は、加入している保険によって多少異なりますが、基本的には以下のものが必要です。
必ず必要なのは、高額介護合算療養費支給申請書、介護保険の自己負担額証明書、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)、医療保険証、振込先口座の情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード)です。
自治体によっては、マイナンバーの記載が必要な場合や、印鑑が必要な場合もあります。事前に窓口に問い合わせるか、自治体のウェブサイトで確認しておくとスムーズです。
申請書は窓口でもらえるほか、多くの自治体や保険者のウェブサイトからダウンロードできます。記入方法がわからない場合は、窓口で相談しながら記入するのが確実です。
申請時に注意すべきポイント

申請する際には、いくつかの注意点があります。
まず、申請には時効があります。計算期間の翌日から2年以内に申請しないと、支給を受ける権利が消滅してしまうんです。たとえば、令和5年8月1日から令和6年7月31日の計算期間分は、令和8年7月31日までに申請する必要があります。
また、支給額が500円以下の場合は支給されません。限度額を超えた金額から500円を差し引くため、超過額が500円以下だと支給対象外になるわけです。
世帯に70歳以上と70歳未満の方が混在している場合、計算方法が複雑になります。窓口で相談しながら申請するのが確実です。また、同じ世帯でも医療保険が異なる場合は合算できないため、事前に確認が必要です。

申請してから支給されるまで、通常2〜3か月程度かかります。気長に待ちましょう。支給が決定すると、通知書が届き、指定した口座に振り込まれます。
高額介護合算療養費をわかりやすく活用するために。まとめ
高額介護合算療養費制度は、医療と介護の両方を利用している世帯の経済的負担を軽減するための重要な仕組みです。年間の自己負担額が所得に応じた限度額を超えた場合、その超過分が払い戻されることで、家計への負担を大きく軽減できます。

制度のポイントを改めて整理すると、計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、この期間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して計算します。高額療養費や高額介護サービス費で既に払い戻しを受けた後の金額を基に計算されるため、二重に支援を受けられる仕組みになっているんです。
高額療養費との違いを理解することも大切です。高額療養費は月単位で医療費のみを対象とする制度で、多くの場合自動的に適用されます。一方、高額介護合算療養費は年単位で医療費と介護費の両方を合算し、自分で申請する必要がある制度です。この違いを知っておくことで、両方の制度を効果的に活用できます。
申請方法は、まず市区町村の介護保険窓口で自己負担額証明書を取得し、それを医療保険の窓口に提出するという流れです。計算期間中に保険を変更した場合や転居した場合は、それぞれの期間の証明書を集める必要があるため、時間に余裕を持って手続きすることをお勧めします。
この制度は、知っているかどうかで年間数万円から十数万円の差が生まれることもあります。医療と介護の両方を利用している世帯は、必ず制度の対象になるか確認し、該当すれば忘れずに申請しましょう。
わからないことがあれば、市区町村の窓口や加入している医療保険の担当窓口に相談してください。窓口の担当者は丁寧に説明してくれますし、申請書の書き方もサポートしてもらえます。
医療と介護の負担は年々増える傾向にあります。
だからこそ、利用できる制度はしっかり活用し、少しでも経済的な負担を軽くすることが大切です。
高額介護合算療養費制度を理解し、適切に申請することで、安心して医療や介護を受けられる環境を整えていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。