「ケアマネジャーって誰を選んでも同じじゃないの?」
「初めて会う時、何を確認すればいいの?」
「合わないと感じたら変更できるの?」
介護サービスを利用する際、多くの方がこのような疑問を抱きます。

実は、ケアマネジャー選びは介護生活の質を左右する重要な決断なんです。知識や経験だけでなく、相性やコミュニケーション能力も大切な選択基準になります。
この記事では、信頼できるケアマネジャーの選び方を詳しく解説します。初回面談で確認すべき質問から、事業所選びのポイント、変更方法まで、実践的な情報をお届けします。
ケアマネジャーの選び方で重視すべき基本ポイント
ケアマネジャーを選ぶ際には、いくつかの重要な基準があります。まずは基本的なポイントから見ていきましょう。
専門知識と経験年数の確認方法

ケアマネジャーの専門性を見極めることは、選び方の第一歩です。
ケアマネジャーになる前の資格(基礎資格)によって、得意分野が異なります。看護師出身なら医療的なケアに詳しく、介護福祉士出身なら日常生活支援に強い傾向があるんです。社会福祉士出身の方は、権利擁護や制度活用に精通していることが多いです。
経験年数も大切な判断材料になります。ケアマネジャーとして5年以上の経験があれば、様々なケースに対応してきた実績があると考えられます。ただし、経験年数だけで判断するのは危険です。10年のベテランでも、特定の分野しか経験していない場合もあります。
初回面談で確認したい専門性
介護支援専門員以外の保有資格、ケアマネジャーとしての経験年数、これまで担当したケースの種類と人数、得意とする分野や専門領域、最近受けた研修の内容
また、担当ケース数も確認しておきましょう。法律上は1人のケアマネジャーが担当できるのは35人までですが、実際には20〜30人程度が適正といわれています。あまりに多くのケースを抱えていると、きめ細かい対応が難しくなる可能性があります。
コミュニケーション能力と相性の見極め方
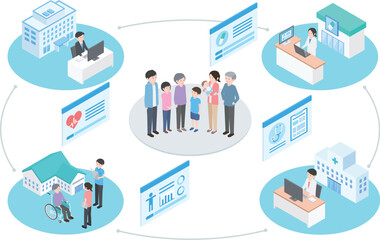
知識や経験と同じくらい大切なのが、コミュニケーション能力と相性です。
良いケアマネジャーは、まず利用者や家族の話をしっかり聞いてくれます。こちらの言葉を遮らず、最後まで耳を傾ける姿勢があるかどうか、初回面談で観察しましょう。また、専門用語をわかりやすく説明してくれるか、質問に丁寧に答えてくれるかも重要なポイントです。
相性については、直感も大切にしてください。「この人なら話しやすい」「信頼できそう」と感じられるかどうか。介護は長期戦になることが多いので、気軽に相談できる関係を築ける相手を選ぶことが大切なんです。
また、人柄や価値観も見ておきましょう。「仕事で心がけていることは何ですか」と質問してみるのも良い方法です。答え方から、その人の介護に対する考え方や姿勢が見えてきます。
対応の速さと連絡の取りやすさ

介護の現場では、迅速な対応が求められる場面も少なくありません。
連絡の取りやすさは、ケアマネジャー選びの重要な基準です。電話がつながりやすいか、留守電に入れたらどれくらいで折り返しがあるか、メールやLINEなどの連絡手段は使えるかなど、具体的に確認しておきましょう。
特に確認したいのが、緊急時の対応体制です。夜間や休日に何かあった時、どこに連絡すればいいのか、どのような対応をしてもらえるのか。これらを明確にしておくことで、いざという時の安心感が全く違います。
また、フットワークの軽さも大切です。「ちょっと相談したい」という時に、すぐに訪問してくれるか、あるいは電話で丁寧に対応してくれるか。これは実際に付き合ってみないとわからない部分もありますが、初回の対応の速さである程度判断できます。
初回面談で確認すべきケアマネジャーの選び方
初回面談は、ケアマネジャーを見極める絶好の機会です。具体的に何を確認すべきか見ていきましょう。
ケアプラン作成に関する具体的な質問

ケアプランは介護サービスの設計図ですから、作成方針をしっかり確認しておきましょう。
まず聞きたいのが、「どのような流れでケアプランを作成するのか」です。良いケアマネジャーなら、本人や家族の希望を丁寧に聞き取り、自宅の環境も確認したうえで、複数の選択肢を提案してくれるはずです。
また、「ケアプランの見直し頻度」も重要なポイントです。状態は変化していきますので、定期的な見直しは欠かせません。通常は3〜6ヶ月ごとですが、状態変化があればすぐに見直してくれるかも確認しておきましょう。
ケアプランについて聞くべきこと
ケアプラン作成の具体的な流れ、利用者や家族の希望の反映方法、サービス事業所の選定基準、ケアプランの見直し時期と頻度、プラン変更時の対応方法、目標設定の考え方
「どのような介護サービスが利用できるのか」という質問も有効です。訪問介護やデイサービスといった一般的なものだけでなく、地域の福祉サービスや民間サービスなど、幅広い選択肢を知っているかがわかります。
緊急時の対応体制についての確認事項

介護では予期せぬ事態が起こることもあるため、緊急時の対応は必ず確認しておきましょう。
「夜間や休日に急変した場合、どこに連絡すればいいのか」は最重要の質問です。ケアマネジャー個人の携帯電話なのか、事業所の代表番号なのか、あるいは緊急連絡専用の番号があるのか。具体的な連絡先を教えてもらい、メモしておきましょう。
また、「緊急時にどこまで対応してもらえるのか」も大切です。電話での助言だけなのか、必要に応じて訪問してくれるのか、医療機関との連携はどうなっているのか。具体的な対応内容を確認しておくことで、いざという時の不安が軽減されます。
「これまでに緊急対応した事例はありますか」と聞いてみるのも良いでしょう。具体的なエピソードから、その人の対応力や経験値が見えてきます。
担当ケース数と訪問頻度の確認

ケアマネジャーの時間的な余裕を確認することも、選び方の重要なポイントです。
「現在何人くらいの方を担当していますか」という質問は、遠慮なくしてください。35人いっぱいまで担当している場合、一人ひとりに割ける時間が限られてしまいます。20〜25人程度なら、比較的ゆとりを持って対応してもらえるでしょう。
訪問頻度についても確認が必要です。法律上は月1回以上の訪問が義務付けられていますが、実際にはどれくらいの頻度で来てもらえるのか。状況に応じて柔軟に対応してもらえるかも大切なポイントです。

担当ケース数が多すぎると、どうしても一人ひとりへの対応が手薄になりがちです。丁寧な対応を求めるなら、担当人数も重要な判断材料になりますよ。
悪いケアマネージャーの見極め方と対処法とは?知っておきたい知識
事業所選びで失敗しないケアマネジャーの選び方
ケアマネジャー個人だけでなく、所属する事業所の特徴も選び方の重要なポイントです。
自宅からの距離と対応エリアの重要性

事業所選びで最初に考えたいのが、自宅からの距離です。
ケアマネジャーは定期的に自宅を訪問しますし、緊急時にも駆けつけることがあります。あまり遠い事業所を選ぶと、対応が遅れる可能性があるんです。できれば車で15〜20分圏内、遠くても30分以内の事業所を選ぶのが理想的でしょう。
また、事業所によって対応エリアが決まっています。自宅がエリア内かどうか、事前に確認しておきましょう。エリアの端の方だと対応が後回しになることもありますので、できればエリアの中心に近い場所にある事業所が安心です。
事業所の規模と組織体制のチェック

事業所の規模と組織体制も、選び方の大切な基準になります。
小規模事業所(ケアマネジャー1〜2人)のメリットは、顔が見える関係を築きやすいことです。担当者が固定されやすく、きめ細かい対応が期待できます。ただし、担当者が休みの時や退職した時のバックアップ体制が弱いという面もあります。
大規模事業所(ケアマネジャー5人以上)は、組織としての安定性があります。担当者が休んでも他のケアマネジャーが対応してくれますし、複数の視点からアドバイスをもらえることもあるんです。ただし、担当者が頻繁に変わる可能性もあります。
事業所規模の特徴
小規模:顔が見える関係、きめ細かい対応、担当変更が少ない、バックアップ体制が弱い
大規模:組織の安定性、充実したバックアップ、多様な専門性、担当変更の可能性
また、事業所の運営母体も確認しておきましょう。社会福祉法人、医療法人、株式会社など様々ですが、それぞれに特徴があります。医療法人系なら医療連携に強く、社会福祉法人系なら福祉サービスとの連携がスムーズといった傾向があります。
併設サービスと連携体制の確認

事業所がどのようなサービスを併設しているかも、選び方のポイントです。
デイサービスや訪問介護を併設している事業所なら、サービス間の連携がスムーズです。情報共有も早く、きめ細かい対応が期待できます。ただし、併設サービスばかりを勧められる可能性もありますので、公平な視点でプランを立ててくれるか確認が必要です。
逆に、居宅介護支援だけを専門にしている事業所は、特定のサービスに偏らない中立的なプランを作りやすいというメリットがあります。どちらが良いかは一概に言えませんが、併設サービスの有無は事前に確認しておきましょう。
ケアマネージャーへの相談。できること・できないことの範囲は?
ケアマネジャーを変更したい時の選び方と手続き
もし担当ケアマネジャーに不満がある場合、変更することは可能です。遠慮する必要はありません。
変更を検討すべき具体的なケース

どのような場合に変更を考えるべきでしょうか。
まず、連絡が取りづらい、約束を守らない、訪問に来ないといった基本的な対応に問題がある場合は、変更を検討すべきです。こちらの希望を聞いてくれない、一方的にサービスを決めてしまう、説明が不十分といった場合も同様です。
また、相性の問題もあります。話しづらい、価値観が合わない、信頼できないと感じる場合、無理に我慢する必要はありません。介護は長期戦ですから、信頼できる相手と組むことが大切なんです。
ただし、ちょっとした行き違いや誤解の場合もあります。まずは率直に不満を伝えてみることも大切です。それでも改善されない場合に、変更を検討しましょう。
スムーズに変更する手順と注意点

ケアマネジャーの変更は、思っているより簡単です。
まず、新しい事業所を探します。市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターで事業所リストをもらい、いくつか候補を選んでください。新しい事業所と面談し、契約することになったら、現在の事業所に変更の意思を伝えます。
変更理由を詳しく説明する必要はありません。「家族の事情で」「別の事業所に変更することにしました」程度で十分です。円満に終了することを心がけましょう。
変更手続きの流れ
新しい事業所を探して面談→新しい事業所と契約→現在の事業所に変更を伝える→介護保険証を返却してもらう→新しい事業所に介護保険証を提示→新しいケアプランで利用開始
注意点として、月の途中で変更すると、その月のサービス調整が複雑になる可能性があります。可能であれば、月末や月初のタイミングで変更するのがスムーズです。
新しいケアマネジャーへの引き継ぎ方法

新しいケアマネジャーへの引き継ぎをスムーズに行うことも大切です。
基本的には、前任のケアマネジャーから新しいケアマネジャーへ、これまでのケアプランや利用状況などの情報が引き継がれます。ただし、利用者や家族から直接伝えた方が良い情報もあるんです。
例えば、前のケアマネジャーへの不満点は、新しいケアマネジャーに伝えておくと良いでしょう。「前は○○で困ったので、こういう対応をお願いしたい」と具体的に伝えることで、同じ問題を繰り返さずに済みます。

ケアマネジャーの変更は、利用者の権利として認められています。我慢せず、より良い関係を築ける相手を探すことが大切ですよ。
ケアマネジャーの選び方。まとめ
ケアマネジャーの選び方は、介護生活の質を大きく左右する重要な決断です。知識や経験だけでなく、コミュニケーション能力や相性も含めて総合的に判断することが大切なんです。

基本的な選び方として、まず専門知識と経験を確認しましょう。基礎資格、経験年数、得意分野、担当ケース数などを初回面談で質問してください。ただし、経験豊富だからといって必ずしも良いとは限りません。話を聞いてくれるか、わかりやすく説明してくれるか、相談しやすい雰囲気かといった人柄も同じくらい大切です。
初回面談では、ケアプラン作成の流れ、緊急時の対応体制、担当ケース数、訪問頻度などを具体的に質問しましょう。「どのような介護プランを提案してくれるのか」「緊急時の連絡先はどこか」「現在何人担当しているか」といった質問は、遠慮なくしてください。
事業所選びも重要です。自宅から近い場所にあり、適切な規模と組織体制を持つ事業所を選びましょう。小規模事業所は顔が見える関係を築きやすく、大規模事業所は安定したバックアップ体制があります。どちらが良いかは、求めるサポートの内容によって異なります。
もしケアマネジャーが合わないと感じたら、変更を検討してください。連絡が取りづらい、希望を聞いてくれない、相談しづらいと感じる場合、我慢する必要はありません。変更は利用者の権利として認められており、手続きも思っているより簡単です。
良いケアマネジャーは、単にサービスを調整するだけでなく、利用者と家族に寄り添い、共に考えてくれる存在です。専門的な知識を持ちながらも、わかりやすく説明してくれる。希望をしっかり聞いてくれる。緊急時にも頼りになる。そんなケアマネジャーと出会えることを願っています。
ケアマネジャー選びは、じっくり時間をかけて行ってください。複数の事業所と面談し、比較検討することも大切です。「この人なら信頼できる」と感じられる相手を見つけることが、安心の介護生活への第一歩になります。
介護は長い道のりです。信頼できるケアマネジャーという心強いパートナーと共に、その人らしい生活を実現していきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。





