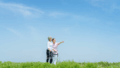「親の介護が必要になったら、退職して面倒を見るべきなのだろうか」「このまま仕事を続けていても、ちゃんと介護できるのだろうか」「退職して介護に専念したほうが、親にとっても自分にとっても良いのではないか」
親の高齢化が進む中で、多くの方がこのような悩みを抱えています。特に最近では、親の認知症が進行したり、要介護度が上がったりするタイミングで、退職を真剣に検討する方が増えています。実際に、まとまった時間を確保して親にしっかりと向き合いたいという気持ちは、とても自然で美しいものです。
しかし、2025年は日本の介護を取り巻く環境が大きく変わる転換点でもあります。団塊の世代が全員75歳以上となる「2025年問題」により、介護需要が急激に増加する一方で、育児・介護休業法の改正により、仕事と介護の両立を支援する制度も大幅に強化されました。この記事では、退職して親の介護をすることを検討している方に向けて、2025年の社会変化を踏まえた新しい視点での判断材料と、準備のポイントについて詳しく解説します。
退職して親の介護を選ぶ背景と2025年問題の影響
2025年、日本は未曾有の超高齢社会を迎えています。この大きな変化が、私たちの介護選択にどのような影響を与えているのかを理解することが重要です。
団塊世代の後期高齢者化で変わる介護環境

2025年、日本は未曾有の超高齢社会を迎えます。約800万人の団塊世代が全員75歳以上の後期高齢者となることで、要介護者数は急激に増加し、これまでとは全く異なる介護環境が生まれています。
2025年問題の具体的な影響
要介護認定者数の急増
2025年には約800万人に達すると予想(現在より約200万人増加)
介護人材の深刻な不足
約32万人から38万人の介護職員が不足予測
地域格差の拡大
都市部では施設不足、地方ではサービス事業者撤退
要介護者数の急増により、介護サービスの需要は爆発的に増加しています。厚生労働省の推計では、2025年には要介護認定者数が約800万人に達すると予想されており、これは現在より約200万人の増加を意味します。
介護人材の深刻な不足も大きな問題となっています。2025年には約32万人から38万人の介護職員が不足すると予測されており、必要なサービスを受けられない「介護難民」の増加が懸念されています。
この状況を受けて、「家族が介護するしかない」と考える方も増えていますが、実際にはこの問題は社会全体で解決すべき課題として位置づけられています。地域包括支援センターや自治体の相談窓口を活用することで、思わぬ解決策が見つかることも少なくありません。
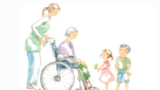
退職による親の介護を考える具体的なきっかけ

退職して親の介護に専念することを考える方の多くが、特定のきっかけを経験しています。これらのきっかけを理解することで、適切な対応策を検討することができます。
親の急激な状態変化が最も多いきっかけです。認知症の症状が進行して徘徊が始まった、転倒により骨折して介護度が上がった、病気により入退院を繰り返すようになったなど、親の状態が急に変わることで「仕事をしている場合ではない」と感じるケースが多くあります。
現在の介護体制への不安も大きなきっかけとなります。デイサービスでの対応に不満がある、ヘルパーとの相性が悪い、夜間の見守りが不十分など、既存のサービスだけでは不安を感じることで、自分が付きっきりで面倒を見たいと考えるようになります。
罪悪感や使命感も重要な要因です。「親に育ててもらった恩を返したい」「最期は自分が看取りたい」「施設に入れるのは可哀想」といった感情は尊いものですが、これらの感情だけで重要な人生選択をすることは危険な場合もあります。
介護難民時代に備える心構えと現実認識

2025年問題により「介護難民」という言葉が注目されていますが、この問題に対する正しい理解と心構えが重要です。
介護難民の実態を正しく理解することが第一歩です。介護難民とは、必要な介護サービスを受けられない状態を指しますが、これは必ずしも「家族が介護するしかない」ことを意味するわけではありません。
利用できるサービスや制度についての情報不足、適切な相談先を知らないことが原因の場合も多く、専門家に相談することで解決できることも少なくありません。
地域資源の活用が介護難民を避ける鍵となります。公的な介護サービスだけでなく、民間のサービス、ボランティア団体、NPO法人、宗教団体など、様々な地域資源が存在します。また、近所の住民同士の助け合いや、同じような状況の家族との情報交換なども重要な資源となります。
社会全体の変化への理解も必要です。2025年問題は確かに深刻ですが、同時に社会全体でこの問題に取り組む機運も高まっています。企業の介護支援制度の拡充、地域包括ケアシステムの整備、テクノロジーの活用など、様々な取り組みが進展しており、これらを活用することで新しい介護のあり方を模索することができます。
退職前に知っておきたい2025年法改正と新制度
2025年4月の育児・介護休業法改正により、仕事と介護の両立環境が大きく改善されています。退職を検討する前に、これらの新制度を十分に理解することが重要です。
育児・介護休業法改正で強化された企業の支援義務

2025年4月の育児・介護休業法改正により、企業の介護支援に関する義務が大幅に強化されました。この改正により、退職せずに仕事と介護を両立する環境が大きく改善されています。
2025年法改正の主要ポイント
個別の制度説明・意向確認の義務化
従業員が介護に直面した際、個別に利用可能制度を説明し希望を確認
40歳前後への事前情報提供義務
介護が始まる前から制度や相談窓口について情報提供
介護休暇制度の要件緩和
勤続1年以上の要件緩和で、働き始めてすぐでも取得可能
個別の制度説明・意向確認の義務化が最も重要な変更点です。企業は従業員が介護に直面した際、その人の状況に応じて利用可能な制度を個別に説明し、どのような支援を希望するかを確認する義務が課せられました。これにより、「制度があることを知らなかった」「どこに相談すればいいかわからなかった」という問題が解消されます。
40歳前後の従業員への事前情報提供も新たに義務化されました。企業は40歳前後の従業員に対して、介護に関する制度や相談窓口について事前に情報提供を行う必要があります。これにより、介護が始まる前から制度について学び、準備をすることができるようになります。
これらの改正により、従来は「退職するしかない」と考えられていた状況でも、新しい選択肢が生まれています。退職を検討する前に、まずは勤務先の人事部門に相談し、どのような支援制度が利用できるかを確認することが重要です。

退職せずに介護と仕事を両立する新しい選択肢

法改正により、仕事と介護の両立はこれまで以上に現実的な選択肢となりました。様々な制度を組み合わせることで、退職せずに質の高い介護を提供することが可能です。
介護休業制度の戦略的活用では、最大93日間の休業を3回まで分割して取得できます。この期間を単純に介護に充てるのではなく、介護体制の構築期間として活用することが重要です。例えば、第1回目は介護サービスの選定と契約、第2回目は親の住環境の整備、第3回目は緊急時の対応体制の確立といった使い方ができます。
テレワークと介護の融合は、特に有効な選択肢です。在宅勤務により通勤時間がなくなることで、その分を介護時間に充てることができます。また、親の様子を見ながら仕事をすることで、緊急事態にも迅速に対応できます。週に2〜3日はテレワーク、残りの日は出社といったハイブリッドな働き方も効果的です。
残業・深夜業務の制限申請により、夜間の介護に備えることができます。法律では、要介護状態の家族を介護する労働者は、深夜業務の制限や残業の免除を申請する権利があります。これにより、夜間の見守りや緊急時の対応に備えることができます。
40歳前後への事前情報提供制度の活用方法

新しく導入された事前情報提供制度は、介護に備える上で非常に重要な制度です。この制度を効果的に活用することで、より良い準備ができます。
制度の内容と目的を正しく理解することが第一歩です。この制度は、親の介護が始まる前から情報を提供することで、いざという時に慌てることなく適切な対応ができるようにすることを目的としています。
事前情報提供制度の効果的活用法
積極的な情報収集姿勢
企業からの情報を受動的に受け取るだけでなく、自分から質問・追加情報を求める
同僚や先輩との情報交換
既に介護を経験している同僚から実体験を聞く
地域情報との照合
会社の情報を基に地域包括支援センターで地域特有の情報を収集
家族との情報共有
得た情報をきょうだいや配偶者と共有し、家族として事前に話し合い
地域の情報との照合も忘れてはいけません。企業から提供される情報は全国共通の制度が中心ですが、実際の介護では地域の特性や利用可能なサービスが重要になります。会社で得た情報を基に、居住地域の地域包括支援センターで相談し、地域特有の情報を収集することが大切です。
定期的な情報更新も重要です。制度は年々改正されており、新しいサービスも続々と登場しています。一度情報を得たからといって安心せず、定期的に最新情報をチェックし、知識をアップデートしていくことが必要です。
退職して親の介護をする場合の準備と注意点
様々な選択肢を検討した結果、退職して親の介護に専念することを選択する場合でも、しっかりとした準備と計画が必要です。感情的な判断だけでなく、現実的な視点での検討が重要です。
経済的シミュレーションと生活設計の重要性

退職して親の介護に専念することを選択する場合、最も重要なのが詳細な経済的シミュレーションです。感情的な判断だけでなく、現実的な数字に基づいた計画が必要です。
詳細な経済的損失の計算例(年収500万円・10年間退職の場合)
・給与収入損失:5,000万円
・退職金減額:約500万円
・厚生年金減額:約1,200万円(生涯)
・健康保険・雇用保険喪失:約360万円
総額損失:約7,060万円
収入の変化を正確に把握することから始めましょう。退職により失う年収に加えて、退職金の減額、厚生年金の加入期間短縮による将来受給額への影響、健康保険や雇用保険の喪失なども含めて総合的に計算する必要があります。
介護費用の詳細な見積もりも欠かせません。在宅介護の場合でも月額5〜15万円程度、施設利用を含めると月額20〜40万円程度の費用が発生します。要介護度の進行に伴い費用は増加するため、5年間、10年間といった長期的な視点での試算が必要です。
家族全体の経済バランスも考慮しなければなりません。自分が退職することで、配偶者の収入だけで家計を維持できるか、子どもの教育費に影響はないか、住宅ローンの支払いは継続できるかなど、家族全体の生活設計への影響を検討する必要があります。
公的支援制度の活用により、負担を軽減することも可能です。高額介護サービス費制度、医療費控除、各種手当など、利用できる制度を最大限活用することで、実質的な負担を軽減できます。
地域資源とテクノロジー活用による負担軽減

退職して介護に専念する場合でも、すべてを一人で抱え込む必要はありません。地域の資源やテクノロジーを積極的に活用することで、負担を大幅に軽減できます。
地域包括支援センターとの連携は最も重要です。退職して時間に余裕ができることで、より密にセンターと連携し、最適なケアプランの策定や定期的な見直しを行うことができます。
見守りテクノロジーの導入により、24時間の監視負担を軽減できます。センサー付きの見守りカメラ、転倒検知センサー、服薬管理システム、GPS機能付きの外出用デバイスなど、様々な技術を組み合わせることで、親の安全を確保しながら介護者の精神的負担を軽減できます。
介護支援ロボットや福祉用具の活用も効果的です。移乗支援ロボット、歩行支援器具、電動ベッド、入浴支援機器など、適切な機器の導入により、介護者の身体的負担を大幅に軽減できます。多くの機器はレンタルで利用でき、介護保険の適用も可能です。
オンラインサービスの活用により、外出の負担を減らすことができます。ネットスーパーによる食材配達、薬局の配達サービス、オンライン診療、遠隔での服薬指導など、様々なサービスを組み合わせることで、外出の回数を減らし、その分を介護時間に充てることができます。

家族間の役割分担と将来への備え方

退職して介護に専念する場合でも、すべてを一人で背負う必要はありません。家族全体での役割分担と将来への備えが重要です。
効果的な家族間役割分担
退職した介護者:日常的なケア・見守り・緊急時対応
他のきょうだい:経済的負担・定期見舞い・手続き代行
配偶者:家事分担・精神的サポート・家計維持
子どもたち:簡単な手伝い・親との交流
きょうだい間での役割分担の明確化が最優先です。退職して介護に専念する人が日常的なケアを担当する一方で、他のきょうだいには経済的な負担、定期的な見舞い、各種手続きの代行、緊急時の対応などを分担してもらうことができます。
地理的に離れているきょうだいも、電話での話し相手や、オンラインでの見守り、介護用品の購入などで貢献することができます。
将来の見通しと段階的計画を立てることも重要です。要介護度の進行に応じて、在宅介護から施設利用への移行、医療的ケアの必要性の増加、看取りの場所の検討など、将来起こりうる変化に対して段階的な計画を立てておきます。
介護者自身のキャリア再開の準備も忘れてはいけません。退職して介護に専念している間も、スキルの維持や向上に努め、将来の再就職に備えることが重要です。オンライン研修の受講、資格の取得、フリーランスとしての小さな仕事の継続など、様々な方法でキャリアを維持することができます。

退職を検討している方は、まず会社の人事部門に相談してみてくださいね。2025年の法改正で両立支援制度が大幅に強化されているので、思わぬ解決策が見つかるかもしれません。一人で悩まず、専門機関にも相談してみることをおすすめします。
まとめ

退職して親の介護に専念するかどうかの判断は、2025年の社会変化を踏まえて慎重に検討する必要があります。団塊世代の後期高齢者化により介護需要が急増する一方で、育児・介護休業法の改正により仕事と介護の両立を支援する制度も大幅に強化されました。
重要なのは、退職という選択肢ありきで考えるのではなく、まずは新しい制度や地域資源を最大限活用して両立の可能性を探ることです。企業の支援義務の強化、テクノロジーの進歩、地域包括ケアシステムの整備など、社会全体で介護を支える仕組みが整いつつある今、個人や家族だけで介護を抱え込む必要はありません。
もし退職して介護に専念することを選択する場合でも、詳細な経済的シミュレーション、地域資源やテクノロジーの活用、家族間での適切な役割分担が欠かせません。一人ですべてを背負うのではなく、社会全体の支援を受けながら、持続可能な介護体制を構築することが重要です。
どのような選択をするにしても、早めの情報収集と準備が鍵となります。40歳前後から会社の制度や地域のサービスについて学び、家族との話し合いを重ね、様々な選択肢を検討しておくことで、いざという時に最適な判断ができるはずです。
親の介護は確かに大きな責任ですが、それを理由に自分の人生を犠牲にする必要はありません。社会全体で介護を支える新しい時代の中で、本人にとっても家族にとっても最善の道を見つけていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。