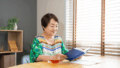「同じ年代の方は何に生きがいを感じているのだろう」「老後をどう過ごせば充実した毎日になるのかわからない」「生きがいを見つけて元気に過ごしたいけれど、何から始めればいいの?」
定年退職や子どもの独立など、ライフスタイルが大きく変わる時期に、何をすれば良いか戸惑ってしまう方は多いです。実際に、高齢者の約3人に2人が生きがいを持って過ごしているという調査結果があり、充実した老後を送るためには生きがいを見つけることが重要だとわかります。
この記事では、高齢者の生きがいランキングTOP10を詳しく解説し、それぞれがもたらす心身への効果、年代別の特徴、そして自分に合った生きがいの見つけ方まで、実践的な情報をお届けします。また、生きがいが見つからない時に家族ができるサポートや、専門家への相談が必要なサインについてもお伝えします。
高齢者が生きがいを持つことの重要性と効果
生きがいとは、生きることに喜びや価値を感じることを指します。高齢者にとって生きがいを持つことは、単に毎日が楽しくなるだけでなく、心身の健康に大きな影響を与えることがわかっています。
3人に2人の高齢者が生きがいを感じている現状

内閣府の調査によると、60歳以上の高齢者のうち約3人に2人が生きがいを持って過ごしていることが明らかになりました。
具体的には、「生きがいを十分感じている」と回答した方が約30%、「多少感じている」と回答した方が約40%で、合わせて約70%の高齢者が何らかの生きがいを感じながら生活しています。
また、「自分の生活に満足しているか」という問いに対して、約76%が「満足している」と回答しており、多くの高齢者が人生に喜びを感じながら過ごしていることがわかります。
一方で、約30%の方は生きがいを感じていないという結果も出ています。生きがいの有無は、日常生活の充実度や健康状態に大きく影響するため、どのように生きがいを見つけるかが重要になります。
生きがいがもたらす心身への具体的なメリット

高齢者が生きがいを持つことで、心身にさまざまな良い効果があることが研究でわかっています。
心理面への効果として、生きがいがあることで毎日に張り合いが生まれ、前向きな気持ちで過ごせるようになります。何かに取り組む目標があることで、朝起きる楽しみができ、生活リズムが整いやすくなります。
また、老後うつの予防効果も期待できます。定年退職や配偶者との死別など、環境の大きな変化がストレスとなり老後うつを発症するケースがありますが、生きがいを持つことで心の支えができ、精神的な安定につながります。
身体面への効果では、生きがいがあることで自然と活動的になり、外出する機会が増えます。歩いたり階段を上ったりする日常動作が運動になり、筋力の維持や体力の向上につながります。
認知症予防や健康寿命延伸につながる理由

生きがいを持つことが、認知症予防や健康寿命の延伸に大きく貢献することが、多くの研究で明らかになっています。
認知症は、社会とのつながりが薄く孤立している高齢者に発症しやすいと言われています。生きがいを持つことで、趣味のサークルに参加したり、友人と交流したりする機会が増え、脳が活性化され認知機能の低下を防ぐ効果があります。
例えば、囲碁や将棋などの戦略的な趣味は、先を読んで考える力を使うため脳のトレーニングになります。また、新しい知識を学ぶことも脳に良い刺激を与え、認知症の発症リスクを下げることがわかっています。
健康寿命の延伸という点では、生きがいがあることで座りっぱなしや寝たきりの時間が減り、自然と体を動かす機会が増えます。日常的に体を動かすことで、筋力が維持され、転倒のリスクが減り、自立した生活を長く続けられるようになります。
また、生きがいを持つことで食欲が湧き、栄養状態が良くなることも健康寿命の延伸につながります。「明日も楽しみがある」という前向きな気持ちが、心身の健康を支える大きな力になるのです。
【親の老後、このままで大丈夫だろうか…】
認知症の介護で家族が限界を感じている場合。共倒れを防ぐ解決策
高齢者の生きがいランキングTOP10を詳しく解説
それでは、実際に高齢者が何に生きがいを感じているのか、内閣府の調査データを基にしたランキングを詳しく見ていきましょう。それぞれの生きがいがもたらす効果も併せて解説します。
家族との団らんや孫との時間が1位の理由

【第1位】家族との団らん・孫との時間(55.3%)
最も多くの高齢者が生きがいを感じているのが、家族や孫と過ごす時間です。子どもが独立して一緒に過ごす時間が減るからこそ、会えた時の喜びがより大きく感じられるのかもしれません。
特に孫の成長を見守ることは、多くの高齢者にとって大きな生きがいとなっています。孫の笑顔を見たい、元気な姿を見たいという気持ちが、「もっと長生きしよう」という前向きな気持ちにつながります。
心身への効果:家族との交流は、孤独感を解消し精神的な安定をもたらします。また、孫の世話をすることで適度な運動になり、体力の維持にもつながります。会話を楽しむことで脳が活性化され、認知症予防の効果も期待できます。

離れて暮らしている場合は、ビデオ通話を活用するのもおすすめです。顔を見ながら話すことで、より深いコミュニケーションが取れますよ。
趣味・スポーツ・食事など日常の喜びランキング

【第2位】美味しいものを食べている時(54.8%)
好きな食事を楽しむことに生きがいを感じる高齢者は、10年前に比べて約15%増加しています。食事は毎日のことだからこそ、日常の中で気軽に喜びを感じられる大切な時間です。
心身への効果:美味しい食事は、心を満たし幸福感をもたらします。また、家族や友人と一緒に食事をすることで会話が弾み、孤独感の解消にもつながります。食事を楽しみにすることで食欲が増し、栄養状態の改善にも効果的です。
【第3位】趣味やスポーツに熱中している時(53.5%)
好きなことに没頭する時間は、多くの高齢者にとって大きな生きがいとなっています。園芸、絵画、音楽、読書など、趣味の種類は人それぞれです。
心身への効果:趣味に打ち込むことで、ストレス発散になり心が安定します。園芸なら土に触れ自然と触れ合うことで癒され、体を動かすことで運動にもなります。囲碁や将棋などの頭を使う趣味は、脳の活性化につながり認知症予防に効果的です。
【第4位】友人・知人と食事や雑談をしている時(52.6%)
友人との交流は、気分転換やストレス発散になり、心のリフレッシュにつながります。
心身への効果:友人と会話をすることで脳が刺激され、認知機能の維持に役立ちます。また、外出して人と会うことで身だしなみに気を付けるようになり、若々しい気持ちを保てます。悩みを相談できる友人がいることで、心の支えになります。
【第5位】テレビやラジオを視聴している時(43.2%)
自宅で気軽に楽しめる娯楽として、多くの高齢者が生きがいを感じています。
心身への効果:好きな番組を見て笑うことで、ストレス解消になり自律神経のバランスが整います。また、ドキュメンタリーやニュースを見ることで新しい知識を得られ、脳の活性化につながります。
【第6位】旅行をしている時(39.8%)
時間に余裕ができる老後は、平日や閑散期に旅行できるため、お得に楽しめます。
心身への効果:非日常の体験は脳に良い刺激を与え、記憶力の維持に役立ちます。また、旅行の計画を立てることも脳のトレーニングになります。新しい場所を訪れることで視野が広がり、人生が豊かになります。
【第7位】夫婦で過ごしている時(34.5%)
長年連れ添ったパートナーとの時間を、改めて大切に感じる高齢者が多いです。
心身への効果:パートナーがいることで孤独感が解消され、精神的な安定につながります。共通の趣味を見つけて一緒に楽しむことで、関係性がより良くなり、2人で協力して生活することで生活の質が向上します。
【第8位】他人から感謝された時(31.7%)
社会活動やボランティアに参加することで、誰かの役に立っている実感を得られます。
心身への効果:人から感謝されることで自己肯定感が高まり、生きる意欲が湧いてきます。地域活動に参加することで新しい友人ができ、社会とのつながりが生まれます。
【第9位】仕事に打ち込んでいる時(30.9%)
実際に65歳から69歳の2人に1人が何らかの仕事をしています。
心身への効果:働くことで生活リズムが整い、健康的な生活を送れます。また、社会とのつながりを感じられ、孤独感の解消につながります。収入を得ることで経済的な安心感も生まれます。
【第10位】十分な収入があると感じる時(24.8%)
経済的な安定は、心の余裕を生み、老後の不安を軽減します。
心身への効果:お金の心配が減ることで精神的なストレスが軽減され、好きなことにお金を使えることで生活の質が向上します。趣味や旅行を楽しむ余裕が生まれ、より充実した老後を送れます。
男女で異なる生きがいの傾向とその背景

高齢者の生きがいには、男女で違いがあることが調査からわかっています。
男性に多い生きがい:男性は「仕事に打ち込んでいる時」が1位で41.5%となっています。長年仕事を中心に生活してきた男性にとって、退職後も何らかの形で働くことが生きがいになりやすい傾向があります。また、「趣味やスポーツに熱中している時」も上位に入っており、ゴルフや釣りなど、アウトドアの趣味を楽しむ男性が多いです。
女性に多い生きがい:女性は「孫など家族との団らんの時」が1位で55.4%と、男性よりも高い割合となっています。また、「友人や知人と食事、雑談している時」も34.8%と男性(20.3%)に比べて高く、人との交流を重視する傾向が見られます。
ただし、これはあくまで傾向であり、個人差が大きいことを理解しておくことが大切です。自分にとって何が生きがいになるかは、性別に関係なく、これまでの人生経験や価値観によって異なります。
親の介護でメンタルがやられる原因と対処法。心の健康を守るには?
年代別で見る高齢者の生きがいの特徴
高齢者といっても、50代、60代、70代以降では、体力や生活スタイルが大きく異なります。それぞれの年代で生きがいの感じ方にも特徴があります。
50代60代は仕事や社会活動に生きがいを感じやすい

50代から60代前半は、まだ体力もあり社会との関わりを強く持っている年代です。
この年代では、仕事に生きがいを感じる方が多く、定年後も再雇用や再就職で働き続ける方が増えています。仕事を通じて社会とのつながりを保ち、自分の経験や知識を活かせることに喜びを感じます。
また、地域のボランティア活動や町内会の役員など、社会貢献活動に参加する方も多い年代です。誰かの役に立っている実感が、生きがいにつながります。
趣味の面では、登山やゴルフ、テニスなど、ある程度体力を使うスポーツを楽しむ方も多いです。健康維持のために積極的に体を動かし、仲間との交流も楽しむことができます。
70代以降は家族との時間や趣味を重視する傾向

70代以降になると、体力面での変化を感じる方が増え、生活の中心が家族や身近な人との時間にシフトしていきます。
この年代では、孫との時間や子どもとの団らんに生きがいを感じる方が特に多くなります。孫の成長を見守ることが何よりの楽しみとなり、孫に会えることを心待ちにする方が多いです。
趣味の面では、激しい運動よりも、園芸、読書、音楽鑑賞、書道など、自宅やその周辺でゆったりと楽しめる活動が好まれます。特に園芸は、自然と触れ合いながら適度に体を動かせるため、70代以降の方に人気です。
また、友人との穏やかな交流も大切にされます。カフェでお茶を飲みながらおしゃべりを楽しんだり、近所を一緒に散歩したりと、無理のない範囲での交流を大切にする傾向があります。
年齢とともに変化する生きがいの見つけ方

年齢とともに体力や生活環境が変化するため、生きがいも柔軟に変えていくことが大切です。
例えば、60代で登山を楽しんでいた方が、70代になって膝に不安を感じるようになったら、ウォーキングや水中ウォーキングに切り替えるなど、体力に合わせて活動内容を調整することで、無理なく生きがいを継続できます。
また、仕事に生きがいを感じていた方が完全に引退した後は、地域のボランティアや趣味のサークルに参加することで、新しい生きがいを見つけることができます。
大切なのは、「以前はできたのに」と過去にこだわるのではなく、「今の自分に何ができるか」「今の自分が楽しめることは何か」という視点で生きがいを探すことです。
高齢者が自分に合った生きがいを見つける5つの方法
ランキングを見ても、なかなか自分の生きがいが見つからないという方もいるでしょう。ここでは、具体的に生きがいを見つけるための5つの方法をご紹介します。
小さな興味や好きなことから始めてみる

生きがい探しは、何か大きなことを始める必要はありません。日常の中にある小さな「好き」や「興味」から始めてみましょう。
例えば、散歩道で見かける花が気になったら、その花の名前を調べてみる。テレビで見た料理が美味しそうだったら、作ってみる。昔好きだった音楽を久しぶりに聴いてみる。こうした小さなきっかけが、大きな生きがいにつながることがあります。
最初から「これを生きがいにしよう」と構える必要はありません。気軽に試してみて、楽しければ続ける、合わなければやめる、という気持ちで始めることが大切です。
小さく始められることの例
・ベランダで花を一鉢育ててみる
・図書館で興味のある本を1冊借りてみる
・近所の公園まで散歩してみる
・好きな音楽を聴きながらお茶を飲む
・簡単な体操を1日5分やってみる
体力や予算に合わせて無理なく続けられるものを選ぶ

生きがいは長く続けられることが大切です。そのためには、自分の体力や経済状況に合ったものを選ぶことが重要です。
体力に不安がある場合は、激しい運動ではなく、ウォーキングや軽い体操、ストレッチなど、無理のない範囲で体を動かせる活動を選びましょう。また、座ってできる趣味も良い選択肢です。読書、編み物、塗り絵、パズルなど、自宅で楽しめるものはたくさんあります。
経済面では、お金をかけなくても楽しめることはたくさんあります。図書館の利用、公園での散歩、地域の無料イベントへの参加、自宅でのラジオ体操など、工夫次第で費用を抑えながら充実した時間を過ごせます。
誰かのために役立つ活動から探してみる

自分が楽しむだけでなく、「誰かの役に立つ」という視点で活動を探すことも、生きがいを見つける有効な方法です。
人は社会の中で誰かの役に立ったり、貢献したりすることで、喜びや「自分が必要とされている」という感覚を得られます。特に定年退職後は社会とのつながりが薄れがちですが、誰かのための活動は、人との関わりを取り戻すきっかけになります。
例えば、地域の清掃活動、見守りボランティア、福祉施設での話し相手、子ども食堂の手伝いなど、さまざまな活動があります。これまでの仕事で得た経験や知識が、意外なところで役立つこともあるでしょう。
人から「ありがとう」と言われたり、頼りにされたりする経験は、日々の生活に新しい意味や充実感を与えてくれます。自分の経験が誰かの役に立つことで、自己肯定感が高まり、生きる意欲にもつながります。
自治体の広報誌や公民館、地域包括支援センターなどで、ボランティア活動の情報を得ることができます。まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
生きがいが見つからない時に知っておきたいこと
生きがいを見つけようと努力しても、なかなか見つからない、何をしても楽しいと感じられないという方もいます。そんな時に知っておいてほしいことがあります。
無気力が続く場合は抑うつの可能性も考慮する

何をしても楽しいと感じられない、やる気が出ない、という状態が2週間以上続く場合は、単なる一時的な気分の落ち込みではなく、老後うつ(高齢者うつ病)の可能性も考慮する必要があります。
老後うつは、定年退職、配偶者や友人との死別、身体機能の低下、経済的な不安など、さまざまな要因で発症します。以下のような症状が見られる場合は注意が必要です。
何に対しても興味が湧かない、楽しめない
食欲がない、または食べすぎてしまう
眠れない、または寝すぎてしまう
疲れやすく、体がだるい
自分を責めてしまう、価値がないと感じる
集中力が低下し、物事が決められない
死について考えることが増えた
高齢者のうつ病は、本人が「単なる年のせい」と思い込んでしまい、発見が遅れることがあります。また、認知症と症状が似ている部分もあるため、専門医による診断が重要です。
家族が見守りながらサポートする方法

家族が高齢者の生きがい探しをサポートする際には、押し付けにならないように注意することが大切です。
「○○をやってみたら?」「△△に参加してみたら?」と勧めることは良いですが、本人が興味を示さない場合は無理強いしないようにしましょう。本人が楽しめるものでなければ、生きがいにはなりません。
一緒に楽しむという姿勢が効果的です。例えば、「一緒に散歩に行こう」「一緒に映画を見よう」と誘うことで、自然と新しい活動に触れる機会ができます。一緒に過ごす時間が増えることで、会話も増え、自然な見守りもできます。
また、小さな変化を見逃さないことも大切です。「最近元気がないな」「食事の量が減っているな」「外出しなくなったな」といった変化に気づいたら、優しく声をかけてみましょう。

「最近どう?」「何か困っていることない?」と、さりげなく話しかけることで、本人の気持ちを知るきっかけになります。話を聞く姿勢が大切ですよ。
専門家への相談が必要なサインと相談窓口

以下のような状態が見られる場合は、専門家への相談を検討すべきサインです。
2週間以上、何に対しても興味が持てない、楽しめない状態が続いている
睡眠や食事に明らかな変化がある
「死にたい」「消えてしまいたい」といった発言がある
身だしなみに構わなくなった
人との交流を極端に避けるようになった
物忘れが急激に増えた(認知症の可能性もあります)
このようなサインが見られたら、まずはかかりつけ医に相談するのが良いでしょう。必要に応じて、精神科や心療内科を紹介してもらえます。また、地域包括支援センターでも、高齢者の心の問題について相談できます。
生きがいを見つけることは大切ですが、それ以前に心の健康が損なわれている場合は、まず心のケアが必要です。専門家の力を借りながら、心の健康を取り戻すことが、生きがいを見つける第一歩になります。
介護うつの症状とは?早期発見のためのチェック項目と適切な対処法
高齢者の生きがいランキングから学ぶ充実した老後:まとめ
高齢者の生きがいランキングと、充実した老後を送るためのヒントについてお伝えしました。
高齢者の約3人に2人が生きがいを持って過ごしており、生きがいを持つことで認知症予防や健康寿命の延伸など、心身に多くの良い効果があることがわかりました。
生きがいランキングTOP3は、家族との団らん(55.3%)、美味しいものを食べる(54.8%)、趣味やスポーツに熱中する(53.5%)でした。それぞれの生きがいが、心の安定や脳の活性化、体力の維持など、さまざまな面で健康に貢献しています。
男女や年代によって生きがいの傾向は異なり、50代60代は仕事や社会活動、70代以降は家族との時間や穏やかな趣味を重視する傾向があります。年齢とともに生きがいが変化することは自然なことで、その時々の自分に合った楽しみ方を見つけることが大切です。
ただし、何をしても楽しめない、無気力な状態が2週間以上続く場合は、老後うつの可能性も考慮し、専門家への相談を検討することが大切です。家族は押し付けにならないようサポートし、一緒に楽しむ姿勢で見守ることが効果的です。
生きがいを持つことは、充実した老後を送るための大きな鍵となります。ランキングを参考にしながら、ご自身や家族にとっての生きがいを見つけ、心身ともに健康で豊かな毎日を過ごしましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。