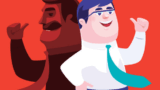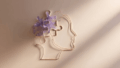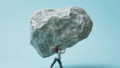「介護の相談はどこにすればいいの?」
「地域包括支援センターと居宅介護支援事業所、何が違うの?」
「うちの親はどちらに相談すべき?」
介護が必要になった時、多くの方がこのような疑問を抱きます。

実は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所は、対象者も役割も大きく異なる機関なんです。適切な相談先を選ぶことで、必要な支援をスムーズに受けられるようになります。
この記事では、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違いを詳しく解説し、どちらに相談すべきかの判断基準をお伝えします。両機関の連携についても紹介しますので、介護サービスを上手に活用するための参考にしてください。
地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の基本的な違い
地域包括支援センターと居宅介護支援事業所は、介護に関わる重要な機関ですが、その役割は明確に異なります。まずは基本的な違いを理解していきましょう。
対象者と役割の違いを理解する

最も大きな違いは、対象となる方の範囲にあります。
地域包括支援センターは、地域に住む65歳以上のすべての高齢者とその家族を対象としています。介護認定を受けていない方でも、将来の介護に備えた相談や、健康づくりに関する相談など、幅広い内容に対応してくれるんです。「まだ介護は必要ないけれど、将来が心配」という段階から気軽に相談できる総合窓口といえます。
一方、居宅介護支援事業所は、要介護1以上の認定を受けた方を専門に支援する機関です。既に介護が必要な状態にある方に対して、具体的な介護サービスの計画を立て、実際のサービス利用をサポートします。
役割についても違いがあります。地域包括支援センターは介護だけでなく、医療・福祉・生活支援まで含めた包括的な相談に対応します。居宅介護支援事業所は、介護サービスの計画作成と調整に特化した機関なんです。
配置される専門職と提供サービスの違い

配置されている専門職にも、それぞれの機関の特徴が表れています。
地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーという3つの専門職が配置されています。保健師は健康面の相談、社会福祉士は権利擁護や生活困窮の相談、主任ケアマネジャーは介護サービスの相談と、それぞれの専門性を活かしたチームで対応してくれるんです。
一方、居宅介護支援事業所には、ケアマネジャー(介護支援専門員)が配置されています。ケアマネジャーは介護サービスの専門家として、利用者一人ひとりに最適なケアプランを作成し、継続的にサポートします。
提供されるサービスの内容も異なります。地域包括支援センターでは、成年後見制度の相談、虐待の相談、認知症に関する相談など、介護以外の幅広い相談にも対応してくれます。居宅介護支援事業所は、介護保険サービスの利用に関する相談と調整に専念しているんです。
運営主体と利用料金の違い

運営の仕組みにも、両機関には大きな違いがあります。
地域包括支援センターは、市区町村が設置主体となっています。直営の場合もあれば、社会福祉法人などに委託して運営している場合もありますが、いずれも公的な性格が強い機関です。各市区町村に必ず設置されており、地域によっては複数のセンターが設けられています。
居宅介護支援事業所は、社会福祉法人、医療法人、株式会社など、様々な法人が運営しています。地域に複数の事業所があり、利用者が自由に選べる仕組みになっているんです。
利用料金については、両機関とも利用者の自己負担はありません。地域包括支援センターの相談は完全無料です。居宅介護支援事業所のケアプラン作成やサービス調整も、介護保険から全額支払われるため、利用者負担はゼロなんです。
比較表で見る主な違い
対象者:地域包括(65歳以上全員)/居宅介護(要介護1以上のみ)
役割:地域包括(総合相談窓口)/居宅介護(ケアプラン作成専門)
専門職:地域包括(3職種)/居宅介護(ケアマネジャー)
運営:地域包括(市区町村主体)/居宅介護(多様な法人)
料金:両機関とも無料
【介護の相談先、どこに連絡すればいいか迷っていませんか?】
悪いケアマネージャーの見極め方と対処法とは?知っておきたい知識
地域包括支援センターの特徴と利用すべきケース
地域包括支援センターは、介護の入口となる総合相談窓口です。具体的にどのような特徴があるのか見ていきましょう。
総合相談窓口としての幅広い支援内容

地域包括支援センターの最大の特徴は、相談内容を選ばない総合窓口という点です。
「最近、親の物忘れが気になる」「一人暮らしの親が心配」「介護保険のことがよくわからない」といった漠然とした不安から、「虐待されているのではないか」「お金の管理ができなくなってきた」といった深刻な問題まで、高齢者に関する様々な相談を受け付けています。
また、相談者も本人だけでなく、家族、近隣住民、民生委員など、誰でも相談できるんです。「向かいのおばあさんが最近姿を見ない」といった地域の気づきも、重要な相談として受け止めてくれます。
相談は電話でも訪問でも可能です。センターに出向くことが難しい場合は、職員が自宅まで来てくれることもあります。
要支援認定者へのケアプラン作成

地域包括支援センターには、要支援1・2の方へのケアプラン作成という重要な役割もあります。
要支援認定を受けた方は、介護予防を目的としたサービスを利用できます。このサービス計画(介護予防ケアプラン)を作成するのが、地域包括支援センターの仕事なんです。デイサービス、訪問介護、福祉用具レンタルなど、必要なサービスを組み合わせて計画を立ててくれます。
ただし、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が、要支援者のケアプラン作成を行う場合もあります。これは地域包括支援センターの業務量によって判断されます。
地域包括支援センターに相談すべき具体例

どのような時に地域包括支援センターを利用すべきか、具体的なケースを見ていきましょう。
まず、介護認定を受けていない段階での相談は、地域包括支援センターが適切です。「親の様子が変わってきた気がする」「転倒が増えてきた」「物忘れが心配」といった変化に気づいた時点で、早めに相談することをお勧めします。
また、介護保険の申請自体がわからない、どこから始めればいいかわからないという場合も、地域包括支援センターが相談窓口になります。申請の手続きから丁寧にサポートしてくれるんです。
認知症に関する相談も、地域包括支援センターの得意分野です。認知症の初期段階での対応、家族の接し方、利用できるサービスなど、包括的にアドバイスしてくれます。

「こんなことで相談していいのかな」と躊躇する必要はないんです。小さな不安でも気軽に相談してみてください。早めの相談が、結果的に良い介護につながりますよ。
地域包括支援センターの対応がひどいと感じた時の対処法。解決策は?
居宅介護支援事業所の特徴と利用すべきケース
居宅介護支援事業所は、要介護者の生活を支える専門機関です。その特徴と利用すべきケースを詳しく見ていきましょう。
要介護者専門のケアプラン作成機関

居宅介護支援事業所の主な役割は、要介護1〜5の方のケアプラン作成です。
ケアプランとは、利用者の状態や希望に応じて、どのような介護サービスをいつ、どれくらい利用するかを決めた計画書のことです。訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具レンタルなど、様々なサービスを組み合わせて、一人ひとりに最適なプランを作成します。
このケアプランは、ケアマネジャーが本人や家族の希望を丁寧に聞き取り、心身の状態を評価したうえで作成されます。医師の意見書や、実際にサービスを提供する事業所の意見も参考にしながら、その人らしい生活を支えるための計画を立ててくれるんです。
また、ケアプランは一度作ったら終わりではありません。定期的に見直しを行い、状態の変化に応じて適切に修正していきます。
ケアマネジャーによる継続的なサポート

居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、利用者と長期的に関わる重要なパートナーです。
ケアプラン作成後も、月に1回以上は自宅を訪問し、サービスが適切に提供されているか、困っていることはないかを確認します。この訪問をモニタリングといい、利用者の状態変化を早期に発見する大切な機会になっているんです。
また、ケアマネジャーは各サービス事業所との調整役も担います。訪問介護事業所、デイサービス、福祉用具事業所など、複数の事業所が関わる場合、それぞれと連絡を取り合い、スムーズなサービス提供を実現します。
急な入院や状態の悪化など、予期せぬ事態が起きた時にも、ケアマネジャーが中心となって対応してくれます。介護生活の心強い味方といえるでしょう。
居宅介護支援事業所を選ぶべき具体例

どのような状況で居宅介護支援事業所を利用すべきか、具体的なケースを確認しましょう。
まず、要介護1以上の認定を受けた方は、必然的に居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランを作成してもらうことになります。認定結果が届いたら、速やかに事業所を探して契約することをお勧めします。
また、要支援から要介護に変更になった場合も、居宅介護支援事業所に切り替える必要があります。この場合、地域包括支援センターが適切な事業所を紹介してくれることが多いです。
複数の介護サービスを組み合わせて利用したい場合も、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談するのが効率的です。各サービスの特徴を理解したうえで、最適な組み合わせを提案してくれます。
居宅介護支援事業所の選び方
自宅からの距離や対応エリア、事業所の規模と対応力、ケアマネジャーの経験や専門性、医療機関との連携体制、口コミや評判を参考にして選びましょう。
ケアマネージャーへの相談。できること・できないことの範囲は?
地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の連携
両機関は独立して機能しているわけではなく、密接に連携しながら高齢者を支えています。その連携の仕組みを見ていきましょう。
両機関が連携する理由と仕組み

地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の連携は、利用者にとって切れ目のない支援を実現するために欠かせません。
地域包括支援センターは地域全体を見渡す立場にあり、様々な相談を受け付けます。その中で要介護認定が必要と判断されたり、既に要介護認定を受けている方からの相談があったりした場合、適切な居宅介護支援事業所を紹介します。
逆に、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、利用者の権利擁護や虐待の問題に気づいた場合、地域包括支援センターに相談します。介護保険サービスだけでは解決できない課題について、専門的な支援を求めるわけです。
要支援から要介護への移行時の連携

特に重要なのが、要支援から要介護に変更になった時の連携です。
要支援の方は地域包括支援センターでケアプランを作成していますが、要介護に認定が変更になると、居宅介護支援事業所に引き継がれます。この移行をスムーズに行うことが、利用者の生活の継続性を保つために大切なんです。
地域包括支援センターは、これまでのケアプランや利用者の状態、家族の状況などの情報を、新しく担当する居宅介護支援事業所のケアマネジャーに丁寧に引き継ぎます。このおかげで、ケアマネジャーが変わっても、利用者は安心してサービスを受け続けられるんです。
利用者にとっての連携のメリット

両機関の連携は、利用者と家族に多くのメリットをもたらします。
まず、どこに相談すればいいかわからない時でも、どちらかに相談すれば適切な窓口につないでもらえます。たらい回しにされることなく、必要な支援に到達できるんです。
また、複雑な問題を抱えている場合も、両機関が協力することで包括的な支援が受けられます。例えば、介護が必要な上に経済的な問題もある、認知症で金銭管理ができないといった場合、それぞれの専門性を活かした対応が可能になります。
さらに、地域全体で高齢者を見守る体制が整います。地域包括支援センターが地域の状況を把握し、各居宅介護支援事業所と情報を共有することで、孤立しがちな高齢者も早期に発見され、適切な支援につながるんです。

両機関の連携があるからこそ、介護が必要になっても安心して地域で暮らし続けられるんですね。困った時は、まずどちらかに相談してみることが大切です。
地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違い。まとめ
地域包括支援センターと居宅介護支援事業所は、それぞれ異なる役割を持ちながら、高齢者の生活を支えています。

地域包括支援センターは、65歳以上のすべての高齢者を対象とした総合相談窓口です。介護認定の有無にかかわらず、介護・医療・福祉・生活支援まで幅広い相談に対応します。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーという3職種が連携し、地域全体を見守る役割を担っているんです。
一方、居宅介護支援事業所は、要介護1以上の認定を受けた方を専門に支援する機関です。ケアマネジャーが一人ひとりに最適なケアプランを作成し、継続的なサポートを提供します。介護サービスの調整役として、利用者の生活を支える重要な存在といえるでしょう。
どちらに相談すべきか迷った時は、まず地域包括支援センターに連絡してみることをお勧めします。適切な窓口を案内してもらえますし、必要に応じて居宅介護支援事業所も紹介してくれます。
両機関の連携により、要支援から要介護への移行もスムーズに行われます。状態が変化しても、切れ目なく適切な支援を受けられる体制が整っているんです。
介護が必要になることは、決して特別なことではありません。誰もが年齢を重ねれば、何らかの支援が必要になります。早めに相談することで、より多くの選択肢と余裕を持って介護に向き合えるようになります。
「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、少しでも不安を感じたら、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に相談してみてください。専門職が親身になって、あなたと家族に合った支援を一緒に考えてくれます。
介護は一人で抱え込むものではありません。地域の支援を上手に活用しながら、その人らしい生活を実現していきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。