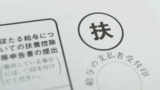「年金だけでは生活できない。生活保護を受けたら年金はどうなるの?」「両方もらえるの?それとも年金が止まってしまう?」「親が年金をもらっているけれど、生活保護の申請はできるのかしら」
年金収入だけでは生活が厳しく、生活保護を検討している方にとって、年金がどうなるかは最も気になる点ですよね。年金が止まってしまうのではないか、両方もらえるとしてもどんな条件があるのか、不安に感じる方は少なくありません。
実際、生活保護と年金の関係は複雑で、世帯の状況や年金額によって受給できるかどうかが変わってきます。正しい知識がないまま申請すると、本来受けられるはずの支援を逃してしまうこともあるのです。
この記事では、生活保護を受けた場合の年金について、両方受給できる条件、年金額への影響、申請手続きの流れまで、わかりやすく解説していきます。制度を正しく理解して、安心して生活できる道を見つけましょう。
生活保護を受けても年金はどうなるのか
結論から言うと、生活保護を受給しても年金は止まりません。生活保護と年金は両方受け取ることができます。ただし、年金は収入とみなされるため、その分だけ生活保護費が減額される仕組みになっています。
生活保護と年金の基本的な関係

生活保護は、生活に困窮するすべての国民に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。一方、年金は若い頃に保険料を納めた対価として受け取る給付金といえます。
この2つの制度は、目的も仕組みも異なります。しかし、両方を同時に受け取ることは可能なのです。生活保護の考え方は、最低生活費と実際の収入の差額を補填するというものです。
具体的な計算式は次の通りです。
生活保護費 = 最低生活費 − 収入(年金を含む)
つまり、年金を受け取っていても、それだけでは最低生活費に満たない場合、その不足分を生活保護で補ってもらえるということです。年金が5万円で最低生活費が12万円なら、差額の7万円が生活保護費として支給されます。
年金を受給しながら生活保護を受けるメリット

年金を受け取りながら生活保護を受けることには、いくつかのメリットがあります。
第一に、医療費が原則無料になります。年金生活者の多くは、通院や薬代などの医療費負担に悩まされていますが、生活保護を受けることで、これらの負担がなくなるのです。ただし、医療を受ける際は事前に福祉事務所に申請し、医療券を発行してもらう必要があります。
第二に、国民年金保険料が免除されます。まだ年金を受給していない方で、国民年金の保険料を支払っている場合、生活保護の生活扶助を受けると、保険料が法定免除となります。審査なしで免除されるため、将来の年金受給権も守られます。
第三に、住宅扶助や生活扶助など、年金だけでは賄えない生活費を補ってもらえます。家賃や光熱費、食費など、日常生活に必要な費用を安定的に確保できるようになります。
年金額が多い場合は生活保護を受けられないケース

年金を受け取っていても生活保護を受けられるとお伝えしましたが、年金額が最低生活費を上回る場合は、生活保護を受けることができません。
例えば、最低生活費が月額12万円の地域で、年金収入が月額13万円ある場合、年金だけで最低生活費を上回っているため、生活保護の対象とはなりません。
ただし、医療費や介護費用など、突発的な支出が多い場合は、実質的な生活が苦しくなることもあります。このような場合でも、年金額だけで判断されるため、生活保護は受けられないのです。
また、年金以外にも収入がある場合は、すべての収入を合算して判定されます。例えば、パートで働いている、不動産収入がある、仕送りを受けているといった場合は、それらも含めて最低生活費と比較されることになります。

年金額が最低生活費に近い場合、わずかな差で生活保護が受けられないこともあります。このようなギリギリのケースは判断が難しいので、まずは福祉事務所に相談してみることをおすすめします。
75歳以上の親を扶養に入れる別居時の手続き。条件と必要書類を解説
生活保護を受けるための条件と年金との関係
生活保護を受けるには、年金額だけでなく、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件を正しく理解しておくことが、スムーズな申請につながります。
収入と資産の要件

生活保護を受けるための第一の条件は、年金を含めたすべての収入が最低生活費を下回っていることです。年金だけでなく、働いて得た収入、不動産収入、仕送りなど、あらゆる収入が対象となります。
さらに、換金できる資産を持っていないことも重要な条件です。具体的には、以下のような資産がある場合、原則として生活保護は受けられません。
保有が認められにくい資産
・預貯金(最低生活費の半分程度を超える額)
・土地や建物(持ち家で資産価値が高い場合)
・自動車(通勤や通院に必須でない場合)
・生命保険(解約返戻金が高額な場合)
・貴金属や骨董品などの高額な動産
ただし、すべての資産を手放さなければならないわけではありません。持ち家でも、資産価値が低く、売却してもほとんどお金にならない場合や、65歳以上の高齢者で要保護世帯向け長期生活支援資金の対象となる場合は、保有が認められることもあります。
自動車についても、地方の交通不便地域で通勤や通院に必須の場合や、障害があって他の移動手段がない場合などは、保有が認められるケースもあるのです。
親族からの援助と扶養照会の問題

生活保護を申請すると、親族に扶養照会がおこなわれます。これは、申請者を援助できる親族がいないかを確認するための手続きです。
扶養照会は、三親等以内の親族(親、子、兄弟姉妹、孫など)に対して行われます。福祉事務所から親族に連絡が行き、経済的な援助が可能かどうかを尋ねられるのです。
多くの方が、この扶養照会を理由に生活保護の申請をためらいます。「子供や兄弟に迷惑をかけたくない」「親族に知られたくない」という気持ちは、よく理解できますよね。
しかし、親族が援助できないと回答すれば、それで問題ありません。親族に法的な扶養義務があるわけではなく、あくまで「援助可能かどうか」を確認するだけの手続きなのです。
また、以下のような場合は、扶養照会を省略できることもあります。
扶養照会が省略されるケース
・親族から虐待やDVを受けていた場合
・親族と長年音信不通で、連絡先がわからない場合
・親族自身が生活に困窮している場合
・親族が遠方に住んでおり、援助が現実的でない場合
扶養照会が心配で申請をためらっている方は、まず福祉事務所の相談員に事情を詳しく説明しましょう。状況によっては、照会を省略したり、配慮ある対応をしてもらえる可能性があります。
働ける能力と他の制度の活用

生活保護の原則として、働ける能力がある場合は、まず働くことが求められます。病気やケガ、高齢などの理由で働けない場合にのみ、生活保護が適用されるのです。
ただし、高齢者の場合は、この条件はそれほど厳しく適用されません。65歳以上であれば、原則として就労を求められることはなく、年金収入だけで生活できない場合に生活保護を受けることができます。
また、他の公的制度を活用しても困窮していることも条件となります。例えば、障害年金や遺族年金を受給できる可能性がある場合は、まずそれらの申請を行う必要があります。
介護保険サービスや障害福祉サービス、医療費助成制度など、利用できる制度はすべて活用した上で、それでも生活が成り立たない場合に、生活保護が最後のセーフティネットとして機能するのです。
親の介護でお金がない時の対処法。公的支援制度や負担軽減策はある?
生活保護を受けた場合の年金手続きと注意点
生活保護を受けることになった場合、年金に関する手続きや注意すべき点があります。これらを理解しておかないと、後で困ることにもなりかねません。
年金収入の申告義務と収入認定

生活保護を受給している間は、すべての収入を福祉事務所に申告する義務があります。年金も例外ではなく、受給した金額を正確に報告しなければなりません。
年金は2ヶ月に1度振り込まれるため、振込があった月には必ずケースワーカーに報告します。報告を怠ると、不正受給とみなされ、生活保護の停止や打ち切り、さらには返還を求められる可能性もあるため注意が必要です。
年金収入は、全額が収入として認定されます。つまり、年金が振り込まれた月は、その金額だけ生活保護費が減額されるのです。例えば、通常の生活保護費が月12万円で、年金が2ヶ月分10万円振り込まれた場合、その月の生活保護費は12万円 − 5万円(1ヶ月分)= 7万円となります。
国民年金保険料の免除手続き

まだ年金を受給しておらず、国民年金保険料を支払っている方が生活保護を受けると、保険料が法定免除となります。これは、生活保護の生活扶助を受けている方に自動的に適用される制度です。
法定免除を受けるには、市区町村の窓口に「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出する必要があります。生活保護の決定通知を受け取ったら、できるだけ早く手続きを行いましょう。
法定免除を受けている期間は、保険料を納付しなくても年金受給資格期間には算入されます。ただし、年金額は通常の半額(国庫負担分のみ)となります。
この点について、「将来の年金額が減るのは困る」と考える方もいるかもしれません。しかし、生活保護を受けている状況で保険料を支払うことは、生活をさらに圧迫することになります。まずは今の生活を安定させることが優先です。

生活保護から抜け出して、経済的に安定したら、その時点で国民年金の追納を検討することもできます。10年前までの期間なら追納可能ですよ。
障害年金や遺族年金も収入認定されるのか

老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金も収入として認定されます。つまり、これらの年金を受け取っている場合も、その金額だけ生活保護費が減額されることになります。
障害年金は、病気やケガで障害を負った方に支給される年金です。障害基礎年金と障害厚生年金があり、障害の程度に応じて1級と2級(厚生年金の場合は3級も)に分かれています。
遺族年金は、生計を支えていた家族が亡くなった場合に支給される年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、配偶者や子供が受給できます。
これらの年金も、受け取った金額は全額収入として認定され、生活保護費から差し引かれます。ただし、年金額が最低生活費を下回っていれば、その差額を生活保護費として受け取ることができるのです。
介護保険料はいつまで払う?支払い期間と免除・軽減制度を詳しく解説
生活保護と年金に関するケース別の対応方法
実際には、親の年金額や世帯状況、介護の有無などによってケースは大きく変わります。ここでは、よくある状況別に対応方法を見ていきましょう。
親が年金をもらっているが生活が苦しい場合

高齢の親が年金を受給しているものの、その金額だけでは生活できず、子供が仕送りをしているというケースは多いですよね。しかし、子供自身の生活も苦しく、仕送りを続けるのが難しい場合もあります。
このような場合、親が生活保護を申請することを検討してもよいでしょう。年金を受給していても、その金額が最低生活費を下回っていれば、差額を生活保護費として受け取ることができます。
ただし、生活保護を申請すると、子供に扶養照会が行われる可能性があります。扶養照会を受けた子供は、経済的な援助ができるかどうかを回答することになります。
「援助できない」と回答すれば、それで問題はありません。法的な扶養義務があるわけではなく、あくまで任意の援助を求めるものだからです。親の生活保護受給が決まれば、子供は仕送りをしなくても済むようになります。
年金を受給していない無年金の高齢者の場合

年金を全く受給していない、いわゆる無年金の高齢者もいます。保険料を納めていなかった、加入期間が不足しているなどの理由で、年金を受け取れない方です。
このような方は、収入が全くない状態ですから、生活保護の対象となりやすいです。ただし、資産がないこと、親族からの援助が受けられないことなど、他の要件も満たす必要があります。
無年金の方が生活保護を受ける場合、年金収入がない分、生活保護費が満額支給されることになります。ただし、国民年金の受給資格を満たせる可能性がある場合は、まず年金の申請を行うよう指導されることもあります。
例えば、過去に厚生年金に加入していた期間があり、合算すると10年以上になる場合や、免除期間を含めると受給資格を満たせる場合などです。このような場合は、年金事務所で相談し、受給の可能性を確認することが求められます。
介護が必要な親の生活保護と年金

親が介護を必要としており、年金だけでは生活も介護費用も賄えないという場合、生活保護の介護扶助を受けることができます。
介護扶助では、介護保険サービスの自己負担分が支給されます。通常、介護保険サービスを利用すると1割から3割の自己負担が発生しますが、生活保護を受けていると、この自己負担がなくなるのです。
デイサービス、訪問介護、ショートステイなど、必要な介護サービスを自己負担なしで利用できるため、家族の介護負担も大きく軽減されます。
ただし、介護扶助を受けるには、まず介護保険の認定を受ける必要があります。要介護認定を受けていない場合は、まず認定の申請を行い、その上で生活保護の申請をすることになります。
生活保護と年金の関係と受給手続き:まとめ
生活保護を受けても年金は止まりません。年金を受給しながら生活保護を受けることは可能です。ただし、年金は収入として認定されるため、その金額だけ生活保護費が減額される仕組みになっています。
生活保護を受けるには、年金を含めたすべての収入が最低生活費を下回っていること、換金できる資産を持っていないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。親族への扶養照会も行われますが、援助できないと回答すれば問題ありません。
生活保護を受けると、医療費が原則無料になる、国民年金保険料が免除されるなど、様々なメリットがあります。介護が必要な方は、介護扶助により介護サービスの自己負担もなくなります。
ただし、年金収入は必ず申告する義務があり、怠ると不正受給とみなされる可能性があります。また、生活保護を受けている間は、預貯金や資産の保有にも制限があることを理解しておく必要があります。
年金だけでは生活できない方にとって、生活保護は安心して暮らすための重要な制度です。正しい知識を持って、適切に制度を活用していきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。