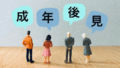「成年後見人の費用が高くて払えない」「申立て費用だけでも十数万円かかると聞いて諦めかけている」「月々の報酬を払い続けられるか不安」
成年後見制度を利用したいけれど、費用面での不安から諦めてしまう方は少なくありません。確かに、申立て費用や継続的な報酬負担は決して安い金額ではなく、年金生活の高齢者世帯には大きな負担となります。
しかし、成年後見人費用が払えない場合でも、様々な支援制度や対処法があります。この記事では、法テラスの立替制度から自治体の助成制度、家庭裁判所への減額申請まで、費用負担を軽減する具体的な方法を詳しく解説します。経済的な理由で制度利用を諦める前に、ぜひ参考にしてください。
成年後見人費用が払えない場合の基本的な対処法
成年後見人の費用負担に困った場合、まずは基本的な対処法を理解することが重要です。費用負担の責任者や支払い方法を工夫することで、多くの場合は解決策を見つけることができます。
家族・親族による費用立替えと費用負担命令

成年後見人の費用は原則として被後見人(本人)が負担しますが、本人に十分な資産がない場合や資産が凍結されている場合は、家族や親族が立替えることができます。
特に多いのは、認知症により本人の預金口座が凍結されてしまい、申立て費用を支払えないケースです。この場合、家族が一時的に費用を立替え、成年後見制度開始後に本人の財産から返済を受けることが可能です。
家庭裁判所に「費用負担命令」を申し立てることで、家族や親族に費用負担を命じることも可能です。これにより、複数の家族がいる場合でも、公平な費用分担を図ることができます。
ただし、弁護士や司法書士への報酬については、被後見人の負担となるのが原則です。申立て手続きを専門家に依頼する場合は、費用負担について事前に確認しておくことが重要です。
法テラスによる立替制度の活用方法

法テラス(日本司法支援センター)の立替制度は、収入や資産が一定以下の方が利用できる非常に有効な支援制度です。
法テラスの立替制度では、相談料が無料となり、着手金や実費を含めて約10万円程度で申立て手続きを依頼できます。通常、弁護士や司法書士に直接依頼すると15万円〜30万円程度かかることを考えると、大幅な費用削減が可能です。
立替えられた費用は、月々5,000円〜1万円程度の分割払いで返済できます。無理のない金額での返済計画を立てられるため、一時的に多額の費用を用意できない方でも制度を利用できます。
生活保護を受給している方の場合は、立替金の償還免除申請も可能です。審査により免除が認められれば、実質的に無料で申立て手続きを行うことができます。
生活保護受給による費用免除・軽減

生活保護を受給することで、成年後見人の費用負担を大幅に軽減できる場合があります。
生活保護受給者の場合、法テラスの立替金償還免除が受けやすくなり、申立て費用が実質的に無料になる可能性があります。また、多くの自治体では生活保護受給者を対象とした成年後見人報酬の助成制度を設けています。
成年後見制度開始後の継続的な報酬についても、自治体の助成制度により月額1万8千円〜2万8千円程度の補助を受けることができます。この金額は一般的な後見人報酬の大部分をカバーするため、実質的な費用負担を大幅に軽減できます。
生活保護の申請を検討している場合は、成年後見制度の利用と合わせて福祉事務所に相談することをおすすめします。両制度を組み合わせることで、より効果的な支援を受けることが可能です。
自治体の成年後見制度利用支援事業(助成制度)
全国の多くの自治体で、経済的理由により成年後見制度の利用が困難な方を支援するための助成制度が設けられています。これらの制度を活用することで、費用負担を大幅に軽減することが可能です。
助成制度の対象条件と申請方法

自治体の助成制度の対象となるのは、主に以下の条件を満たす方です:
生活保護を受給している方や、市区町村民税が非課税の世帯が最も一般的な対象条件です。また、預貯金やその他の資産が一定額以下の方も対象となることが多く、多くの自治体では60万円以下を基準としています。
申請方法は自治体により異なりますが、一般的には福祉課や高齢者支援課の窓口で申請書を提出します。申請には本人の収入証明書、資産状況を示す書類、成年後見制度の利用に関する書類などが必要となります。
重要なのは、制度利用開始前に申請することが原則であることです。ただし、自治体によっては一定期間遡って申請を受け付けている場合もあるため、詳細は各自治体に確認することが必要です。
各自治体の具体的な助成内容と限度額

自治体の助成制度の内容は地域により異なりますが、代表的な例をご紹介します。
世田谷区では、月額上限2万8千円まで後見人報酬を助成しています。京都市では在宅の場合月額1万8千円、施設入所中の場合月額1万円を上限としています。府中市では月額2万3千円を上限とし、立川市では月額1万8千円を基本としています。
申立て費用についても助成している自治体があります。実費相当額(収入印紙代、郵便切手代、鑑定費用など)を全額助成する自治体が多く、弁護士や司法書士への報酬についても一部助成する場合があります。
助成期間についても自治体により異なり、多くは年度単位での更新制となっています。毎年申請が必要ですが、条件を満たしている限り継続して助成を受けることができます。
主要自治体の助成上限額例
・世田谷区:月額2万8千円
・京都市:在宅1万8千円、施設1万円
・府中市:月額2万3千円
・立川市:月額1万8千円
・横浜市:月額2万8千円
助成制度利用時の注意点と制限事項

助成制度を利用する際は、いくつかの注意点があります。
親族が後見人になった場合は、助成対象外となる自治体が多いことです。助成制度は主に専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士など)への報酬を対象としており、親族後見人が無報酬の場合は助成の必要がないと判断されるためです。
任意後見制度を利用している場合も、助成対象外となることがあります。また、他の公的助成を受けている場合は、重複しての支給を受けられない場合があります。
助成を受けている間は、定期的な現況報告が必要です。収入状況や資産状況に変化があった場合は、速やかに自治体に報告する義務があります。条件を満たさなくなった場合は、助成が停止される可能性があります。
申立て費用と報酬それぞれが払えない場合の対策
成年後見制度の費用は、申立て時にかかる初期費用と、制度開始後の継続的な報酬に分けられます。それぞれの費用が払えない場合の具体的な対策を詳しく解説します。
申立て費用が払えない場合の具体的解決策

申立て費用は一時的に必要な費用のため、工夫次第で負担を軽減することができます。
最も基本的な方法は、家族や親族による立替えです。申立て費用は通常10万円〜20万円程度なので、複数の家族で分担すれば個人の負担を軽減できます。立替えた費用は、制度開始後に本人の財産から返済を受けることが可能です。
法テラスの立替制度を利用すれば、相談料無料で着手金・実費込みで約10万円程度に費用を抑えることができます。この費用も月々5,000円〜1万円の分割払いが可能なため、一度に多額の費用を用意する必要がありません。
自治体の助成制度では、申立て費用についても補助を受けられる場合があります。収入印紙代、郵便切手代、鑑定費用などの実費は全額助成、弁護士・司法書士費用についても一部助成を受けられることがあります。
申立ての準備を自分で行い、専門家への依頼を最小限に抑えることで費用を削減することも可能です。書類作成のみを依頼し、手続きの一部は自分で行うことで、費用を半分程度に抑えることができる場合があります。
継続的な報酬が払えない場合の対処法

成年後見制度開始後の継続的な報酬については、より長期的な対策が必要です。
最も効果的なのは、自治体の報酬助成制度を利用することです。条件を満たせば月額1万8千円〜2万8千円程度の助成を受けることができ、一般的な後見人報酬(月額2万円〜6万円)の大部分をカバーできます。
家族や親族が後見人に選任されれば、報酬が発生しない場合があります。ただし、近年は専門職後見人が選任される傾向が強く、家族の希望通りに選任されない可能性があることも考慮する必要があります。
複数の家族で報酬を分担することも可能です。家庭裁判所に費用負担命令を申し立てることで、法的に家族間での費用分担を決めることができます。これにより、一人の家族に過度な負担をかけることを避けることができます。
本人の財産状況に応じて、報酬の支払い方法を工夫することも可能です。不動産などの資産がある場合は、必要に応じて処分して報酬に充てることや、預貯金が不足している場合は年金収入から分割払いすることも検討できます。
家庭裁判所への支払い猶予・減額申請

やむを得ない事情により費用を支払えない場合は、家庭裁判所に対して支払い猶予や減額の申請を行うことができます。
支払い猶予申請では、一時的な収入減少や医療費の増大など、特別な事情がある場合に報酬の支払いを一定期間猶予してもらうことができます。猶予期間は通常3ヶ月〜1年程度で、状況が改善した後に支払いを再開します。
減額申請では、本人の資産状況や収入に応じて、報酬額の減額を求めることができます。特に本人の収入が年金のみで、報酬支払いにより生活に支障をきたす場合などは、減額が認められる可能性があります。
申請には、収入証明書、医療費の領収書、預貯金通帳の写しなど、経済状況を示す詳細な資料の提出が必要です。家庭裁判所は提出された資料を基に、支払い能力を総合的に判断します。
重要なのは、支払いが困難になった時点で速やかに相談することです。滞納が続いてから申請するよりも、早期に相談することで適切な対応策を見つけることができます。

成年後見人の費用が払えなくても、諦める必要はありません。様々な支援制度がありますから、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。きっと解決策が見つかりますよ。
成年後見人費用を抑える予防策と代替手段
成年後見人の費用負担を根本的に解決するには、制度利用前の準備や代替手段の検討が重要です。適切な選択をすることで、費用負担を大幅に軽減したり、回避したりすることが可能です。
親族後見人選任による費用削減の可能性

親族が後見人に選任されれば、報酬を受け取らないことにより費用負担を回避することができます。
親族後見人の場合、家庭裁判所が報酬を付与しないことが多く、仮に報酬が付与されても親族が受け取りを辞退することが可能です。これにより、専門職後見人に支払う月額数万円の報酬を節約できます。
親族後見人が選任されやすくする方法として、申立て前の準備が重要です。候補者となる親族が後見業務について十分に理解していることや、適切な財産管理能力があることを申立書で具体的に示す必要があります。
また、親族間での合意形成も重要です。後見人候補者以外の家族が反対していると、家庭裁判所は「親族間に対立がある」と判断し、第三者の専門職を選任する傾向があります。事前に家族全員で話し合い、合意を形成しておくことが重要です。
ただし、近年は専門職後見人が選任される割合が約7割以上となっており、親族後見人の選任は必ずしも保証されません。家庭裁判所は「客観性」や「専門性」を重視する傾向が強くなっています。
家族信託など代替制度による費用回避

成年後見制度以外の代替制度を活用することで、根本的に費用負担を回避することが可能です。
家族信託は最も有効な代替手段の一つです。本人が判断能力のあるうちに、信頼できる家族に財産管理を託すことで、成年後見制度を利用せずに財産管理ができます。初期設定費用(通常30万円〜100万円)は必要ですが、継続的な費用負担はありません。
任意後見制度では、本人が将来の後見人を自分で選び、報酬額も事前に決めることができます。法定後見のように家庭裁判所が決定するのではなく、本人の意思に基づいた契約のため、費用面でも柔軟な対応が可能です。
財産管理委任契約や見守り契約などの民事契約を組み合わせることで、より低コストで本人の生活を支援することも可能です。これらの契約は必要に応じて内容を変更したり、終了したりできるため、状況に応じた柔軟な対応ができます。
重要なのは、本人の判断能力があるうちに検討・準備することです。認知症が進行してからでは選択肢が限られてしまうため、早期の相談と計画が重要です。
専門家相談による最適な制度選択

費用負担を最小限に抑えるためには、専門家のアドバイスを受けながら最適な制度を選択することが重要です。
複数の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士、ファイナンシャルプランナーなど)から意見を聞くことで、各家庭の状況に最適な選択肢を見つけることができます。費用面だけでなく、本人の状況や家族の希望も総合的に考慮したアドバイスを受けることが重要です。
地域の成年後見センターや社会福祉協議会でも相談を受け付けています。制度の基本的な説明から、自治体の助成制度の詳細まで、幅広い情報を無料で得ることができます。
費用負担の不安から制度利用を諦める前に、まずは専門家に相談することをおすすめします。初回20分の無料相談で現在の状況を整理し、利用可能な支援制度や代替手段を確認することができます。
一人で悩まず、専門家のサポートを受けながら、経済的に無理のない範囲で最適な制度を選択していきましょう。
まとめ
成年後見人費用が払えない場合でも、様々な支援制度や対処法があります。法テラスの立替制度では月々5,000円からの分割払いが可能で、自治体の助成制度により月額最大2万8千円程度の報酬補助を受けることができます。
生活保護受給者の場合は立替金の償還免除申請も可能で、実質的に無料で制度を利用できる場合があります。また、家族による費用立替えや家庭裁判所への支払い猶予・減額申請なども有効な対処法です。
根本的な解決策として、親族後見人の選任による費用削減や、家族信託などの代替制度による費用回避も検討すべき選択肢です。
費用面での不安は、適切な情報と支援があれば解決できることが多いです。一人で抱え込まず、利用可能な制度を積極的に活用して、安心できる財産管理と生活支援を実現していきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。