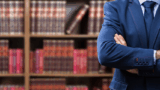「一人っ子だから親の介護費用が全部自分にかかってくる」
「月10万円を超えて、自分の生活が破綻しそう」
「兄弟がいれば費用を分担できるのに…誰にも頼れない」
一人っ子として親の介護を担っている方から、このような深刻な経済的悩みをよく聞きます。兄弟姉妹がいれば「今月は兄が、来月は私が」といった形で費用分担ができますが、一人っ子の場合はすべての経済的負担が一人にかかってしまいます。
親の介護には平均して月8.3万円、総額約580万円がかかると言われていますが、適切な制度を活用し、親の資産を優先的に使うことで、一人っ子でも経済的負担を大幅に軽減できます。住民税非課税世帯なら月1.5万円に抑えることも可能です。この記事では、一人っ子で親の介護にお金がない状況を乗り越えるための具体的な解決策をお伝えします。
一人っ子が親の介護でお金がない3つの理由
まず、なぜ一人っ子の介護者が経済的困窮に陥りやすいのか、その構造的な問題を理解することが重要です。
すべての介護費用を一人で負担する経済的重圧

一人っ子が親の介護でお金に困る最大の理由は、介護に関するすべての費用を一人で負担しなければならないことです。兄弟姉妹がいれば費用分担ができますが、一人っ子の場合はそれができません。
特に親の年金が少ない場合や、貯蓄が底をついた場合は、介護費用のほとんどを子どもが負担することになります。要介護認定を受けてから平均で4年11か月の介護期間があると言われており、その間ずっと高額な費用を一人で支払い続けるのは、一般的な収入では非常に厳しいものです。
この状況は、介護者自身の老後資金や生活費を圧迫し、将来への不安を増大させます。「親の介護で自分の人生が破綻する」という恐怖は、一人っ子介護者に特有の深刻な問題なのです。
介護離職による収入減少と生活費圧迫の悪循環

一人っ子で親の介護にお金がない状況をさらに深刻化させるのが、介護離職による収入減少です。親の要介護度が上がると、仕事と介護の両立が困難になります。特に一人っ子の場合、介護を代わってくれる家族がいないため、重要な介護場面では必ず自分が対応しなければなりません。
一人っ子の介護離職パターン
・正社員からパートタイムへの転換
・時短勤務への変更で収入30%減
・完全な離職で収入ゼロ
・転職による収入減と不安定化
・フリーランス転換で社会保障喪失
厚生労働省の調査によると、介護を理由とした離職・転職者は年間約10万人に上り、その多くが経済的困窮に陥っています。一人っ子の場合、介護離職による収入減少は介護費用の負担をさらに重くします。収入が減っているのに支出は増える。この悪循環により、貯蓄を切り崩しながら介護を続けることになり、最終的には「お金がない」状況に追い込まれてしまうのです。
【体験談】一人っ子で親の介護費用に追われた40代女性

神奈川県在住のDさん(45歳女性・パート職員)は、一人っ子として80代の母親を介護しています。父親は3年前に他界し、母親は認知症を発症。当初は「自分がやらなければ」と正社員の仕事を続けながら介護をしていましたが、次第に経済的に追い詰められていきました。

母の年金は月6万円だけ。デイサービスや訪問介護を使うと月10万円以上かかって、毎月4万円以上を自分が負担していました。一人っ子だから相談する兄弟もいない。このままでは自分の老後資金がなくなってしまう…
限界を感じたDさんは、地域包括支援センターに相談。高額介護サービス費制度や、親の預貯金を優先的に使うこと、費用を抑えられる大規模デイサービスの活用などをアドバイスされました。「一人っ子でも、全部自分で抱え込まなくていいんだと気づきました。今は月の負担が2万円以下に抑えられています」
親の資産を最優先活用|一人っ子でも負担を減らせる
一人っ子で親の介護にお金がない状況を改善するために、まず理解しておくべきは「親の資産活用の原則」です。
「親の介護費用=子が払う」は間違い

多くの人が誤解していますが、「親の介護費用は子どもが負担するもの」という考え方は正しくありません。実際には、介護費用は「まず親本人の資産・年金から充当する」のが基本原則です。
親に年金収入や預貯金がある場合は、それらを優先的に介護費用に充てるべきなのです。「親の貯金を使うのは申し訳ない」と感じる方もいますが、親が長年積み立てた資産は、まさに老後の生活や介護のためのものです。
民法では確かに親族間の扶養義務が定められていますが、これは「自分の生活に余裕がある範囲で」の義務です。つまり、子ども自身の生活が困窮するほどの負担義務は法的にも課されていません。「親の介護のために子どもが破産する」ような状況は、法律が想定するものではないのです。
親の年金・貯蓄・不動産の活用順位

一人っ子で親の介護にお金がない場合、親の資産をどのように活用するかが重要です。以下の順序で検討しましょう。
親の資産活用の具体的手順
ステップ1:年金収入の把握
国民年金、厚生年金、企業年金、個人年金などの月額総額を確認。これを介護費用の基礎とする。
ステップ2:預貯金の確認
親の預貯金残高を把握し、年金で不足する介護費用を補填。将来の相続を考慮しつつ、現在の介護に必要な範囲で活用。
ステップ3:不動産資産の活用
自宅がある場合、リバースモーゲージ(自宅を担保にした融資)、リースバック(売却後も住み続ける)、売却などを検討。
リバースモーゲージでは、自宅を担保にして金融機関から融資を受け、親が亡くなった後に自宅を売却して返済します。親は住み慣れた家で生活を続けながら、まとまった資金を介護費用に充てることができます。一人っ子の場合、将来の相続財産が減ることになりますが、現在の介護費用負担を大幅に軽減できるメリットがあります。
扶養義務の正しい範囲と法的根拠

一人っ子だからといって、無限に親の介護費用を負担する義務があるわけではありません。民法第877条で定められた扶養義務は、「自分の生活に余裕がある範囲で」という前提があります。
つまり、一人っ子で親の介護にお金がない状況で、自分の生活が破綻するほどの負担をする法的義務はないのです。親自身の資産を活用し、公的制度を最大限に利用した上で、それでも不足する場合にのみ、自分の生活に余裕がある範囲で援助すればよいのです。
一人っ子が使うべき公的制度で月1.5万円に抑える方法
適切な公的制度を活用することで、一人っ子でも介護費用の負担を大幅に軽減できます。
高額介護サービス費で月15,000円上限(住民税非課税)

一人っ子で親の介護にお金がない状況を改善する最も効果的な制度が「高額介護サービス費制度」です。この制度では、1か月の介護保険サービス自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻されます。
高額介護サービス費の負担上限額
・住民税非課税世帯:月15,000円(最も安い)
・住民税課税世帯(課税所得145万円未満):月37,200円
・住民税課税世帯(課税所得145万円以上690万円未満):月44,400円
・住民税課税世帯(課税所得690万円以上):月93,000円
例えば、一人っ子で親が住民税非課税世帯の場合、どれだけ介護サービスを使っても月の自己負担は最大15,000円で済みます。デイサービスを週5回、訪問介護を週3回利用しても、月15,000円を超えた分は払い戻されるのです。
生活福祉資金貸付580万円(年1.5%・無利子)

介護保険だけでは賄えない費用については、「生活福祉資金貸付制度」の活用を検討しましょう。この制度は、都道府県社会福祉協議会が実施する公的な貸付制度で、一人っ子で親の介護にお金がない方にとって非常に有効です。
一人っ子の場合、連帯保証人を立てるのが難しいケースもありますが、保証人なしでも年1.5%という低金利で借りられます。銀行のカードローン(年10~15%)と比べて圧倒的に有利な条件です。申請は各市区町村の社会福祉協議会で受け付けており、民生委員の面接や審査を経て貸付が決定されます。
医療費控除で介護費用も対象に

一人っ子で親の介護にお金がない場合、医療費控除も忘れずに活用しましょう。年間10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた医療費は所得控除の対象となり、所得税・住民税の軽減につながります。
医療費控除対象となる介護サービス
・訪問看護、訪問リハビリテーション:全額対象
・訪問介護(医療系サービスと併用の場合):全額対象
・デイサービス、ショートステイ:食費・居住費を除く部分
・特養・老健の利用料:食費・居住費を除く部分
・おむつ代(医師の証明書があれば対象)
一人っ子の場合、親を扶養に入れていれば、親の医療費・介護費を自分の医療費控除に合算できます。確定申告の際に、領収書をまとめて申請することで、数万円の税金が還付される可能性があります。
【一人っ子で親の介護お金がないあなたへ】
一人っ子が費用を抑える実践的な工夫
制度活用だけでなく、日常的な工夫により、一人っ子でもさらなる費用削減が可能です。
ケアマネに「予算月3万円以内」と明確に伝える

一人っ子で親の介護にお金がない場合、ケアマネジャーには経済状況を包み隠さず相談しましょう。「月の介護費用は3万円以内に抑えたい」「介護保険の限度額を超える部分は利用できない」といった具体的な制約を伝えることで、予算内で最大限の効果を得られるプランを提案してもらえます。
ケアマネジャーは地域の介護事業所の料金や特徴を熟知しているため、同じサービスでもより安価な事業所を紹介してもらえることもあります。また、介護保険外の安価なサービス(シルバー人材センター、ボランティア団体など)の情報も教えてもらえる場合があります。
大規模デイサービスで料金を抑える選び方

経済的負担を抑えるためには、同じサービスでもより低料金で利用できる事業所を選ぶことが重要です。一人っ子の場合、誰にも相談できずに最初に見つけた事業所を使い続けてしまいがちですが、事業所によって料金が異なることを知っておきましょう。
費用を抑えるデイサービスの選び方
・大規模型(利用定員26人以上)は小規模型より安い
・送迎範囲が広い事業所は送迎費が安い
・食事代や教材費などの実費部分を比較
・レクリエーション充実度と料金のバランス
・同一地域内で複数の事業所を比較検討
ショートステイも同様に、併設型(特養等に併設)は単独型より料金が安く、多床室(相部屋)は個室より大幅に安くなります。一人っ子で費用を抑えたい場合は、プライバシーよりも経済性を優先することも選択肢の一つです。
特養・老健・軽費老人ホームの低料金施設活用

一人っ子で親の介護にお金がない場合、施設入所を検討する際は低料金の公的施設を優先的に検討しましょう。
特に、低所得の場合は「特定入所者介護サービス費(補足給付)」により食費・居住費が軽減される場合があります。一人っ子で経済的に厳しい場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、この制度の対象になるか確認しましょう。
一人っ子の介護お金がない時の相談先
一人っ子で親の介護にお金がない時こそ、一人で抱え込まず専門家に相談することが重要です。
地域包括支援センター・福祉課への具体的相談法

ケアマネジャーだけでは解決できない経済的問題については、地域包括支援センターや市区町村の福祉課への相談が効果的です。
相談時に準備すべき情報
・親の要介護度と現在利用中のサービス
・月々の介護費用の内訳
・親の年金・預貯金額
・自分の収入と家計状況
・一人っ子で費用分担できないこと
・困っている具体的な内容
多くの自治体では、独自の介護者支援制度を設けています。介護用品の支給、介護者のリフレッシュ事業、交通費助成、税の減免など、様々な支援が受けられる可能性があります。窓口の担当者が制度に詳しくない場合もあるため、「一人っ子で経済的に厳しい。他にも何か制度はありませんか」と念押しして確認することも大切です。
生活保護申請の流れと一人っ子のケース

どうしても親の介護費用が賄えない場合は、生活保護制度の活用も検討する必要があります。一人っ子の場合、「親を生活保護にするのは恥ずかしい」と感じるかもしれませんが、生活保護は国民の権利であり、要件を満たしていれば誰でも申請できます。
生活保護制度では、介護費用も生活保護費の一部として支給されます。要介護者本人が生活保護を受給する場合、介護保険サービスの自己負担分は生活保護から支払われ、実質的に無料でサービスを利用できるようになります。
一人っ子の場合、扶養義務者への調査が行われますが、自分自身の生活が困窮している場合や、扶養できる経済的余裕がないことを説明すれば、扶養義務は免除されます。家庭裁判所が個別に判断するため、まずは福祉事務所に相談してみましょう。
一人で抱え込まない専門家サポート

一人っ子で親の介護にお金がない場合、経済的に非常に困窮している時は、以下の専門家への相談も有効です。
一人っ子が相談できる専門家
・社会福祉士:介護と経済の両面からアドバイス
・ファイナンシャルプランナー:家計の見直しと資金計画
・弁護士:法的な権利や制度の活用方法
・民生委員:地域の福祉制度の紹介
・社会福祉協議会:生活福祉資金貸付の相談

一人っ子だからといって、すべてを一人で抱え込む必要はありません。専門家の知識と経験を借りることで、思わぬ解決策が見つかることも多いのです。「恥ずかしい」と思わず、勇気を出して相談してみましょう。
まとめ:一人っ子でも全部抱えず乗り切れる

一人っ子で親の介護にお金がない状況は確かに厳しいものですが、適切な制度活用と工夫により乗り越えることが可能です。
まず理解すべきは、親の資産を優先的に活用することと、子どもの生活を破綻させるほどの負担義務は法的にも課されていないということです。その上で、高額介護サービス費制度(住民税非課税なら月1.5万円上限)、生活福祉資金貸付制度(580万円・年1.5%)、医療費控除などを組み合わせることで、経済的負担を大幅に軽減できます。
何より大切なのは、一人で抱え込まないことです。経済的な悩みは人に話しにくいものですが、専門家に相談することで具体的な解決策が見つかることが多いものです。「誰にも言えない」お金の不安も、適切なサポートを受けることで軽減することができます。
一人っ子だからといって、自分の人生を犠牲にする必要はありません。利用できる制度を最大限に活用し、専門家の力を借りながら、持続可能な介護のスタイルを見つけていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。