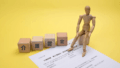今回お話を伺ったのは、埼玉県在住の鈴木健太さん(仮名・45歳)。母親の介護のために退職を決意しかけていた鈴木さんに、決断の前に何が起きたのか、そしてどう前に進んだのかを語っていただきました。※ご本人の同意を経て掲載しています。
「あのまま勢いで退職届を出していたら、今頃どうなっていたか分かりません。立ち止まって考える時間があって、本当に良かったです」
「もう限界だ。仕事を辞めるしかない」
鈴木さんは都内の中堅企業で営業職として15年間勤務していました。母親(78歳)は要介護3の認定を受け、実家で一人暮らしをしていました。
「デイサービスとヘルパーさんを使っていましたが、母から『健太に来てほしい』という電話が週に3〜4回は来るようになって。仕事を抜けて実家に行くことが増えました」
平日の昼間に母親から「具合が悪い」「不安で仕方ない」という電話が入ると、鈴木さんは営業の外回りを中断して実家に駆けつけることが増えました。
「急いで実家に行くと『やっぱり大丈夫』ということも多くて。でも母が不安がっている以上、無視するわけにはいきません。営業先との約束をキャンセルすることも何度かありました」
遅刻や早退が重なり、同僚からの視線も気になるようになりました。
「『また鈴木さん、早退?』という空気を感じるようになって。直接言われるわけじゃないけど、みんなが我慢して残業している中、自分だけ帰るのは辛かったです」
上司との面談でも、厳しい言葉をかけられました。
「『気持ちは分かるが、このままだと営業成績に影響が出る』と言われて。会社に介護休業制度はありましたが、無給だし期間も限られています。根本的な解決にはならないと思いました」
退職届を書き始めた夜
追い詰められた鈴木さんは、ある晩、退職を決意しました。
「『母のためなら退職も仕方ない』と思い始めていました。妻に相談すると『あなたが決めたことなら応援する』と言ってくれて。退職届を書き始めていたんです」
母一人、息子一人。父は5年前に他界しており、鈴木さんしか頼れる人がいませんでした。
「『僕が支えなければ誰が支えるんだ』という気持ちでした。『これは親孝行の最後のチャンスかもしれない』と思ったんです」
でも、提出する前にどうしても不安が消えませんでした。
「『本当にこれでいいのか?』って。退職金と貯金はあるけど、45歳で無職になって大丈夫なのか。母の介護費用はいくらかかるのか。再就職できるのか。考えれば考えるほど不安になりました」
でも、他に選択肢が思いつきませんでした。
「施設に入れるという選択肢もあったけど、『施設=母を見捨てる』というイメージがあって。絶対に嫌だと思っていました」

退職届を出す前に、偶然見つけたサイト
退職を決めた週末、鈴木さんは最後の確認のつもりでスマホで検索していました。
「『介護 仕事 辞める 判断』と検索したら、ココマモという介護家族向けのサイトが出てきて。『介護のために退職すべきか迷っている人へ』という記事を読みました」
その記事には、退職せずに両立している人の事例や、退職して後悔した人の体験談が載っていました。
「『退職は最後の手段』『まず判断基準を作ることが大事』と書いてあって。自分は感情だけで決めようとしていたんだと気づきました」
記事の最後に、『介護決断サポートキット』というものが紹介されていました。
「『施設か在宅か』『退職か継続か』を感情ではなく数値で判断できるワークブックがあると書いてあって。客観的に判断する方法があるなら、試してみる価値はあると思いました」
購入ボタンを押す時、少し迷いました。
「正直、今さら何かが変わるとは思っていませんでした。でも『退職届を出すのは、これを試してからでも遅くない』と思ったんです」
3日後、アンケートに答えた後にワークブックが届きました。
ワークシートで見えてきた「本当の問題」
キットを開くと、最初に「迷いタイプ診断」がありました。
「5つの質問に答えると、自分の迷いのタイプが分かる仕組みでした。『母の状態は?』『現在の介護体制は?』『経済的な余裕は?』といった質問に答えていきました」
診断結果は「介護体制の見直し不足タイプ」でした。
「『退職前に、まず現在の介護体制を見直すことで解決できる可能性があります』と書いてあって。退職以外の選択肢があるかもしれないと初めて思いました」
「経済的安定」が最優先だと気づいた
次に「優先順位マトリクス」というワークがありました。
「『母の安全』『自分の仕事』『経済的安定』『家族との時間』。それぞれに1〜10点で重要度をつけて、優先順位を決めるシートです」
書き込んでいくうちに、鈴木さんは重要なことに気づきました。
「母の安全:8点、自分の仕事:7点、経済的安定:10点、家族との時間:6点。僕が一番優先したいのは『経済的安定』だったんです」
それまで「母のため」と思っていた退職が、実は自分と家族を犠牲にする選択だと分かりました。
「母のそばにいたい気持ちより、家族を養う責任の方が重かった。でもそれを認めることが『親不孝』だと思って、目を背けていたんです」
数値で見た「施設という選択肢」
次に「施設 vs 在宅 決断シート」に取り組みました。
「母の状態を12項目で評価していくんです。『24時間見守りが必要か』『徘徊のリスクは』『夜間対応は可能か』『認知症の進行度は』。それぞれに点数をつけていきました」
すべて記入し終わると、在宅42点 vs 施設78点という結果になりました。
「数値で見ると、客観的な事実が見えてきました。母は要介護3だけど、徘徊や暴力的な行動はない。デイサービスでは楽しそうにしている。母には施設という選択肢もあるんだと」
それまで感情だけで「在宅しかない」と思い込んでいた鈴木さんにとって、大きな気づきでした。
「僕が仕事を辞めなくても、母を守る方法はあるんだと分かりました。いや、むしろ仕事を続けた方が、経済的に母を支えられるんだと」
「施設=見捨てる」という思い込みが消えた
でも、鈴木さんには大きな罪悪感がありました。
「『施設に入れるのは、母を見捨てることだ』とずっと思っていたんです。だから退職しか選択肢がないと思い込んでいました」
キットには「罪悪感チェックリスト」がありました。
「自分の罪悪感が『事実』なのか『思い込み』なのかを判定するシートです。『施設入所後、本人の表情が明るくなったケース78%』『家族との関係が改善したケース82%』といったデータが載っていました」
データを見て、鈴木さんの考え方が変わり始めました。
「施設=悪いこと、じゃないんだと初めて思えました。むしろ、プロのケアを受けることで、母も僕も幸せになれるかもしれないって」
「罪悪感を書き換えるワーク」も効果的でした。
「『施設=見捨てる』という考え方を、『施設=プロに任せて、自分は心のケアに集中』という考え方に書き換えるワークです。文字にして書き出すことで、考え方が変わっていくのを感じました」
妻との話し合いが、30分で決着した
キットには「家族会議シナリオテンプレート」もありました。
「穴埋め式で、家族に何を伝えればいいか整理できるんです。『現状』『問題点』『優先順位』『提案』という順番で話す台本が作れます」
それを使って、鈴木さんは妻ともう一度話し合いました。
今までは感情論で話していました。
「『母がかわいそう』『でも生活もある』『どうしよう』って堂々巡りだったんです。でもシナリオ通りに話したら、30分で結論が出ました」
鈴木さんは妻に、優先順位マトリクスの結果を見せました。
「『僕は経済的安定を最優先したい。だから仕事は続けたい。母の状態を数値で見ると、施設という選択肢もある。施設に入れることは見捨てることではない』と伝えました」
妻も納得してくれました。
「『それが現実的だと思う。あなたが無理して倒れたら、みんな困るから』と言ってくれて。感情ではなく、事実とデータで話すことで、建設的な話し合いができました」

退職せずに、新しい介護体制を作った
鈴木さんは退職届を破り捨て、別の選択をしました。
「まず、近隣の施設を3つ見学しました。キットの『施設見学チェックリスト』を持って行って、見るべきポイントを確認しながら回りました」
チェックリストには30項目の確認事項が載っていました。
「スタッフの対応、施設の清潔さ、医療体制、レクリエーション内容。感情ではなく事実ベースで判断できるようになっていました」
最終的に、母は有料老人ホームに入所することになりました。
「最初は『息子に見捨てられた』と泣かれました。本当に辛かったです。でも今は『ここの方が安心』『友達もできた』と言ってくれています」
週末は必ず面会に行きます。
「仕事で疲れていた時より、ずっと穏やかに母と接することができるようになりました。介護で倒れかけていた時は、正直イライラしていたので」
母との関係も良くなりました。
「週末に会うからこそ、話したいことがたくさんあるんです。毎日一緒にいた時より、会話が増えました」
毎朝届くメールが支えになった
キットを購入すると、半年間毎日メールが届きます。
「毎朝7時に届くメールを読むのが日課になりました。『あなたには、あなたの人生を守る権利がある』『休息は介護者の権利です』『施設入所は見捨てることではない』」
そういう言葉を毎日読むことで、罪悪感から解放されていきました。
「母を施設に入れたことへの罪悪感は、完全には消えませんでした。でも『これで良かったんだ』と思えるようになりました」
介護で退職を考えている方へ
現在、鈴木さんは正社員として働き続けています。
「退職していたら、今頃どうなっていたか分かりません。経済的にも精神的にも、追い詰められていたと思います」
鈴木さんと同じように退職を考えている方に伝えたいことがあります。
「感情で決めないでください。『母がかわいそう』『親孝行しなきゃ』という気持ちだけで退職すると、後で必ず後悔します」
「僕は偶然キットに出会えて、客観的に判断する方法を知ることができました。それがなければ、勢いで退職届を出していたと思います」
「退職は最後の手段です。その前に、本当に他に選択肢はないのか、冷静に考える時間を持ってください」
「施設に入れることは、見捨てることじゃありません。プロに任せることで、自分は心のケアに集中できる。そう考えられるようになると、選択肢が広がります」
まとめ。感情ではなく、判断基準で決める
鈴木さんの体験談は、介護の決断において「判断基準」を持つことの重要性を示しています。「親孝行」「かわいそう」という感情だけで退職を決めかけていた鈴木さんが、ワークシートを使って自分の本当の優先順位を知り、データで客観的に判断することで、退職せずに済みました。
介護離職は一度実行してしまうと元に戻すのが困難です。しかし、感情ではなく事実ベースで判断する方法を知っていれば、後悔しない選択ができます。
もし今、介護のための退職を考えている方がいらっしゃいましたら、鈴木さんのように一度立ち止まって、本当にそれしか選択肢がないのかを冷静に考えてみてください。きっと別の道が見えてくるはずです。