「親の介護が始まって、仕事との両立がもう限界」「このままでは親をしっかりと看てあげられない」「仕事を辞めるしかないのかな」
親の介護が必要になった時、多くの方がこのような悩みを抱えることになります。急な呼び出しで仕事を早退したり、夜中の介護で睡眠不足になったり、職場に迷惑をかけているのではないかという罪悪感を感じたり。そんな中で「いっそ仕事を辞めて介護に専念したほうがいいのでは」と考えるのは、とても自然な気持ちです。
実際に、親の介護を理由に仕事を辞める「介護離職」は年間約10万人にも上り、決して珍しいことではありません。しかし、介護離職には想像以上に大きなリスクが伴うことも事実です。この記事では、親の介護で仕事を辞めることを検討している方に向けて、介護離職の現実とリスク、そして仕事を辞めずに両立するための具体的な方法について詳しく解説します。
親の介護で仕事辞める理由と介護離職の現実
まずは、なぜ多くの人が介護離職を選択してしまうのか、その背景と現実を詳しく見ていきましょう。
仕事と介護の両立が困難になる具体的な状況

親の介護で仕事を辞めざるを得ないと感じる状況は、想像以上に多岐にわたります。介護離職の最も大きな理由として挙げられるのが「仕事と介護の両立が難しい職場環境」で、全体の約59%を占めています。
急な呼び出しと突発的な対応が最も多い困りごとです。親が転倒してけがをした、熱を出して病院に連れて行く必要がある、デイサービスを急に休むことになった。こうした予期せぬ事態は介護では日常茶飯事ですが、職場では「また早退か」「今度はいつ休むのか」という雰囲気になりがちです。
夜間の介護による睡眠不足も深刻な問題です。認知症の方の夜間徘徊、夜中のトイレ介助、不安になって何度も起こされるなど、十分な睡眠がとれない状況が続くと、日中の仕事に大きな支障をきたします。集中力の低下、ミスの増加、居眠りなどにより、職場での評価も下がってしまいます。
長期的な介護の見通しが立たない不安も大きな負担となります。「いつまで続くのかわからない」「もっと症状が悪化したらどうしよう」という不安を抱えながら働き続けることは、精神的に非常に辛いものです。
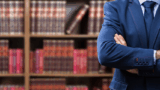
年間10万人が選ぶ介護離職の背景と心理

厚生労働省の調査によると、介護離職者は年間約10万人に上り、そのうち約8割が女性となっています。この数字の背景には、日本の介護環境と働き方の構造的な問題があります。
介護離職の構造的問題
家族介護への依存度の高さ
「家族が介護するのが当たり前」という文化的背景により、特に長男の嫁や長女に介護の責任が集中
職場制度活用の低さ
介護休業制度があっても利用率は非常に低く、「知らなかった」「利用しにくい雰囲気」が障壁に
介護者の心理的負担も深刻です。「親に恩返しをしたい」「最期まで自分が看てあげたい」という思いは美しいものですが、一方で「私が頑張らなければ」「他の人に任せるのは申し訳ない」という責任感が過度なプレッシャーとなることもあります。
男性の介護離職も増加傾向にあります。従来は女性が中心でしたが、最近では男性の介護離職も目立つようになりました。特に、一人息子の場合や、妻も働いているため男性が介護を担わざるを得ない場合などに、介護離職を選択するケースが増えています。
これらの状況を踏まえると、介護離職は個人の問題ではなく、社会全体で解決すべき構造的な課題であることがわかります。
「自分だけが介護できる」という思い込みの危険性

介護離職を選択する人の多くが抱いているのが「自分だけが親の介護ができる」という思い込みです。この考え方は一見美しく見えますが、実際には多くの問題を含んでいます。
介護の質の向上につながらない場合もあることも知っておくべきです。仕事を辞めて介護に専念したからといって、必ずしも介護の質が向上するわけではありません。むしろ、経済的な余裕がなくなることで十分な介護サービスを利用できなくなったり、介護者のストレスが高まることで親子関係が悪化したりするケースも多くあります。
長期的な視点の欠如も問題です。介護は長期間にわたって続くものですが、介護離職を選択する際には目の前の状況にだけ目が向きがちです。5年後、10年後の自分や家族の生活を考えたとき、介護離職が本当に最善の選択なのかを慎重に検討する必要があります。
「自分だけが」という思い込みから脱却し、周囲のサポートを積極的に活用することが、持続可能な介護には欠かせません。
親の介護で仕事辞めることのメリットとデメリット
介護離職を検討する前に、そのメリットとデメリットを客観的に理解することが重要です。感情的な判断ではなく、長期的な視点で検討しましょう。
介護離職で得られる精神的なメリットと安心感

親の介護で仕事を辞めることには、確かにメリットも存在します。特に精神的な面では、大きな安心感や満足感を得られることがあります。
時間的な余裕による質の高い介護が最大のメリットです。仕事をしていると、どうしても介護にかけられる時間が限られてしまいます。仕事を辞めることで、親の体調に合わせてゆっくりと食事介助をしたり、一緒に散歩をしたり、話し相手になったりする時間を十分に確保できます。
緊急時の対応力向上も大きなメリットです。親が体調を崩した時や、突然の事故があった時にも、仕事を気にすることなくすぐに対応できます。病院への付き添いや、ケアマネジャーとの面談なども、時間を気にせずに参加できるため、より良いケアプランを立てることができます。
罪悪感からの解放も重要なポイントです。「仕事のせいで親をちゃんと看てあげられない」「職場に迷惑をかけている」といった罪悪感から解放され、精神的な負担が軽減されます。「親孝行ができている」という満足感や達成感を得ることもできます。
親子関係の深化もメリットの一つです。忙しい仕事に追われている時には気づかなかった親の気持ちや、今まで聞けなかった人生の話などを聞く機会が増えます。残された時間を大切に過ごすことで、後悔のない介護ができると感じる方も多いです。

収入減少と再就職困難という深刻なリスク

しかし、介護離職には想像以上に深刻なリスクが伴います。特に経済面でのダメージは、想像を超える場合が多いのが現実です。
収入の完全停止による生活困窮が最も深刻な問題です。正社員として働いていた場合、月収30万円の人が介護離職すると年間360万円の収入を失うことになります。貯蓄があったとしても、介護費用や生活費で急速に減っていき、数年で底をついてしまうケースも珍しくありません。
具体的な経済的損失例
月収30万円の場合の年間損失
・給与収入:360万円
・厚生年金保険料(会社負担分):約32万円
・健康保険料(会社負担分):約18万円
・退職金積立相当額:約24万円
年間総損失額:約434万円
介護費用の増大も見落とされがちなリスクです。在宅介護でも月に数万円から十数万円の費用がかかり、施設利用や医療費を含めると月20〜30万円になることも珍しくありません。収入がない状態でこれらの費用を支払い続けることは、経済的に非常に厳しいものです。
再就職の困難さは、多くの人が想像している以上に深刻です。介護離職した人の正社員としての再就職率は約50%程度で、元の収入水準まで回復できる人はさらに少なくなります。介護期間が長くなるほど、就職活動は困難になり、年齢的なハンディキャップも加わってきます。
介護離職を後悔する人が多い理由

統計によると、介護離職を経験した人の多くが「後悔している」と回答しています。その理由を詳しく見てみましょう。
経済的困窮による生活の質の低下が最も多い後悔の理由です。「親のために良かれと思って仕事を辞めたのに、お金がなくて必要な介護サービスを利用できない」「自分たちの生活もままならない」といった状況に陥ってしまうケースが多くあります。
介護の長期化による疲弊も深刻な問題です。介護離職する時には「数年で終わるだろう」と考えていても、実際には10年以上続くことも珍しくありません。収入がない状態で長期間の介護を続けることは、精神的にも肉体的にも非常に厳しいものです。
「辞めなくても良い方法があったのでは」という後悔も多く聞かれます。介護離職後に制度やサービスについて詳しく知り、「もっと早く相談していれば」「制度を活用すれば両立できたのでは」と後悔する人も少なくありません。
親の介護で仕事辞める前に活用すべき支援制度
仕事を辞める前に、まず活用できる支援制度や働き方の選択肢を十分に検討することが重要です。多くの人がこれらの制度を知らずに介護離職を選んでしまっているのが現状です。
介護休業制度と介護休暇の具体的な活用方法

仕事を辞める前に、まず検討すべきなのが法律で定められた介護支援制度の活用です。多くの人がこれらの制度を知らずに介護離職を選んでしまっているのが現状です。
介護休業制度の詳細
休業期間:最大93日間(分割取得可能・最大3回まで)
給付金:雇用保険から通常賃金の67%支給
具体例:月給30万円の場合 → 約20万円/月の給付
活用方法:親の入院時、退院後の環境整備、介護体制構築など
介護休業制度は、要介護状態の家族を介護するために最大93日間の休業を取得できる制度です。この期間中は雇用保険から介護休業給付金として、通常の賃金の67%が支給されます。
介護休業は分割して取得することも可能で、同一の対象家族について最大3回まで分けて利用できます。例えば、親の入院時に1ヶ月、退院後の環境整備に1ヶ月、その後の介護体制構築に1ヶ月といった使い方ができます。
介護休暇制度の詳細
取得日数:年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)
取得方法:1日または時間単位で取得可能
活用場面:病院付き添い、ケアマネジャー面談、介護サービス手続きなど
給与:無給(会社によっては有給の場合あり)
時短勤務やテレワークなど働き方の調整選択肢

介護と仕事の両立のためには、働き方そのものを調整することも重要な選択肢です。多くの企業で様々な制度が整備されており、これらを組み合わせることで両立が可能になる場合があります。
短時間勤務制度では、通常の勤務時間を短縮することで介護の時間を確保できます。例えば、通常9時〜18時の勤務を10時〜16時に変更したり、週4日勤務にしたりすることで、親の通院付き添いや介護サービスの調整時間を作ることができます。
テレワーク(在宅勤務)制度は、介護との両立において非常に有効な選択肢です。通勤時間がなくなることで介護の時間を確保でき、親の様子を見ながら仕事をすることも可能です。週に数日だけテレワークを利用するという部分的な活用も効果的です。
これらの制度を活用する際は、人事部門や上司と十分に相談し、業務に支障をきたさないよう配慮することが重要です。また、同僚の理解と協力を得るために、状況を適切に説明し、感謝の気持ちを示すことも大切です。

地域包括支援センターと介護サービスの活用

仕事と介護の両立を実現するためには、外部の介護サービスを積極的に活用することが不可欠です。一人ですべてを抱え込もうとせず、専門家のサポートを受けることで負担を大幅に軽減できます。
地域包括支援センターは、介護に関する総合的な相談窓口として非常に重要な役割を果たしています。ケアマネジャーの紹介、介護サービスの情報提供、家族の相談対応など、幅広いサポートを無料で受けることができます。
働きながら活用できる主な介護サービス
デイサービス(通所介護)
日中の時間帯に親を預けることで安心して仕事に集中。送迎サービスも利用可能
ショートステイ(短期入所)
数日~数週間の短期間預かり。出張や繁忙期に活用
訪問介護(ホームヘルパー)
自宅での身体介護・生活援助。時間帯も相談可能
地域包括支援センターでは、働きながら介護をする人向けの相談も行っており、具体的な両立方法についてアドバイスを受けることができます。「平日は仕事があるので夜間や土日にサービスを利用したい」「短時間でも利用できるサービスはないか」といった相談にも応じてくれます。
福祉用具のレンタルサービスを活用すれば、介護の負担を軽減できます。電動ベッド、車椅子、歩行器などをレンタルすることで、介護者の身体的負担が減り、仕事への影響も少なくなります。
これらのサービスを効果的に組み合わせることで、介護離職をしなくても質の高い介護を提供することが可能です。重要なのは、早めに相談し、適切なサービスを選択することです。

介護離職を検討している方は、まず地域包括支援センターに相談してみてくださいね。あなたの状況に合った支援制度やサービスを提案してもらえますし、仕事と介護の両立方法についても具体的なアドバイスをもらえますよ。
まとめ

親の介護で仕事を辞めるかどうかは、人生を大きく左右する重要な決断です。介護に専念したいという気持ちは尊いものですが、介護離職には経済的困窮、再就職の困難、将来への不安など、深刻なリスクが伴うことも事実です。
大切なのは、感情的になって急いで決断するのではなく、まずは利用できる支援制度や介護サービスについて十分に情報収集することです。介護休業制度、時短勤務、テレワークなどの職場制度と、デイサービス、ショートステイ、訪問介護などの介護サービスを組み合わせることで、仕事を続けながら質の高い介護を提供することは十分可能です。
また、一人ですべてを抱え込もうとせず、家族間での役割分担を見直したり、地域包括支援センターなどの専門機関に相談したりすることも重要です。「自分だけが介護できる」という思い込みから脱却し、周囲のサポートを積極的に活用することが、持続可能な介護には欠かせません。
どうしても仕事と介護の両立が困難な場合でも、介護離職が唯一の選択肢ではないかもしれません。転職、パートタイムへの変更、フリーランスとしての働き方など、様々な選択肢を検討することができます。
最終的にどのような選択をするにしても、それが長期的に見て本人と家族にとって最善の道となるよう、十分な検討と準備を重ねることが大切です。一人で悩まず、専門家に相談しながら、納得のいく決断を下していただければと思います。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。



