「親の介護が必要になったけれど、正直なところお金に余裕がない」「毎月の介護費用が重荷になって、自分の生活も圧迫されている」「介護保険だけでは賄えない費用をどうやって工面すればいいのか」
親の介護でお金がない状況は、多くの家族が直面する深刻な問題です。厚生労働省の調査によると、介護費用の平均は月額約8.3万円、総額では500万円を超えることも珍しくありません。しかし、この経済的負担をすべて家族だけで背負う必要はありません。
実は、日本には経済的に困窮した介護者を支援するための充実した制度が数多く存在しています。適切な制度を活用し、効率的なサービス利用を心がけることで、介護費用の負担を大幅に軽減することが可能です。この記事では、親の介護でお金がない状況を克服するための具体的な解決策と、知っておくべき支援制度について詳しく解説します。
親の介護でお金がない状況に陥る原因と背景
なぜ多くの家族が親の介護費用に悩まされるのか。その根本的な原因を理解することが、解決策を見つける第一歩となります。
介護費用の実態と家計への深刻な影響

親の介護でお金がない状況の背景には、介護費用の予想以上の高額さがあります。多くの人が「介護保険があるから大丈夫」と思いがちですが、実際の負担は想像を大きく超えるものです。
介護保険サービスの自己負担分だけでも、要介護度に応じて月1万円から3万円程度かかります。さらに、保険対象外の費用が積み重なります。
要介護度が高くなると、これらの費用はさらに膨らみます。要介護4・5の場合、月額15万円を超えることも珍しくありません。年金だけでは到底賄えない金額となり、子世代への経済的負担が重くのしかかってきます。
また、介護は長期化する傾向にあります。平均的な介護期間は約5年間ですが、10年以上続く場合も決して珍しくありません。この長期間にわたって高額な費用を支払い続けることが、多くの家庭の家計を圧迫しているのです。

介護離職による収入減少と経済的悪循環

親の介護でお金がない状況をより深刻にしているのが、介護離職による収入減少です。介護と仕事の両立が困難になり、やむを得ず仕事を辞める人は年間約10万人にも上ります。
介護離職は段階的に進行することが多く、最初は有給休暇や欠勤で対応しますが、やがて時短勤務、パート勤務、そして最終的には完全離職という流れをたどります。収入が減少する一方で、介護費用は増加するという経済的悪循環に陥ってしまうのです。
介護離職による経済的影響
・正社員からパート転換:年収300万円→100万円
・完全離職の場合:年収500万円→0円
・退職金の早期使用による老後資金の枯渇
・社会復帰時の就職困難と収入低下
・失業給付終了後の生活困窮
特に深刻なのは、女性の介護離職です。厚生労働省の統計によると、介護離職者の約8割が女性で、多くが40~50代の働き盛りです。この年代での離職は、キャリアの断絶だけでなく、将来の年金額にも大きな影響を与えます。
さらに問題なのは、介護終了後の社会復帰の困難さです。介護期間中のブランクにより、以前と同水準の仕事に就くことが難しくなり、生涯年収の大幅な減少につながります。これが「介護貧困」と呼ばれる深刻な社会問題の背景にあるのです。

扶養義務の誤解と親の資産活用の重要性

親の介護でお金がない状況を悪化させる要因の一つに、扶養義務に対する誤解があります。多くの人が「親の介護費用はすべて子どもが負担しなければならない」と思い込んでいますが、これは正しくありません。
実際の費用負担の優先順位は以下の通りです:
1. 親本人の年金・預貯金
2. 親の不動産等資産の活用
3. 配偶者(いる場合)の資産
4. 子ども世代の経済的余裕範囲内での支援
多くの高齢者は、子どもに迷惑をかけたくないという思いから、自分の資産を使うことを躊躇します。しかし、親自身の資産を介護費用に充てることは当然の権利であり、決して「子どもに頼る」ことではありません。
重要なのは、親が元気なうちから資産状況を把握し、将来の介護費用について家族で話し合うことです。いざ介護が必要になってから慌てるのではなく、事前の準備と計画立てが経済的困窮を防ぐ鍵となります。
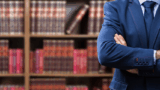
親の介護でお金がない時に活用すべき公的支援制度
経済的に困窮した状況でも、適切な公的制度を活用することで負担を大幅に軽減できます。ここでは、知っておくべき重要な支援制度について詳しく解説します。
高額介護サービス費制度と負担限度額認定の詳細解説

親の介護でお金がない時に、まず活用すべきなのが「高額介護サービス費制度」です。この制度により、どれだけ多くの介護サービスを利用しても、月の自己負担額には上限が設けられています。
負担上限額は所得水準により異なり、住民税非課税世帯なら月15,000円〜24,600円、一般世帯でも月44,400円が上限となります。超過分は申請により払い戻されるため、実質的に無制限に介護サービスを利用することが可能です。
高額介護サービス費の負担上限額(月額)
・生活保護受給者:15,000円
・住民税非課税世帯(年金収入等80万円以下):15,000円
・住民税非課税世帯(その他):24,600円
・住民税課税世帯(一般):44,400円
・現役並み所得者:93,000円
さらに重要なのが「負担限度額認定証」です。この認定を受けることで、介護施設やショートステイ利用時の居住費・食費が大幅に軽減されます。
認定条件は住民税非課税世帯であることと、預貯金等が単身1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)であることです。多くの方が対象となる可能性があるため、積極的に申請することをお勧めします。
「高額医療・高額介護合算療養費制度」も併せて活用しましょう。年間の医療費と介護費の合算額が基準を超えた場合、超過分が支給される制度です。持病のある親の介護では、この制度により年間数十万円の軽減を受けられることもあります。
生活保護制度と介護扶助による包括的サポート

親の介護でお金がない状況が深刻な場合、生活保護制度が最後のセーフティネットとなります。生活保護には「介護扶助」という項目があり、介護に関わるあらゆる費用について支援を受けることができます。
介護扶助では、介護保険サービスの自己負担分が全額支給されるだけでなく、介護保険の対象外サービスや福祉用具の購入費、住宅改修費なども支援の対象となります。
生活保護の申請に抵抗を感じる方も多いでしょうが、これは国民の正当な権利です。保護費は税金から支出されますが、これは社会保障制度の一環であり、困った時に利用するのは当然のことなのです。
申請の際は、収入・資産状況の調査、扶養義務者への照会などが行われますが、扶養義務者自身の生活に支障がある場合は扶養義務は免除されます。つまり、子ども世代が経済的に困窮していれば、親の扶養義務を果たせなくても問題ないのです。
自治体独自制度と生活福祉資金貸付の活用方法

親の介護でお金がない時に見落としがちなのが、各自治体が独自に実施している支援制度です。これらは地域によって大きく異なるため、お住まいの自治体で利用可能な制度を詳しく調べることが重要です。
多くの自治体で実施されているのが「介護用品支給事業」です。紙おむつ、尿とりパッド、清拭用品などが月数千円分支給され、年間では数万円の節約になります。要介護度や所得に応じた支給条件がありますが、多くの方が対象となる可能性があります。
自治体独自制度の例
・介護用品支給:月3,000円〜6,000円相当
・家族介護慰労金:年額50,000円〜100,000円
・福祉タクシー券:月2,000円〜4,000円分
・配食サービス助成:1食300円〜500円の自己負担
・緊急通報システム:月額300円〜500円で利用可能
生活福祉資金貸付制度も重要な選択肢です。この制度は社会福祉協議会が窓口となり、低所得世帯や高齢者世帯に対して低金利(年1.5%または無利子)で資金を貸し付ける制度です。
この貸付制度は、介護サービス利用費、福祉用具購入費、住宅改修費、施設入所の初期費用など、幅広い介護関連費用に利用できます。銀行などの民間金融機関と比べて格段に低い金利で利用できるため、一時的な資金不足の際には非常に有効です。
申請は各市区町村の社会福祉協議会で受け付けており、民生委員との面談を経て貸付が決定されます。審査には時間がかかる場合があるため、資金需要が見込まれる段階で早めに相談することをお勧めします。

お金がない状況での介護費用削減の実践的手法
公的制度の活用に加えて、日常的な工夫により介護費用をさらに削減することが可能です。効率的なサービス利用と費用対効果を重視した選択が重要になります。
費用対効果の高いサービス選択と事業所比較のコツ

親の介護でお金がない時には、同じサービスでもより費用対効果の高い事業所を選択することが重要です。介護サービスは事業所によって料金体系やサービス内容に差があるため、比較検討により大幅な費用削減が可能です。
デイサービスを例に取ると、大規模事業所(定員26人以上)は小規模事業所より基本料金が安く設定されています。また、半日利用と一日利用では費用が大きく異なるため、必要最小限の利用時間に調整することで負担を軽減できます。
サービス選択の費用削減ポイント
・大規模事業所の選択:月2,000円〜5,000円の削減
・半日利用への変更:月10,000円〜15,000円の削減
・地域密着型サービス活用:月5,000円〜10,000円の削減
・複数事業所の料金比較:月3,000円〜8,000円の削減
訪問介護では、身体介護と生活援助で大きく料金が異なります。本当に専門的な介助が必要な部分のみを身体介護とし、掃除や買い物などは生活援助やシルバー人材センターなどの安価なサービスを活用することで、大幅な費用削減が可能です。
福祉用具については、購入とレンタルの使い分けが重要です。車椅子や介護ベッドなど高額な用具は介護保険でのレンタルを活用し、ポータブルトイレやシャワーチェアなど比較的安価で衛生面を考慮すべき用具は購入を選択するなど、戦略的な判断が費用削減につながります。
在宅介護と施設介護の費用比較と最適化戦略

親の介護でお金がない状況では、在宅介護と施設介護のコスト比較を正しく理解することが重要です。一般的に在宅介護の方が安いと思われがちですが、要介護度や家族の状況によっては施設介護の方が経済的な場合もあります。
在宅介護では、介護保険サービスの自己負担分は月1万円〜3万円程度ですが、これ以外にも様々な費用がかかります。介護者の交通費、特別な食事代、住宅改修費、介護用品代などを含めると、実際の費用は月5万円〜8万円程度になることが多いのです。
在宅介護vs施設介護の費用比較(月額)
【在宅介護】
・介護保険サービス:15,000円〜30,000円
・介護用品・食事代等:20,000円〜30,000円
・介護者の機会費用:50,000円〜100,000円
【施設介護(特養)】
・介護保険サービス:20,000円〜30,000円
・居住費・食費:40,000円〜70,000円
・その他費用:5,000円〜10,000円
施設選択では、特別養護老人ホームが最も費用を抑えられる選択肢です。負担限度額認定を受ければ、月額5万円〜8万円程度での利用が可能です。待機期間が長いデメリットはありますが、早めの申し込みにより対応できます。
在宅介護を継続する場合は、ショートステイの戦略的活用が重要です。介護者の休息と費用削減を両立させるため、月の利用日数を調整しながら効率的に利用することで、介護負担の軽減と経済性を両立できます。

専門家連携による予算内ケアプラン作成術

親の介護でお金がない状況を乗り切るためには、ケアマネジャーとの密接な連携が不可欠です。経済状況を包み隠さず相談し、予算制約の中で最大限の効果を得られるプランを作成してもらいましょう。
ケアマネジャーに相談する際は、「月の介護費用は○万円以内」「介護保険の限度額は○割まで」といった具体的な予算制約を明確に伝えることが重要です。これにより、限られた予算内で最適なサービス組み合わせを提案してもらえます。
地域包括支援センターも重要な相談先です。ケアマネジャーでは解決できない経済的問題について、より包括的な支援策を提案してもらえます。地域の社会資源情報にも精通しているため、介護保険外の安価なサービス情報なども教えてもらえます。
専門家活用の具体的手順
1. ケアマネジャーに経済状況と予算制約を相談
2. 地域包括支援センターで制度活用方法を確認
3. 市区町村福祉課で独自制度の情報収集
4. 社会福祉協議会で貸付制度の相談
5. 定期的な見直しと最適化の実施
重要なのは、経済的困窮を恥ずかしがらずに相談することです。多くの専門家は、限られた予算内で最適なケアを提供する経験を豊富に持っています。「お金がないから良い介護ができない」と諦めるのではなく、専門家の知識と経験を活用して、予算内で最良の介護を実現しましょう。
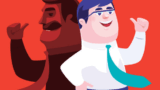

「お金がないから」と一人で抱え込まず、利用できる制度を最大限活用することが大切です。専門家に相談すれば、思わぬ解決策が見つかることも多いんですよ。
親の介護お金問題解決への道筋:まとめ
親の介護でお金がない状況は確かに深刻な問題ですが、適切な対策と制度活用により必ず解決できる課題です。まず重要なのは、すべての経済的負担を家族だけで背負う必要がないことを理解することです。
公的支援制度の活用により、介護費用は大幅に軽減できます。高額介護サービス費制度や負担限度額認定により月数万円の軽減が可能で、生活保護制度では介護関連費用がほぼ全額支援されます。各自治体の独自制度や生活福祉資金貸付制度も組み合わせることで、さらなる負担軽減が期待できます。
費用削減の実践的手法では、事業所の比較選択や在宅・施設介護の戦略的判断、専門家との連携による予算内ケアプラン作成が重要です。同じサービスでも選択方法により月数万円の差が生じることもあるため、情報収集と比較検討を怠らないことが大切です。
何より重要なのは、一人で抱え込まないことです。経済的な悩みは相談しにくいものですが、専門家のサポートを受けることで必ず道筋が見えてきます。親の介護でお金がない状況は、あなただけの問題ではなく、社会全体で支え合うべき課題なのです。
利用できる制度を積極的に活用し、専門家の知識と経験を借りながら、経済的に持続可能な介護体制を築いていきましょう。そうすることで、親にとっても家族にとっても最適な介護の形を実現できるはずです。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。



