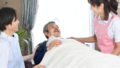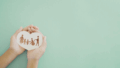「なんで私ばかりが親の介護をしなければいけないの?」
「兄弟は何もしないのに、私だけが犠牲になっている」
「もう限界…でも、どうすればいいか分からない」
親の介護をしていると、こんな気持ちになったことはありませんか?
実際に、みんなの介護が実施した調査では、介護を理由に「家族仲が悪くなった」と回答した人は全体の約9割にものぼります。あなたが感じている不公平感は、決して被害妄想でも、あなたのわがままでもありません。
この記事では、こんなことが分かります:
✓ なぜ「私ばかり」の状況が生まれるのか(構造的な理由)
✓ 兄弟姉妹に協力してもらうための具体的な伝え方
✓ 話し合いで解決しない時の法的対処(家庭裁判所の調停)
✓ 「介護しない嫁」への対処と嫁の立場での適切な対応
✓ 「私ばかり」で疲れ切った心と体の立て直し方
一人で抱え込まず、状況を改善する道筋を一緒に見つけていきましょう。
親の介護で「なぜ私ばかり」不公平感の正体と構造的問題
親の介護で「私ばかり」という状況が生まれるのには、明確な理由があります。これは偶然ではなく、構造的な問題として多くの家庭で起こっているのです。
兄弟姉妹は何もしないのに私だけ…親の介護の偏りが生まれる理由

親の介護が一人に集中してしまう最も多い理由は、物理的な距離の問題です。親の近くに住んでいる子どもに、自然と介護の負担が集中してしまいます。
「近くにいるから」「長女だから」「結婚していないから」といった、なんとなくの理由で役割が決まってしまうのです。しかし、これらは本当に公平な理由でしょうか?
また、兄弟姉妹の中で一人だけが「責任感が強い」「断れない性格」だと、周りの家族がそれに甘えてしまうパターンも多く見られます。「○○さんがやってくれるから大丈夫」という空気ができあがってしまい、他の家族は親の介護から距離を置いてしまうのです。
さらに、経済的な理由で介護せざるを得ない状況もあります。仕事を辞めたり時短に変更したりして、「時間があるから」という理由で親の介護を一手に引き受けることになるケースです。
「親の介護を私ばかり、損をしている」と感じる心理メカニズム

親の介護をしていると、どうしても他の兄弟姉妹と自分を比べてしまいます。
「私は毎日病院に付き添っているのに、兄は月に一回顔を見せるだけ」
「妹は遠方にいるからって理由で何もしてくれない」
そんな状況を目の当たりにすると、不公平感が募るのは当然です。
この感情は、心理学では「相対的剥奪感」と呼ばれています。絶対的な負担の重さよりも、他の人との比較によって生まれる感情です。
特に辛いのは、親の介護をしていない兄弟姉妹から「ありがとう」の言葉すらもらえない時です。当たり前のように思われてしまうと、「私の努力は何なの?」という虚しさが襲ってきます。
また、親の介護をしていると自分の時間、自分の人生を犠牲にしている感覚が強くなります。友人との時間、趣味の時間、キャリアアップの機会…これらを諦めながら介護をしているのに、周りは自由に生活している。この格差が、不公平感をより強くしてしまいます。

「親の介護を私ばかり」という感情を抱くことは決して悪いことではありません。むしろ、正常な反応です。大切なのは、この感情を一人で抱え込まず、適切に処理していくことですね。
【体験談】親の介護を私ばかりしていた時の実情

実際に「親の介護を私ばかり」の状況を経験された田中さん(仮名・50代女性)と佐藤さん(仮名・40代女性)の体験談をご紹介します。
【田中さんのケース:兄弟格差に苦しんだ5年間】
田中さんは、認知症の母親の介護を5年間一人で担ってきました。3人兄弟の長女である田中さんは、弟二人から「お疲れさま」と言われるだけで、具体的な協力は一切ありませんでした。
「最初は『私がやらなきゃ』という使命感でした。でも、だんだん『なぜ私だけ?』という気持ちが強くなって。弟たちは普通に働いて、家族と過ごして、趣味も楽しんでいる。一方で私は、母の介護で一日が終わる毎日でした」
転機が訪れたのは、田中さん自身が体調を崩した時でした。
「ある日、突然めまいがして倒れてしまったんです。病院で『ストレスと疲労が原因』と言われて、初めて自分の限界に気づきました。それから家族会議を開いて、弟たちにも協力してもらうことになりました」
【佐藤さんのケース:嫁の立場での介護負担】
佐藤さんは、夫の両親の介護を約3年間担いました。夫には兄がいましたが、「嫁がいるから安心」と言われ、実質的にすべての介護を任されてしまいました。
「夫は仕事が忙しいと言い、義兄は『弟の嫁がいるから』と完全に他人事。でも法的には、私には介護義務はないんですよね。それなのに、なぜ私だけが…と毎日思っていました」
佐藤さんの場合、最終的に夫と真剣に話し合い、介護サービスを活用することで負担を軽減できました。
「今思えば、『私がやらなきゃ』という思い込みが強すぎたんです。夫に『あなたの親なのだから、まずあなたが責任を持つべき』とはっきり伝えたことで、状況が変わりました」
親の介護「私ばかり」の状況を変える5つのステップ
「親の介護を私ばかり」の状況は変えることができます。適切な方法で家族にアプローチし、専門機関のサポートを活用することで、必ず改善の道筋が見えてきます。
ステップ1:「親の介護を私ばかり」の状況を客観視するための相談

「親の介護を私ばかりしている」と感じている時、その状況を客観的に見ることは実は非常に難しいものです。介護をしている当事者は、日々の大変さの中にいるからです。
だからこそ、第三者に相談することが重要になります。
専門の相談員や、同じような経験をした人に話を聞いてもらうことで、自分の状況を冷静に整理できます。また、あなたが感じている不公平感が正当なものかどうかも、客観的に判断してもらえます。
相談する時のコツは、遠慮しないことです。「こんなことで相談していいのかな」と思わず、素直に今の気持ちを伝えてください。
また、具体的な状況(親の介護にかけている時間、他の家族の関わり方、自分が犠牲にしていること)を整理して伝えると、より的確なアドバイスを得られます。
親の介護で相談できる主な窓口
□ 地域包括支援センター:介護全般の相談ができる(無料)
□ ケアマネジャー:介護サービスの提案と調整
□ 市区町村の介護保険窓口:制度や手続きの相談
□ 介護者の集い:同じ境遇の人との交流
□ オンラインコミュニティ:匿名で気軽に相談できる
ステップ2:家族に「親の介護をなぜ私だけ?」を理解してもらう効果的な伝え方

家族に現状を理解してもらうのは、想像以上に難しいものです。特に、親の介護に直接関わっていない兄弟姉妹には、日常の大変さが伝わりにくいのです。
しかし、適切な伝え方をすれば、必ず理解してもらえます。
まず大切なのは、感情的にならずに事実を伝えることです。「あなたたちは何もしてくれない!」と責めるのではなく、「私が今、こんなことで困っている」という現状を具体的に説明しましょう。
効果的な伝え方のポイント
□ 一日のスケジュールを具体的に説明する
□ 数字を使って負担の重さを示す(「月に20回病院付き添い」など)
□ 自分が犠牲にしていることを正直に伝える
□ 責めるのではなく「協力してほしい」というスタンスで話す
□ 親のためにも家族で支えたいという気持ちを伝える
□ 「親の介護を私ばかり」という言葉を使って状況を伝える
家族会議を開く時の準備
家族会議を開く際は、事前に話し合いの目的を明確にしておくことが重要です。
- 「現状の介護負担を見直したい」
- 「みんなで親を支える体制を作りたい」
といった具体的な目標を設定し、建設的な話し合いができる環境を整えましょう。
ステップ3:一人だけに親の介護の負担が集中しない仕組みづくり

家族の理解が得られたら、次は具体的な役割分担を決めていきます。
ここでポイントとなるのは、それぞれの事情に合わせた分担を考えることです。完璧な分担を求めるのではなく、それぞれができる範囲で協力してもらい、負担を少しでも分散させることが目標です。
物理的に遠方にいる兄弟姉妹には、直接的な介護以外の役割を担ってもらいましょう。
- 経済的な支援
- 介護用品の購入
- 情報収集
- 月一回の様子見
- 定期的な電話での安否確認
近くにいても仕事が忙しい家族には、時間を区切った役割をお願いします。
- 「土曜日の午後は必ず顔を見せる」
- 「月に一回は病院に付き添う」
- 「平日の夕方1時間だけ様子を見に行く」
など、具体的で実現可能な約束をしましょう。
ステップ4:介護サービスを使って親の介護の負担を減らす具体的な方法
親の介護保険サービスを積極的に活用することも重要です。
- デイサービス
- ショートステイ
- 訪問介護
- 訪問看護
- 福祉用具レンタル
など、プロのサポートを受けることで、家族の負担は大幅に軽減されます。
「家族で面倒を見るべき」という考えにとらわれず、使える制度やサービスはどんどん利用しましょう。
ステップ5:それでも親の介護の状況が変わらない時の次の一手
家族との話し合いや介護サービスの活用を試みても、「親の介護を私ばかり」の状況が改善されない場合もあります。
そんな時は、さらに踏み込んだ対処を検討する必要があります。
- 家庭裁判所での調停を申し立てる(詳しくは次の章で解説)
- 施設入居を真剣に検討する
- 自分の生活を優先する選択をする
最も大切なのは、あなた自身が「完璧な介護者」になろうとしないことです。できないことはできないと正直に伝え、助けを求めることが、結果的に親にとっても家族にとっても最良の選択となります。
【「親の介護を私ばかり」状況を変えたいあなたへ】
親の介護義務と法的対処―裁判という選択肢も含めて
「親の介護を私ばかりしている」状況が改善されない場合、法的な観点からの対処も検討する必要があります。親の介護に関する法的義務や、最終手段としての裁判について詳しく解説します。
そもそも親の介護は誰の義務?法的根拠を詳しく解説

親の介護義務について、まず法的な根拠を正しく理解しておくことが重要です。
民法第877条には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と記されています。
ここで重要なのは、法律で定められているのは「扶養義務」であり、必ずしも「直接的な介護義務」ではないということです。
扶養とは、自力で生活を成立させられない親族に対する金銭面の支援のことを指します。
親の介護を誰が行うべきかについて、法律上の優先順位は定められていません。兄弟姉妹の年齢や同居の有無、性別などの条件も関係ありません。
つまり、「長女だから」「近くに住んでいるから」という理由で、法的に親の介護義務が発生するわけではないのです。
また、直系血族である子に配偶者がいても、扶養義務が生じるのはその子のみです。法律的には、子の配偶者(いわゆる「嫁」や「婿」)に、義理の親を介護する義務はありません。
家庭裁判所での調停―話し合いで解決しない場合の法的手続き

家族間での話し合いでは解決できない場合、民法878条および第879条により、扶養すべき者の優先順位や、それぞれの扶養の程度・方法を、家庭裁判所に定めてもらうことができます。
家庭裁判所での調停は、以下のような流れで進められます。
1. 調停の申立て
扶養に関する処分調停の申立てを家庭裁判所に行います。申立ては扶養義務者なら誰でも可能で、費用は収入印紙1,200円程度と比較的安価です。
2. 調停期日での話し合い
裁判官1名と調停委員2名が関わり、当事者間での合意を目指します。各当事者の収入、資産、健康状態、家族構成などを総合的に考慮して、公平な分担案が検討されます。
3. 調停成立または審判
合意に至れば調停成立となり、合意できない場合は裁判官が審判を下します。審判には法的拘束力があり、従わない場合は制裁措置も可能です。
調停で考慮される要素
□ 各扶養義務者の収入・資産状況
□ 要扶養者(親)との関係性
□ 地理的条件(距離・交通の便)
□ 各自の家族状況(子どもの有無・健康状態等)
□ 既に行っている親の介護の程度
□ 「親の介護を私ばかり」という現状の不公平性
「親の介護をしない嫁」への対処と嫁の立場での適切な対応

夫側の主張として「嫁が義理の親の介護をしない」という問題は、多くの家庭で起こっています。しかし前述の通り、法的には配偶者に親の介護義務はありません。
この点を踏まえて、適切な対応を考える必要があります。
嫁の立場での適切な対応
まず、法的には義理の親への介護義務がないことを理解し、過度に罪悪感を抱く必要がないことを認識しましょう。
ただし、家族の一員として、可能な範囲での協力は検討すべきでしょう。
重要なのは、夫との話し合いです。「私には法的義務はないが、家族として何ができるか一緒に考えたい」というスタンスで話し合いを進めることで、建設的な解決策を見つけることができます。
義理の親の介護を求められた場合の対処法
もし義理の家族から親の介護を強く求められた場合は、まず冷静に状況を整理しましょう。
感情的にならず、「法的義務がないこと」「自分の生活への影響」「可能な協力の範囲」を明確に伝えることが重要です。
また、夫が親の介護に消極的な場合は、「あなたの親なのだから、まずあなたが責任を持つべき」という姿勢で話し合うことも必要です。
最終的に家庭裁判所での調停になった場合も、嫁に法的義務がない以上、直接的な親の介護を強制されることはありません。
親の介護「私ばかり」で疲れ切った心と体の立て直し方
長期間「親の介護を私ばかり」の状況が続くと、心身ともに大きなダメージを受けてしまいます。自分自身を守りながら、健全な介護を続けるための方法を身につけましょう。
不公平感によるストレスのセルフチェックと対処法

「親の介護を私ばかり」という不公平感は、知らず知らずのうちに心と体にダメージを蓄積させています。まずは、あなたの現在の状態をチェックしてみましょう。
身体的なサイン:
- 慢性的な疲労感が続いている
- 肩こりや頭痛が頻繁にある
- 食欲がない、または食べ過ぎてしまう
- 眠れない、または眠りが浅い
- 風邪をひきやすくなった
精神的なサイン:
- イライラすることが増えた
- 些細なことで怒りを感じる
- 無力感や絶望感を覚える
- 集中力が続かない
- 物事を楽しめなくなった
- 「親の介護を私ばかり」と常に考えている
行動面のサイン:
- 人と会うのが億劫になった
- 趣味や娯楽に興味がなくなった
- 家族以外との交流が減った
特に注意したいのは、「これくらい我慢しなきゃ」「親のためだから仕方ない」という思考パターンです。
あなた自身の健康を損ねてしまっては、結果的に親の介護にも支障が出てしまいます。ストレスサインに気づいたら、それは「休息が必要」という体からのメッセージとして受け取りましょう。
「親の介護を私だけが頑張っている」思考から抜け出す認知の転換

「親の介護を私だけが頑張っている」という思考は、介護者を孤立させ、さらなるストレスを生み出します。この思考パターンから抜け出すためには、意識的な取り組みが必要です。
視点を変える練習
まず、「頑張る」の定義を見直してみてください。親の介護は、24時間365日完璧にこなすことが「頑張る」ことではありません。あなたができる範囲で、親を支えることが本当の「頑張る」なのです。
他の家族についても、見方を変えてみましょう。直接介護をしていないからといって、何もしていないわけではないかもしれません。それぞれが何らかの負担を感じている可能性があります。
認知転換の実践方法
□ 毎日寝る前に、その日の小さな良いことを3つ書き出す
□ 「親の介護を私だけ」ではなく「私も」という視点で考える
□ 完璧主義を手放し、60点を合格点にする
□ 親に対するイライラも含めて、すべての感情を受け入れる
□ 「私がやらなきゃ」から「みんなで支える」への意識転換
感謝の気持ちを意識的に見つけることも重要です。毎日寝る前に、その日にあった小さな良いことを3つ書き出してみてください。
- 「親が笑顔を見せてくれた」
- 「近所の人が声をかけてくれた」
- 「ケアマネジャーが親身に相談に乗ってくれた」
など、どんな小さなことでも構いません。続けることで、物事の見方が少しずつ変わってきます。
同じ境遇の人とつながり理解し合う場所の活用

一人で抱え込まずに済む最も効果的な方法の一つが、同じような境遇の人とのつながりです。「親の介護を私ばかり」という思いを理解してくれる人との出会いは、心の大きな支えになります。
地域の介護者の集い
多くの自治体で、介護者同士の交流会やサポートグループが開催されています。月に一回程度、親の介護の悩みを共有したり、情報交換をしたりする場です。
「こんな大変な思いをしているのは私だけじゃないんだ」ということを実感できると、孤独感が大幅に軽減されます。
オンラインコミュニティの活用
対面での参加が難しい場合は、オンラインの介護者コミュニティも活用できます。時間や場所を選ばず、同じような悩みを持つ人たちと交流できるのがメリットです。
匿名で参加できるため、普段は言えない本音も吐き出しやすい環境です。
つながりを持つことは、決して贅沢ではありません。あなた自身の心の健康を保つために必要なことなのです。
一人で頑張りすぎず、周りの人の力を借りながら、親の介護と向き合っていきましょう。
まとめ:親の介護「私ばかり」から「みんなで」へ
「なぜ私ばかりが親の介護を」という不公平感は、多くの介護者が経験する自然で正当な感情です。あなたが感じているその気持ちは、決して間違っていませんし、我慢し続ける必要もありません。
重要なポイントを整理すると、まず法的な観点から、直接的な親の介護義務は特定の人に課されるものではないということです。家族間での話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での調停という選択肢もあります。
また、配偶者(嫁・婿)には法的な介護義務がないことも理解しておくべきでしょう。
実践的な改善方法として、家族への適切な働きかけ、専門機関への相談、介護サービスの活用、そして自分自身のケアが重要です。
完璧な介護者になろうとするのではなく、「できる範囲で親を支える」という現実的な目標を設定しましょう。
親の介護は長期戦です。あなたが健康で安定していることが、結果的に親にとっても家族にとっても最良の選択なのです。
時には手を抜いても、イライラしても、それは人間として当たり前のことです。
もし今、一人で抱え込んで辛い思いをしているなら、まずは誰かに相談してみてください。あなたの気持ちを理解し、具体的な解決策を一緒に考えてくれる人は必ずいます。
「親の介護を私ばかり」から「みんなで」へ。
この小さな意識の変化が、あなたの介護生活を大きく変える第一歩となるでしょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。