「最近親の物忘れが増えてきた」「歩き方が不安定になってきた」
そんな変化を感じて、親の介護がいつから必要になるのか不安を抱いていませんか。介護は突然始まると思われがちですが、実は小さなサインから徐々に始まっているのです。
この記事では、親の介護がいつから始まるのか、その兆候と準備すべきタイミングを詳しく解説します。早めの気づきと準備が、あなたと親の未来を大きく変えることになるでしょう。
親の介護はいつから必要になるのか年齢と現実
親の介護がいつから始まるかは、誰もが気になる疑問です。統計データと現実を見ながら、介護開始時期について理解を深めていきましょう。
平均75歳からでも個人差が大きい介護開始時期

統計によると、親の介護が始まる平均年齢は75歳から80歳とされています。
しかし、これはあくまで平均値。実際には60代で介護が必要になる人もいれば、90歳を過ぎても元気な人もいるのが現実です。
要介護認定を受ける人の割合を見ると、75歳を境に急激に増加します。75歳未満では約4%ですが、75歳以上になると約23%まで跳ね上がるのです。
ただし、健康寿命と平均寿命の差は男性で約9年、女性で約12年。この期間が何らかの支援が必要な時期と考えられています。
突然始まることが多い介護の実態

「介護は計画的に始まるもの」と思っている方も多いでしょう。しかし実際は突然始まることがほとんどなのです。
転倒による骨折、脳卒中の発症、認知症の進行。これらは予測できないタイミングで起こり、一夜にして介護生活が始まることもあります。
昨日まで元気だった親が、今日から要介護になる。そんな急激な変化に戸惑う家族は少なくありません。
特に一人暮らしの親の場合、変化に気づくのが遅れがち。久しぶりに会ったら別人のように衰えていたという話もよく聞きます。
早い人では60代から介護が必要になるケース
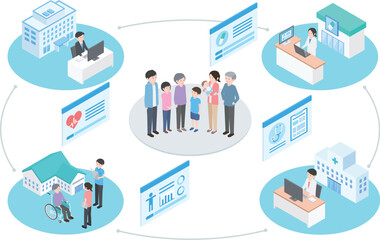
60代で介護が必要になるケースも決して珍しくありません。若年性認知症や脳血管疾患は60代でも発症するからです。
特に生活習慣病を抱えている場合、介護リスクは高まります。糖尿病、高血圧、脂質異常症などは、脳卒中や認知症のリスクを上げる要因となるのです。
また、がんの治療後に体力が戻らず介護が必要になることも。60代でも油断はできないということを理解しておく必要があります。
子ども世代が40代で親の介護に直面するケースも約7%存在します。まだ子育て中の世代にとって、親の介護は想定外の負担となることでしょう。

「まだ若いから大丈夫」は危険な思い込み。親の健康状態を定期的にチェックすることが大切ですよ。
親の介護がいつから始まるか分かる初期サイン
介護の必要性は、ある日突然現れるのではありません。小さなサインを見逃さなければ、早めの対応が可能です。
身体的な変化に気づいたら介護の入口

身体的な変化は最も分かりやすい介護のサインです。歩行が不安定になる、転びやすくなるといった変化に注意しましょう。
食事量の減少も重要なサイン。「最近食が細くなった」という変化は、噛む力や飲み込む力の低下を示している可能性があります。
トイレの失敗が増えるのも見逃せません。間に合わない、場所が分からないといったトラブルは、身体機能の低下を表しています。
体重の急激な減少や増加も要注意。栄養状態の悪化や運動不足は、介護が必要になる前兆かもしれません。
チェックすべき身体的変化
□ 歩くスピードが遅くなった
□ 階段の昇り降りが辛そう
□ 立ち上がりに時間がかかる
□ 箸やスプーンをうまく使えない
□ 薬の管理ができなくなった
認知面の変化は介護開始の重要なシグナル

認知面の変化は、身体的変化より気づきにくいもの。しかし認知症は介護が必要になる最大の原因となっています。
同じことを何度も聞く、約束を忘れる。これらは単なる物忘れではなく、認知機能低下の可能性があります。
性格の変化も重要なサイン。穏やかだった人が怒りっぽくなる、社交的だった人が引きこもるといった変化は要注意です。
被害妄想や幻覚も現れることがあります。「財布を盗まれた」「知らない人が家にいる」といった訴えは、認知症の症状かもしれません。
生活面での困りごとが増えてきた時

生活面での変化も、介護の始まりを告げるサインです。家事ができなくなる、買い物に行けなくなるといった変化に注目しましょう。
ゴミ出しができない、部屋が散らかっている。これらは単なる怠慢ではなく、生活能力の低下を示しているのかもしれません。
金銭管理のトラブルも増えてきます。同じものを何度も買う、通帳や印鑑を紛失する、詐欺に遭いやすくなるなどの変化があります。
通院の付き添いが必要になるのも一つのサイン。一人で病院に行けない、薬の管理ができないといった状況は、支援の必要性を示しています。
親の介護をいつから準備すべきか具体的タイミング
介護の準備は「まだ早い」と思う時期から始めるのがベスト。具体的なタイミングと準備内容を見ていきましょう。
70歳を過ぎたら家族で話し合いを始める時期

親が70歳を過ぎたら、介護について家族で話し合う時期です。元気なうちだからこそ、冷静な話し合いができるのです。
「もしもの時はどうしたい?」という問いかけから始めてみましょう。在宅介護か施設介護か、親の希望を聞いておくことが大切です。
兄弟姉妹がいる場合は、役割分担の話も必要。誰が中心となって介護するのか、費用負担はどうするのか、早めに決めておきましょう。
エンディングノートの作成もおすすめ。医療や介護の希望、財産のことなど、親の意思を文書に残しておくと安心です。
介護保険の申請タイミングと手続き

介護保険の申請は、介護の必要性を感じたらすぐに行うべきです。早めの申請で、適切なサービスを受けられます。
申請から認定まで約1ヶ月かかるため、急に介護が必要になってからでは遅いのです。予防的な意味でも早めの申請をおすすめします。
65歳以上なら、市区町村の窓口で申請可能。40歳以上64歳以下でも、特定疾病があれば申請できます。
地域包括支援センターでの相談も有効です。申請のタイミングや必要書類について、詳しくアドバイスしてもらえます。
今からできる心と環境の準備

介護への心の準備も重要です。「自分一人で背負わない」と決めておくことが、長続きする介護の秘訣となります。
介護に関する知識を身につけることも大切。介護教室や講座に参加して、基本的な介護技術を学んでおきましょう。
住環境の改善も今からできる準備。手すりの設置や段差の解消など、バリアフリー化を進めておくと安心です。
介護費用の準備も忘れずに。親の年金額や貯蓄を把握し、介護にかかる費用を試算しておくことが重要です。
親の介護がいつから始まっても慌てないための:まとめ
親の介護はいつから始まるか、正確に予測することはできません。平均は75歳からですが、60代でも90代でも起こり得るのが現実です。
大切なのは、小さなサインを見逃さないこと。身体的変化、認知面の変化、生活面での困りごと。これらに早く気づけば、適切な対応が可能になります。
70歳を過ぎたら家族で話し合いを始め、介護保険の申請も視野に入れる。心と環境の準備を整えることで、突然の介護にも対応できるようになります。
「まだ早い」と思う時期こそ、準備のチャンス。介護を始めないための予防的な行動が、親と自分の未来を守ることにつながるのです。
ココマモで介護の悩みを相談できます
「まだ介護は始まっていないけど不安」という方も多いでしょう。介護家族のためのオンライン相談サービス「ココマモ」では、介護が始まる前の予防相談も承っています。親の変化に気づいた時、どう対応すればいいか迷った時、専門相談員が適切なアドバイスをいたします。初回20分の無料相談で、あなたの不安を一緒に整理しましょう。早めの相談が、安心への第一歩になります。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。






