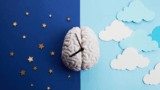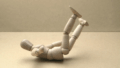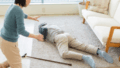「座っていても、すぐ立ち上がる」「家の中を歩き回り続ける」「夜も動き回って眠れない」。認知症の家族がじっとしていられず、一瞬も目が離せない日々を送っていませんか。
転倒や事故の恐怖、睡眠不足、精神的な消耗。休む時間がないという状況が、あなたを限界まで追い詰めているのではないでしょうか。
この記事では、認知症でじっとしていられない理由を医学的・心理的に理解し、安全を守りながら落ち着かせる対処法をお伝えします。さらに、一瞬も目が離せない介護者自身の心を守る方法、休息を取るための具体的な支援まで、実践的な内容をご紹介します。
認知症でじっとしていられない理由を理解する
じっとしていられず動き回るのは、決してわがままでも意地悪でもありません。そこには、本人にもどうしようもない理由があるのです。
脳の機能障害と不安が落ち着かなくさせる

認知症でじっとしていられない最大の理由は、脳の神経細胞の障害です。記憶や判断力をつかさどる部分が損傷することで、自分の意志で行動をコントロールできなくなります。
「座っていよう」「静かにしよう」と思っても、脳からの指令がうまく伝わらないのです。さらに、認知機能の低下により、今の状況を理解できないため、常に不安と混乱の中にいます。
自分が何をすべきかわからない、どこにいるのかわからない、何が起こっているのかわからない。この深い不安と焦りが、じっとしていられない状態を作り出します。動くことで、何かを確認しようとしているのです。
身体の不快感や痛みで動き回る

見落とされがちですが、身体的な不快感がじっとしていられない原因になることも多いです。痛み、かゆみ、便秘、尿意、空腹。これらを言葉で表現できないため、動くことで訴えています。
特に便秘は、認知症の方に非常に多い問題です。お腹の張りや不快感があっても、それを「便秘だ」と認識できません。ただ「苦しい」「落ち着かない」という感覚だけが残り、動き回ることで紛らわせようとするのです。
また、関節痛や腰痛などの慢性的な痛みも関係しています。同じ姿勢でいると痛みが増すため、無意識に動き続けます。座っていられないのは、座っていると痛いからかもしれないのです。
チェックすべき身体的要因
・便秘や尿意の我慢
・痛み(関節痛、腰痛、頭痛など)
・かゆみや湿疹
・空腹や喉の渇き
・衣服の不快感
・室温の暑さ寒さ
・薬の副作用
昼夜逆転と刺激過多による多動

認知症が進行すると、体内時計が乱れ、昼夜逆転が起こります。夜になっても眠れず、家の中を歩き回る。これは睡眠障害という認知症の症状の一つです。
昼間の活動が少ないと、夜に眠くなりません。日光を浴びない、体を動かさない生活が続くと、生活リズムが崩れ、夜間の多動につながります。
また、刺激が多すぎても、じっとしていられなくなります。テレビの音、人の話し声、来客、環境の変化。情報を処理しきれないため、興奮状態になり、動き回るのです。
逆に、刺激が少なすぎても落ち着かなくなります。することがない、退屈だという感覚が、そわそわした行動を引き起こします。適度な刺激のバランスが難しいのです。
認知症でじっとしていられない時の安全な対処法
じっとしていられない状態を、無理に止めることはできません。しかし、安全を守りながら落ち着かせる方法はあります。
無理に止めず環境を整える基本対応

じっとしていられない時の基本的な対処法は、無理に止めないことです。「座りなさい」「動かないで」と強く言っても、本人は理解できず、かえって混乱と不安が増します。
動きたいという欲求を受け入れ、安全に動ける環境を整えることが大切です。転倒の原因になる段差をなくす、つまずきやすい物を片付ける、滑りにくい床にする。危険を減らす工夫が重要です。
室内を歩き回るなら、その動線を確保します。家具の配置を変える、危険な場所には柵をつける、階段には転落防止ゲートを設置する。本人が安全に動き回れるスペースを作りましょう。
また、身体的な不快感がないか確認することも大切です。トイレに行きたいのか、お腹が空いているのか、暑すぎるのか。原因を取り除くことで、落ち着くことがあります。
気をそらし穏やかにする声かけの工夫

落ち着かない時は、穏やかな声かけが効果的です。「大丈夫ですよ」「一緒にいますよ」「安心してください」。優しく、ゆっくりとした口調で、安心感を与える言葉をかけましょう。
気をそらすことも有効な方法です。「一緒にお茶を飲みませんか」「写真を見ませんか」「外の景色を見ましょう」。別のことに意識を向けることで、多動が収まることがあります。
身体に触れることも安心感を与えます。手を握る、肩に手を置く、背中をさする。優しいスキンシップは、言葉以上に「一人じゃない」というメッセージを伝えます。
ただし、触られることを嫌がる場合もあります。本人の反応を見ながら、無理強いはしないことが大切です。拒否されたら、距離を保ちながら見守りましょう。

声かけのポイントは、短く、穏やかに、繰り返すことです。長い説明は理解できません。「大丈夫」「安心して」と、シンプルな言葉を優しく繰り返しましょう。
危険を減らす環境づくりと見守り

じっとしていられず動き回る以上、事故を防ぐ環境づくりが不可欠です。転倒、転落、誤飲、徘徊による行方不明。これらのリスクを最小限に抑える工夫が必要です。
床には滑り止めマットを敷く、段差をなくす、角にクッション材をつける。階段には転落防止ゲート、玄関にはセンサーを設置する。危険な物は手の届かない場所に片付ける。できる限りの安全対策を講じましょう。
見守りカメラやGPSも活用できます。別の部屋にいても様子を確認できるカメラ、外出時の位置を知らせるGPS機器。テクノロジーの力を借りることで、少しでも安心を得られます。
また、日中の活動を増やすことも重要です。散歩、デイサービス、簡単な作業。適度に体を動かし、日光を浴びることで、夜の睡眠が改善し、夜間の多動が減ることがあります。
安全対策チェックリスト
・床の滑り止め対策
・段差の解消
・家具の角にクッション
・階段の転落防止ゲート
・玄関のセンサー設置
・危険物の片付け
・見守りカメラの設置
・GPSの携帯
・近隣への声かけ(徘徊対策)
じっとしていられない家族を見守る介護者の心を守る
じっとしていられない家族の介護は、想像を絶する疲労をもたらします。あなた自身の心を守ることも、同じくらい大切です。
一瞬も目が離せない疲労を認める

じっとしていられない家族を見守ることは、一瞬も気が抜けない状態です。転倒するかもしれない、外に出てしまうかもしれない、何か危ないことをするかもしれない。この緊張が、24時間続くのです。
睡眠も満足に取れない、トイレにも安心して行けない、食事もゆっくり食べられない。常に気を張り詰めている状態は、心身を確実に蝕んでいきます。
「もう限界だ」「休みたい」「誰か代わってほしい」。そう思うことは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、正常な反応です。あなたは十分すぎるほど頑張っています。
レスパイトケアで完全に休む時間を作る

じっとしていられない家族の介護では、完全に離れる時間を作ることが不可欠です。ショートステイ、デイサービス、レスパイト入院。これらのサービスを積極的に活用しましょう。
ショートステイは、数日から数週間、施設に宿泊するサービスです。その間、あなたは完全に介護から解放されます。罪悪感を持つ必要はありません。休息は必要なことなのです。
デイサービスは、日中だけ施設に通うサービスです。数時間でも家族がいない時間があれば、心は休まります。その間に睡眠を取る、外出する、何もしない時間を持つ。それだけで、心は回復します。
レスパイト入院は、医療的ケアが必要な方が一時的に病院に入院するサービスです。医師や看護師が24時間体制で見守るため、安心して休むことができます。

専門家の支援を受ける選択肢

じっとしていられない症状は、薬物療法で改善できることもあります。かかりつけ医や認知症専門医に相談し、適切な治療を受けることを検討してください。
抗不安薬や睡眠薬、認知症の進行を遅らせる薬など、様々な選択肢があります。薬には副作用もあるため、医師とよく相談することが大切ですが、症状が軽減されれば、介護の負担も減ります。
訪問看護や訪問介護も活用しましょう。専門職が定期的に訪問し、状況を見てくれます。家族だけでは気づかない対処法や、環境調整のアドバイスをもらえることもあります。
ケアマネジャーにも、正直に状況を伝えてください。「もう限界だ」「夜も眠れない」「事故が怖い」。こうした訴えが、サービスの見直しや追加につながります。弱音を吐くことは恥ではないのです。
施設入所という選択も必要な時がある

じっとしていられない状態が続き、在宅での介護が困難になった時、施設入所を検討することも必要です。これは決して親を見捨てることではありません。
施設では、複数のスタッフが24時間体制で見守ります。転倒や事故のリスクも、プロの目で管理されます。家族が心身ともに限界を迎えて倒れるよりも、専門的なケアを受ける方が、本人にとっても良い選択になることがあります。
施設入所により、家族関係が改善することもあります。介護の負担から解放されることで、面会時には穏やかに接することができます。親子として、家族として、愛情を注ぐことに専念できるようになるのです。
認知症でじっとしていられない時の対処法:まとめ
認知症でじっとしていられないのは、脳の機能障害、不安、身体的不快感、昼夜逆転など、様々な理由があります。本人は決してわがままで動き回っているわけではなく、どうしようもない状態なのです。
対処法としては、無理に止めず環境を整える、穏やかな声かけで気をそらす、危険を減らす工夫をするなどがあります。動くこと自体を止めるのではなく、安全に動ける環境を作ることが重要です。
しかし、最も大切なのは介護者自身の心を守ることです。一瞬も目が離せない状態は、想像を絶する疲労をもたらします。その疲れを認め、限界を感じたら、遠慮なく助けを求めてください。
ショートステイ、デイサービス、レスパイト入院などのサービスを活用し、完全に休む時間を作りましょう。専門家に相談し、薬物療法や環境調整のアドバイスを受けることも大切です。
じっとしていられない家族を見守ることは、24時間気が抜けない緊張の連続です。睡眠も取れない、事故の恐怖に怯える日々。その辛さは、経験した人にしかわかりません。
しかし、あなたは一人ではありません。同じように悩み、疲れ、それでも前を向いている人がたくさんいます。そして、あなたを支えたいと思っている専門家やサービスもあります。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。