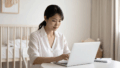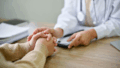「親が癌治療をしないと決めた」「高齢だから無理に延命するより自然に…と本人が言っている」「治療をやめる選択は間違っているのだろうか」
大切な家族が癌になり、治療をしないという選択をしたとき、周囲の家族は大きな葛藤を抱えることになります。本人の意思を尊重したい気持ちと、何かできることはないかという思いの間で揺れ動くでしょう。
この記事では、癌治療をしないという選択の背景にある考え方と、家族としてどのように向き合い、支えていけばよいのかについて解説します。医療的な判断ではなく、家族の心情やケアの視点から、後悔しない選択をするためのヒントをお伝えします。
癌治療をしない選択とはどういうことか
癌治療をしないという選択は、決して「何もしない」「諦める」という意味ではありません。本人の生活の質や価値観を最優先にした、前向きな医療の選択肢のひとつです。
治療しない選択が増えている背景

近年、特に高齢者において癌治療をしない選択をする方が増えています。その背景には、医療技術の進歩により治療の選択肢が広がった一方で、治療による負担と得られる効果を天秤にかけ、本人の意思を尊重する考え方が浸透してきたことがあります。
抗がん剤治療や手術には、体力的な負担や副作用が伴います。高齢の方や持病のある方の場合、治療そのものが生活の質を大きく低下させる可能性があるのです。吐き気、脱毛、倦怠感などの副作用により、残された時間を苦しみながら過ごすことになるかもしれません。
また、積極的な治療を行っても必ずしも治癒するとは限らず、延命効果が数ヶ月程度にとどまるケースもあります。そうした状況で、限られた時間を治療のために費やすのではなく、穏やかに過ごすことを選ぶ方が増えているのです。
治療しない場合の経過と緩和ケアの役割

癌の治療をしない場合、病状は進行していきます。ただし、その速度や症状の現れ方は、癌の種類や進行度、本人の体力によって大きく異なります。すぐに状態が悪化するケースもあれば、数年単位でゆっくり進行するケースもあるのです。
重要なのは、治療をしない選択をしても、医療的なサポートが終わるわけではないという点です。緩和ケアという形で、痛みや不快な症状を軽減し、生活の質を保つための医療が提供されます。
緩和ケアでは、痛み止めの適切な使用、吐き気や呼吸困難への対処、精神的な不安への支援などが行われます。在宅で受けられる緩和ケアもあり、住み慣れた自宅で穏やかに過ごすことも可能です。
本人の意思を尊重する大切さ

癌治療をしないという決断において最も重要なのは、本人の意思です。家族としては「何とか治療してほしい」と願うのは当然の感情ですが、治療を受けるのは本人自身であり、その苦痛も本人が負うことになります。
本人が「これ以上の治療は望まない」「残された時間を自分らしく過ごしたい」と決めた場合、その意思を尊重することが何よりも大切です。無理に治療を勧めることで、本人との関係が悪化したり、最期の時間を争いの中で過ごすことになってしまうかもしれません。
ただし、本人が十分な情報を得た上で決断しているか、家族としてしっかり確認することも必要です。「家族に迷惑をかけたくない」という遠慮から治療を拒否している場合もあるからです。
癌治療をしない選択をした家族の葛藤
本人が治療をしないと決めても、家族の心の中には様々な葛藤が生まれます。その感情を理解し、どう向き合えばよいのかを考えていきましょう。
後悔と罪悪感との向き合い方

「本当にこの選択で良かったのだろうか」「もっと強く治療を勧めるべきだったのではないか」という後悔や罪悪感は、治療をしない選択をした家族の多くが感じる感情です。
特に本人の状態が悪化していく様子を目の当たりにすると、「あの時治療を始めていれば」と自分を責めてしまうことがあります。しかし、大切なのはその時点での最善の判断をしたことを思い出すことです。
治療をしていても、必ずしも良い結果が得られたとは限りません。副作用に苦しみ、残された時間を病院で過ごすことになっていたかもしれません。結果論で判断するのではなく、本人の意思を尊重し、その時できる最善を尽くしたことを認めてあげましょう。
周囲からの無理解への対処

癌治療をしない選択に対して、周囲の人々から理解を得られないことも、家族にとって大きなストレスとなります。「なぜ治療しないのか」「諦めたのか」「もっと頑張るべきだ」といった言葉をかけられることもあるでしょう。
こうした言葉は悪意からではなく、癌治療をしない選択の背景を理解していないことから生まれます。本人の年齢、体力、価値観、生活の質への考え方など、様々な要因を総合的に判断した結果であることを、必要に応じて説明することも大切です。
ただし、すべての人に理解してもらう必要はありません。本人と家族が納得していれば、それで十分なのです。無理解な発言に傷つけられた時は、距離を置くことも選択肢のひとつです。
家族間での意見の対立

癌治療をしない選択について、家族間で意見が分かれることもよくあります。「母の意思を尊重すべき」という立場と、「何とか治療を受けてほしい」という立場で対立が生まれるのです。
特に、日常的に介護や看護を担当している家族と、離れて暮らしている家族との間で意見が異なることがあります。日々の様子を見ている家族は本人の苦痛や負担を実感しているため、治療をしない選択に理解を示しやすい一方、離れている家族は「もっとできることがあるはず」と考えがちです。
こうした対立を避けるためには、家族で情報を共有し、話し合いの場を持つことが重要です。医師から直接説明を聞く機会を設けたり、本人を交えて家族会議を開くことで、お互いの理解を深めることができます。
癌治療をしない選択を支える家族のケア
本人が治療をしない選択をした場合、家族としてどのように支えていけばよいのでしょうか。具体的なケアの方法と心構えについて解説します。
生活の質を保つための日常ケア

治療をしない選択をした場合でも、生活の質を保つための工夫は数多くあります。痛みや不快な症状を軽減し、本人が穏やかに過ごせる環境を整えることが家族の大切な役割です。
痛みへの対応は最も重要です。我慢させるのではなく、医師と相談しながら適切な痛み止めを使用しましょう。「痛み止めに頼りたくない」と考える方もいますが、痛みをコントロールすることで日常生活の質が大きく向上します。
食事の工夫も大切です。食欲が落ちることもありますが、本人の好きなものや食べやすいものを少量ずつ提供することで、食事の時間を楽しめるようにします。栄養バランスよりも、本人が美味しいと感じられることを優先しましょう。
清潔の保持も快適さに繋がります。体を拭いたり、口腔ケアをすることで、さっぱりとした気持ちで過ごせます。無理のない範囲で、本人の希望に合わせて行いましょう。
コミュニケーションと心のつながり

癌治療をしない選択をした本人は、様々な感情を抱えています。不安、恐れ、寂しさ、そして時には安堵や解放感も感じているかもしれません。家族との心のつながりが、何よりの支えとなります。
話をしたい時には耳を傾け、沈黙を望む時にはそっと寄り添う。無理に励ましたり、前向きな言葉を強要する必要はありません。本人の気持ちを否定せず、ありのままを受け止めることが大切です。
「ありがとう」「愛している」といった感謝や愛情の言葉を伝えることも、今のうちにしておきたいことです。後から「伝えておけば良かった」と後悔しないよう、素直な気持ちを言葉にしましょう。
また、本人が人生を振り返る時間を持つことも大切です。思い出話をしたり、写真を見返したり、やり残したことがないか尋ねることで、本人が自分の人生を受け入れ、心の準備をすることができます。
専門家や地域の支援を活用する

癌治療をしない選択をした場合でも、専門家や地域の支援を活用することで、本人も家族も安心して過ごすことができます。一人で全てを抱え込む必要はありません。
緩和ケアチームは、痛みや症状のコントロールだけでなく、精神的なサポートも提供してくれます。病院の緩和ケア外来や、在宅緩和ケアを利用することで、専門的なケアを受けながら自宅で過ごすこともできます。
訪問看護を利用すれば、看護師が定期的に自宅を訪問し、症状の観察や医療的なケアを行ってくれます。家族だけでは対応が難しいことも、専門家の助けを借りることで安心して在宅療養を続けられます。
地域包括支援センターでは、介護保険サービスの利用や、地域の支援制度について相談できます。介護ベッドのレンタルや、ヘルパーの派遣など、家族の負担を軽減するサービスを利用しましょう。

癌治療をしない選択を支えることは、家族にとっても大きな負担です。一人で抱え込まず、専門家や支援制度を積極的に活用してくださいね。
癌治療をしない選択と家族の支え方:まとめ
癌治療をしない選択は、本人の生活の質や価値観を尊重した、前向きな医療の選択肢のひとつです。家族としては葛藤を抱えることも多いでしょうが、本人の意思を尊重することが何よりも大切です。
治療をしないことの意味を正しく理解しましょう。それは「何もしない」ことではなく、苦痛を伴う治療ではなく、穏やかに過ごすことを選ぶということです。緩和ケアや在宅療養の支援により、生活の質を保ちながら過ごすことができます。
家族の葛藤は当然のものです。後悔や罪悪感、周囲からの無理解に苦しむこともあるでしょう。しかし、その時点での最善の判断をしたことを認め、本人との残された時間を大切に過ごすことに意識を向けましょう。
家族にできることは、生活の質を保つケア、心のつながりを大切にすること、そして専門家や地域の支援を活用することです。一人で全てを抱え込まず、様々な支援を受けながら、本人を支えていきましょう。
癌治療をしない選択は、本人にとっても家族にとっても大きな決断です。その選択を支え、残された時間を穏やかに過ごせるよう、できることから始めていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。