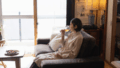「親の介護が必要になったけれど、介護休業を取るべきか迷っている」
「仕事を休んで介護に専念すれば、全てが解決するのだろうか」
「介護休業を取ったら、職場復帰できなくなるのでは」
介護休業の取得を考える時、多くの人がこのような不安を抱えます。

介護休業は、仕事と介護の両立を支援する重要な制度です。しかし、メリットだけでなくデメリットも存在し、取得すれば全てが解決するわけではないんです。制度の特徴を正しく理解した上で、自分の状況に合った判断をすることが大切になります。
この記事では、介護休業のメリットとデメリットを客観的に解説し、どのような場面で活用すべきか、デメリットをどう最小限にするかを具体的にお伝えします。介護休業を取得するかどうか判断する際の参考にしてください。
介護休業のメリットと活用できる場面
介護休業には、介護離職を防ぎながら家族の介護に向き合えるという大きなメリットがあります。まずは制度の利点から見ていきましょう。
仕事を続けながら介護体制を整えられる

介護休業の最大のメリットは、仕事を辞めずに一定期間介護に専念できる点です。対象家族1人につき通算93日まで、3回に分割して取得できます。
親の介護が突然必要になった時、最初にやるべきことは介護サービスの手配や生活環境の整備です。地域包括支援センターへの相談、要介護認定の申請、ケアマネージャーとの面談、デイサービスやヘルパーの契約など、やるべきことは山積みになります。
これらの準備を働きながら進めるのは困難です。介護休業を取得することで、落ち着いて介護体制を構築する時間が確保できるんです。93日あれば、必要な手続きを一通り済ませ、実際にサービスを利用しながら調整することもできます。
介護休業は「介護をするための休業」ではなく、「介護をしながら働き続けるための体制を整える休業」という位置づけです。この期間に適切な介護サービスを導入し、仕事と介護の両立ができる状態を作ることが目的なんです。
介護休業給付金で収入面の不安を軽減

介護休業を取得すると、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。これは休業前の賃金の約67%が支給される制度です。
完全に無給になるわけではないため、短期間であれば経済的な不安を抱えずに介護に専念できます。たとえば、月給30万円の人が介護休業を取得した場合、約20万円の給付金を受け取れる計算になるんです。
給付金の申請は会社を通じて行います。介護休業開始日から4か月以内にハローワークに申請する必要がありますが、通常は会社の人事部や総務部が手続きを代行してくれます。
ただし、給付金は休業前の賃金の67%であり、生活費や介護費用を考えると十分とは言えません。また、給付金の支給は休業後になるため、一時的に収入が途絶える期間があることも理解しておく必要があります。
介護離職を防ぎキャリアを守れる

介護休業の重要なメリットは、介護離職を防げる点です。一度仕事を辞めてしまうと、再就職は極めて困難になります。
厚生労働省の調査によると、介護離職した人の約8割が再就職できていない、または非正規雇用での再就職となっています。年齢が高くなるほど再就職のハードルは上がり、これまで築いてきたキャリアを失うことになるんです。
介護休業を利用すれば、仕事を辞めずに介護体制を整えられます。復職後は以前と同じ職場、同じ待遇で働き続けられるため、経済的な基盤とキャリアを維持できるわけです。
また、社会保険も継続されるため、健康保険や厚生年金の加入期間が途切れません。将来の年金額にも影響しないという点も大きなメリットになります。

介護は長期化することが多いです。最初から離職してしまうと、介護が終わった後の人生設計が非常に困難になります。介護休業を活用して仕事を続けることが、長期的には自分自身を守ることになるんです。
介護休業のデメリットと注意すべき点
介護休業にはメリットがある一方で、見過ごせないデメリットも存在します。現実を理解した上で判断することが重要です。
収入減少と経済的負担の増加

介護休業の最大のデメリットは、収入が大きく減少することです。給付金が支給されても休業前の賃金の67%であり、3割以上の収入減になります。
さらに、介護には予想以上にお金がかかります。介護保険サービスの自己負担分、おむつなどの消耗品代、通院の交通費、住宅改修費用など、様々な出費が発生するんです。収入が減る一方で支出は増えるため、家計は急速に圧迫されます。
93日間の介護休業を取得した場合、給付金を受け取っても実質的な収入減は数十万円に上ります。貯蓄が十分にない世帯では、生活費にも困る可能性があるでしょう。
また、介護休業を取得することで、利用できる介護サービスの選択肢が狭まる矛盾も生じます。収入が減ったために自己負担の大きいサービスを諦め、結局自分で介護をする時間が増えてしまうケースも少なくありません。
職場復帰後のキャリアへの影響

介護休業を取得すると、職場でのキャリアに影響が出る可能性があります。法律上は不利益な取り扱いが禁止されていますが、現実は異なることもあるんです。
長期間職場を離れることで、重要なプロジェクトから外されたり、昇進のタイミングを逃したりすることがあります。特に、管理職やリーダー的な立場にいる人は、休業中に後任に引き継がれ、復帰後に元のポジションに戻れないケースも報告されています。
また、介護休業を複数回取得する必要が生じた場合、職場での評価がさらに下がる恐れがあります。「また休むのか」という雰囲気が生まれ、働きづらくなることもあるでしょう。
復職後の業務内容が変わったり、やりがいのある仕事を任されなくなったりすることもあります。こうした変化が積み重なると、結局は自主退職に追い込まれるケースもあるんです。
介護休業だけでは介護問題は解決しない現実

介護休業の最も大きなデメリットは、休業を取得しても介護問題が根本的に解決するわけではないという点です。
93日間休んで介護体制を整えても、親の状態が改善するわけではありません。むしろ、介護に専念したことで精神的・肉体的な負担が増大し、復職後もその負担が続くケースが多いんです。
介護は長期化することが一般的です。93日間で全てが解決することはなく、復職後も介護は続きます。仕事との両立が困難になり、結局は介護離職を選択せざるを得なくなる人も少なくありません。
また、介護休業中に親子関係が悪化することもあります。24時間一緒にいることでストレスが溜まり、イライラして親に当たってしまったり、親が子どもに依存的になったりするケースがあるんです。
介護休業は「介護を乗り切るための魔法の杖」ではありません。あくまで一時的に介護に専念するための制度であり、その後も長期的な介護との向き合い方を考え続ける必要があるんです。
一人暮らしの高齢者の限界サインは?安全な生活を続ける基準を解説
介護休業のデメリットを最小限にする方法
介護休業のデメリットを理解した上で、それを最小限に抑えながら制度を活用する方法を考えましょう。
介護サービスの活用で負担を分散

介護休業のデメリットを減らす最も効果的な方法は、介護サービスを積極的に活用することです。自分一人で介護を抱え込まないことが重要になります。
介護休業期間中に、デイサービス、訪問介護、ショートステイなど様々なサービスを実際に利用してみましょう。どのサービスが親に合うか、どの程度の頻度で利用すべきかを見極める期間として活用するんです。
復職後も介護サービスを継続して利用することで、自分の負担を軽減できます。費用はかかりますが、仕事を続けられることで長期的には経済的に安定します。介護休業給付金の一部を介護サービスの利用料に充てることも検討しましょう。
介護休業中に整えるべきこと
ケアマネージャーとの信頼関係構築、複数の介護サービス事業者との契約、緊急時の連絡体制の確立、家族間での役割分担の明確化、親の財産状況の把握と今後の費用計画、地域の介護資源の情報収集
また、地域包括支援センターに定期的に相談し、利用できる制度や助成金の情報を得ることも大切です。介護休業は「体制を整える期間」として有効活用することで、デメリットを最小限に抑えられます。
職場との事前相談で復帰後の不安を解消

キャリアへの影響を最小限にするには、職場との丁寧なコミュニケーションが欠かせません。
介護休業を取得する前に、上司や人事部と十分に相談しましょう。どのくらいの期間休業するのか、復帰後の業務はどうなるのか、休業中の引き継ぎはどうするかなど、具体的に話し合うんです。
休業中も定期的に職場と連絡を取り、復帰時期や業務の状況を確認することで、スムーズな復職につながります。完全に連絡を絶つのではなく、月に一度程度は状況報告をすることをお勧めします。
また、復職後も介護が続くことを理解してもらい、急な休みや遅刻・早退の可能性があることを伝えておくことも重要です。正直にコミュニケーションを取ることで、職場の理解と協力を得やすくなるんです。
介護休暇や時短勤務との併用で柔軟に対応

介護休業だけに頼るのではなく、他の制度と組み合わせて活用することが賢明です。
介護休暇(年5日または10日)は、突発的な通院付き添いや手続きに使えます。時間単位でも取得できるため、ちょっとした用事にも対応できるんです。介護休業で大きな体制を整え、復職後は介護休暇で細かな対応をするという使い分けが効果的です。
また、時短勤務や所定外労働の制限、深夜業の制限など、介護をする労働者が利用できる制度は他にもあります。これらを組み合わせることで、長期的に仕事と介護を両立できる環境を作れます。
介護は長期戦です。最初から全力で走り続けると、すぐに疲弊してしまいます。様々な制度を上手に使いながら、持続可能な形で仕事と介護を両立させることが大切なんです。

介護休業は「使えば全て解決する制度」ではありません。でも、正しく理解して計画的に活用すれば、介護離職を防ぎながら家族を支える貴重な手段になります。
ココマモで介護の悩みを相談できます
オンライン相談サービス「ココマモ」では、介護のお悩みについて専門相談員に相談できます。初回20分の無料相談もありますので、一人で悩まず気軽に相談してみてください。
介護休業のメリットとデメリットを理解して活用を。まとめ
介護休業は、仕事と介護の両立を支援する重要な制度です。メリットもデメリットも存在し、どちらも正しく理解した上で活用することが大切になります。

メリットとしては、仕事を辞めずに一定期間介護に専念できること、介護体制を整える時間が確保できること、介護休業給付金により収入面の不安がある程度軽減されること、介護離職を防ぎキャリアを守れることが挙げられます。対象家族1人につき通算93日まで、3回に分割して取得できるという柔軟性も大きな利点です。
一方、デメリットとしては、収入が大きく減少すること、介護費用の負担と合わせて経済的に厳しくなること、職場復帰後のキャリアに影響が出る可能性があること、介護休業を取得しても介護問題が根本的に解決するわけではないことが挙げられます。給付金があっても休業前の67%の収入であり、生活や介護にかかる費用を考えると十分とは言えません。
デメリットを最小限にするには、介護サービスを積極的に活用し自分だけで抱え込まないこと、職場と丁寧にコミュニケーションを取り復帰後の働き方を事前に相談すること、介護休暇や時短勤務など他の制度と組み合わせて柔軟に対応することが重要です。
介護休業は「介護を乗り切るための魔法の杖」ではありません。あくまで一時的に介護体制を整えるための制度であり、その後も長期的に仕事と介護の両立を続ける必要があります。
しかし、適切に活用すれば、介護離職を防ぎながら家族を支える貴重な手段になります。
介護が突然必要になった時、焦って仕事を辞める前に、まず介護休業の活用を検討してください。
メリットとデメリットを天秤にかけ、自分の状況に合った判断をすることが大切です。
必要に応じて専門家に相談しながら、持続可能な形で仕事と介護を両立させる道を見つけていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。