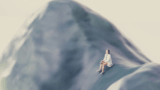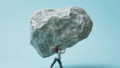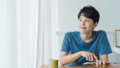「遠方に住む親の通院に付き添いたいけれど、同居していないから介護休暇は使えないのでは」
「別居している家族の介護で会社を休むのは難しいだろうか」
「介護休暇って同居が条件なんじゃないの」
そんな不安を抱えていませんか。

実は、介護休暇は同居していない家族の介護でも取得できる制度なんです。遠方に住む親の通院付き添いや介護サービスの手続きのために使うことが法律で認められています。
この記事では、同居していない家族の介護で介護休暇を取得するための条件、対象となる家族の範囲、具体的な申請方法まで詳しく解説します。知っているだけで仕事と介護の両立がぐっと楽になる情報をお伝えしていきます。
同居していない家族でも介護休暇を取得できる
介護休暇制度について、最も大きな誤解が「同居が必要」という思い込みです。実際には同居の有無は問われません。まずはこの基本を押さえましょう。
介護休暇の対象家族と同居要件の有無

厚生労働省が定める介護休暇制度では、対象家族の居住地は一切問われません。同居していようが別居していようが、対象となる家族であれば介護休暇を取得する権利があるんです。
対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫の7つの続柄です。これらの家族であれば、たとえ県外に住んでいても、海外に住んでいても、介護休暇の対象になります。
逆に対象外となるのは、伯父や伯母、いとこ、甥や姪などです。血縁関係があっても、法律で定められた続柄以外は対象になりません。
同居要件がないということは、実家に帰省して親の介護をする場合や、新幹線や飛行機で移動が必要な遠距離介護の場合でも、正当に介護休暇を使えるということです。会社側は「同居していないから」という理由で取得を拒否できません。
別居中の親や家族の介護で使える具体例

同居していない家族の介護で介護休暇が使えるケースは、実に多様です。
最も多いのは、遠方に住む親の通院付き添いです。親が高齢になり一人で病院に行くのが不安になった場合、子どもが実家に帰って付き添うために介護休暇を取得できます。検査の説明を聞く、診察に同席する、入院の手続きをするといった場面で活用されています。
介護保険の申請や介護サービスの契約といった手続きのための休暇も認められます。地域包括支援センターへの相談、ケアマネージャーとの面談、デイサービスの見学や契約など、介護体制を整えるための活動も介護休暇の対象になるんです。
また、親の入退院時の付き添いや、施設への入所手続き、自宅の介護環境を整えるための準備なども該当します。介護ベッドの搬入立ち会いや、住宅改修の業者との打ち合わせなども含まれます。
介護休暇が使える具体的な場面
病院への通院付き添い、介護保険の申請手続き、ケアマネージャーとの面談、デイサービス等の見学や契約、入退院時の付き添い、施設見学や入所手続き、自宅の介護環境整備、緊急時の駆けつけなど
さらに、親の容態が急変した時の駆けつけや、介護サービス事業者とのトラブル対応なども対象です。「介護をするため」「介護に関わる手続きをするため」という目的であれば、幅広く認められるのが介護休暇の特徴なんです。
介護が必要な状態の判断基準

介護休暇を取得するには、対象家族が「2週間以上、常時介護を必要とする状態」である必要があります。
ただし、要介護認定を受けていることや、医師の診断書の提出は必須ではありません。介護が必要な状態であるという事実があれば、厳格な証明書類がなくても取得できるんです。
「常時介護を必要とする状態」とは、日常生活の基本的な動作に支援が必要な状態を指します。具体的には、食事、排泄、入浴、着替え、移動などに何らかの介助が必要な状態です。認知症で見守りが必要な場合も含まれます。
「2週間以上」という期間は、一時的な風邪や軽い怪我ではなく、継続的な介護が必要な状態を想定しています。ただし、実際には2週間経過を待たずに介護休暇を取得することも可能です。医師から「今後継続的な介護が必要」と言われた時点で対象になります。
【仕事と介護の両立、一人で悩んでいませんか?】
同居していない場合の介護休暇取得条件
同居の有無は問われませんが、介護休暇を取得するためにはいくつかの条件があります。自分が対象になるか確認しましょう。
雇用形態による取得資格の違い

介護休暇は、正社員だけでなくパートタイムやアルバイトでも取得できる制度です。雇用形態による制限はほとんどありません。
取得できる人の条件は、会社に雇用されている労働者であることです。週の所定労働日数や労働時間に関係なく、雇用契約があれば原則として取得できます。正社員、契約社員、パートタイム、アルバイト、すべての雇用形態が対象になるんです。
ただし、「日々雇用される労働者」は対象外です。日雇いで働いている場合は、介護休暇を取得する権利がありません。また、労使協定により、入社6か月未満の従業員や、週の所定労働日数が2日以下の従業員を対象外とすることが認められています。
会社の就業規則で、法律よりも有利な条件が定められている場合もあります。たとえば、入社直後から取得可能としている会社や、週1日勤務でも取得できる会社もあるんです。自社の就業規則を確認してみることをお勧めします。
取得可能な日数と時間単位での利用方法

介護休暇の取得可能日数は、対象家族1人につき年間5日までです。2人以上の家族を介護する場合は、年間10日まで取得できます。
「年間」とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間を指すのが一般的ですが、会社によっては入社日を基準とする場合もあります。就業規則で確認が必要です。
介護休暇の大きな特徴は、時間単位での取得が認められている点です。1日単位だけでなく、1時間単位で細かく取得できるため、柔軟な働き方が可能になるんです。
たとえば、午前中だけ休んで親の通院に付き添い、午後から出勤するといった使い方ができます。また、始業時間を2時間遅らせて介護サービス事業者との打ち合わせに参加したり、終業時間を1時間早めて親の様子を見に行ったりすることも可能です。
ただし、時間単位での取得を認めるかどうかは会社の判断に委ねられている部分もあります。日単位のみとしている会社もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
有給か無給かは会社の就業規則次第

介護休暇の給与の扱いは、法律では無給とされています。つまり、介護休暇を取得した日や時間分の給与を支払う義務は会社にありません。
ただし、会社の就業規則で有給と定めることは可能です。実際に、福利厚生の一環として介護休暇を有給としている企業も増えています。全額支給する会社もあれば、半額支給とする会社もあります。
無給の場合でも、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)は通常通り徴収されます。給与は減りますが、保険料の負担は変わらない点に注意が必要です。
給与が出ないことを理由に介護休暇の取得を諦める必要はありません。有給休暇が残っている場合は、有給休暇を使う選択肢もあります。ただし、有給休暇は自分の都合で使える貴重な権利なので、介護休暇と併用しながら上手に活用することをお勧めします。
介護休暇の申請方法と必要な手続き
同居していない家族の介護で介護休暇を取得する際、どのように申請すればよいのか具体的な手順を見ていきましょう。
申請書の書き方と提出タイミング

介護休暇の申請は、口頭でも法律上は有効です。ただし、実務上は申請書を提出するのが一般的で、会社側も記録を残すために書面での申請を求めることが多いんです。
申請書には、介護が必要な家族の氏名、続柄、取得希望日時、介護が必要な事実などを記載します。会社が用意した申請書のフォーマットがある場合はそれを使い、ない場合は人事部や総務部に相談して必要事項を確認しましょう。
提出のタイミングは、できるだけ早めが望ましいですが、緊急の場合は事後の提出も認められています。たとえば、親が突然倒れて急きょ駆けつける必要が生じた場合、まず口頭で上司に伝え、後日申請書を提出する形でも問題ありません。
申請書に記載する主な項目
申請者の氏名・所属部署、介護対象者の氏名・続柄、介護が必要な状態の概要、取得希望日または希望期間、取得する単位(日単位または時間単位)、時間単位の場合は具体的な時間
時間単位で取得する場合は、何時から何時までという具体的な時間を明記します。また、複数回に分けて取得する予定がある場合は、その旨も伝えておくとスムーズです。
証明書類は必要か不要か

法律上、介護休暇の取得に診断書や要介護認定書の提出は義務付けられていません。介護が必要な事実があれば、証明書類がなくても取得できるんです。
ただし、会社の就業規則で証明書類の提出を求めている場合があります。特に初回の申請時や、長期にわたって取得する場合は、会社側も状況を把握するために何らかの書類を求めることがあるでしょう。
証明書類として認められるのは、医師の診断書、要介護認定書、介護保険被保険者証などです。これらの書類がない場合でも、介護サービス事業者との契約書や、病院の診察券なども参考資料として提出できます。
同居していない家族の介護の場合、「本当に介護が必要なのか」と会社に疑われることを心配する人もいますが、法律で認められた権利ですから、堂々と申請して問題ありません。必要に応じて状況を説明し、理解を求めることが大切です。
会社に拒否された場合の対処法

介護休暇は法律で認められた権利であり、会社は原則として拒否できません。正当な理由なく取得を拒否することは違法です。
もし会社から「同居していないから取得できない」と言われた場合、それは誤った認識です。厚生労働省のウェブサイトや、介護休暇に関するパンフレットを見せながら、同居要件がないことを説明しましょう。
また、「人手不足だから無理」「繁忙期だから困る」といった理由での拒否も認められません。業務の都合を理由に介護休暇の取得を拒否することはできないんです。
取得を拒否されたり、取得したことで不利益な扱いを受けたりした場合は、記録を残しておくことが重要です。いつ、誰に、どのような理由で拒否されたか、どのような不利益を受けたかを記録し、必要に応じて労働局に相談しましょう。
ただし、対立を深める前に、まずは会社との対話を試みることをお勧めします。上司が制度を理解していないだけの場合もあるため、人事部に相談したり、制度の説明資料を提示したりすることで解決することも多いんです。

介護休暇は労働者の権利です。遠慮する必要はありません。必要な時に適切に使うことで、仕事と介護の両立が可能になります。
同居していない家族の介護休暇活用法。まとめ
介護休暇は、同居していない家族の介護でも取得できる制度です。これは法律で明確に認められた労働者の権利であり、会社は正当な理由なく拒否できません。

対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫の7つの続柄で、これらの家族が介護を必要とする状態であれば、どこに住んでいても介護休暇を取得できます。遠方に住む親の通院付き添い、介護サービスの手続き、緊急時の駆けつけなど、幅広い場面で活用できるんです。
取得可能日数は対象家族1人につき年間5日まで、2人以上の場合は年間10日までです。日単位だけでなく時間単位での取得も認められているため、午前中だけ休む、始業時間を遅らせる、終業時間を早めるといった柔軟な使い方ができます。
雇用形態による制限はほとんどなく、正社員、契約社員、パートタイム、アルバイト、派遣社員など、会社に雇用されている労働者であれば原則として取得できます。ただし、日々雇用される労働者は対象外です。
給与については、法律上は無給ですが、会社の就業規則で有給と定めることも可能です。無給だからといって取得を諦める必要はなく、有給休暇との併用も視野に入れながら、必要な時に適切に使うことが大切です。
申請は口頭でも法律上は有効ですが、実務上は申請書を提出するのが一般的です。緊急の場合は事後の提出も認められています。また、診断書や要介護認定書の提出は法律上義務付けられていないため、証明書類がなくても取得できる点を覚えておきましょう。
会社から「同居していないから取得できない」と言われた場合、それは誤った認識です。法律で認められた権利を正しく理解し、必要に応じて厚生労働省の資料を示しながら説明することが大切です。不当に拒否された場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
介護は突然始まることが多く、しかも長期化する傾向があります。
同居していないからといって介護の責任から逃れられるわけではなく、むしろ遠距離介護特有の負担が生じることもあるでしょう。
そんな時に介護休暇を適切に活用することで、仕事を続けながら家族の介護をすることが可能になります。
制度を正しく理解し、遠慮せずに活用していきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。