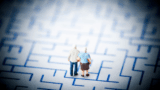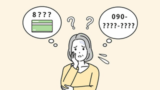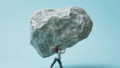今回お話を伺ったのは、神奈川県在住の田中美咲さん(仮名・52歳)。アルツハイマー型認知症と診断された母親(76歳)を3年半自宅で介護している田中さんに、母の記憶がどのように変化していったのか、そして今でも残り続けているものは何なのかを語っていただきました。※ご本人の同意を経て掲載しています。
「母が私の名前を忘れた日、私の世界は崩れ落ちました。でも最近、名前なんかより大切なものが、母の中にずっと残り続けていることに気づいたんです」

始まりは「あれ?お母さん、大丈夫?」だった
73歳の誕生日を迎えた頃、母に最初の違和感を覚えました。電話で話した内容を、すぐに忘れてしまうようになったのです。
「午前中に『今日の夕飯、カレーにするね』って電話したのに、夕方また電話すると『今日の夕飯、何にする?』って聞かれて。最初は『あれ、聞いてなかったのかな』って思う程度でした」
同じ話を繰り返す母に、私はキレてしまった

診断から半年後のある日曜日。母と実家でお茶を飲んでいた時のことです。
「母が隣の家の猫の話をし始めたんです。『あの猫、かわいいのよね』って。へえ、と相槌を打ちました。5分後、また同じ猫の話。『さっき聞いたよ』と言うと、母は『え、そうだったかしら』って」
それから10分おきに、計7回同じ話を聞かされました。
「さすがに7回目で、『お母さん、それもう何回も聞いたから!』って声を荒げてしまったんです」
母の顔が一瞬で曇りました。小さな声で「ごめんね」と謝る母。田中さんは今でもその表情を忘れられないといいます。
「母は何度も『ごめんね、覚えてなくて。ごめんね』って繰り返すんです。私、何てひどいことを言ったんだろうって。母だって好きで忘れているわけじゃないのに」
孫の顔を覚えていない祖母

認知症の進行とともに、昨日や先週の記憶も消えていきました。
「週末に家族みんなで母の家に集まったんです。孫たちも来て、にぎやかに食事をして。でも翌週、母に電話すると『最近みんな来てくれないわね』って寂しそうに言うんです」
写真を見せても「あら、こんな写真あったかしら」と不思議そうな顔をする母。
「一番ショックだったのは、毎週遊びに来ている孫の顔を覚えていなかったことです。孫が『おばあちゃん、僕だよ』って言っても、母は『あら、誰だったかしら』って」
小学生の孫は泣きながら「おばあちゃん、僕のこと嫌いになっちゃったの?」と聞きました。
「違うのよ、おばあちゃんは病気で忘れちゃうだけなの。あなたのこと、大好きなのよ。そう説明しても、子供には理解するのが難しくて」
認知症の一人暮らし、身寄りなしの場合どうすれば?ポイントを解説
でも戦争の記憶は鮮明すぎるほど残っていた

昨日のことは忘れる母が、60年以上前の記憶を語り始めた時、田中さんは驚きました。
「戦時中の疎開先での話を、昨日のことのように語るんです。『あの日は雪が降っていてね、足袋が濡れて冷たくて。でも疎開先のおばあさんが炭火で温めてくれたの』って。感触まで覚えているんですよ」
初めて聞く話も多くありました。
「母が子供の頃、近所の男の子と喧嘩して、泣きながら家に帰ったら、祖母が『やられたらやり返しなさい』って言ったそうなんです。そんなエピソード、認知症になるまで一度も聞いたことなかった」
古い記憶を語る時の母は、目がキラキラと輝いていました。
「今の母は混乱していることが多いけど、昔の話をしている時は別人のように生き生きしているんです。その時間だけは、母が母らしくいられる時間なんだと思います」
「あなた、どちら様?」世界が終わった朝
介護を始めて2年目。田中さんは人生で最も辛い瞬間を経験します。
娘だと分からない母

去年の春のことでした。いつものように「お母さん、おはよう」と声をかけた田中さん。
「母が不思議そうな顔で私を見るんです。そして『あなた、どちら様ですか?』って」
最初は冗談かと思いました。
「『お母さん、何言ってるの。私よ、美咲よ』って笑いながら言ったんです。でも母は真顔で『美咲?美咲はまだ小学生のはずだけど』って」
その瞬間、田中さんの中で何かが崩れ落ちました。
「母の中で、私の時間は小学生の時で止まっていたんです。目の前にいる52歳の私を、母は『美咲』だと認識できない」
必死に「私は美咲よ。あなたの娘よ」と繰り返しましたが、母は首を傾げるばかり。
「『でもあなた、美咲よりずいぶん年上に見えるわ』って母が言った時、もう耐えられなくなって。トイレに駆け込んで、声を殺して泣きました」
「こんなに介護してきたのに」という怒り

トイレの個室で、田中さんは様々な感情に襲われました。
「悲しみだけじゃなかった。怒りもあったんです。『こんなに毎日通って、食事作って、トイレの世話までして。なのに、私のこと覚えてないなんて』って」
同時に、そう思う自分を責める気持ちも湧いてきました。
「『母は病気なのに、なんて自分勝手なことを考えているんだろう』って。でも、やっぱり悲しくて。私の努力は何だったんだろうって」
10分ほど泣いた後、顔を洗って母の部屋に戻りました。
「母は心配そうに私を見て、『どうしたの?顔が赤いわよ』って。私が誰か分からなくても、目の前の人が泣いていたことは分かるんだって思いました」
ココマモを知った経緯

その日から数週間、田中さんは深く落ち込みました。
「『母に忘れられた』という事実が、どうしても受け入れられなくて。誰に相談すればいいのか分からず、一人で抱え込んでいました」
そんなある夜、深夜2時。眠れずに布団の中でスマホを握りしめていました。
「『認知症 忘れられた 辛い』って検索したら、ココマモという介護家族向けのサイトが出てきたんです」
そこには、田中さんと同じように悩んでいる人たちの体験談がたくさん載っていました。
「『母に忘れられて、どうしていいか分からない』『自分を責めてしまう』。私と全く同じことで苦しんでいる人がこんなにいるんだって。初めて『一人じゃないんだ』と思えました」
記事を読み進めていくと、『介護決断サポートキット』というものが紹介されていました。(※キットの詳細は記事の一番下)
「自分の気持ちを整理するワークブックと、半年間毎日届くメール。『これなら誰にも会わずに、自分のペースで向き合えるかも』って思って。藁にもすがる思いで購入ボタンを押しました」
アンケートに答えた後にしばらくしてワークブックが送られてきました。
「最初のページに『迷いの言語化シート』というワークがあって。質問に沿って、自分の気持ちを書き出していきました」
母への愛情、怒り、罪悪感、悲しみ。すべてを書き出しました。
「書き終わった時、頭の中がスッキリしていたんです。自分で書いて整理することで、何に一番苦しんでいるのかが見えてきました」
特に「罪悪感セルフチェックシート」が、田中さんを救いました。
「『母に忘れられたのは私の介護が足りなかったから』と思い込んでいたんです。でもシートの質問に答えていくと、それが完全な思い込みだと分かって。認知症の進行は、私のせいじゃないって」
翌朝から届き始めたメールも、田中さんの支えになりました。
「毎朝7時に届くメールを読むのが日課になって。『あなたは一人じゃない』『休息は介護者の権利です』。そんな言葉に、何度救われたか分かりません」
それから、母への接し方が変わっていきました。
「実際、母は私を見ると笑顔になるんです。『あなた、優しい人ね』『いい人ね』って毎日言ってくれる。名前は忘れても、感情は残るんだって分かってから、介護が少し楽になりました」
認知症の介護で家族が限界を感じている場合。共倒れを防ぐ解決策
母の指が覚えていた60年分の人生
認知症が進行する中でも、田中さんは母の身体が覚えている記憶に何度も驚かされています。
ピアノの前に座った瞬間、別人になった母

母は40年間、ピアノ教師をしていました。先月、デイサービスでの出来事をスタッフから聞いた時、田中さんは驚きました。
「スタッフさんが『弾いてみませんか?』と声をかけたら、母の表情が一変したそうなんです。さっきまでボーッとしていたのに、ピアノの前に座った瞬間、背筋がシャンと伸びて」
そして、楽譜も見ずにショパンの『ノクターン』を弾き始めたといいます。
「動画を見せてもらった時、涙が出ました。娘の顔も忘れた母が、60年前に覚えた曲を完璧に弾いている。指が、すべてを覚えていたんです」
曲が終わると、母は周りから拍手を受けて、照れくさそうに笑ったそうです。
「その笑顔を見て、『ああ、母はまだここにいるんだ』って思えました。頭では色々なことを忘れても、身体が覚えている記憶は消えないんだって」
洗濯物をたたむ母の手が美しかった

今も週に数回、田中さんは母と一緒に家事をします。
「『お母さん、これたたんでくれる?』って洗濯物を渡すと、母の手が自然に動き始めるんです」
タオルを手に取り、縦半分に折り、さらに横半分に折る。その動作は淀みなく、美しいリズムを持っています。
「『これ、どうやるんだっけ?』って聞きながらも、手は完璧に動いている。50年間毎日やってきた動作は、身体が覚えているんです」
たたみ終わった洗濯物を見て、母が嬉しそうに笑います。
「『上手にできたわね』って母が言うんです。『お母さん、すごく上手だよ。ありがとう』って伝えると、母は本当に嬉しそうで。誰かの役に立てること、それが母の自尊心を守っているんだと思います」
今も母の中に残り続けているもの
認知症が進行する中でも、田中さんは母の中に確かに残り続けているものを感じています。
『この道』を聴くと涙ぐむ母

最近、母は言葉数が減ってきました。それでも、音楽への反応だけは変わりません。
「母が一番好きだった『この道』という童謡を流すと、目がうっすらと潤むんです。口は動かない、言葉も出ない。でも、確かに何かを感じているんだって分かります」
先週も、一緒にその歌を聴きました。
「母の手を握りながら『お母さん、この歌好きだったよね』って話しかけたら、ほんの少しだけ手を握り返してくれたんです。歌詞も、メロディーの名前も忘れても、この歌に込められた感情だけは残っているんだって」
手を握ると、いつも握り返してくれる

言葉でのコミュニケーションが難しくなっても、身体的な触れ合いへの反応は今も残っています。
「毎日母の手を握ります。すると、母も握り返してくれる。目は開けていなくても、手のぬくもりは感じているんだと思います」
先日、施設のスタッフがこう言いました。
「『美咲さんが来ると、お母様の表情が穏やかになるんですよ』って。私が誰か分かっているかは分からない。でも、優しく触れてくれる人だということは感じてくれているんだと思います」
母が見せてくれる小さな笑顔

つい先週のことです。いつものように母の横に座って手を握っていた時のことでした。
「『お母さん、私よ。美咲よ。いつもそばにいるからね』って話しかけたら、母が小さく笑ったんです」
目は開けていない、声も出ない。それでも、確かに笑顔でした。
「その瞬間、今までの介護が報われたと思いました。母は私が誰か分からなくても、この人といると安心するという感情だけは、まだ持ち続けてくれているんだって」
田中さんは、これからもこの介護を続けていくと決めています。
「辛いこともたくさんあります。でも、母の小さな笑顔を見るたびに、『ああ、母はまだここにいるんだ』って思えるんです」

記憶は消えても、感情は残る。家族の愛情は、言葉や記憶を超えて伝わり続けるんですね。
介護の中で私が学んだこと
3年半の介護を続ける中で、田中さんは多くのことを学びました。
「覚えていてほしい」を手放した日

「最初は『母に私のことを覚えていてほしい』『娘として認識してほしい』って、ずっと思っていました」
しかし、介護決断サポートキットのワークに取り組んだ中で、その期待が自分を苦しめていることに気づきました。
「『罪悪感を書き換えるワーク』で、『無理に覚えていてもらおうとしなくていい。お母様が安心して過ごせることの方が大切』という一文があって。ああ、そうだったんだって」
それからは、毎回初対面のように接するようにしています。
「母が『どちら様ですか?』と聞いたら、『美咲です。お母さんの娘です』って笑顔で答える。何度聞かれても、優しく答え続ける。そう決めたら、気持ちが楽になりました」
できることを一緒にやる幸せ

「認知症だから何もできない」。そう思い込んでいた自分を反省したといいます。
「洗濯物をたたむ、野菜を洗う、お茶を入れる。母ができることは、まだたくさんあるんです」
一緒にできることをやる時間が、お互いにとって大切な時間になっています。
「『お母さん、これお願いできる?』って頼むと、母は本当に嬉しそうにやってくれます。誰かの役に立てること、それが母の自尊心を守っているんだと思います」
一人で抱え込まないと決めた

田中さんは、介護者自身のケアの重要性を痛感しています。
「介護を始めた頃は『母のために全てを犠牲にするべきだ』って思っていました。でも、それは間違いでした」
4ヶ月前、ココマモで介護決断サポートキットを知って購入してから、考え方が変わったそうです。
「キットの『自分時間の可視化ワーク』で、自分の時間がゼロだと気づいて。このままじゃ私が倒れるって、数値で分かったんです」
毎朝届くメールも、田中さんの支えになっています。
「『あなたには、あなたの人生を守る権利がある』『休息は介護者の権利です』。そんなメッセージが毎日届くだけで、一人で抱え込まないと決められました」
月に数日はショートステイも利用しています。
「最初は罪悪感がありました。でも、離れることで心がリセットされて、また優しく母に接することができる。休息は介護者の権利なんだって、今は分かります」
介護うつの症状とは?早期発見のためのチェック項目と適切な対処法
同じ悩みを抱えている方へ
田中さんは、認知症介護で苦しんでいる方に伝えたいことがあるといいます。
一人で抱え込まないで

「母に忘れられた時、本当に辛くて、誰かに話したかった。でも、この悲しみを理解してくれる人が周りにいなかったんです」
地域包括支援センターにも相談しましたが、深い感情を吐き出す場所が見つかりませんでした。
「『認知症だから仕方ない』。それは頭では分かっているんです。でも、心が納得できない。この矛盾した気持ちを、どこで吐き出せばいいか分からなかった」
そんな時、ココマモというサイトで介護決断サポートキットを知りました。
「同じように悩んでいる人の体験談を読んで、このキットのことを知って。ワークシートに書き込んでいくだけで、自分の気持ちが整理されていく。そして毎朝届くメールで『あなたの気持ちは当然です』と言ってもらえただけで、こんなに心が軽くなるんだって思いました」
名前より大切なものがある

田中さんが最も伝えたいこと。それは「名前を覚えていることが全てではない」ということです。
「母は私の名前を忘れました。顔も忘れました。でも、『この人といると安心する』という感情だけは、今も残っているんです」
名前や関係性より、もっと深いところで繋がっている。
「だから、もし今、家族に忘れられて悲しんでいる方がいたら伝えたい。あなたの愛情は、必ず伝わっていますって」
認知症で最後まで残る記憶を知って。まとめ
田中さんの3年半の介護体験から見えてきたこと。それは、認知症で失われるものと、決して失われないものがある、ということでした。

さっきの記憶、昨日の記憶、そして大切な人の名前さえも忘れていく。それが認知症の現実です。
「母は私の名前も顔も忘れてしまいました。でも、私といる時の安心感だけは、今も持ち続けてくれている。それが分かっただけで、介護を続ける力が湧いてきます」
認知症の方から忘れられることは、家族にとって大きな悲しみです。でも、名前や顔を忘れても、一緒にいる時の幸せな感情は残り続けます。
だからこそ、毎日の優しい言葉がけ、温かい触れ合い、一緒に過ごす穏やかな時間が意味を持つのです。
「母が見せてくれる小さな笑顔。その笑顔が教えてくれます。家族の愛情は、記憶を超えて、心の一番深いところに残り続けるんだって」
もし今、認知症の家族から忘れられて悲しんでいる方、どう接すればいいか分からず悩んでいる方がいらっしゃいましたら。
田中さんのように一人で抱え込まず、『介護決断サポートキット』のような具体的なツールを使って、自分の気持ちを整理してみてください。あなたの気持ちは決して間違っていません。そして、新しい関わり方が必ず見つかるはずです。
「情報はわかった。でも…私はどうすればいいの?」

この記事を読んで、少しは気持ちが楽になったかもしれません。
でも、こんな思いが残っていませんか?
- 「この先、私はどうなってしまうんだろう…」
- 「家族に相談しても『お前に任せる』って…」
- 「もう限界なのに、誰もわかってくれない」
知識は増えた。気持ちも少し整理できた。
でも、決断はできない。
実は、87%の介護家族が同じ悩みを抱えています。
地域包括に行っても、ケアマネに相談しても、
「最終的な判断は、ご家族で」
と言われるだけ。
誰も、「あなたの場合はこう決断すべき」とは教えてくれません。
だから、夜中に天井を見つめて一人で悩み続けることになるんです。
もし、「あなた専用の判断基準」があったら?

想像してみてください。
- 施設か在宅か、感情ではなく事実で判断できる
- 家族との話し合いが、感情論ではなく具体案で進む
- 「親を見捨てる」という罪悪感から解放される
- 自分の人生を取り戻しながら、介護も続けられる
🌿 18年間で3,200件以上の相談に応えた介護福祉士が、「迷いを整理する方法」を体系化しました
『介護決断サポートキット』
制度の解説ではありません。メンタルケアや体験談でもありません。
「あなた自身の判断基準の作り方」だけに特化した、 日本で唯一のキットです。
すでに2,847名の介護家族が、このキットで決断を前に進めました。
「3年間迷い続けた決断が、1週間で決まりました」
「罪悪感があっても、決断していいと気づけた」
「家族会議が、初めて前に進んだ」
もう一人で抱え込まなくていい。
あなたには、あなたの人生を守る権利があります。