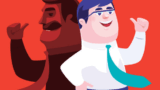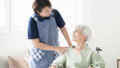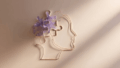「ケアマネの態度にむかつく」
「何様のつもりなの?」
「こんなに横柄な対応をされるなんて」
介護を頑張っているあなたが、そう感じてしまうことがあるかもしれません。

実は、ケアマネにむかつくと感じている家族は少なくありません。上から目線の態度、説明不足、希望が反映されないケアプランなど、様々な理由でストレスを抱えている方がいるんです。
この記事では、ケアマネにむかつく理由を整理し、感情的にならずに問題を解決する方法をお伝えします。担当変更の手順や苦情申し立ての方法まで、具体的な対処法をご紹介します。
ケアマネにむかつくと感じる主な理由
まずは、なぜむかつくと感じるのか、その理由を冷静に見ていきましょう。
上から目線の態度や何様という印象を受ける原因

ケアマネの上から目線の態度に、むかつくと感じる方は多いです。
「これはできません」「それは無理です」と一方的に断られたり、「こうするべきです」と決めつけられたり。利用者や家族の希望を聞かず、専門家としての判断を押し付けてくる態度に、何様のつもりなのかと感じてしまうんです。
このような態度の背景には、ケアマネの責任感の強さがあることも事実です。ケアプランを作成する責任があり、介護保険制度の中で適切なサービスを提供しなければならないというプレッシャーから、自信が独断的な態度に見えてしまう場合があります。
ただし、説明の仕方が下手なだけで、悪意はない場合もあります。専門職としての自信と、コミュニケーション能力の不足が重なって、むかつく態度に見えてしまうケースも少なくないんです。
コミュニケーション不足と説明の欠如

ケアマネとのコミュニケーション不足も、むかつく原因の一つです。
連絡しても折り返しがない、約束した訪問に来ない、重要な変更を事前に相談なく決めてしまう。このような対応をされると、自分たちが軽視されていると感じてしまいます。
また、説明不足も大きな問題です。なぜそのサービスを勧めるのか、なぜ希望が叶わないのか、きちんと説明してくれないまま「これで行きます」と一方的に決められる。理由がわからないまま決定されることへの不満が、むかつくという感情につながるんです。
ケアマネは多くのケースを抱えており、忙しさから対応が雑になっている可能性もあります。ただし、忙しいことは利用者には関係ありません。適切な説明とコミュニケーションは、ケアマネの基本的な役割なんです。
希望が反映されないケアプランへの不満

家族の希望が反映されないケアプランも、むかつく大きな原因です。
「もっと訪問介護の回数を増やしてほしい」「このデイサービスは合わないから変更したい」と伝えても、「予算の関係で」「空きがないので」と断られる。確かに介護保険には限度額があり、全ての希望が叶うわけではありません。
しかし、問題は断り方なんです。なぜできないのか丁寧に説明し、代替案を提示してくれれば納得できます。ところが、一方的に不可能だと決めつけて、他の選択肢も示さない態度に、むかつくと感じてしまうわけです。
希望が反映されない理由
介護保険の限度額を超えている、希望するサービスの空きがない、本人の状態に合わないとケアマネが判断、事業所との関係で特定のサービスを優先、ケアマネの経験不足で選択肢を知らない
また、併設サービスばかり勧めてくる場合も要注意です。自分の事業所の利益を優先し、利用者に最適なサービスを探そうとしない姿勢は、プロとして問題があります。
ケアマネの態度が悪いと感じた時の冷静な対処法
むかつくと感じた時、感情的に対応しても状況は改善しません。冷静に対処する方法を見ていきましょう。
感情的にならず具体的に不満を伝える方法

まず大切なのは、感情的にならず具体的に伝えることです。
「むかつく」「態度が悪い」といった感情をそのままぶつけても、相手は防御的になるだけです。代わりに、何が問題なのかを具体的に伝えましょう。「先週お願いした件について、まだ返事がありません。いつ頃返答いただけますか」といった具合です。
不満を伝える前に、メモを作成することをお勧めします。いつ、どのような対応があったのか、何が問題だと感じたのか、どうしてほしいのか。事実と希望を整理してから話すことで、冷静に伝えられます。
また、「私は○○だと感じています」という主語を「私」にする伝え方(アイメッセージ)も有効です。「あなたの態度が悪い」ではなく、「私は説明が不十分だと感じています」と伝える方が、相手も受け入れやすくなります。
やり取りを記録して証拠を残す重要性

ケアマネとのやり取りは記録として残すことが大切です。
日付、時間、誰が、何を言ったか、どう対応したか。これらを具体的にメモしておきましょう。後で「そんなこと言っていない」と否定されても、記録があれば事実を示せます。
可能であれば、重要な連絡はメールや書面で行うことをお勧めします。電話だと記録が残りませんが、メールなら証拠になります。口頭で伝えたことも、後からメールで確認を送ると良いでしょう。
記録に残すべき内容
日時と場所、誰とのやり取りか、具体的な会話内容、約束した事項、問題だと感じた対応、その時の状況や証人の有無
重要な話し合いの際は、家族など第三者に同席してもらうのも有効です。後で「言った」「言わない」の水掛け論になることを防げます。
事業所の管理者への相談という選択肢

担当ケアマネに直接言いづらい場合は、事業所の管理者に相談しましょう。
居宅介護支援事業所には必ず管理者がいます。担当ケアマネの対応に問題がある場合、管理者に相談することで、指導や改善を促してもらえる可能性があるんです。
相談する際は、記録を基に具体的な事実を伝えましょう。「態度が悪い」という抽象的な訴えより、「○月○日の訪問時、このような対応がありました」と具体的に説明する方が、管理者も対応しやすくなります。

管理者への相談は、担当変更の前段階としても有効です。まず改善を求めて、それでもダメなら変更を検討するという流れが自然ですよ。
悪いケアマネージャーの見極め方と対処法とは?知っておきたい知識
むかつくケアマネを変更する具体的な手順
改善が見込めない場合、担当変更を検討するのは正当な選択です。
同じ事業所内で担当者を変更する方法

まず検討したいのが、同じ事業所内での担当変更です。
事業所に複数のケアマネジャーがいる場合、管理者に相談して担当を変更してもらえる可能性があります。「現在の担当者とコミュニケーションがうまくいかないので、別の方にお願いできますか」と伝えれば良いでしょう。
この方法のメリットは、ケアプランの引き継ぎがスムーズなことです。同じ事業所内なので、これまでの経過や利用しているサービスの情報が共有されやすく、利用者への負担が少なくて済みます。
ただし、小規模な事業所ではケアマネが1〜2人しかおらず、担当変更が難しい場合もあります。その場合は、事業所ごと変更することになります。
事業所ごと変更する際の注意点

事業所ごと変更する場合、いくつかの注意点があります。
まず、新しい事業所を探す必要があります。市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターで事業所リストをもらい、いくつか候補を選んでください。新しい事業所と面談し、納得できれば契約を結びます。
その後、現在の事業所に変更の意思を伝えます。詳しい理由を説明する必要はありません。「家族の事情で」「別の事業所に変更します」程度で十分です。円満に終了することを心がけましょう。
変更には1〜2週間程度かかることが多いです。その間もサービスは継続されますので、安心してください。
地域包括支援センターへの相談手順

どこに相談すればいいかわからない時は、地域包括支援センターが頼りになります。
地域包括支援センターは、高齢者に関する様々な相談を受け付ける総合窓口です。ケアマネとのトラブルについても相談できますし、新しい事業所の紹介もしてくれます。
相談する際は、これまでの経緯を時系列で説明できるよう準備しておきましょう。記録があれば持参してください。地域包括支援センターの職員が、客観的な立場からアドバイスしてくれます。
地域包括支援センターでできること
ケアマネとのトラブルについての相談、新しい事業所の紹介、事業所間の調整、必要に応じて現在の事業所への指導、市区町村への報告、今後の対応方法のアドバイス
地域包括支援センターの対応がひどいと感じた時の対処法。解決策は?
ケアマネとの関係改善が難しい時の最終手段
それでも問題が解決しない場合、より公的な対応を検討する必要があります。
市区町村の介護保険窓口への苦情申し立て

深刻な問題がある場合、市区町村の介護保険窓口に正式な苦情を申し立てることができます。
介護保険サービスについての苦情は、市区町村が受け付けています。書面で苦情を提出すると、市区町村が事業所に対して調査や指導を行います。悪質な場合は、事業所の指定取り消しといった処分もあり得るんです。
苦情申し立てには、これまでの記録が重要になります。いつ、どのような対応があり、どう問題だったのか。具体的な事実に基づいた苦情でなければ、行政も動きづらいからです。
ただし、苦情申し立ては最終手段です。まずは話し合いや担当変更で解決を図り、それでもダメな場合に検討してください。
第三者を交えた話し合いの効果

当事者だけでは解決が難しい場合、第三者を交えた話し合いが効果的です。
地域包括支援センターの職員や、市区町村の介護保険担当職員に同席してもらい、三者で話し合うことで、冷静な議論ができます。第三者がいることで、ケアマネも誠実に対応せざるを得なくなるんです。
話し合いでは、感情的にならず事実を淡々と伝えることが大切です。「こういう対応があり、このように困っています。改善してほしい点は○○です」と、具体的に要望を伝えましょう。
記録と証拠に基づいた正式な対応依頼

どうしても改善されない場合、記録と証拠に基づいて正式な対応を依頼します。
これまで記録してきた内容を整理し、時系列でまとめてください。メールのやり取り、メモ、第三者の証言など、証拠となるものを揃えます。そして、市区町村の介護保険課に書面で提出するんです。
書面には、問題の経緯、具体的な被害や困りごと、これまでの対応と結果、改善を求める内容を明確に記載します。感情的な表現は避け、事実を客観的に記述することが大切です。

正式な苦情は重大な手続きですが、正当な権利です。我慢し続ける必要はありません。適切な介護サービスを受けるために、必要な行動を取ってください。
ケアマネにむかつく気持ちへの対処法。まとめ
ケアマネにむかつくと感じることは、決して珍しいことではありません。上から目線の態度、コミュニケーション不足、希望が反映されないケアプランなど、様々な理由で不満を抱えている家族がいるんです。

むかつくと感じた時、最も大切なのは感情的にならず冷静に対処することです。「態度が悪い」という抽象的な訴えではなく、「いつ、どのような対応があり、何が問題だったのか」を具体的に伝えましょう。
記録を残すことも忘れないでください。日時、内容、状況を具体的にメモしておくことで、後で説明する際の証拠になります。可能であれば、メールなど形に残る方法でやり取りすることをお勧めします。
改善が見込めない場合、担当変更は正当な選択です。まず事業所の管理者に相談し、同じ事業所内での変更を検討してください。それが難しければ、事業所ごと変更することも可能です。我慢し続ける必要はありません。
地域包括支援センターは、ケアマネとのトラブルについても相談できる総合窓口です。新しい事業所の紹介や、現在の事業所との調整もしてくれます。一人で悩まず、専門機関に相談してください。
それでも改善されない場合は、市区町村の介護保険窓口に正式な苦情を申し立てることもできます。これは最終手段ですが、適切な介護サービスを受けるための正当な権利です。
ケアマネの態度の背景には、責任感の強さや業務の忙しさがある場合もあります。ただし、それは利用者には関係ありません。丁寧な説明とコミュニケーションは、ケアマネの基本的な役割なんです。
むかつくという感情を我慢する必要はありません。ただし、感情的に対応しても状況は改善しません。冷静に、具体的に、段階的に対処することが、問題解決への近道です。
介護は長期戦です。信頼できるケアマネと良い関係を築くことが、安心の介護生活につながります。合わないと感じたら、遠慮なく変更を検討してください。あなたと家族にとって最適なサポートを受ける権利があるのです。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。