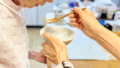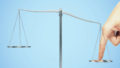「何度交換しても、オムツから漏れてしまう…」
「夜中に何度も起きて、シーツを洗う毎日」
「どうすれば漏れを防げるの?もう限界…」
そんな悩みを抱えていませんか?

実は、オムツの漏れは当て方や選び方の工夫で、大幅に減らすことができます。多くの介護者が同じ悩みを抱えながら、試行錯誤を重ねて漏れない方法を見つけています。
この記事では、介護オムツが漏れてしまう原因を整理し、漏れを防ぐための具体的な方法をお伝えします。当て方のコツ、製品の選び方、夜間対策まで、すぐに実践できるテクニックをご紹介します。
介護オムツが漏れてしまう主な原因
オムツの漏れには、必ず原因があります。まずは、なぜ漏れてしまうのか、その理由を一緒に見ていきましょう。
サイズが合っていない

オムツ漏れの最も多い原因は、サイズが合っていないことなんです。
大きすぎるオムツは、太ももや腰周りに隙間ができて、そこから漏れてしまいます。「大きめの方が安心」と思って選んでいると、かえって漏れやすくなるんですよね。
逆に小さすぎると、圧迫されて不快感が出たり、ギャザーが機能しなくなったりします。体型が変わってきたら、こまめにサイズを見直すことが大切です。
ギャザーが立っていない

オムツの内側にある立体ギャザーは、横漏れを防ぐ堤防の役割を果たしています。
このギャザーが寝てしまっていると、堤防がない状態になって、尿が横から漏れ出してしまうんです。パッドを入れる時や装着する時に、ギャザーを押し込んでしまっているケースが多くあります。
ギャザーは装着前に、指で軽くなぞって立たせる、横に引っ張って立体的にするなど、ちょっとした工夫で機能するようになります。
吸収量が足りていない

尿量に対してオムツやパッドの吸収量が足りないと、当然漏れてしまいます。
特に夜間は長時間の使用になるため、昼用と同じ製品では吸収量が足りないことが多いんです。また、水分摂取量が多い方や、利尿剤を服用している方は、通常よりも尿量が増えるため注意が必要です。
吸収量の目安は製品パッケージに記載されていますが、実際の尿量は個人差が大きいため、漏れが続く場合は吸収力の高い製品への切り替えを検討しましょう。
介護オムツの漏れない当て方の基本
オムツの漏れを防ぐには、正しい当て方をマスターすることが最も重要です。ここでは、タイプ別の漏れない当て方をご紹介します。
パンツタイプの漏れない当て方

パンツタイプは立って履ける方に便利ですが、背中側の引き上げが甘いと漏れやすくなります。
パンツタイプの当て方手順
1. 前後を確認し、片足ずつ通して太ももまで上げる。2. 左右交互にお尻を浮かせて、少しずつウエストまで引き上げる。3. 背中側もウエストまでしっかり引き上げる。4. パッドを使う場合は、ギャザーを潰さないように入れる。5. 太もも周りのギャザーが内側に折れ込んでいないか確認する。
特に重要なのは、背中側の引き上げです。前側はしっかり上げても、背中側が下がっていると、そこから漏れてしまいます。介助する場合は、背中側を最後にもう一度確認しましょう。
テープタイプの漏れない当て方

テープタイプは寝たきりの方に適していますが、テープの止め方次第で漏れやすさが大きく変わります。
テープタイプの当て方手順
1. パッドをギャザーの内側にセットする。2. 体を横向きにし、オムツの中心を背骨に合わせて置く。3. 上側のテープが腰骨より上になるよう位置を調整。4. 仰向けに戻し、パッドとオムツを太ももの付け根まで引き上げる。5. ギャザーを脚の付け根に沿わせる。6. シワを伸ばしながら、下側のテープをクロスで止める。7. 上側のテープもクロスで止める。
テープの止め方は、必ず「クロス止め」にしましょう。平行に止めるよりも、体へのフィット感が格段に上がります。下側のテープを斜め上に、上側のテープを斜め下に止めることで、しっかり固定できます。
パッドの正しい使い方

尿取りパッドを併用することで、交換の手間が減り、経済的にもなります。ただし、使い方を間違えると漏れの原因になるんです。
まず、パッドの前後を確認しましょう。片方が幅広いパッドの場合、男性と女性で向きが違います。女性の場合は後ろ側(お尻側)を幅広い方に、男性の場合は前側(お腹側)を幅広い方にします。
パッドのギャザーは、装着前にしっかり立たせることが重要です。両端を持って軽く引っ張ると、ギャザーが立ち上がります。
親の介護でお金がない時の対処法。公的支援制度や負担軽減策はある?
夜間のオムツ漏れを防ぐ方法
夜間の漏れ対策は、昼間とは別のアプローチが必要です。長時間の使用に耐えられる製品選びと装着の工夫が重要になります。
夜用の高吸収製品を選ぶ

夜間の漏れを防ぐには、夜用の高吸収製品を使うことが最も効果的です。
夜用製品は、昼用と比べて吸収量が2〜3倍多く、幅や長さも大きめに設計されています。「アテント 夜1枚安心パンツ」は8回分(約1200ml)の吸収力があり、背モレ防止ポケット付きで安心です。
パッドタイプでは、「ライフリー 一晩中あんしん尿とりパッド 夜用スーパー」が約900ml(6回分)を吸収し、ワイド設計で横漏れも防ぎます。「カミ商事 いちばん ビッグパッド夜用」も同等の吸収力で、全面通気性に優れています。
就寝前の水分調整

夜間の尿量を減らすために、就寝前の水分調整も効果的です。
寝る2〜3時間前からは、水分摂取を控えめにしましょう。ただし、脱水にならないよう、日中はしっかり水分を摂ることが大切です。利尿作用のあるカフェイン飲料やアルコールは、夕方以降は避けるようにします。
また、就寝前にトイレに行く習慣をつけることで、夜間の尿量を減らせます。
夜間の装着の工夫

夜間は寝返りによってオムツがずれやすくなります。装着の工夫で漏れを防ぐことができます。
テープタイプの場合は、通常よりも少しきつめに止めることで、寝返りによるずれを防げます。ただし、締めすぎは血行不良の原因になるため、指が1本入る程度の余裕は必要です。
パンツタイプの場合は、就寝前にもう一度フィット感を確認しましょう。特に背中側が下がっていないか、太もも周りのギャザーが立っているかをチェックします。
防水シーツを併用することで、万が一漏れてもベッドを汚さずに済みます。洗い替えを用意しておくと、夜中の交換も楽になります。

夜用製品と装着の工夫を組み合わせることで、朝まで安心して眠れるようになりますよ。
オムツ漏れ対策で見落としがちなポイント
基本的な当て方をマスターしても、細かいポイントを見落としていると漏れてしまうことがあります。ここでは、意外と見落としがちな対策をご紹介します。
肌着を挟み込まない

パンツタイプのオムツを履く時、肌着の裾を挟み込んでしまうと、その肌着を伝って尿が漏れることがあります。
オムツを装着する際は、肌着がオムツの外に出ているか、必ず確認しましょう。特に長めの肌着を着ている場合は注意が必要です。肌着をまくり上げてからオムツを履くようにすると、挟み込みを防げます。
交換のタイミングを見直す

「まだ大丈夫そう」と交換を先延ばしにしていると、吸収量の限界を超えて漏れてしまうことがあります。
オムツやパッドは、吸収量の7〜8割程度で交換するのが理想的です。満タンになる前に交換することで、漏れを防ぎやすくなります。
排泄のタイミングがある程度決まっている方は、その前後に交換することで、漏れのリスクを大幅に減らせます。食後1〜2時間後、起床後、就寝前など、生活リズムに合わせた交換スケジュールを作りましょう。
製品の組み合わせを最適化する

オムツとパッドの組み合わせ方次第で、漏れにくさが大きく変わります。
テープタイプのオムツには、テープ用パッドを使いましょう。パンツ用パッドは形状が異なるため、テープタイプとの相性が悪く、隙間ができやすくなります。
同じメーカーの製品同士を組み合わせると、サイズや形状の相性が良いことが多いです。ただし、他メーカーの組み合わせでも問題ない場合もあるため、実際に試してみることが大切です。
軟便が多い方は、軟便専用パッドを使うことで、漏れを防ぎやすくなります。通常のパッドは液体の吸収に特化しているため、軟便には対応しきれないことがあるんです。
親の介護をしない兄弟と相続問題。公平な遺産分割を実現するには?
排泄介助の負担と向き合う
ここまで、オムツの漏れを防ぐ方法をご紹介してきました。
でも、正直にお伝えしたいことがあります。
排泄介助は、介護の中で最も精神的・体力的な負担が大きい部分なんです。
技術よりも心の負担が大きい現実

オムツの当て方をどれだけ工夫しても、夜中に何度も起きてシーツを交換する日々が続くと、心身ともに疲弊していきます。
「漏れ対策」そのものよりも、「夜中に何度も起きる」「介護で眠れない」「毎日シーツを洗う」という状況の方が、実は深刻なケースも多いんです。
親や配偶者の排泄を介助することに、罪悪感や戸惑いを感じる方も少なくありません。「こんなことを思ってはいけない」と自分を責めながら、一人で抱え込んでしまう方が本当に多いんです。
使える制度とサービスを活用する

排泄介助の負担を軽減するために、使える制度やサービスは積極的に活用しましょう。
訪問介護サービスでは、排泄介助も依頼できます。プロの介護職員に任せることで、技術的にも安心ですし、自分の休息時間も確保できます。
夜間対応型訪問介護を利用すれば、夜中のオムツ交換も依頼できます。「夜だけでも任せたい」という気持ちは、決してわがままではありません。
ショートステイを利用することで、数日間だけでも排泄介助から解放される時間を作ることができます。「親を施設に預けるなんて」と罪悪感を持つ必要はありません。介護者が休息を取ることは、長期的に介護を続けるために必要なことなんです。
レスパイトケアとは。簡単にわかる基本知識。種類・費用・利用方法は?
介護オムツの漏れない方法。まとめ
介護オムツの漏れは、サイズ選び、当て方、製品の組み合わせなど、様々な工夫で防ぐことができます。

最も大切なのは、適切なサイズを選び、ギャザーをしっかり立たせ、体にフィットさせることです。この基本を押さえるだけで、漏れは大幅に減らせます。
夜間の漏れ対策では、夜用の高吸収製品を使い、就寝前の水分調整と装着の工夫を組み合わせることで、朝まで安心して眠れるようになります。
ただし、どれだけ技術を磨いても、排泄介助の負担は大きいものです。
特に夜間の介助で睡眠不足が続くと、心身ともに限界を迎えてしまいます。
一人で抱え込まず、訪問介護やショートステイなど、使える制度は積極的に活用しましょう。プロに任せることは、決して親への愛情がないわけではありません。むしろ、長期的に介護を続けるために必要な選択なんです。
「もう限界かも」と感じた時は、一人で悩まずに相談してください。
排泄介助の悩みは、なかなか人に話しづらいものです。
でも、同じような悩みを抱えている人は数多くいますし、サポートしてくれる専門家も存在します。
オムツの漏れ対策と同時に、あなた自身の心と体も大切にしてください。

排泄介助は本当に大変です。技術も大事ですが、あなた自身が潰れてしまわないことが一番大切なんですよ。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。