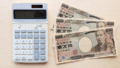「親が特別養護老人ホームに入所することになったけど、家族全員が生活保護を受けなければならないの?」「特養の費用が払えず生活が苦しいが、世帯分離すれば親だけ生活保護を受けられる?」「世帯分離の基準が厳しいと聞いたけど、どんな場合に認められるの?」
特別養護老人ホーム(特養)への入所費用は、家族にとって大きな経済的負担となります。その費用が家計を圧迫し、生活が困窮してしまう場合、生活保護と世帯分離を活用することで、入所者本人のみが生活保護を受けられる可能性があります。
この記事では、特別養護老人ホーム入所時の生活保護と世帯分離の基本、認められる基準とケース、認められないケース、具体的な手続きの流れまで、詳しく解説します。厳格な審査を通過し、適切に制度を利用するための完全ガイドです。
特別養護老人ホーム入所時の生活保護と世帯分離の基本
まず、特別養護老人ホーム入所に伴う生活保護と世帯分離の基本的な仕組みを理解しましょう。
生活保護における世帯分離の意味と目的

生活保護は、世帯単位で認定されるのが原則です。同居している家族全員の収入と資産を合算し、世帯全体の生活費が最低生活費を下回る場合に生活保護が適用されます。
しかし、この原則を厳格に適用すると、介護が必要な高齢者が施設に入所した際の費用負担により、働いている家族まで生活保護を受けなければならなくなることがあります。これでは、家族の自立を阻害し、かえって生活保護受給者を増やしてしまいます。
そこで、生活保護における世帯分離という仕組みがあります。これは、同居していても、または施設に入所していても、生活保護の認定上は「別世帯」として扱い、入所者本人のみが生活保護を受けることを可能にする制度です。
世帯分離が認められれば、入所者の特養費用は生活保護から支給され、同居家族は生活保護を受けずに自立した生活を続けることができます。
特別養護老人ホーム入所で世帯分離が必要になる理由

特別養護老人ホームの入所費用は、月額6万円から15万円程度が一般的です。年金だけでは賄えない場合、家族が不足分を負担することになります。
例えば、父親が特養に入所し、月額費用が12万円、父親の年金が月8万円の場合、毎月4万円の不足が生じます。これを子ども世帯が負担し続けると、年間48万円、10年間で480万円もの負担となります。
子ども世帯が住宅ローンを抱えていたり、孫の教育費がかかる時期であったりすると、この負担は家計を圧迫し、世帯全体が要保護状態に陥る可能性があります。
このような場合、世帯分離によって父親のみが生活保護を受けることができれば、特養費用は生活保護から支給され、子ども世帯は自立した生活を維持できます。これが、特養入所時に世帯分離が必要となる典型的な理由です。
特養入所で世帯分離が必要となる具体例
状況:父親(75歳)が特養入所、特養費用月12万円、父の年金月8万円
不足額:月4万円を子ども世帯が負担
子ども世帯:夫婦と子ども2人、住宅ローン月9万円、夫の収入月35万円
問題点:特養費用負担により生活が圧迫、教育費も捻出困難
解決策:世帯分離により父のみ生活保護受給、特養費用は生活保護から支給
住民票の世帯分離と生活保護の世帯分離の違い

「世帯分離」という言葉には、実は2つの異なる意味があります。混同されやすいので、明確に区別しましょう。
住民票の世帯分離:
市区町村の住民課で手続きをして、同じ住所に住んでいても住民票上の世帯を分けることです。この手続きは比較的簡単で、住民異動届を提出すればすぐに完了します。
住民票の世帯分離は、介護保険の負担限度額認定や高額介護サービス費の軽減などを目的として行われることが多く、住民税非課税世帯となることで様々な優遇措置を受けられます。
生活保護の世帯分離:
生活保護における世帯分離は、住民票とは関係なく、生活の実態に基づいて判断されます。福祉事務所が、収入状況、資産状況、生活実態などを総合的に審査し、「この世帯を分けて認定することが適切か」を判断します。
住民票で世帯分離をしていても、生活保護の世帯分離が自動的に認められるわけではありません。逆に、住民票が同一世帯であっても、生活保護の世帯分離が認められることもあります。
老人ホームの費用が払えない時は?早期相談と公的支援で解決する方法
【特養の費用負担で、家族の生活まで破綻しそうな方へ】
特別養護老人ホームで世帯分離が認められる基準
生活保護における世帯分離は、厚生労働省の「生活保護実施要領」に基づいて判断されます。特養入所時に認められる具体的な基準を解説します。
要保護世帯となる場合の判断基準

世帯分離が認められる最も基本的な基準は、「世帯分離を行わなければ、その世帯全体が要保護世帯となる場合」です。
要保護世帯とは、世帯の収入が最低生活費を下回り、生活保護を受けなければ生活できない状態の世帯を指します。特養入所費用の負担により、同居家族まで含めた世帯全体が要保護状態になる場合、入所者のみを世帯分離することが認められます。
具体的には、以下のような計算で判断されます。
判断の流れ:
1. 世帯全体の収入を計算:父親の年金+子ども世帯の収入
2. 世帯全体の最低生活費を計算:世帯人数と年齢に応じた基準額
3. 特養費用の不足分を差し引く:収入から特養費用の不足分を引いた額
4. 要保護かどうか判断:差し引き後の額が最低生活費を下回れば要保護
この場合、特養費用の負担により世帯全体が要保護状態となるため、父親のみを世帯分離して生活保護を受けることが認められる可能性が高くなります。
生活保持義務者の所得と世帯分離の関係

世帯分離の判断では、生活保持義務者の所得も重要な要素となります。
生活保持義務とは、夫婦間や未成熟の子に対する親の義務など、自分の生活を犠牲にしてでも相手の生活を保持しなければならない義務です。一方、成人した子から親への扶養義務は「生活扶助義務」であり、自分の生活に余裕がある範囲で援助すればよいとされています。
厚生労働省の生活保護実施要領では、「所得が本人の一般生活費以下の生活保持義務者がいる場合」にも世帯分離が認められるとされています。
つまり、同居している子ども世帯の収入が、自分たちの生活を維持するのに必要な金額(一般生活費)と同程度しかない場合、親の特養費用まで負担する余裕はないと判断され、世帯分離が認められやすくなります。
生活保持義務者の所得判断の例
子ども世帯:夫婦と子ども2人の4人世帯
夫の収入:月35万円
一般生活費:4人世帯で約32万円が目安
余裕額:35万円 – 32万円 = 3万円
判断:余裕額が少なく、特養費用月4万円を継続的に負担する余裕がない→世帯分離が認められる可能性あり
世帯分離が認められる具体的なケース

実際に世帯分離が認められた具体的なケースを見てみましょう。
ケース1:介護費用負担による家計圧迫
父親(78歳)が脳梗塞で倒れ、要介護5となり特養に入所。特養費用は月13万円、父の年金は月7万円で、毎月6万円の不足が発生しました。
同居の息子(50歳)は会社員で月収32万円、妻(48歳)はパート で月収8万円、子ども2人は高校生と中学生です。住宅ローンが月10万円残っており、特養費用を負担すると世帯の生活が成り立たなくなります。
福祉事務所の審査の結果、特養費用の負担により世帯全体が要保護状態となると判断され、父親のみを世帯分離して生活保護を受けることが認められました。
ケース2:配偶者の介護により収入激減
母親(72歳)が認知症となり、特養に入所。それまで母親を自宅介護していた父親(75歳)は、介護疲れで体調を崩し、パートの仕事を辞めざるを得なくなりました。
同居の娘(45歳)は派遣社員で月収20万円、娘の夫(48歳)も月収25万円です。母親の特養費用は月11万円、母の年金は月6万円で、毎月5万円の不足が発生します。
父親の収入がなくなったことと、特養費用の負担により、世帯全体の生活が困窮。母親のみを世帯分離することで、母親の特養費用は生活保護から支給され、娘世帯と父親は自立した生活を維持できることになりました。
親の介護でお金がない時の対処法。公的支援制度や負担軽減策はある?
特別養護老人ホームで世帯分離が認められないケース
一方で、世帯分離が認められないケースも多くあります。どのような場合に却下されるのかを理解しましょう。
単に受給目的の世帯分離が認められない理由

生活保護の世帯分離は、「単に生活保護を受給するため」だけの目的では認められません。実際に世帯全体が困窮しており、世帯分離が必要不可欠な状況であることが求められます。
福祉事務所は、以下のような点を厳しく審査します。
審査される主な項目:
・世帯全体の収入と資産の状況
・特養費用を負担した場合の家計の実態
・他に節約できる支出がないか
・親族からの援助の可能性
・資産の活用可能性(不動産、貯金、保険など)
これらを総合的に判断し、「本当に世帯分離が必要か」「単に受給を目的としていないか」を見極めます。
このような場合、「生活保護を受けるための便宜的な世帯分離」と判断され、却下される可能性が高くなります。
世帯全体に収入がある場合の判断

世帯全体に一定以上の収入がある場合、特養費用の負担があっても、「要保護世帯」とは認められません。
例えば、子ども世帯の収入が高く、特養費用を負担しても最低生活費を十分に上回る場合は、世帯分離は認められません。生活保護は「最低限度の生活を維持できない人」を対象とする制度であり、ある程度の余裕がある世帯は対象外となります。
また、入所者本人にも一定の収入(年金)がある場合、その収入で特養費用の大部分を賄える場合は、世帯分離の必要性が低いと判断されます。
世帯分離が認められにくい収入水準の例
世帯構成:入所者(父)、母、息子夫婦、孫2人の6人世帯
収入:父の年金月8万円、母の年金月5万円、息子の収入月50万円、合計63万円
特養費用不足:月4万円
最低生活費:6人世帯で約40万円
判断:63万円 – 4万円 = 59万円 > 40万円(最低生活費)→要保護世帯ではない→世帯分離は認められない
世帯分離却下の具体例と理由

実際に世帯分離が却下されたケースを見てみましょう。
却下ケース1:十分な収入があるケース
母親(80歳)が特養に入所、特養費用月12万円、母の年金月6万円で、月6万円の不足が発生。同居の息子(55歳)は会社員で年収700万円、妻(52歳)もパートで年収200万円あります。
住宅ローンは完済しており、子どもも独立済みです。月6万円の特養費用を負担しても、世帯の生活に余裕があり、最低生活費を大きく上回ります。
却下理由:世帯全体に十分な収入があり、特養費用を負担しても要保護世帯とはならない。生活保護の必要性が認められない。
却下ケース2:他の親族が援助可能なケース
父親(77歳)が特養に入所、費用の不足分を長男世帯が申請。しかし、父親には他に2人の子ども(次男、三男)がおり、いずれも安定した収入があります。
福祉事務所が親族調査を行ったところ、次男と三男も費用分担に協力できる経済状況であることが判明しました。
却下理由:複数の子どもで費用を分担すれば、各世帯の負担は軽減され、要保護状態にはならない。親族間での費用分担が優先される。
一人っ子の親の介護でお金がない時の解決策。全部一人で抱え込まないために
特別養護老人ホーム入所時の世帯分離手続きの流れ
では、実際に世帯分離と生活保護を申請する場合、どのような手続きが必要なのかを詳しく解説します。
福祉事務所での申請と必要書類

特養入所に伴う生活保護の世帯分離申請は、居住地を管轄する福祉事務所で行います。
申請の流れ:
1. 福祉事務所への相談:まず福祉事務所の生活保護担当窓口で、特養入所に伴う経済的困窮について相談します。ここで世帯分離の可能性について説明を受けます。
2. 申請書の提出:生活保護申請書を提出します。世帯分離を希望する旨も併せて申し出ます。
3. 必要書類の準備:様々な書類の提出が求められます。
主な必要書類:
・特養入所に関する書類:入所契約書、費用の明細書、支払い状況がわかる書類
・収入証明書類:入所者の年金振込通知書、源泉徴収票、同居家族全員の収入証明
・資産に関する書類:預貯金通帳のコピー、不動産登記簿謄本、生命保険証券のコピー
・家計状況がわかる書類:住宅ローン返済予定表、教育費の支出がわかる書類
・身分証明書:世帯全員の身分証明書、住民票
・その他:扶養照会に関する書類、健康保険証のコピーなど
調査と審査の具体的な内容

申請後、福祉事務所による厳格な調査と審査が行われます。
1. 家庭訪問調査:
ケースワーカーが自宅を訪問し、生活実態を確認します。居住環境、生活状況、本当に困窮しているかを実際に見て判断します。申請から1週間以内に訪問されることが一般的です。
2. 資産調査:
金融機関への照会により、預貯金、有価証券、保険などの資産状況を調査します。申告漏れがないかを厳しくチェックされます。
3. 扶養義務者調査:
親族(子ども、兄弟姉妹など)に対して扶養照会が行われます。「この方の生活を援助できますか?」という照会書が送られ、親族の援助可能性を確認します。
4. 特養との連携:
特養に対しても、入所者の状況や費用について確認が行われます。
審査期間と決定
・審査期間:原則として申請から14日以内(最長30日)
・決定通知:書面で認定または却下の通知が届く
・認定の場合:世帯分離が認められ、入所者のみ生活保護受給
・却下の場合:理由が記載され、不服申立ての方法も案内される
認定後の生活保護費と施設費用の仕組み

世帯分離が認められ、生活保護の受給が開始されると、特養費用の支払い方法が変わります。
生活保護費の支給:
入所者本人に対して、以下の扶助が支給されます。
・介護施設入所者基本生活費:日常生活に必要な最低限度の費用
・介護保険料:生活保護から支払われる
・医療扶助:医療費は全額公費負担
特養費用の支払い:
入所者の年金と生活保護費を合わせて、特養費用が支払われます。一般的には以下のような流れになります。
1. 入所者の年金が特養に支払われる
2. 不足分が生活保護費から支給される
3. 福祉事務所から特養へ直接支払われる場合もある
家族の負担:
世帯分離が認められた場合、家族は特養費用を負担する必要がなくなります。これにより、家族は自立した生活を維持できます。

特養の費用負担で家計が苦しくなっている場合、一人で悩まず、まず福祉事務所に相談してみることが大切です。世帯分離が認められるかどうかは、個別の状況によって異なるので、専門家に相談することをおすすめします。
特別養護老人ホームでの生活保護と世帯分離:まとめ
特別養護老人ホーム入所に伴う費用負担により家計が圧迫される場合、生活保護の世帯分離を活用することで、入所者本人のみが生活保護を受け、同居家族は自立した生活を維持できる可能性があります。
世帯分離が認められる基本的な基準は、「世帯分離を行わなければ、その世帯全体が要保護世帯となる場合」です。特養費用の負担により、世帯の収入が最低生活費を下回る場合や、生活保持義務者の所得が一般生活費程度しかない場合に認められやすくなります。
一方、世帯全体に十分な収入がある場合や、単に生活保護を受給するためだけの目的では認められません。福祉事務所による厳格な審査があり、収入状況、資産状況、生活実態などを総合的に判断されます。
住民票の世帯分離とは異なり、生活保護の世帯分離は生活実態に基づいて判断されます。住民票で世帯を分けただけでは、自動的に生活保護の世帯分離が認められるわけではないので注意が必要です。
申請から認定までは原則14日以内(最長30日)で、その間に家庭訪問、資産調査、扶養義務者調査などが行われます。認定されれば、特養費用は入所者の年金と生活保護費で賄われ、家族の負担はなくなります。
特養入所は、家族にとって大きな決断です。経済的な不安があっても、適切な制度を利用することで、親に必要な介護を受けてもらいながら、家族も安定した生活を維持することができます。制度を正しく理解し、必要に応じて活用しましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。