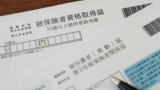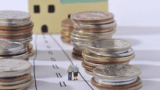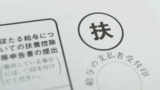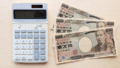「別居している親への仕送りを続けてきたけど、親の経済状況が改善したので返してもらえるの?」「親から『仕送りを返す』と言われたけど、税金の問題はないの?」「数年分まとめて返してもらったら贈与税がかかるって本当?」
長年にわたって別居の親に仕送りをしてきた方の中には、親の状況が変わったり、自分の経済状況が厳しくなったりして、仕送りを返してもらいたいと考える方もいるでしょう。しかし、仕送りを返してもらうことには、贈与税をはじめとする税務上の問題や、扶養条件への影響など、様々なリスクがあります。
この記事では、別居の親への仕送りを返してもらう際の法的・税務上の問題点、贈与税が発生する条件、見落としがちな注意点、適切な対処方法まで、詳しく解説します。親子間の金銭のやり取りで後悔しないための完全ガイドです。
別居の親への仕送りを返してもらうことは可能か
まず、別居している親への仕送りを返してもらうことの法的性質と、それに伴う問題点を理解しましょう。
仕送りの法的性質と返還の問題点

親への仕送りは、法的には「贈与」として扱われるのが一般的です。贈与とは、財産を無償で相手に譲渡することであり、基本的に返還義務は発生しません。
通常、子から親への生活費の援助は「扶養義務の履行」として行われます。民法では、直系血族(親子や祖父母と孫)はお互いに扶養する義務があるとされており、親が生活に困窮している場合、子がその生活を支えることは法的義務でもあります。
この扶養義務に基づく仕送りは、税法上も「生活費として必要な範囲」であれば贈与税の課税対象にならないとされています。つまり、仕送りは「あげたもの」であり、「貸したもの」ではないという前提で法的に扱われるのです。
したがって、過去に送った仕送りを親から返してもらうことは、法的には「新たな贈与を親から受ける」ことになります。これが税務上の問題を引き起こす原因となります。
仕送りを返してもらう場合の贈与税リスク

親から仕送りを返してもらう場合、親から子への贈与として贈与税の課税対象になる可能性があります。
贈与税は、個人から財産をもらった場合にかかる税金です。年間110万円の基礎控除があるため、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。しかし、これを超える金額を受け取った場合は、贈与税の申告と納税が必要になります。
例えば、毎月5万円ずつ10年間仕送りを続けた場合、合計600万円になります。親の経済状況が改善して、この600万円を一括で返してもらった場合、600万円の贈与を受けたとみなされ、約116万円の贈与税が発生することになります。
このように、善意で行った仕送りを返してもらうだけで、多額の税負担が発生してしまう可能性があります。
扶養条件への影響と社会保険上の問題

仕送りを返してもらうことは、扶養条件にも影響を与える可能性があります。
別居している親を社会保険の扶養に入れている場合、親の収入が仕送り額より少ないことが条件の一つです。仕送りを返してもらうということは、親に返還できる資力があるということであり、「仕送りによって生計が維持されている」という扶養の実態に疑義が生じます。
また、仕送りを返してもらう取り決めがあった場合、そもそも最初の仕送りが「生活費の援助」ではなく「貸付」とみなされる可能性もあります。この場合、過去にさかのぼって扶養の条件を満たしていなかったと判断され、扶養認定の取り消しや保険料の返還請求が行われるリスクがあります。
扶養条件に与える影響
・親に返還資力があることで扶養の実態に疑義
・返還前提の仕送りは「貸付」とみなされる可能性
・過去にさかのぼって扶養取り消しのリスク
・扶養控除の否認や追徴課税の可能性
税法上の扶養控除についても同様です。扶養控除は「生計を一にしている」ことが条件ですが、返還前提の金銭のやり取りは生計を一にしているとは認められず、過去の扶養控除が否認される可能性があります。
仕送りを返してもらう際の贈与税の仕組み
仕送りを返してもらう場合の贈与税について、具体的な仕組みと計算方法を詳しく解説します。
年間110万円の基礎控除と課税の基準

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。これは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからないという制度です。
重要なのは、この110万円は「贈与者ごと」ではなく「受贈者(もらう側)の合計」で判断されるという点です。例えば、親から80万円、別の親族から50万円の贈与を受けた場合、合計130万円となり、基礎控除110万円を超えるため贈与税の申告が必要になります。
仕送りの返還についても同様で、親から返してもらった金額が年間110万円を超える場合は贈与税の対象となります。
したがって、仕送りを返してもらう場合は、年間110万円以内に収まるよう分割して返してもらうことが、贈与税を回避する一つの方法となります。例えば、年間100万円ずつ複数年に分けて返してもらえば、贈与税はかかりません。
一括返還と分割返還での税務上の違い

仕送りの返還を一括で受けるか、分割で受けるかによって、税務上の扱いは大きく異なります。
一括返還の場合:
例えば、10年間で合計500万円の仕送りをしており、それを一括で返してもらった場合、その年に500万円の贈与を受けたことになります。
課税価格:500万円 – 110万円 = 390万円
贈与税額:390万円 × 20%(税率)- 25万円(控除額)= 53万円
このように、一括返還では多額の贈与税が発生します。
分割返還の場合:
同じ500万円を5年間に分けて、毎年100万円ずつ返してもらった場合、各年の贈与額は110万円以内に収まるため、贈与税は一切かかりません。
返還方法による贈与税の比較(500万円の場合)
一括返還:贈与税約53万円
分割返還(年100万円×5年):贈与税0円
差額:約53万円
ただし、分割返還にも注意点があります。税務署が「最初から一括贈与するつもりだったが、贈与税逃れのために分割しただけ」と判断した場合、定期贈与とみなされ、全額に対して贈与税が課されることがあります。
定期贈与と判断されないためには、毎年の贈与について都度贈与契約を結ぶ、贈与額や時期を変える、贈与契約書を作成するなどの対策が必要です。
贈与税申告が必要になるケースと計算方法

仕送りを返してもらった金額が年間110万円を超えた場合、贈与税の申告と納税が必要になります。
贈与税の申告期限:
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、税務署に贈与税の申告書を提出し、税金を納付する必要があります。申告を忘れた場合や故意に申告しなかった場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科されます。
贈与税の計算方法:
贈与税は累進課税制度を採用しており、贈与額が多いほど税率が高くなります。親から子への贈与の場合、「特例税率」が適用されます。
例えば、親から300万円の仕送り返還を受けた場合の計算は以下のようになります。
課税価格:300万円 – 110万円 = 190万円
贈与税額:190万円 × 10% = 19万円
このように、返還額によっては相当額の税負担が発生することになります。
親を扶養に入れるメリット・デメリットを徹底比較。損しない判断基準
仕送り返還で見落としがちな税務上の注意点
仕送りを返してもらう際には、一般的に知られていない税務上の落とし穴がいくつかあります。これらを見落とすと、予期せぬ税負担やペナルティが発生する可能性があります。
仕送りの使途と贈与税課税の関係

子から親への仕送りが贈与税非課税となるのは、「生活費や教育費など、通常必要と認められる範囲」で使われた場合に限られます。
もし親が受け取った仕送りを生活費として使わず、貯蓄していた場合はどうなるでしょうか。税務上は、生活費として必要でない金銭の移動は「贈与」とみなされ、本来は贈与税の課税対象となります。
例えば、毎月10万円の仕送りをしていたが、親の年金で生活できていたため、実際には仕送りの大部分を貯金していたというケースです。この場合、親が貯金していた仕送り額については、最初の時点で贈与税の課税対象になっていた可能性があります。
そして、その貯金を後から返してもらった場合、再度「親から子への贈与」として贈与税が課される可能性があります。つまり、二重に贈与税が課されるリスクがあるということです。
このような事態を避けるためには、仕送りは親の実際の生活費に見合った適切な金額に設定し、過剰な仕送りは避けるべきです。
複数年分まとめて返還する場合のリスク

複数年分の仕送りをまとめて返してもらうことは、最も税務リスクが高い行為です。
例えば、10年間で合計1,000万円の仕送りをしており、それを一括で返してもらった場合、その年に1,000万円の贈与を受けたことになり、約240万円もの贈与税が発生します。
課税価格:1,000万円 – 110万円 = 890万円
贈与税額:890万円 × 30% – 90万円 = 177万円
さらに、大きな金額の移動は税務署の目に留まりやすく、税務調査の対象となる可能性が高まります。調査の結果、「最初から返還前提の貸付だった」と判断されれば、過去の扶養控除が否認され、追徴課税や延滞税が発生する可能性もあります。
まとめて返還する場合の主なリスク
・高額な贈与税の発生
・税務調査の対象になりやすい
・返還前提の貸付と判断されるリスク
・過去の扶養控除否認の可能性
・追徴課税や延滞税の発生
どうしてもまとめて返してもらう必要がある場合は、事前に税理士に相談し、適切な対応策を検討することを強くおすすめします。
【親との金銭のやり取り、これで本当に大丈夫?】
税務調査で指摘されやすいポイント

税務署は様々な情報から贈与の事実を把握しています。仕送りの返還について、特に以下のような点で税務調査の対象となりやすいです。
銀行口座の大きな入金:
親から子の口座への数百万円単位の振込は、金融機関から税務署に情報が提供される場合があります。特に100万円を超える現金の預入れや、通常の生活費の範囲を大きく超える振込は注目されやすいです。
他の贈与との合算:
仕送りの返還だけでなく、同じ年に他の親族から贈与を受けている場合、それらを合算した金額が110万円を超えていないか確認されます。申告漏れがあれば指摘されます。
過去の扶養控除との整合性:
仕送りを返してもらえるということは、親に返還資力があるということです。過去に親を扶養に入れて扶養控除を受けていた場合、「本当に扶養の実態があったのか」が疑問視され、扶養控除の適用が否認される可能性があります。
税務調査が入った場合、過去5年分(悪質な場合は7年分)にさかのぼって調査されます。その結果、申告漏れや虚偽申告が発覚すれば、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税、重加算税などのペナルティが科されることになります。
確定申告の「別居の親族」とは。一人暮らしの親を扶養に入れるには?
仕送りを返してもらう場合の適切な対処法
では、どうしても仕送りを返してもらう必要がある場合、どのように対応すべきでしょうか。適切な対処法をご紹介します。
事前に親子間でルールを決める重要性

仕送りによるトラブルを防ぐ最も効果的な方法は、仕送りを始める前に親子間でルールを明確にしておくことです。
税理士など専門家の多くが推奨するのは、「仕送りは返還を前提としない贈与である」という合意を親子間で形成することです。仕送りは扶養義務に基づく援助であり、将来返してもらうものではないという認識を共有します。
このルールを明確にしておけば、後から「やっぱり返してほしい」「返したい」という話が出てきても、原則として返還しないという方針を維持できます。これにより、贈与税の問題も、扶養条件の問題も発生しません。
また、仕送りを始める際には、親の実際の生活費を把握し、過剰な仕送りにならないよう注意することも大切です。親が貯蓄できるほどの金額を送ることは、税務上のリスクを高めます。
金銭の貸借として記録を残す方法

もし最初から返してもらうことを前提としている場合は、仕送りではなく「貸付」として処理する方法があります。
親子間であっても、金銭の貸借契約を正式に結び、以下の要件を満たすことで、税務上も貸付と認められる可能性があります。
金銭消費貸借契約書の作成:
貸付金額、返済期間、返済方法、利息などを明記した契約書を作成します。利息を設定しない場合、利息相当額が贈与とみなされる可能性があるため、最低限の利息(年0.5%~1%程度)を設定することが推奨されます。
実際に返済が行われること:
契約書があっても、実際に返済が行われなければ貸付とは認められません。毎月または定期的に、契約通りの返済を受け、その記録を残す必要があります。
ただし、貸付として処理した場合、扶養の条件を満たさなくなる可能性が高いです。社会保険の扶養は「仕送りによって生計が維持されている」ことが条件であり、貸付は仕送りではありません。税法上の扶養控除についても、貸付は「生計を一にしている」とは認められません。
したがって、貸付として処理する場合は、親を扶養に入れないか、別の方法で扶養の条件を満たす必要があります。
税理士など専門家への相談が必要なケース

以下のようなケースでは、必ず税理士など専門家に相談することをおすすめします。
高額な仕送りを返してもらう場合:
返還額が数百万円以上になる場合は、贈与税の負担も大きくなります。税理士に相談することで、贈与税を最小限に抑える方法や、分割返還のスケジュールなどについてアドバイスを受けることができます。
過去に扶養控除を受けていた場合:
仕送りの返還によって、過去の扶養控除の適用が問題になる可能性があります。税理士に相談し、どのような影響があるか、どう対応すべきかを確認することが重要です。
既に返還を受けてしまった場合:
既に親から仕送りを返してもらってしまい、贈与税の申告をしていない場合は、早急に税理士に相談しましょう。自主的に期限後申告をすることで、ペナルティを軽減できる場合があります。
専門家への相談が特に重要なケース
・返還額が300万円以上の高額な場合
・複数年分をまとめて返してもらう場合
・過去に扶養控除を受けていた場合
・既に返還を受けて申告していない場合
・税務調査の通知を受けた場合
税理士への相談費用は一般的に数万円程度ですが、適切なアドバイスを受けることで、数十万円から数百万円の税負担を回避できる可能性があります。費用対効果を考えれば、専門家への相談は決して高くはありません。
75歳以上の親を扶養に入れる別居時の手続き。条件と必要書類を解説

親子間の金銭のやり取りは、税務上も感情的にも複雑な問題ですよね。「こうすべきだった」と後悔する前に、専門家に相談して適切な方法を選択することが大切です。
別居の親への仕送りと返還:まとめ
別居している親への仕送りを返してもらうことは、税務上も法律上も多くのリスクを伴います。最も重要なのは、仕送りは原則として「返還を前提としない贈与」であるという認識を持つことです。
仕送りを返してもらった場合、親から子への贈与として贈与税が課される可能性があります。年間110万円を超える返還を受けた場合は、贈与税の申告と納税が必要になり、申告を怠れば無申告加算税や延滞税などのペナルティが科されます。
また、仕送りの返還は扶養条件にも影響します。親に返還資力があることや、返還前提の仕送りだったことが判明すれば、過去にさかのぼって扶養控除が否認され、追徴課税を受ける可能性もあります。
親への仕送りは、扶養義務に基づく家族の支え合いです。しかし、その善意の行為が後に税務上の問題を引き起こすことのないよう、事前の準備と正しい知識が欠かせません。
もし既に仕送りを返してもらってしまい、どう対応すべきか迷っている場合は、早めに税理士に相談しましょう。自主的に期限後申告をすることで、ペナルティを軽減できる可能性があります。
親子関係は一生続くものです。金銭のやり取りで関係が悪化することのないよう、事前の準備と適切な対応を心がけましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。