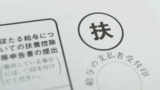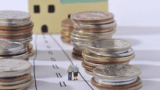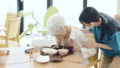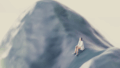「75歳の親を扶養に入れたら税金が安くなるって本当?」「後期高齢者医療制度に入っている親でも扶養にできるの?」「扶養に入れたら介護費用が高くなるって聞いたけど…」
親が75歳以上の後期高齢者になると、扶養に入れるべきかどうか悩む方は多いのではないでしょうか。扶養に入れることで税金が安くなるというメリットがある一方で、思わぬデメリットもあります。
実は、75歳以上の後期高齢者は、健康保険の扶養には入れません。しかし、税法上の扶養には入れることができ、所得税や住民税が軽減されます。ただし、扶養に入れることで介護保険料や医療費の自己負担が増えるケースもあるため、慎重な判断が必要です。
この記事では、後期高齢者を扶養に入れるとどうなるのか、税法上と社会保険上の違い、具体的なメリットとデメリット、手続きの方法と注意点を詳しく解説します。同居・別居それぞれのケースでの違いも含めて、判断に必要な情報をすべてお伝えします。
後期高齢者を扶養に入れる基本的な理解
まず、後期高齢者を扶養に入れることについて、基本的な仕組みを理解しましょう。税法上と社会保険上では、扱いが大きく異なります。
後期高齢者医療制度とは何か

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方(65歳以上で一定の障害がある方も含む)が加入する医療保険制度です。75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から自動的に移行します。
この制度では、すべての75歳以上の方が個別に被保険者となります。つまり、誰かの扶養に入るという概念がなく、一人ひとりが独立して保険料を支払います。保険料は年金から天引きされるか、納付書で支払います。
後期高齢者医療制度の保険料は、お住まいの都道府県ごとに異なります。所得に応じた「所得割」と、全員が負担する「均等割」の合計で計算されます。低所得の方には軽減措置もあります。
税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い

「扶養」には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、それぞれまったく別の制度です。後期高齢者を扶養に入れる際は、この違いを正しく理解することが重要です。
税法上の扶養とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養親族がいることで控除を受けられる制度です。後期高齢者である親も、条件を満たせば税法上の扶養に入れることができます。
税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い
【税法上の扶養】
・所得税・住民税の控除が受けられる
・75歳以上でも入れることができる
・年収や所得の条件がある
・年末調整や確定申告で手続き
【社会保険上の扶養】
・健康保険料の負担がなくなる
・75歳以上は入れることができない(後期高齢者医療制度に移行するため)
・収入の条件がある
・会社や健康保険組合で手続き
社会保険上の扶養とは、健康保険の被扶養者になることで、自分で保険料を払わずに健康保険に加入できる制度です。しかし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入するため、社会保険上の扶養には入れません。
つまり、後期高齢者を扶養に入れるというのは、実質的には「税法上の扶養に入れる」ことを意味します。健康保険料が安くなるわけではなく、あくまで所得税・住民税が軽減されるだけという点を理解しておきましょう。
後期高齢者を扶養に入れる条件

後期高齢者を税法上の扶養に入れるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
「生計を一にする」とは、同じ財布で生活しているということです。必ずしも同居している必要はなく、別居していても定期的に仕送りをしている場合は「生計を一にしている」と認められます。
年金収入の条件について、もう少し詳しく見てみましょう。65歳以上の方の場合、公的年金等の収入が158万円以下(所得にすると48万円以下)であれば、扶養に入れることができます。年金収入が月13万円程度以下なら、この条件を満たします。
75歳以上の親を扶養に入れる別居時の手続き。条件と必要書類を解説
後期高齢者を扶養に入れるメリット
後期高齢者を扶養に入れることで得られるメリットは、主に税金面での優遇です。具体的にどのくらい得になるのか見ていきましょう。
所得税と住民税の控除額

後期高齢者(70歳以上)を扶養に入れると、老人扶養親族として扶養控除を受けることができます。控除額は、同居しているか別居しているかで異なります。
老人扶養親族の控除額
【所得税】
・別居の場合:48万円
・同居の場合:58万円
【住民税】
・別居の場合:38万円
・同居の場合:45万円
同居している場合は「同居老親等」として、より高い控除額が適用されます。別居よりも所得税で10万円、住民税で7万円多く控除されます。
では、実際にどのくらい税金が安くなるのでしょうか。具体例で見てみましょう。
【例】年収500万円の会社員が、75歳の親を扶養に入れた場合
同居している場合:
・所得税の軽減額:約11万6,000円(58万円×20%)
・住民税の軽減額:約4万5,000円(45万円×10%)
・合計:約16万1,000円の節税
別居している場合:
・所得税の軽減額:約9万6,000円(48万円×20%)
・住民税の軽減額:約3万8,000円(38万円×10%)
・合計:約13万4,000円の節税
年収や所得税率によって軽減額は変わりますが、年間10万円以上の節税効果が期待できるケースが多いです。
手続きの簡便さと経済的メリット

税法上の扶養に入れる手続きは、比較的簡単です。会社員の場合は年末調整で、自営業の場合は確定申告で手続きができます。
会社員の方は、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等申告書」に親の情報を記入するだけです。別居している場合は、仕送りの証明(振込記録など)を求められることもありますが、基本的には書類一枚で完了します。
節税効果は一年だけでなく、条件を満たす限り継続します。10年間扶養に入れれば、累計で100万円以上の節税になる可能性もあります。
同居と別居での控除額の違い

先ほども触れましたが、同居と別居では控除額に大きな差があります。同居の場合は「同居老親等」として、別居よりも優遇されます。
ここでいう「同居」とは、住民票が同じ住所であり、実際に一緒に暮らしていることを指します。住民票が別でも実態として同居していれば認められる場合もありますが、原則として住民票も同じにしておくのが確実です。
「別居」でも、定期的に仕送りをして生活を支えている場合は、扶養に入れることができます。ただし、控除額は同居よりも少なくなります。
同居か別居かで年間2〜3万円の差が出るため、もし同居を検討しているなら、税制面でもメリットがあると言えます。
親を扶養に入れるメリット・デメリットを徹底比較。損しない判断基準
後期高齢者を扶養に入れるデメリットと注意点
メリットがある一方で、後期高齢者を扶養に入れることで生じるデメリットも存在します。特に介護や医療費の面で影響が出ることがあるため、注意が必要です。
介護保険料が高くなる可能性

後期高齢者を扶養に入れる最大のデメリットは、親の介護保険料が高くなる可能性があることです。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、本人の所得と世帯の住民税課税状況によって決まります。親を扶養に入れて同居すると、世帯全体の所得が上がり、住民税の課税状況が変わるため、親の介護保険料が上がることがあるのです。
例えば、ある自治体では:
・世帯全員が住民税非課税の場合:年額約2万6,000円
・世帯に住民税課税者がいる場合:年額約7万5,000円
このように、年間5万円近く保険料が上がるケースもあります。扶養による節税効果が年間13万円程度だとしても、介護保険料の増加分を考慮すると、実質的なメリットは8万円程度に減ってしまいます。
介護サービス費用や医療費の自己負担増加

親を扶養に入れることで、介護サービスの自己負担額や高額療養費の限度額が上がる可能性もあります。
介護サービスの自己負担限度額は、世帯の所得によって決まります。
高額介護サービス費の自己負担限度額(月額)
・生活保護世帯:1万5,000円
・世帯全員が住民税非課税:2万4,600円
・住民税課税〜課税所得380万円未満:4万4,400円
・課税所得380万円〜690万円未満:9万3,000円
・課税所得690万円以上:14万100円
親だけの世帯で住民税非課税だった場合、限度額は2万4,600円です。しかし、子どもの扶養に入り、世帯の課税所得が690万円以上になると、限度額は14万100円に跳ね上がります。月額で約12万円、年間では約140万円の差が出る可能性があります。
高額療養費制度でも同様のことが起こります。医療費の自己負担限度額が、親だけの非課税世帯なら月額2万4,600円だったのが、扶養に入ることで月額5万7,600円以上になることもあります。
このような場合、扶養による節税効果よりも、介護・医療費の負担増の方が大きくなる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
【扶養に入れるべきか、判断に迷っていませんか?】
別居の場合の証明書類と手続きの負担

別居している親を扶養に入れる場合、「生計を一にしている」ことを証明する必要があります。これが意外と負担になることがあります。
税務署から求められる可能性がある証明書類には、以下のようなものがあります:
特に送金記録は重要です。現金で渡している場合は証明が難しいため、銀行振込で定期的に送金している記録を残しておく必要があります。振込先が親本人の口座であることも確認されます。
また、税務調査が入った場合、仕送り額が親の生活費として妥当かどうかもチェックされます。形だけの少額の仕送りでは認められない可能性があります。
このように、別居の場合は書類の管理や証明の手間がかかります。同居よりも控除額が少ないうえに手間もかかるため、メリットとデメリットをよく比較する必要があります。
確定申告の「別居の親族」とは。一人暮らしの親を扶養に入れるには?
後期高齢者を扶養に入れる手続きと必要書類
実際に後期高齢者を扶養に入れる場合の手続き方法と、必要な書類について詳しく見ていきましょう。
年末調整と確定申告での手続き方法

後期高齢者を税法上の扶養に入れる手続きは、会社員なら年末調整、自営業者なら確定申告で行います。
【会社員の場合:年末調整】
毎年11月頃に会社から配布される「給与所得者の扶養控除等申告書」に、親の情報を記入します。
別居している場合は、会社から送金の証明を求められることがあります。その場合は、振込明細のコピーなどを提出します。
【自営業者の場合:確定申告】
毎年2月16日〜3月15日の確定申告期間に、確定申告書の「扶養控除」の欄に親の情報を記入します。e-Taxを利用すれば、自宅から申告できます。
自営業者の場合も、別居であれば送金の証明書類を求められることがあります。
同居と別居で異なる必要書類

同居と別居では、必要となる書類が異なります。
同居の場合の必要書類
・親のマイナンバーがわかるもの
・親の年金収入がわかる書類(源泉徴収票など)
※通常は上記のみで手続き可能
別居の場合の必要書類
・親のマイナンバーがわかるもの
・親の年金収入がわかる書類
・親の住民票
・送金の証明(銀行振込の明細、通帳のコピーなど)
・場合によっては、親の生活費の内訳がわかる資料
別居の場合は、「生計を一にしている」ことを客観的に証明できる資料が重要になります。定期的な送金記録は必ず保管しておきましょう。
手続きのタイミングと注意事項

扶養に入れるタイミングは、いつでも可能です。年の途中からでも扶養に入れることができ、その年の12月31日時点で扶養関係にあれば、1年分の控除が受けられます。
注意すべき点として、親の年収が条件を超えた場合は、速やかに扶養から外す必要があります。例えば、パートを始めて収入が増えた、遺産相続で所得が発生したなどの場合です。
また、虚偽の申告は絶対にしてはいけません。税務調査で発覚すると、追徴課税や延滞税が課されるだけでなく、悪質な場合は重加算税が課される可能性もあります。
後期高齢者を扶養に入れるとどうなるかの判断基準:まとめ
後期高齢者を扶養に入れるとどうなるかについて、重要なポイントをまとめます。
まず、75歳以上の後期高齢者は、健康保険の扶養には入れません。後期高齢者医療制度に加入しているため、社会保険上の扶養という概念がないのです。しかし、税法上の扶養には入れることができ、所得税・住民税の控除を受けられます。
メリットとしては、年間10万円以上の節税効果が期待できます。同居している場合は「同居老親等」として、より高い控除額(所得税58万円、住民税45万円)が適用されます。別居の場合でも、定期的に仕送りをしていれば扶養に入れることができます。
一方、デメリットも存在します。親の介護保険料が年間5万円近く上がる可能性があり、介護サービスの自己負担限度額や高額療養費の限度額も上がることがあります。特に、親が要介護認定を受けている、定期的に通院しているといった場合は、扶養による節税効果よりも負担増の方が大きくなる可能性があります。
手続きは、会社員なら年末調整、自営業者なら確定申告で行います。同居の場合は比較的簡単ですが、別居の場合は送金記録などの証明書類が必要になります。
後期高齢者を扶養に入れるかどうかは、税金面のメリットと介護・医療費の負担増を総合的に判断する必要があります。一概に「入れた方が得」とも「入れない方が良い」とも言えません。親の健康状態、介護の必要性、家計の状況などを考慮して、個別に判断することが大切です。
判断に迷う場合は、ケアマネージャーや税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。長期的な視点で、家族全体にとって最適な選択をしましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。