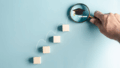「将来の介護を考えて平屋を検討しているけれど、どんな間取りにすればいいの?」「親の介護がしやすい住まいに建て替えたいけれど、具体的に何を意識すればいいのかわからない」「バリアフリーにすればいいというけれど、本当に介護の負担は軽減されるの?」
在宅介護を考えている方や、将来の親の介護に備えたい方にとって、住まいの間取りは非常に重要な要素です。実際に、適切な間取り設計により介護者の身体的負担が30%以上軽減されたという調査結果もあり、住環境が介護の質と継続性に大きく影響することが明らかになっています。
この記事では、介護しやすい平屋の間取りについて、単なる住宅設計の話ではなく、介護負担の軽減という視点から徹底解説します。動線設計から廊下幅の具体的な寸法、見落としがちな注意点、実際の間取り図で確認すべきポイントまで、在宅介護の現場で本当に役立つ情報をお届けします。
介護しやすい平屋の間取りが介護負担を軽減する理由
なぜ平屋の間取りが介護に適しているのか、その理由を具体的に見ていきましょう。単に「階段がない」という表面的な理由だけでなく、介護の現場で実感できるメリットがあります。
階段移動がない平屋が介護者と要介護者双方の負担を減らす

平屋最大の特徴は、階段がないワンフロアの生活空間です。この特徴が介護の負担軽減に直結します。
2階建ての住宅では、寝室が2階にある場合、トイレに行くたびに階段を昇り降りする必要があります。高齢になると階段での転倒リスクが高まり、実際に高齢者の家庭内事故の約8割が階段や段差で発生しているというデータもあります。
介護者の立場から見ても、階段での介助は大きな身体的負担となります。特に夜間のトイレ介助で何度も階段を上り下りすることは、介護者の睡眠不足や腰痛の原因にもなるのです。
平屋であれば、このような階段移動のストレスから完全に解放され、要介護者が自力で移動しやすく、介護者も見守りやすい環境を実現できます。
動線がコンパクトになり介護の移動距離が短縮できる

平屋の間取りでは、生活に必要な全ての空間をワンフロアに配置するため、自然と動線がコンパクトになります。
介護においては、寝室からトイレまでの距離、リビングから寝室までの距離、洗面所から寝室までの距離といった、日常的な移動距離の短さが介護負担に直結します。移動距離が短いほど、要介護者の体力消耗が少なく、介護者の介助回数や時間も削減できるのです。
特に認知症の方の場合、トイレの場所がわかりやすく、寝室から近い位置にあることで、失禁のリスクを減らすこともできます。また、介護者が家事をしながら要介護者を見守りやすい配置にすることで、目の届く範囲で安全を確保できるというメリットもあります。
バリアフリー設計を取り入れやすく将来の変化に対応しやすい

平屋は構造上、完全なバリアフリー設計を実現しやすいという大きな利点があります。
2階建ての住宅では、どうしても階段という段差が存在してしまいますが、平屋であればフラットな床面を全室で実現できます。段差をなくすことで、車椅子での生活はもちろん、歩行器や杖を使った移動もスムーズになります。
また、将来的に介護度が上がった場合にも、リフォームや設備の追加がしやすいのも平屋の特徴です。手すりの設置、スロープの追加、車椅子対応の洗面台への交換など、必要に応じて柔軟に対応できます。
さらに、平屋は基礎が広く安定しているため、将来的に介護用リフトや電動ベッドなどの重量のある設備を導入する際にも、構造的な心配が少ないというメリットがあります。
在宅介護で家族の負担を軽減するには?持続可能な介護体制の構築法
介護しやすい平屋の間取りを実現する7つの設計ポイント
具体的に、介護しやすい平屋の間取りを実現するためには、どのような設計ポイントを押さえればよいのでしょうか。住宅設計の専門家だけでなく、介護の現場を知る専門家の視点も取り入れた、実践的なポイントをご紹介します。
LDKと寝室・水回りの動線を最短距離でつなぐ配置

介護しやすい平屋の間取りで最も重要なのは、日常生活で頻繁に使う空間を近くに配置することです。
特に重視すべきは以下の3つの動線です。
LDK(リビング・ダイニング・キッチン)と寝室の距離:日中はリビングで過ごし、疲れたら寝室で休むという移動が頻繁に発生します。この距離が短ければ、要介護者が自力で移動しやすく、介護者も目が届きやすくなります。
寝室とトイレの距離:特に夜間のトイレ利用を考えると、寝室とトイレは可能な限り近い位置に配置すべきです。ただし、音が気になる場合は、間に収納スペースを設けるなどの工夫も有効です。
LDKと水回り(洗面所・浴室)の距離:洗顔や入浴の介助をする際、キッチンで準備をしながら対応できる距離感があると、介護者の負担が大きく軽減されます。
理想的な動線配置の例
寝室を中心に、トイレを隣接させ、LDKと洗面所・浴室を寝室から3〜5m以内に配置する。この配置により、介護に必要な全ての移動を最小限に抑えることができます。
廊下幅90cm以上確保と引き戸採用で車椅子移動をスムーズに

介護しやすい平屋の間取りでは、廊下や通路の幅が非常に重要です。一般的な住宅の廊下幅は約78cmですが、これでは車椅子での移動が困難です。
最低でも90cm以上、理想的には1m以上の廊下幅を確保することで、車椅子での移動が可能になります。手すりを設置する場合は、さらに10cm程度の余裕を持たせると安心です。
また、ドアの選択も重要なポイントです。引き戸は開き戸に比べて開閉時のスペースが不要で、車椅子でも楽に通過できます。特に「上吊り引き戸」を採用すれば、床にレールがないため完全にフラットな状態を保て、つまずきのリスクもありません。
ドアの有効幅も重要で、車椅子が通過できる80cm以上を確保する必要があります。一般的な住宅のドア幅は75cm程度ですが、介護を考えるなら85cm以上が理想的です。
回遊動線と座れる場所の設置で介護者の負担を軽減

回遊動線とは、行き止まりのない、ぐるりと回れる動線設計のことです。この設計を介護しやすい平屋の間取りに取り入れることで、介護の効率が大きく向上します。
例えば、キッチンを中心に回遊できる設計にすれば、食事の準備をしながら要介護者の様子を確認し、必要に応じてすぐに対応できます。アイランドキッチンを採用すると、キッチンの周りをぐるりと回れるため、車椅子での移動もスムーズです。
また、見落としがちですが重要なのが、室内の各所に「座れる場所」を設けることです。高齢になると、長時間立っているのが困難になります。
玄関にベンチを設置すれば、靴の脱ぎ履きが楽になります。洗面脱衣室に椅子を置けるスペースがあれば、着替えの際に座って休めます。小上がりの畳コーナーがあれば、ちょっと横になりたい時にも便利です。
さらに、キッチンや洗面台などの設備は、足元に空間を設けて車椅子でも使いやすい設計にすることが重要です。一般的なキッチンは足元に収納がありますが、車椅子対応にする場合は足元を空洞にして、車椅子に座ったまま使えるようにします。
介護しやすい平屋の間取りで見落としがちな注意点
介護しやすい平屋の間取りを考える際、基本的なポイントを押さえるだけでは不十分です。実際に介護が始まってから「こんなはずではなかった」と後悔しないために、見落としがちな注意点を確認しましょう。
玄関から寝室までの距離と駐車場スペースの確保

室内の動線ばかりに気を取られて、玄関から寝室までの距離を見落としてしまうケースが多くあります。
LDKと寝室、トイレの距離を優先した結果、玄関から寝室までが遠くなってしまうと、外出や帰宅時の負担が大きくなります。デイサービスの送迎車からの乗り降り、通院後の帰宅時など、玄関と寝室が近いことで介助の負担が大きく軽減されます。
また、災害時の避難経路としても、寝室と玄関の距離は重要です。地震や火災が発生した際、短時間で外に避難できる配置になっているかを確認しましょう。
駐車場のスペース確保も見落としがちな重要ポイントです。一般的な駐車スペースは横幅2.3m程度ですが、車椅子の乗り降りを考慮すると最低でも3.5m以上の幅が必要になります。
デイサービスの送迎車が停車できるスペースも考慮が必要です。送迎車は一般車よりも大きいことが多いため、回転スペースや乗降スペースを含めて余裕を持った駐車場設計をしましょう。
収納位置と設備の足元スペースへの配慮

収納の位置と使いやすさは、介護しやすい平屋の間取りで非常に重要ですが、見落とされがちなポイントです。
高い位置の収納や、奥行きが深すぎる収納は、高齢者にとって使いづらく、転倒の原因にもなります。手の届きやすい高さで、奥行き浅めの収納を多めに設けることが理想的です。
具体的には、床から40cm〜140cm程度の高さに収納の中心を設けると、立った状態でも座った状態でも使いやすくなります。可動式の棚を採用すれば、身体状況の変化に応じて高さを調整できます。
また、動線上に家具や収納を置かないことも重要です。間取り図上では廊下幅が十分でも、実際に家具を配置すると通路が狭くなってしまうケースがよくあります。間取り検討時には、家具の配置も含めて実際の通路幅を確認しましょう。
設備面では、キッチンや洗面台の足元スペースの確保が重要です。一般的なキッチンや洗面台は足元に収納がありますが、車椅子での使用を考える場合は、足元を空洞にする必要があります。
家具配置を考慮した通路幅の実測が重要

間取り図だけを見て安心してしまうのは危険です。実際に家具を配置した状態での通路幅を確認することが非常に重要です。
例えば、廊下幅が100cmあっても、壁際に置く予定の収納棚が30cm出っ張れば、実質的な通路幅は70cmになってしまいます。これでは車椅子での移動は困難です。
間取り検討時には、以下のポイントを実測して確認しましょう。
ベッドを配置した後の寝室の通路幅:ベッドの周囲に介助スペースとして最低60cm、できれば80cm以上の通路幅を確保します。
家具を配置した後のリビングの動線:ソファやテーブルを配置した状態で、車椅子が通れる80cm以上の通路幅を確保できるか確認します。
キッチンでの作業スペース:対面キッチンの場合、背面の収納との距離が重要です。2人で作業することを考えると、最低でも90cm、理想的には120cm以上のスペースが必要です。
通路幅実測のポイント
間取り図に実際の家具の寸法を書き込んで、残りのスペースを計算しましょう。可能であれば、実際の家具を配置したモックアップや3D図面を作成して、視覚的に確認するとより確実です。
また、段差の解消も重要な注意点です。室内の段差は3mm以下に抑えるのが理想です。玄関や浴室など、構造上どうしても段差が必要な場所は、手すりやスロープを設置して安全性を高めます。
親の介護でお金がない時の対処法。公的支援制度や負担軽減策はある?
介護しやすい平屋の間取り実例と間取り図のチェックポイント
ここまでの設計ポイントを踏まえて、実際の介護しやすい平屋の間取り実例と、間取り図を見る際のチェックポイントをご紹介します。
介護動線を優先した2LDK・3LDKの間取り例

介護しやすい平屋の間取りとして、まず2LDKの間取り例を見てみましょう。
【2LDK間取りの基本構成】
中央にLDK(18〜20畳)を配置し、その両側に寝室を配置する構成が基本です。LDKに隣接する形で主寝室(8畳程度)を配置し、寝室からすぐにトイレにアクセスできるようにします。
もう一方の居室は、将来的に介護者の休息室や、一時的な介護用品の収納スペースとしても活用できます。水回り(洗面所・浴室)は、LDKと主寝室の両方からアクセスしやすい中間位置に配置します。
この配置により、LDKから寝室まで約3m、寝室からトイレまで約2mという最短動線を実現できます。
【3LDKの介護重視間取り例】
3LDKの場合は、広めのLDK(22〜24畳)を中心に、主寝室、予備室、介護者用の個室を配置できます。
理想的な配置は、LDKに隣接して主寝室を配置し、主寝室に隣接してトイレと洗面所を配置します。予備室は、将来的に要介護度が上がった際の介護用個室として活用できるよう、主寝室の近くに配置します。
介護者用の個室は、少し離れた位置に配置することで、介護者がしっかり休息を取れるプライベート空間を確保できます。
間取り図で確認すべき寸法と配置の具体的基準

介護しやすい平屋の間取り図を検討する際、具体的にどの寸法を確認すればよいのでしょうか。チェックすべき具体的な基準をまとめました。
【廊下・通路の幅】
一般廊下:最低90cm、理想100cm以上
玄関ホール:最低120cm、理想150cm以上
トイレ前の通路:最低100cm以上(車椅子での方向転換を考慮)
【ドアの有効幅】
各部屋のドア:最低80cm、理想85cm以上
トイレのドア:最低80cm以上
玄関ドア:最低90cm以上
【部屋と部屋の距離】
LDKから主寝室:5m以内
寝室からトイレ:3m以内
玄関から寝室:8m以内
【トイレの広さ】
介助を考慮する場合、トイレは最低でも1.5畳(約2.4㎡)、理想的には2畳(約3.3㎡)以上の広さが必要です。車椅子での出入りや、介助者が横に付き添えるスペースを確保します。
【洗面脱衣室の広さ】
洗面脱衣室も、介助を考慮すると最低2畳、理想的には3畳以上の広さが必要です。椅子を置いて座って着替えられるスペース、介助者が動けるスペースを確保します。
リフォームより新築時の設計が介護負担軽減に効果的

既存住宅を介護しやすくリフォームすることも可能ですが、新築時から介護を見据えた設計をする方が、はるかに効果的です。
リフォームでは、構造上の制約により、廊下幅を広げたり、部屋の配置を変更したりすることが困難な場合が多くあります。また、リフォーム費用も、新築時に組み込むよりも高額になる傾向があります。
新築時であれば、将来の介護を見据えた設計を最初から組み込むことができ、コストも抑えられます。例えば、以下のような設計を新築時に組み込んでおくと便利です。
手すりの下地を壁に入れておく(後から取り付けが容易)
電動ベッドやリフト用の電源コンセントを寝室に多めに設置
将来的なスロープ設置を考慮した玄関周りの設計
車椅子対応の洗面台や浴室への交換がしやすい配管設計
特に平屋の場合、新築時にバリアフリー設計を徹底することで、築後30年、40年経っても介護しやすい住まいとして機能し続けます。長期的な視点で住まいづくりを考えることが、結果的に家族全員の負担軽減につながるのです。
寝たきりの在宅介護が無理と感じた時の対処法。限界から健全な介護へ
介護しやすい平屋の間取りと専門家への相談の重要性
介護しやすい平屋の間取りを実現するために、専門家への相談が非常に重要です。住宅設計だけでなく、介護の実態を知る専門家の視点を取り入れることで、より実用的な住まいづくりができます。
建築前の介護経験者や専門家への相談が後悔を防ぐ

住宅設計の専門家は、構造や法規制については詳しくても、実際の介護現場での使いやすさまで熟知しているとは限りません。
建築前に、実際に介護を経験した方や、介護の専門家に相談することで、間取り図だけではわからない実用的なアドバイスを得ることができます。
例えば、「トイレのドアは内開きと外開きのどちらがいいか」という質問に対して、介護経験者であれば「トイレ内で倒れた時のことを考えると外開きが安全」という実体験に基づいたアドバイスができます。
また、「洗面所にどのくらいのスペースが必要か」という質問に対しても、「車椅子での出入りだけでなく、介助者が横に立って支えるスペースも考慮すべき」といった、現場目線のアドバイスが得られます。
介護と住まいの両面から相談できる窓口の活用

介護しやすい平屋の間取りを考える際、介護と住まいの両面から相談できる窓口を活用することが重要です。
住宅メーカーの中には、福祉住環境コーディネーターの資格を持つスタッフがいる会社もあります。また、地域包括支援センターでは、住宅改修に関する相談も受け付けています。
さらに、介護保険を利用した住宅改修には補助金が出る場合もあるため、介護保険制度に詳しい専門家に相談することで、費用面でのメリットも得られます。
建築前の段階で、将来的にどのような介護サービスを利用する可能性があるか、デイサービスの送迎はどのように行われるか、訪問介護の頻度はどの程度かなど、介護サービスの利用を具体的にイメージしながら間取りを検討することが大切です。

間取り図を見ながら「実際にここで介護ができるか」を具体的にイメージすることが大切です。図面上では広く見えても、実際に家具を配置したり、車椅子で移動したりすると狭く感じることもあるんですよ。
将来の介護を見据えた住まい選びで家族全員の生活を守る

介護しやすい平屋の間取りを考えることは、単に要介護者の生活を便利にするだけでなく、介護者の負担を軽減し、家族全員の生活の質を守ることにつながります。
介護は長期間にわたることが多く、適切な住環境がなければ、介護者が心身ともに疲弊してしまいます。介護うつや介護離職といった問題も、住環境の改善により一定程度防ぐことができるのです。
将来の介護を見据えて住まいを選ぶ際、「いつから介護が必要になるかわからない」という不安を感じる方も多いでしょう。しかし、介護が必要になってから慌てて対応するよりも、事前に準備しておく方がはるかに負担が少ないのです。
介護に関する悩みや、住まいづくりについての不安がある方は、一人で抱え込まず、専門家に相談することをおすすめします。
介護しやすい平屋の間取り設計のポイント:まとめ
介護しやすい平屋の間取りを実現するためのポイントをまとめます。
平屋が介護に適している理由は、階段移動がないこと、動線がコンパクトになること、バリアフリー設計を取り入れやすいことです。これらの特徴により、要介護者と介護者双方の負担が大きく軽減されます。
設計で重視すべき7つのポイントは、LDKと寝室・水回りの動線を最短距離でつなぐこと、廊下幅90cm以上を確保し引き戸を採用すること、回遊動線と座れる場所を設けることです。これらを実現することで、日常的な介護負担が大幅に軽減されます。
見落としがちな注意点として、玄関から寝室までの距離と駐車場スペースの確保、収納位置と設備の足元スペースへの配慮、家具配置を考慮した通路幅の実測が挙げられます。これらのポイントを押さえることで、後悔のない住まいづくりができます。
最も重要なのは、建築前に介護経験者や専門家に相談することです。住宅設計の専門家だけでなく、介護の現場を知る専門家の視点を取り入れることで、より実用的な住まいづくりができます。
介護しやすい平屋の間取りは、要介護者の自立を支援し、介護者の負担を軽減し、家族全員が長く安心して暮らせる住まいを実現します。将来を見据えた住まいづくりを、今から始めてみませんか。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。