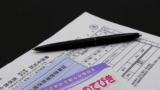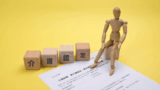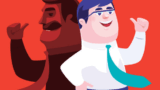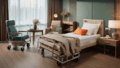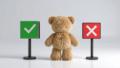「親の介護が必要になったけれど、介護認定を受けるにはどうすればいいの?」「申請手続きが複雑で何から始めればよいかわからない」「必要な書類や条件について詳しく知りたい」
介護が必要になった時、まず考えるのが介護保険サービスの利用です。しかし、これらのサービスを利用するためには介護認定を受けることが必須となります。
介護認定の申請は一見複雑に見えますが、正しい手順と必要な準備を理解すれば、スムーズに進めることができます。申請から認定まで通常30日程度かかるため、早めの準備と申請が大切です。
この記事では、介護認定を受けるための条件から申請手続き、認定調査、結果通知まで、一連の流れを詳しく解説します。初めての方でも安心して申請できるよう、実践的なポイントや注意点もお伝えします。
介護認定を受けるには?基本的な条件と対象者
介護認定を受けるためには、まず自分や家族が対象者に該当するかを確認することが重要です。介護保険制度では、年齢や状況によって申請できる条件が明確に定められています。
65歳以上の第1号被保険者が受けるための条件

65歳以上の方(第1号被保険者)は、原因を問わず日常生活で介護や支援が必要になった場合に介護認定を受けることができます。
具体的には、加齢による体力低下、認知症、脳梗塞の後遺症、骨折による歩行困難、パーキンソン病など、あらゆる理由で介護が必要になった状況が対象となります。病気の種類に制限はなく、日常生活に支援が必要と感じた時点で申請が可能です。
ただし、65歳になる誕生日の前日からしか申請できないため、64歳の時点では申請できません。また、介護保険料を納付していることが前提条件となります。
40~64歳の第2号被保険者が受けるための条件

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が介護認定を受けるには、加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限られます。
特定疾病は以下の16種類が指定されています
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これらの疾病以外が原因で介護が必要になった場合、たとえ重篤な状態であっても介護保険の対象外となります。例えば、交通事故による脳外傷や先天性疾患などは対象外です。
介護認定を受けるとどうなる?利用できるサービス

介護認定を受けると、要支援1~要介護5の7段階のいずれかに認定され、認定度に応じた介護保険サービスを1割〜3割の自己負担で利用できます。
在宅サービスでは、ホームヘルパーによる生活援助、デイサービス、ショートステイ、福祉用具レンタルなどが利用可能です。要介護3以上の認定を受けると、特別養護老人ホームへの入所申込みもできるようになります。
認定を受ける最大のメリットは、本来なら全額自己負担となる高額な介護サービスを、大幅に軽減された費用で利用できることです。例えば、要介護3の方が月20万円分のサービスを利用しても、自己負担は2万円(1割負担の場合)で済みます。
また、医療費控除や障害者控除の対象となる場合もあり、税制面でのメリットも期待できます。
【介護認定の申請、何から始めればいいかわからず困っていませんか?】
介護認定を受けるには何が必要?申請の準備と手続き
介護認定を受けるための申請手続きは、必要書類の準備から始まります。事前にしっかりと準備することで、スムーズな申請が可能になります。
申請に必要な書類と準備すべきもの

介護認定の申請には、以下の書類が必要です:
必須書類:
・要介護・要支援認定申請書(窓口で入手可能)
・介護保険被保険者証(65歳になると郵送される)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
40~64歳の第2号被保険者の追加書類:
・健康保険証
・特定疾病を証明する医師の診断書または意見書
代理申請の場合の追加書類:
・代理人の身分証明書
・委任状(本人の署名・押印が必要)
・親族関係を証明する書類(戸籍謄本など、親族以外が代理する場合)
申請場所と申請方法の詳細

申請場所は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。具体的には以下の場所で申請できます:
・市区町村役場の介護福祉課・高齢者福祉課
・地域包括支援センター
・市区町村の出張所(取り扱っている場合のみ)
申請方法は主に以下の3つです:
1. 窓口での直接申請
必要書類を持参して窓口で申請します。職員が書類をチェックし、その場で不備があれば修正できるため、最も確実な方法です。受付時間は平日の8時30分〜17時15分が一般的です。
2. 郵送申請
一部の市区町村では郵送での申請を受け付けています。書類の不備があると再提出が必要になるため、事前に電話で確認することをおすすめします。
3. オンライン申請
マイナポータルを通じてオンライン申請ができる自治体も増えています。24時間申請可能で便利ですが、添付書類は別途郵送が必要な場合があります。
代理申請の方法と注意点

本人が申請できない場合は、以下の方が代理で申請できます:
・家族(配偶者、子、孫、兄弟姉妹など)
・親族(3親等以内)
・成年後見人
・居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
・地域包括支援センター職員
・介護保険施設の職員
家族が代理申請する場合、本人の意思確認が重要です。認知症などで判断能力が低下している場合でも、可能な限り本人に申請の意思があることを確認し、その旨を申請書に記載します。
ケアマネジャーや地域包括支援センターに代理申請を依頼する場合は、事前に相談し、申請理由や本人の状況を詳しく伝えておく必要があります。
介護認定を受けるには病院との連携が重要
介護認定の申請において、医療機関との連携は極めて重要です。特に主治医意見書は認定判定に大きく影響するため、事前の準備と医師とのコミュニケーションが必要です。
主治医意見書の重要性とかかりつけ医の選び方

主治医意見書は、介護認定の判定において極めて重要な役割を果たします。医学的見地から本人の心身の状態や介護の必要性を評価し、認定調査では把握しきれない医療的な情報を提供します。
かかりつけ医がいない場合は、申請前に医師を見つける必要があります。以下の点を考慮して選びましょう
かかりつけ医選びのポイント
・本人の病状を理解している医師
・定期的に診察を受けている医師
・介護認定に理解のある医師
・アクセスの良い医療機関の医師
複数の医療機関を受診している場合は、最も頻繁に診察を受けている医師、または主たる疾患を診ている医師を選ぶのが一般的です。専門医よりも、日常的な身体状況を把握している内科医などが適している場合も多くあります。
病院での診察と医師への相談のポイント

申請前の診察では、日常生活での困りごとを正確に医師に伝えることが重要です。医師は主治医意見書で以下の項目について記載する必要があります
・現在の病状と今後の見通し
・認知症の有無と程度
・日常生活の自立度
・必要な医療的ケア
・薬物療法の状況
・特別な医療処置の必要性
医師への相談で伝えるべき内容
・具体的な日常生活の困難さ(歩行、入浴、食事、トイレなど)
・症状の変化や悪化の状況
・家族の介護負担の状況
・これまでの経過と現在の治療内容
診察時には、可能であれば普段介護をしている家族が同行し、医師に状況を説明することが効果的です。医師が把握していない在宅での様子を伝えることで、より正確な意見書の作成につながります。
医療情報の整理と準備すべき内容

医師への相談前に、以下の医療情報を整理しておきましょう
準備すべき医療情報
・現在服用中の薬剤リスト(お薬手帳)
・これまでの入院歴や手術歴
・他の医療機関での検査結果
・リハビリテーションの実施状況
・医療機器の使用状況(酸素療法、人工透析など)
日常生活の状況記録
・食事の摂取状況と介助の必要性
・排泄の状況と失禁の頻度
・入浴時の介助の必要性
・歩行状況と転倒リスク
・認知症状(物忘れ、徘徊、興奮など)の具体例
これらの情報は、できるだけ具体的な事例とともに記録しておきます。「時々困ることがある」よりも「週に3回程度、食事中にむせることがある」など、頻度や程度を明確にすることが重要です。
介護認定を受けるには:認定調査から結果通知まで
申請が受理されると、認定調査から結果通知までの手続きが始まります。この段階での準備と対応が、適切な認定結果につながる重要なポイントです。
認定調査の流れと準備のコツ

認定調査は、申請から1〜2週間後に市区町村の職員または委託された調査員が自宅や施設を訪問して実施されます。
認定調査の内容
・基本調査(全国統一の74項目)
・特記事項(基本調査では表現しきれない詳細な状況)
・概況調査(現在受けているサービスや住環境)
基本調査では、身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応などについて詳しく聞き取りが行われます。調査時間は通常60〜90分程度です。
認定調査の準備のコツ
・調査当日は本人の体調が良い時間帯を選ぶ
・普段の状況がわかる家族が同席する
・日常生活の困りごとを具体的にメモしておく
・遠慮せずありのままの状況を伝える
・「できる」「できない」だけでなく、頻度や程度も伝える
審査会での判定プロセスと認定基準

認定調査と主治医意見書が揃うと、以下の手順で判定が行われます
1. 一次判定(コンピュータ判定)
認定調査の基本調査項目をコンピュータに入力し、要介護認定等基準時間を算出します。この時間に基づいて、コンピュータが暫定的な要介護度を判定します。
2. 二次判定(介護認定審査会)
保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成される介護認定審査会で最終判定を行います。一次判定結果、主治医意見書、特記事項を総合的に検討し、最終的な要介護度を決定します。
認定基準の考え方:
要介護認定は、「どのくらいの介護の手間がかかるか」を基準としています。病気の重さではなく、日常生活における介護の必要度が評価のポイントです。
・要支援1・2:基本的な生活は自立しているが、一部支援が必要
・要介護1・2:部分的または軽度の介護が必要
・要介護3・4:中等度から重度の介護が必要
・要介護5:最重度の介護が必要
結果通知と今後の手続き

認定結果は、申請から原則30日以内に郵送で通知されます。遅れる場合は市区町村から連絡があります。
結果通知に含まれる内容
・認定結果(要支援1〜要介護5、または非該当)
・認定有効期間(新規申請は6ヶ月、更新は12ヶ月が基本)
・区分支給限度額(月額の利用可能額)
・介護保険被保険者証(認定結果記載)
認定後の手続き:
要支援1・2の場合:地域包括支援センターに連絡し、介護予防ケアプランを作成
要介護1〜5の場合:居宅介護支援事業者を選び、ケアマネジャーとケアプランを作成
非該当の場合:市区町村の介護予防事業や地域支援事業の利用を検討
認定結果に納得できない場合は、結果通知から60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申立てができます。また、状態が変化した場合は区分変更申請も可能です。

認定結果が出たら、できるだけ早くサービス利用の準備を始めましょう。ケアマネジャー選びは今後の介護生活に大きく影響するため、しっかりと相談して決めることが大切ですよ。
悪いケアマネージャーの見極め方と対処法とは?知っておきたい知識
複雑な手続きで不安な時は専門家に相談を

介護認定の申請手続きは多くの準備が必要で、初めての方には複雑に感じられることも多いでしょう。「申請書の書き方がわからない」「認定調査で何を話せばよいかわからない」「結果に納得できない場合の対処法を知りたい」といった不安を抱える方も少なくありません。
また、家族だけで判断することが難しい状況も多く、「本当に申請すべき状態なのか」「どのような準備をすれば適切な認定が受けられるのか」など、専門的な知識が必要な場面も多くあります。
専門相談員は、申請前の準備から認定調査の対策、結果への対応まで、一連のプロセスを熟知しています。「書類の準備方法がわからない」「認定調査でどう答えればよいか不安」「結果に納得できない」といった具体的な悩みに対して、実践的で具体的なアドバイスを受けることができます。
初回20分の無料相談では、現在の状況を整理し、最適な申請戦略について相談できます。夜の時間帯にも対応しているため、日中は忙しい方でも利用しやすくなっています。
「一人で手続きを進めるのは不安」「専門的なアドバイスが欲しい」「適切な認定を受けるための準備を相談したい」といった場合は、専門家のサポートを受けることで、より安心して申請手続きを進めることができるでしょう。
介護認定を受けるには知っておきたい注意点とコツ:まとめ
介護認定を受けるための手続きは複雑に見えますが、正しい準備と手順を理解すれば決して難しくありません。
申請成功のための重要ポイント
まず、年齢と状況に応じた申請条件を正しく理解することが大切です。65歳以上なら原因を問わず申請でき、40〜64歳なら特定疾病が対象となります。必要書類は事前にしっかり準備し、かかりつけ医との連携を密にすることで、スムーズな申請が可能になります。
認定調査では、普段の生活状況をありのままに伝えることが最も重要です。「まだ大丈夫」と遠慮せず、具体的な困りごとを正確に伝えましょう。家族の同席により、本人が気づかない部分を補足することも効果的です。
介護認定を受けることで、本格的な介護生活をより安心して、そして経済的負担を抑えながら送ることができます。適切な手続きを経て、必要な支援を受けながら、本人も家族も安心できる介護環境を整えていきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。